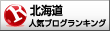幼くして両親を同時に失った境遇が、そんな彼女の傾向を強めた。
「私は優しくない女よ」
それが東京に出てからの彼女が、ことあるごとに自身にかける言葉だった。
いつもそんな風に言い続けているうちに9年が経ち、気がついたら伯母に出す音信は所在が変わ
った時と年賀状だけになっていた。
今度伯母を訪ねることになって、あやは再びあの入江の家に帰り、赤間家の姉妹に再開した時の
ことを思い出していた。
自分が優しくない女であり、情のない冷たい女なのは充分に分かっていた。
しかし、それは何故なのだろう。
あやは一時期鉄五郎に向けていた、激しい怒りのことを思った。
あの根深い怒りが、全ての始まりのような気がしてならなかった。
謂われない鉄五郎への恨みが時の流れの中で消えてしまった今も、怒りのしこりのようなものは
しぶとく身体のどこかに潜んでいる。
確かにそれは時折、気味悪く蠢くのを感じるのだ。
「どうしょうもない」
あやは伯母を訪ねる列車の中で、半ば開きなおってつぶやいていた。
あやの気持ちをよそに、伯母は9年前と少こしも変わらずに陽気で優しく、我が子のように迎え
てくれた。
伯母にとってはそれは極く当たり前のことなのだ。あやは懐かしい広い玄関で、変わらぬ話題で
迎えられて、そのことに気付いた。