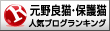二十
花も終わった頃に、高志がここを出て行くと聞いて、あやは落ち着きがなかった。
戻った時から長居をする気など毛頭なかったのに、今になってみるとやはり、病の不安のある鉄
五郎を一人にして出て行くことに後ろめたいものを感じていた。7年もの間、音信不通を続けてお
いて、何を今さらという気がしないでもなかった。
心冷たい薄情者は薄情者らしく、自分のことだけを考えていれば良いのだ。
少なくともここに戻ってくる前の自分なら、そのように考え行動することに、躊躇はなかったは
ずだ。
それがここで海を眺め、子供の頃の暮らしぶりを思い出しているうちに、調子が狂ってきた。
時々、今まで何をしてきたのか、分からなくなることがある。
足元から波に洗われて、砂が崩れていくように、どんどん自分が頼りなくなっていく。
この落ち着かない不安は、どうやら鉄さんのことが気がかりというだけではなさそうだ。
特に高志がここを出て行くと聞いてから、一層増してきたような気がする。
彼については、あの人はそういう人なのだと、さしたる疑問を感じることはなかった。
直きにここを去って行くのは、分かっていた。
それなのに、いざ時期を示されて出て行くと知らされると、初めてそんなことは思いもよらなか
ったと感じている。
急になにもかもがあやふやになって、まるで自分が見えなくなっている。
またしても自分が自らのことを、何も知らずにいたことに気付く。