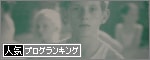作品情報⇒https://movie.walkerplus.com/mv71214/






以下、公式HPよりあらすじのコピペです。
=====ここから。
1933年、ヒトラーに取材した経験を持つ若き英国人記者ガレス・ジョーンズには、大いなる疑問があった。世界恐慌の嵐が吹き荒れるなか、なぜスターリンが統治するソビエト連邦だけが繁栄しているのか。
その謎を解くために単身モスクワを訪れたジョーンズは、外国人記者を監視する当局の目をかいくぐり、すべての答えが隠されているウクライナ行きの汽車に乗り込む。やがて凍てつくウクライナの地を踏んだジョーンズが目の当たりにしたのは、想像を絶する悪夢のような光景だった……。
ジョーンズはいかなる苦難の末に、スターリンの“偽りの繁栄”の実態を暴いたのか。そしてソ連の執拗な妨害工作に阻まれるなか、果たしてその一大スクープを世に知らしめることができるのだろうか。
巨悪な力に屈せず、正しい道を選ばんとした名もなき人間の実録ドラマが、現代を生きる我々に問い質すものとは ??? ?
=====ここまで。
☆゜'・:*:.。。.:*:・'゜☆゜'・:*:.。。.:*:・'☆゜'・:*:.。。.:*:・'゜☆゜'・:*:.。。.:*:・'☆゜'・:*:.。。.:*:・'゜☆
ロシアに行ったせいか、ソ連とかロシアものにやたら目が行ってしまう……。これも、チラシで見てから、公開されたら劇場へ行こうと思っていた作品。監督がアグニェシカ・ホランドってのも見たいと思った理由の一つ。『太陽と月に背いて』、『ソハの地下水道』と、かなり毛色の違う作品を撮っているけど、どちらも面白かったので。
◆ウクライナに何かある、、、。
このガレス・ジョーンズという記者は、もちろん実在した人で、ケンブリッジを卒業後に、ロイド・ジョージの外交アドバイザーに命じられた、、、というんだが、大学出たばっかの若造をアドバイザーにするっていうのは、どういう仕組みなんだろう。序盤に、ガレスがロイド・ジョージらが集う会議の席で、ヒトラーについて「アイツはヤバい男だ、危険!」(もちろん、セリフはもっと知的です)とオッサンたち相手に説明するシーンがあるんだけど、若造が故に(?)オッサンたちには鼻で笑われてしまっている。
どうして、ロイド・ジョージの外交アドバイザーになったのか、、、といういきさつは全く描かれていないので分からない。でもまあ、優秀だったんだろう。いくらヒトラーに直接インタビューしたって、その危険性を早期に見抜けないヤツは一杯いたんだから。現に、ロンドンのお偉方は揃いも揃って一笑に付しているのだし。
で、ソ連が変だ、、、ということにも気が付いたガレス。ソ連が変なことに気付いていた人は他にもいただろうが、現地に潜入取材してしまうというのは、ガレスくらいだったんだろう。大体、外国人記者はモスクワから出してもらえない、ましてや現地(ウクライナ)になんぞ行かせてもらえないんだからね。ガレスは、監視の目を欺いて、現地の人しか乗らない汽車に乗り換える。
この汽車の中のシーンが怖ろしい。そこまでガレスが乗って来たのは、食堂車もある豪華列車。賑やかな車内は、内装も色彩豊かで、ガレスは監視者と酒を飲みながら食事をする。監視者がウォツカを飲み過ぎて酔っ払った隙に乗り換えた汽車の中は、灰色一色。壁も座席も、人々の着ている者も、、、色がない。そしてシーンと静まりかえっている。その落差に愕然とする。
突然乗り込んできたガレスに、現地の人たちは皆一様に不審の目を向ける。ガレスも一瞬戸惑うものの、まだ実態を分かっていない彼は、しばらくすると手荷物の中からパンを取り出して口へ運ぶ。乗り合わせている人々は一斉にガレスに注目し「食べ物だ……」と囁く声もする。列車が揺れた拍子にガレスがパンを取り落とすと、一斉に皆がそのパンにたかる。その様は、例えが悪いが、本当に、まるでハエのよう、、、。
それを見て、ガレスもようやく、ここの人たちが“異常な飢え”の状態にあることを察する。……とはいっても、本当に凄まじい光景を目にするのはその後なんだが。凄まじいと言っても、本作内の描写は抑制的で、それほど凄惨なシーンはないが、当然カニバリも出てくるし、痩せ細った死体を山積みにした荷車が通り過ぎていくシーンもある。
それを目の当たりにして、ガレスは怖れをなして引き返す、、、どころか、さらに真相を探ろうと、身の危険も顧みずに現地の人に「これは一体どういうことなんだ?」等と聞き回るのだ。そして、案の定、捕えられる。
◆おそロシアに生きる。
普通だったら、ここで殺されるところを、NYタイムズのモスクワ支局長ウォルター・デュランティというアメリカ人の口利きで救われる。このデュランティ、スターリン賞賛記事を書いてピューリッツァー賞なんぞももらっているんだが、半面、モスクワで乱交パーティーに興じるなど、共産主義の闇を見ぬ振りをして恩恵だけ享受しているという、曲者。外国人記者のよしみだろうか、スターリンをバックにガレスを助けてくれたわけだ。
結局、ガレスはソ連から追い出され、ロンドンに戻ってウクライナで見てきたことを記事にする(史実ではロンドンではなく、ドイツに戻った様子)。しかし、デュランティはそれを真っ向から否定する記事をNYタイムズにデカデカと書き、ガレスはロイド・ジョージにもクビにされるわ、ソ連からはさらに睨まれるわで、居場所がなくなる。
でも、そこでめげないのがガレスのすごいところ。『市民ケーン』で描かれたアメリカの新聞王ウィリアム・ランドルフ・ハーストに直談判して、NYタイムズに大々的な反論記事を書いて載せるのだ。
本作は、ここで終わっている。しかし、史実では、これによってソ連に決定的にマークされることとなり、その2年後、満州で殺された。満州にはソ連に内通しているものがいて、それらに殺されたという見方がされているみたい。真相は今も分かっていないとのこと。
……まぁ、彼の生き様に見合った最期なんだろうが、今も、ロシアでは体制に(というかプーチンに)逆らうと毒を盛られるという、本作の頃からの精神が脈々と受け継がれている。まさしく、“おそロシア”を地で行く国である。
ガレスが命の危険を冒してまでウクライナを取材し記事化したのは、恐らくは記者としての使命感と、人としての正義感によるものだろう。それは誰にでも真似できるものではないけれども、そうすることで、悪を挫くことには大抵はならず、正義を通した方が冷や飯を食わされるのが、現実世界なのである。最悪の場合は、ガレスのように命を奪われる。日本でだって、、、ねぇ。公文書改ざんのスクープ記事が出たら、一昔前までなら内閣は吹っ飛んでいたはずなのに。スクープすれば斬られる、飛ばされる。一方で、悪はさらに強大化して居座り続ける、、、がーん。
片やデュランティは、死んじまったらおしまいとでも言わんばかりに、現実主義を貫く。記者の風上にも置けぬイヤらしいヤツだが、彼のピューリッツァー賞は剥奪もされておらず、恐らく天命を全うしている。
どちらの生き方が正解かなんて、誰にも言えない。そりゃ、ガレスみたいに生きられたらカッコイイけどね。
自分だったら、、、まぁ、私はガレスにもデュランティにもならない、というかそもそもなれないが、なれる能力があったとしてもならないだろうな、と。ある意味、私は、デュランティよりも卑劣で、記者なんか早々に辞めて、高みの見物を決め込むのではないかと思う。ガレスのように闘う気力もないし、デュランティのような権力欲もない。それか、西側に亡命するかもなぁ。今の日本でもイヤなのに、ソ連で生活できたとは思えない、、、。
◆カニバリの歌、オーウェル、HBCの曾祖父さま、その他もろもろ、、、
ウクライナの雪深い林を彷徨っているガレスの映る背景に流れる歌が、もの凄く怖い。メロディは単調だが哀しげで、歌声は今にも消え入りそうなか細さ。しかも歌詞がグロい。
♪飢えと寒さが家の中を満たしている/食べるものはなく寝る場所もない/私たちの隣人は もう正気を失ってしまった/そして ついに……
これを子どもたちが無表情で口ずさんでいるのである。ホラー映画よりも遙かに怖ろしい光景だと思った。
ガレスが降り立った駅では、ホームや道ばたで人が倒れて(死んで)いるが、誰も気にも留めない。もはや、風景の一部になっている。これと似たシーンは、『戦場のピアニスト』でもあった。ゲットー内を歩くシュピルマンの足下には死体がゴロゴロ転がっているが、道行く人も、シュピルマンも、それを避けて歩くだけ。
この、ウクライナの飢饉はあの『チャイルド44 森に消えた子供たち』でも背景として描かれていたが、私は本作を見るまで、それがただの飢饉だとしか思っていなかった。でも、実際は“人工的な大飢饉”であったと知り、驚いた。ホロドモールと呼ばれ、虐殺とされている。ソ連が隠蔽したので正確な実態は分かっていないが、犠牲者は300万人を超えると言われている、、、とのこと。このことは、現在のウクライナーロシア関係にも影を落としているらしいが、……まあそらそーだよね、こんなことがあれば。
あと、本作では、あのジョージ・オーウェルも出てくる。史実と年代が少しズレているけれども、『動物農場』を執筆しているシーンが所々で挟まれ、終盤ではガレスと直接対面するシーンもある。『動物農場』は、原作の方が面白いけれど、アニメもまあまあ良いので、一見の価値はあるかも。演じていたのが、ジョゼフ・マウルというイギリス人俳優だが、何となくオーウェルの風貌に似ている(まあ、そういう人を選んでいるんだろうが)。
一番印象に残ったのは、デュランティを演じていたピーター・サースガード。何ともイヤらしい感じがよく出ていた。『エスター』で無残に殺される父親役だったのかぁ、、、。『ブルー・ジャスミン』にも出ていたのね。
ガレスがアドバイザーを務めていたロイド・ジョージは、アスキス首相の総辞職を受けて、首相に就いている。アスキス首相といえば、私の愛するHBCの曾祖父さま。本作では、ロイド・ジョージはあんまし良い感じには描かれていないけど、本作は、首相を退いた後の話になるみたい。ますます、若い兄ちゃんガレスが外交アドバイザーとして選ばれたのが面白い。
モスクワの街並みとか、クレムリンとかがちょろっとでも出てくるかと思って楽しみにしていたけれど、、、、ゼンゼンだった。……ガックシ。
極限の飢え、、、想像を絶する。