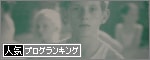ジョナサン(クリント・イーストウッド)の、表の顔は大学教授&登山家、裏の顔は元殺し屋。
ある日、足を洗ったはずの殺し屋稼業に再び戻らざるを得なくなる。たった1度だけ、という約束で依頼を完遂するが、その帰り道に美女の誘惑に乗り、再度、殺しをしなければならなくなる。しかも、その舞台は、今まで2度とも登頂に失敗しているアイガー北壁。殺す相手も不明。
、、、ツッコミどころ満載ながら、まだイイ男だったイーストウッドを隅から隅まで味わえる、イースドウッド・ファンしか楽しめない(と思われる)作品。
☆゜'・:*:.。。.:*:・'゜☆゜'・:*:.。。.:*:・'☆゜'・:*:.。。.:*:・'゜☆゜'・:*:.。。.:*:・'☆゜'・:*:.。。.:*:・'゜
もちろん、私は、俳優イーストウッドの半ば信者なので、十二分に楽しめますけれど。、、、一体、何度見たことやら、と思いつつも、BSでオンエアしていたので、ついつい録画して観てしまいました。う~~ん、カッチョええわぁ、イーストウッド

◆すぐにパンツを脱ぐ殺し屋が、アイガー北壁に挑む。
まあ、正直言うと、本作のジョナサンのキャラは、あんまし好きじゃないんです。イーストウッドが演じる中でのベスト・キャラは、そらもう、ハリー・キャラハンなわけで。ジョナサンは、いくらなんでもマヌケ過ぎで、見た目がカッコイイだけに余計にバカに見えるという、イマイチなキャラです。
最初の殺しも、びっくりするくらいの杜撰さ。あれでよく敵に気取られずに殺せたよなぁ、、、と。“まあこれは映画だもんね”としかコメントのしようのないお仕事の仕方です。排水管を伝ってよじ登るとことか、後半にあんだけ登山シーンで身体機能見せつけるんだから、別に今やらなくてもいいんじゃない? と、必死でよじ登っているイーストウッドにツッコミを入れてしまいます。
でもって、女と見ると、すぐに寝るジョナサン。殺し屋なのに、そこまで下半身が緩くてよろしいの? と、またまたツッコミ。ここでも、“まあこれは映画だもんね”と思う次第。
そして、最大の見せ場のアイガー北壁。確かに、絶壁を上るシーンは手に汗握る素晴らしさ。どうやって撮影したんだろう? と、素直に感動。イーストウッドも絶壁をまたまたよじ登っています。
で、終盤、こいつがターゲットだったのか……!! とジョナサンは初めてそこで知るんだけど、見ている方は、とっくに察しがついている。サスペンスとしては、イマイチどころか、かなりダメダメな展開。
イーストウッドがザイルを切る瞬間のドキドキ度といったら!!! 落っこちないの分かっているけど、もう怖くて見てられません

◆映像はさすが、、、なのでは。
本作は、監督もイーストウッドが務めていて、もう文字通り、イーストウッドの・イーストウッドによる・イーストウッドのための映画なわけです。
で、内容的にはツッコミだらけなんですけど、映像は、結構素晴らしいと思うのです。技術的なことは分かりませんが、この頃からすでに腕は確かだったんでしょう。
登山シーンのアイガーを臨むホテルからの眺めや景色の美しさ・明るさ・解放感、対比するかのように青い空が上の方にだけ見えている周囲を岩に囲まれたモニュメント・バレーでの訓練シーン、殺し屋の元締めドラゴンの暗室みたいな部屋でのシーン、、、と、実に画になるシーンがたくさん。内容がスカスカでも、これだけで見応え十分。
あとは、45歳で脂の乗り切った俳優イーストウッドのカッコイイお姿を拝んでいれば、この作品は、美味しく味わえるのです。
今回見て思ったのは、この頃のイーストウッドは、マイケル・ヴァルタンにちょっと似ているってこと。知名度的にはゼンゼン違うけど、ヴァルタンを、もう少しごつくした感じでしょうか。顔だけ見れば、ホント、雰囲気がそっくりです。私がヴァルタン教の信者になったのも、まあ、必然だったのかもなぁ、と妙に納得しました。
ちなみに、ヴァルタンが、『アリー・myラブ』で出演したときの役の名も、ジョナサンでした。すごいどーでもよいネタをすみません。
イーストウッド氏、今年86歳なのですねぇ。いやぁ、すんごいお元気。創作意欲は枯れることなく、素晴らしいです。あと何本撮ってくれるんでしょうか。いつもに増して中身のない感想で重ね重ねすみません、、、。
あんまし感想を書く気にならない映画です。
★★ランキング参加中★★