






ある列車に乗った人々の、列車内でのせいぜい数時間でのできごとを描写するだけで、その人々の人生を垣間見せる、これぞ映画の真骨頂的な作品。
キアロスタミ、ローチ他1名、計3名の監督による連作。
☆゜'・:*:.。。.:*:・'゜☆゜'・:*:.。。.:*:・'☆゜'・:*:.。。.:*:・'゜☆゜'・:*:.。。.:*:・'☆゜'・:*:.。。.:*:・'゜
リンク先の本作の紹介文には「オムニバス作品」とあるけれど、正確にいうと、オムニバスとは違うかと。一つの作品になっていますので。構成上、3幕に分かれている、って感じですかね、舞台でいうと。
で、第1幕。正直、うーん、あんまし好きじゃないというか。老人が、美しい中年女性に恋心を抱く、、、っていう設定だけで、ダメでした。うーん、、、まあ、分かりますよ、美しい女性に優しくされて、ちょっと勘違いさせられるような言葉を言われたら、そういう気持ちになってしまうのは。でもねぇ、、、なんかダメでした。老人を演じた俳優さんのルックスがダメだったのかも、という気もします。
というわけで、私が心に残ったのは、第2幕と、第3幕でございました。
第2幕は、キアロスタミによるものです。とにかく、ここで出てくるおばちゃんが、すんごい不機嫌なわけです。最初から、フキゲン。理由は分かりません。ただただ不機嫌。イライラし、人に当たり散らすのですね。
一緒にいる青年は、最初、誰もがこのおばちゃんの「息子」と思うでしょう。もちろん、私もそう思って見ていました。すると、途中でそうでないことが分かります。このおばちゃんと青年の関係の明かし方が実に上手いなぁ、と。
青年は、兵役義務の一環として、将軍の未亡人=おばちゃんの付添いをしていたのです。で、未亡人=おばちゃんは、亡き夫=元将軍の1周忌の墓参りに行く途中だったというわけです。・・・もちろん、これで不機嫌の理由にはならないのですが、おばちゃんが笑顔でない理由には十分なります。
傍若無人なおばちゃんに、青年は実に従順に仕えているのですが、終盤、彼の中で何かがプツンと切れたのでしょう。おばちゃんを足蹴にして去ってしまいます。もちろん、列車内なので、どこかにはいるはずなのですが、おばちゃん、必死になって探すも見つけられず、、、。
下車駅にて、おばちゃんは一人、途方に暮れています・・・。
続く第3幕は、ローチによるもの。これは、ローチらしいというか。扱ったのは、アルバニアからの移民家族と、英国からの旅行青年3人組。3人のうちの1人が、列車の切符をなくします。
慌てる3人は、どこでなくしたか、思い出すうちに、食堂車で移民の青年にサッカーの試合のチケットを見せたことを思い出し、そのチケットと切符を財布に入れていたことから、移民の青年が盗んだのではないか、という疑惑が生まれます。
、、、果たして真相は。
ローチのアプローチ(ダジャレではありません)は、相変わらずシビアでして、見ていてドキドキします。3人のうち、一番、移民青年を疑い、移民家族にキツく当たっていた青年が、最後にした選択が、ローチらしからぬような・・・。でも、『ジミー、野を駆ける伝説』にも書いたけれど、初期作品ではいかにもな「救い」はほとんどなかったのに、この辺りでは既に「救い」があるものを描いていたのですね。
で、ラスト、ローマ駅に着いたとき、3人の青年たちと、移民家族、それぞれ無事に列車の旅を終えるのですが、駅を歩く人ごみの中には、第2幕で消えた青年もちゃんと歩いています。、、、と言う具合に、この作品は3幕で一つの作品なのです。
第2幕のおばちゃんを見ていて、私は、ちょっと反省しました。パートナー(以下、Mr.P)に対する日頃の態度を、、、。
子どもの頃、ヒステリックに喚いている母親を見て「何であんな言い方するんだろう・・・?」としょっちゅう思っていて、さんざん反面教師にしてきたはずなのに、ふとした瞬間に、私自身がMr.Pに母親とおんなじ口調で小言を言っていることに気付くのです。そして自己嫌悪に・・・。その度に、いかんいかん、と思うのですが、Mr.Pが、ゴミを床に捨てっぱなしにしていたり、タオルは広げて掛けておいてと何度頼んでも棒状に掛けてあったり、玄関に靴がハの字に脱いであったりするのを見ると、つい、冷静さを欠いてしまうのです。あのおばちゃんの不機嫌な佇まいは、私のそれと同じだ・・・、と。
がしかし、そう思った、その日の夜に、また私は同じことをMr.Pにしておりまして、ゼンゼン反省していないことに、またまた気付きました。ま、この先も、自己嫌悪との闘いの日々なんだろうなぁ、、、。24時間、日常的に不機嫌なわけじゃないのですが・・・。
日常的に不機嫌な人、というのは、やっぱり、精神的に何か問題を抱えているのだろうと思います。そしてそれは自分の力じゃどうしようもないこと、ではないかな。自分のコントロールの域を超えたところにある(と本人は信じている)ものに、苦しめられているのでしょう。
でも、傍から見ると、それは、自分の心持次第でいくらでもコントロール下に置くことができるもの、ってことも。
しかし、人生は、そんなコントロールできるものばかりじゃなく、そもそも、不条理そのものだ、と言っているのが第3幕なのです。出自なんて、本人に何の責任もありません。生まれた国が、あるいは、家庭が貧しかった、というだけで抱える不条理。これを、ローチは容赦なく描いています。
、、、いや、3幕とも、人生の不条理さが通底しているのかも知れません。一番、表面に出ているのが第3幕であるとは思いますが。第2幕のおばちゃんも、第1幕の老人も、不条理を抱えて、折り合いをつけたりつけられなかったりしてきたのです。それが実に切れ味良く描かれています。
多分、若い頃に見ても、ふーん、、、で終わっていたであろう作品です。味わい深い逸品です。
人生とは不条理なり。
★★ランキング参加中★★
クリックしていただけると嬉しいです♪
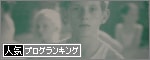
















※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます