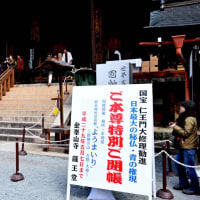最近は西洋アジサイ、ガクアジサイの中でも品種によって色、形の種類が豊富にあります。

















アジサイはアジア、北アメリカに約40種類が分布する低木で、日本には約10種類自生しています。
アジサイは非常に多くの形態があり、アジサイの仲間として知られているものは主に以下のものがあります。
1 ガクアジサイ 日本の海岸地方に自生するアジサイ。漢字で書くと「額紫陽花」で目立たない両性花の周りに咲く装飾花を額縁に見立てたもの。
2 アジサイ(ホンアジサイ) ガクアジサイの両性花がすべて装飾花に変化した個体をさす。いちばん先に付けられた学名(H.macrophlla)がこの個体に付けられたため狭い意味でアジサイというと本種をさします。
3 ヤマアジサイ 日本の山林の谷部に自生し、ガクアジサイを小ぶりにした花姿で野趣に富む。
4 アメリカノリノキ 北アメリカに分布。園芸種に球状の大きな白い花を咲かせるアナベルが有名。
5 ノリウツギ アジサイの中では高性で5m近くになります。円錐状の花穂からピラミッドアジサイとも呼ばれます。樹皮から採れる樹液が和紙のつなぎ(糊)に使われたのでこの名前があります。
6 カシワバアジサイ 北アメリカ原産、葉の形が落葉樹のカシワに似ているのでこの名前があります。花色は白、円錐状に咲く花が特徴的です。
7 タマアジサイ 日本に自生する種で蕾がまん丸で玉のように見えるのでこの名前があります。
アジサイの花には両性花と装飾花の2種類があります。ガクアジサイの標準花は花の中心部に小さな両性花(雄花と雌花があり結実する)があり、周辺部に4弁の装飾花を付け、装飾化を額縁(がくぶち)と見なし「額縁咲型」と呼びます。
一方、よく見るアジサイの花はほとんどの花が装飾花(無性花)で半球状に咲く花を「てまり咲型」と呼びます。この種類は江戸時代後期に広がったガクアジサイの変種ですが、アジサイと言えばこの花を指すようになりました。
また、ヨーロッパで品種改良され、西洋アジサイとかハイドランジアと呼ばれるものはすべて装飾花のてまり咲型が主で花色も青・桃・白等あり、この花が普通のアジサイと呼ばれています。
近年はさらに品種改良が進みさまざまな形、色のアジサイが作られ、アジサイのイメージも大きく変わってきたと思います。
名前の由来
アジサイは奈良時代万葉集にも歌われていて「安治佐為」「味狭藍」「集真藍」などと表記されています。
アジサイの語源は藍色の花が集まる(める)という意味の「あづさあい(集真藍)」から変化いたと言われます。
アジサイは紫陽花と書きますがこれは唐代の詩人白楽天が紫色のライラックらしい花の名前を友人から訊ねられた時に即興詩で陽光に映える紫色の花なので紫陽花と答えたことが白氏文集の紫陽花詩に記載されているそうです。
これを読んだ平安時代の学者で36歌仙の一人源順が紫陽花をアジサイと解釈し誤って伝えたためアジサイの漢字は「紫陽花」となったそうです。
因みに日本のアジサイの中国漢字表記は「八仙花」又は「緑球花」と書きます。
また、アジサイには「七変化」という異名もあります。
一般的には土壌の酸度が一つの要因となりアルカリ性では赤かっぽく、酸性では青っぽくなるとされます。
アジサイの花の色は発色の色素及び補助色素、土壌の酸度(PH)とアルミニウム量。開花からの日数などにより、さまざまに変化します。
花の色はクロロフィル(緑色の色素)カロチノイド(黄・橙・赤・紫色の色素)フラボン(白・黄色・無色の色素)などで構成されます。
まず、クロロフィルの色があせるとカロチノイドの色が目立ってきます。次にカロチノイドも分解するとフラボンが強くなり、見た目には青くなります。
また、光合成によって葉から作くられる糖分も花に影響し、アントシアン(赤・青・紫・紫黒色の色素)に変化し、その後細胞液の酸でマグネシウムが分解し、カリウムが結合して紫色に変化すると言われます。
このようにアジサイの花は緑→黄→青→赤→紫の順に変化することがあります。