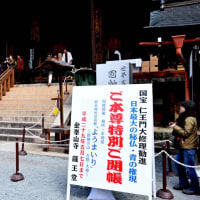散歩道🚶♀️🚶♂️
旧村の歩道を歩く
稲も随分と育っている
風に揺れる緑の絨毯

歩道脇に穂状の花序が出ている植物を見つけた
みた事がない。なんだろう?
自宅に帰り調べると「数珠玉(じゅずだま)」だった
野生化している
数珠玉は
雌雄同株である。 上部の葉の脇からたくさんの花穂を立てる。
硬くて艶のある壷(苞鞘)の中に雌花穂があり、その先に雄花穂が垂れ下がる。

葉は玉蜀黍(トウモロコシ)に似た線状の披針形で、互い違いに生える(互生)。
長さは30~60センチ、幅は2~4センチで先が尖り、縁はざらつく。

果期になると、苞鞘は白、灰色、灰褐色、黒などに色づく。
これに糸を通して数珠のようにつなげて遊んだのが名の由来である

根は生薬で川穀根(せんこくこん)といい、煎じて飲むとリューマチ、神経痛、肩こりなどに効く。
種子は川穀(せんこく)といい、煎じて飲むと美肌保全、健胃、解熱、利尿などの薬効がある。

ジュズダマ(数珠玉、Coix lacryma-jobi)は、水辺に生育する大型のイネ科植物の一種である。東南アジア原産。
郊外の水辺などに生える野草で、草丈1 - 2メートルほどになる。
実は硬くて光沢があり、昔はつないで数珠の玉にした。食用品種をハトムギと呼ぶ。

和名のジュズダマは、かつて球形状の実(苞鞘)をつないで数珠の玉にしたことに由来する。
別名で、ズズ、ズズゴ、ツシダマ、トウムギ、
地方によっては、ズウズク(千葉県)、スズ(和歌山県)、ボダイズ(岡山県)の方言名でも呼ばれる。

熱帯アジア原産
稲の伝播とともに
食用作物として渡来した。
・水辺や荒地に生える。帰化植物
稲の伝播とともに
食用作物として渡来した。
・水辺や荒地に生える。帰化植物

ハトムギ
食用品種のハトムギ(C. lacryma-jobi var. ma-yuen)は、ジュズダマを改良した栽培種である。
全体がやや大柄であること、花序や果実が垂れ下がること、
実(つぼ)が薄くそれほど固くならないことが、原種ジュズダマとの相違点である。
ハトムギの実は卵形で光沢がなく、固くなって指でつぶれる。また薬効も異なる。


散歩道🚶♀️🚶♂️