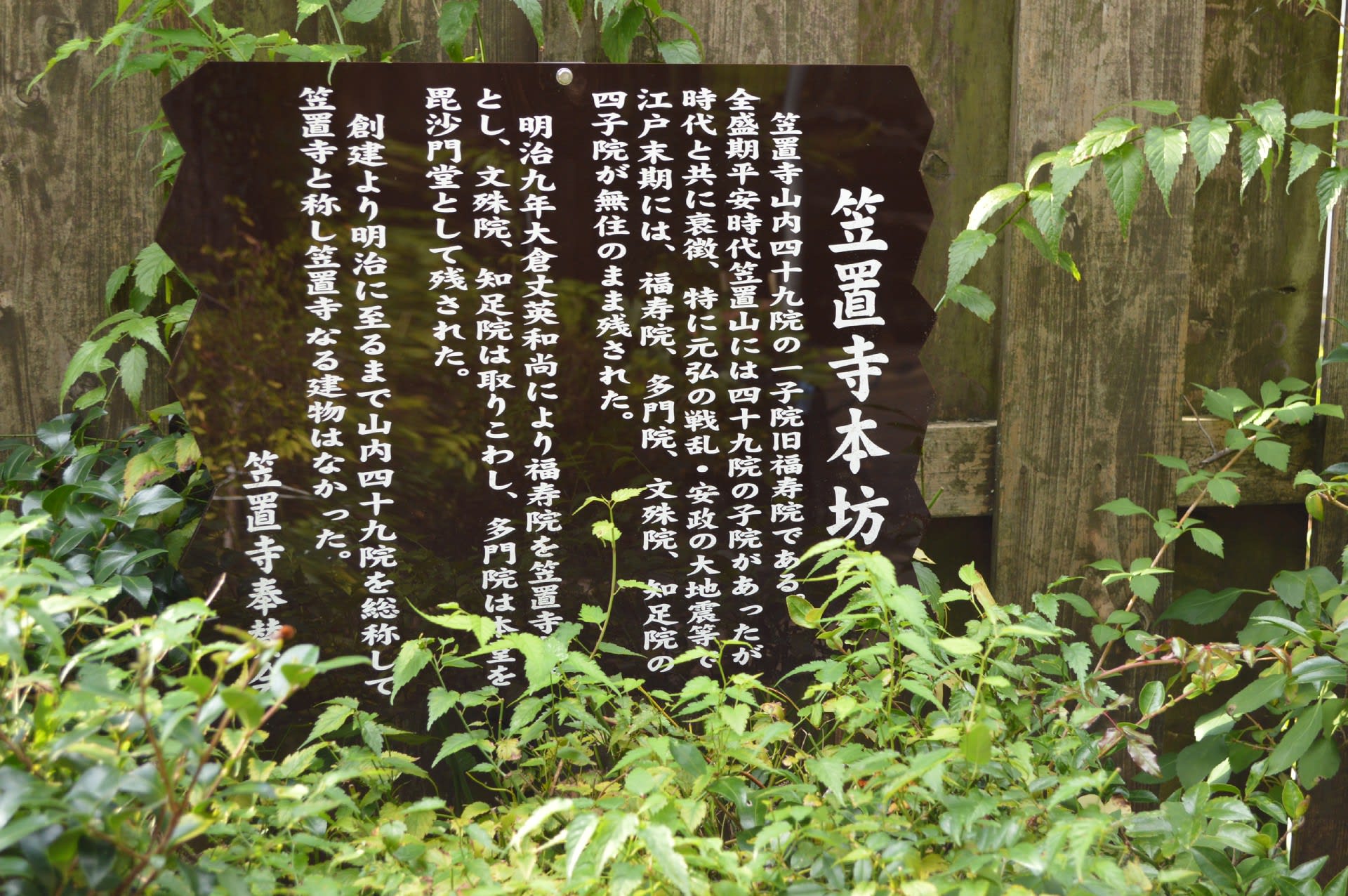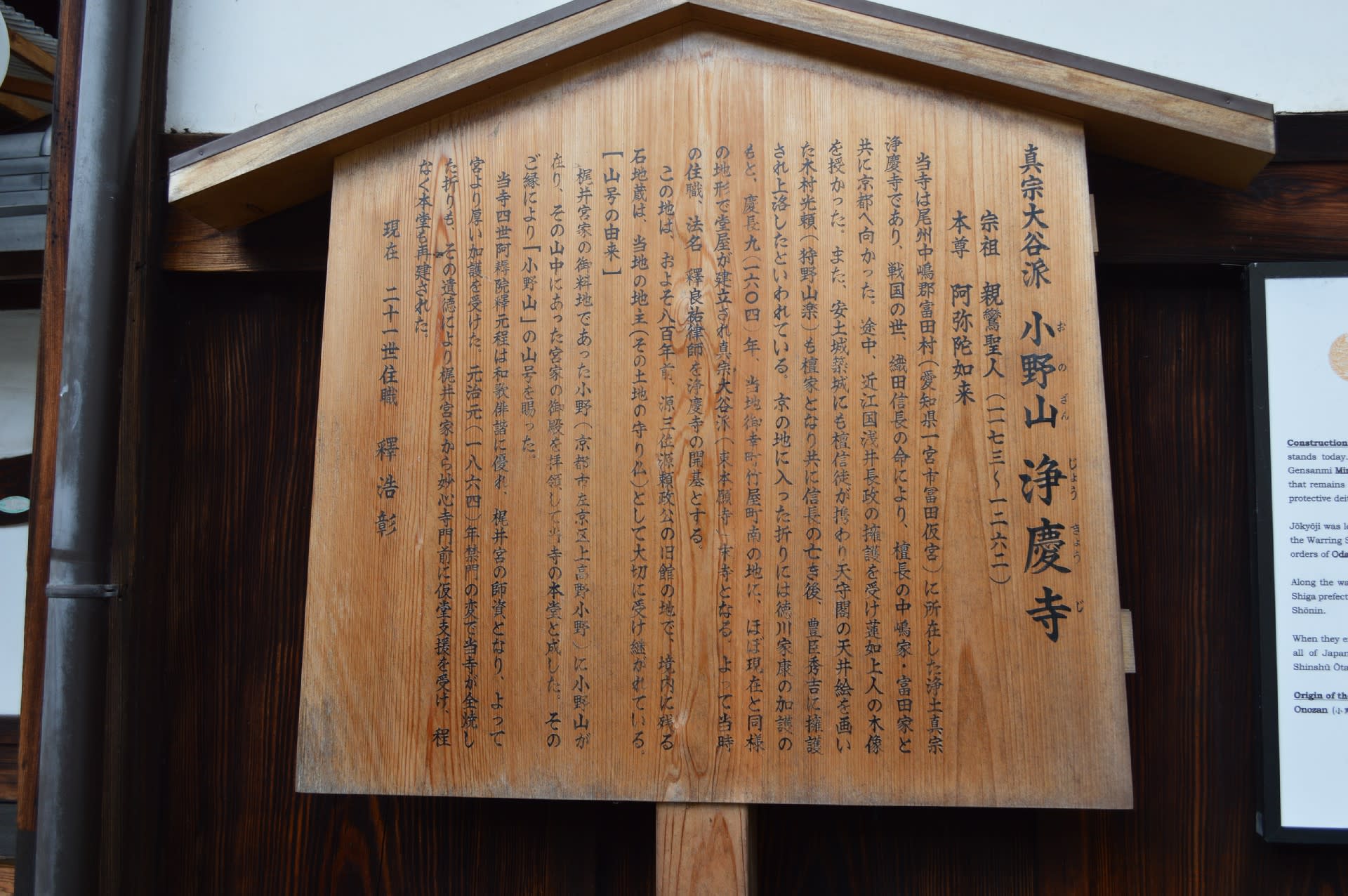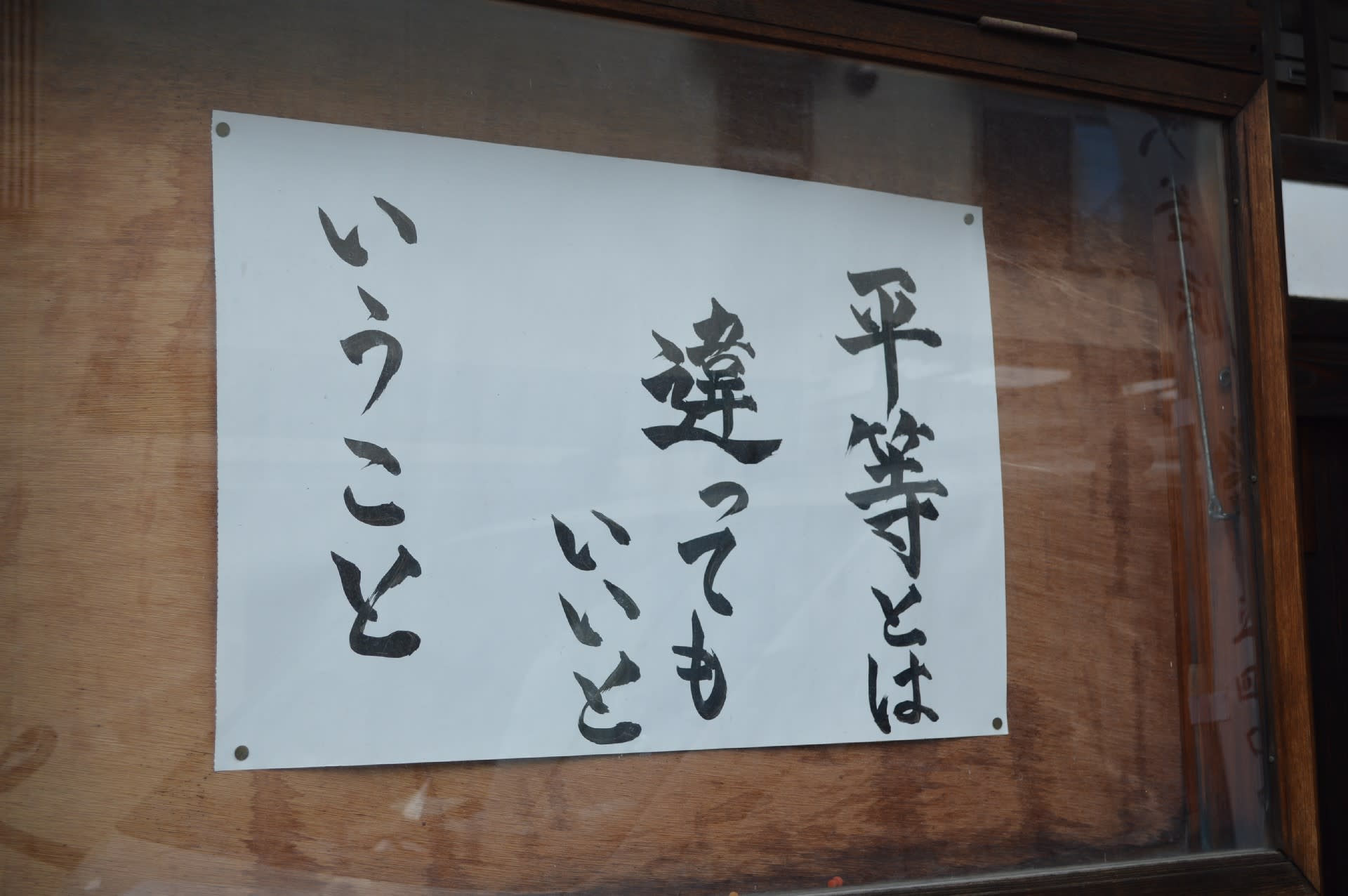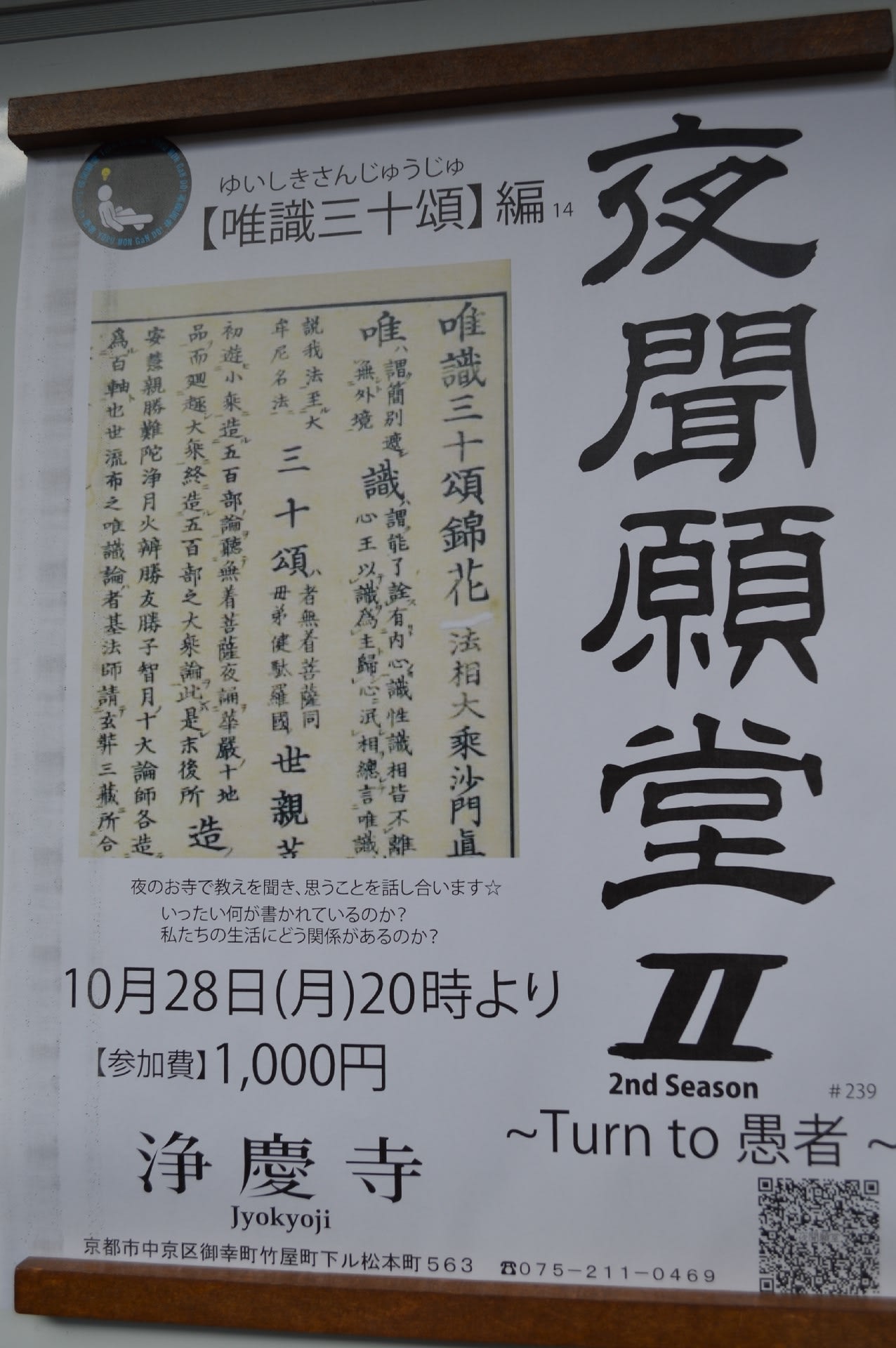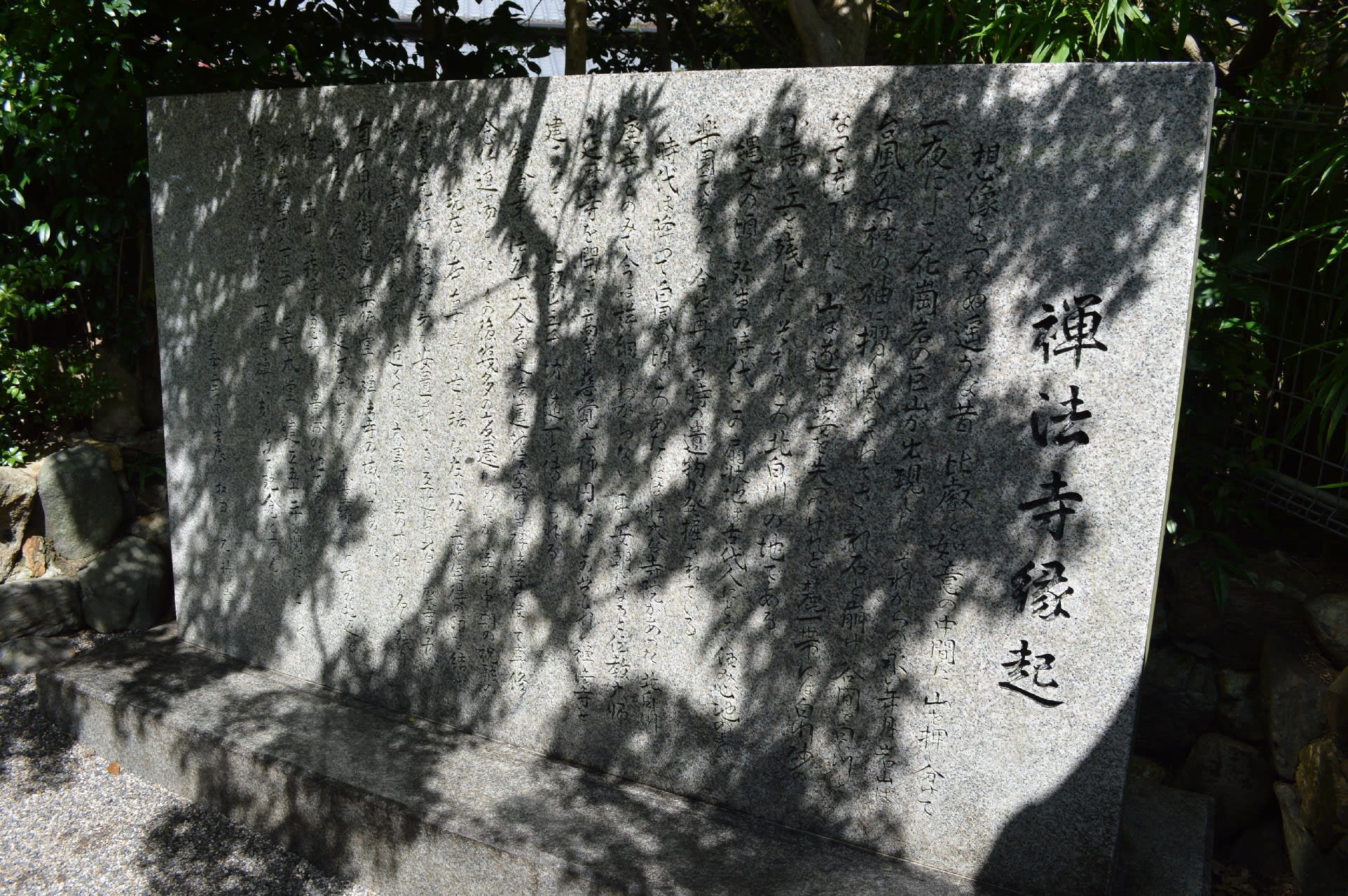千手窟
「笠置の龍穴」とも呼ばれ、社には龍神を祀る。天平勝宝3年(751)「東大寺 実忠和尚、ここより未未仏 弥勒菩薩の住する世界、都率天に至り、天乗の行ずる修法を伝授され人間界に移した」と縁起に記される。
11面観音悔遇行発祥の場、仏の世界への入り口である。実忠和尚、天平勝宝4年(752)、笠置寺大内に正月堂を建立され天乗より伝授された行法を修法。和尚により同年2月、東大寺に二月堂が建立され、この行法が修された。
これが、今日まで続く二月堂の悔遇行(通称お水取り)である。
゛悔遇゛とは我々が知らず知らずに犯す罪について11面観音の宝前において懺悔いることである。
ちなみに東大寺山内には、二月堂・三月堂・四月堂があるが、正月堂はない。実忠和尚建立の正月堂は、ここ笠置寺にある。

千手窟
1200年来、笠置寺の修行場であり二月堂のお水取りの行法も実忠和尚がこの修行場で行中感得されたものである。東大寺大仏殿建立の用材は木津川を利用し奈良へ送る計画をたてたが日照りつづきで水量少なく計画通り大仏殿の建立があやぶくなったとき実忠和尚がこの場で雨乞いの修法をおこない大雨を降らせ予定通り大仏殿を完成させたと伝う。この故事から以後大仏殿の修理の折りは必ずこの場で無事完成を願っての祈願法要が執り行われたという。



寺院 前回の記事 ⇒ 寺院笠置0728 笠置寺 弥勒磨崖仏
次回の記事 ⇒ 寺院笠置0730 笠置寺 伝 虚空蔵磨崖仏
下の地図のユーザー地図 の囲みをクリックすると 付近の記事が探せます