肺炎球菌は、ヒブよりもはるかにありふれた人間の常在菌です。それが抵抗力が落ちた時に発病するのです。麻疹のようにかかったら8~9割発病するというものではありません。少し難しい論文ですが、やさしく書き直す時間がなく、質問も多いために、とりあえず書きました。ヒブワクチンの項も一緒にご覧ください。
肺炎球菌ワクチン(乳幼児用)の話
肺炎球菌結合型ワクチンは三種あり、乳幼児用7価と13価と高齢者用23価があります。
肺炎球菌とはどんな菌か。
肺炎球菌は双球菌で、その大多数は外側に莢膜を持ち、莢膜型は現在約100種類あります。莢膜型が病原性を持ちます。小児から成人まで幅広い年齢層に感染します。
多くの健康な人にいる菌です。
肺炎球菌は気道の常在菌であり、保菌していても必ず症状が出る訳ではありません。健康保菌者(肺炎球菌を体内に保有しているが発病していない人)は、佐渡島出生コホート研究2008年の出生349名で、生後4か月で17.3%、7か月で27.5%、10か月で36.2%、1歳6か月で48%、3歳で38.2%が保菌者でした。また累積保菌率でみると、10か月児で約半数、3歳児で80%近くが少なくとも1度は肺炎球菌を保菌していました。竹内一によると、保育園児の入園時27.8%が肺炎球菌を保菌し、入園後1~2か月経つと88.9%が保菌していたと言います。多くの乳児が肺炎球菌を高率に保有しているのです。
アメリカのハリソン内科書によると、1歳までに小児の約半数は少なくとも、1回は肺炎球菌の定着を起こしていると言います。健康保菌者は、5歳未満の小児で20~50%とし、世界的な横断的研究では5歳までに70~90%の小児が肺炎球菌を鼻咽頭に保有するようになっていると言います。定着は高頻度に見られますが、疾患を起こすことは稀です。特に非特異的な自然免疫を阻害するような疾患があると発症しやすい素因になります。さらに適応免疫は1~2歳未満では十分に発達しておらず、感染しやすくなるといいます。
感染経路はどこからか。
呼吸時の飛沫による感染です。
生体防御機構はどうか。
自然免疫 正常な気道上皮と生体の非特異的な自然免疫因子(粘液、脾機能、補体、好中球、マクロファージ)が、肺炎球菌に対する防御の最前線を形成します。
適応免疫 定着により誘導される適応免疫は、T細胞非依存性抗原であるために、B細胞は抗体を産生し、適応免疫ができます。1~2歳未満では、その働きが十分発達していない為、幼少児の肺炎球菌への高い感受性に関係しています。
これらの働きで、感染し、定着しても、発病することは少ないのです。
抵抗力の落ちた時に発病する菌です。
肺炎球菌は、ヒブ感染と同じく、菌を持っていても、健康な時には発病せず、抵抗力(生体防御機構の働き)が落ちた時に発病し、その落ちる程度によって、軽く済むか重症化するかが決まります。ヒトの鼻咽頭に定着した後、多くは直接鼻・咽頭喉頭・気管支に侵入し、副鼻腔炎、中耳炎、気管支炎などの感染を起こします。一部が血中に入り、重症化します。山本英彦によれば、小児では21~59%が、ある時期にのどに菌を持つ。一度新種がのどにつくと、一か月以内に発病すると言い、その程度は、咽頭喉頭炎、中耳炎などの軽症が多いと言います。
重症化したらどうなるか。
乳幼児の三大感染症の敗血症、髄膜炎、肺炎を起こし、これらは現代ではヒブと同じく侵襲性感染症と呼ばれ、さらに喉頭蓋炎や特にウイルス感染(特にインフルエンザ)後の二次感染症の主要な原因にもなります。1999~2001年の感染症発生動向調査で、細菌性髄膜炎は763人で、半数の病原菌が判り、そのうち肺炎球菌は90人(全体の12%)でした。
国立感染症研究所のファクトシートでは、侵襲性感染症は、5歳未満人口10万人当たり21.7人(2008年)から23.6人(2009年)で、全国での年間推定発生は1177人(2008年)から1281人(2009年)でした。
そして罹患率は、ハリソン内科書によると、社会経済的状況と潜在的危険因子と遺伝的要因によると見られていると言います。厚生労働省のQ&Aでは、肺炎球菌は年1,200~1,300人罹患し、うち髄膜炎は150人、死亡率はその2%の3人くらい、後遺症は10%の15人くらいで治癒88%と言います。侵襲性感染症は、日本は低く、アメリカの10分の1で、欧米諸国も日本より数倍高いのです。
後遺症はどうか。
国立感染症研究所のファクトシートでは、難聴、精神発達障害、四肢麻痺、てんかんなどが、10%残ると言います。
ワクチンの有効性はどうか。
肺炎球菌による病気の内、ワクチンのカバー率は77.8%でした。しかも、カバーしている種類でも、接種してもアメリカの成績では、1~3%はかかってしまいます。アメリカの実験では、ワクチン4回接種者でも肺炎球菌菌血症になっています。また、ワクチンに含まれていない種類の肺炎球菌でも髄膜炎などの重症感染症は起きます。合計25種類の肺炎球菌が重症感染症を起こすことが判っています。でも小児には、7価または13価ワクチンしか使われていません。
効果の証明は、侵襲性感染症の発症率が日本の10倍も高い、アメリカの疫学データを根拠とし、日本での根拠のデータはないです。しかもサーベイランスの充実が無いため、効果判定は主観的です。しかも、世界の共同研究による効果判定には、肺炎球菌の生態環境が、地域、社会の経済状態、気候、人口密度、個人の生活レベル、保育環境、母親の保育の仕方などの違いによりさまざまなので、判定の誤差(バイアス)があります。
ワクチンの副反応はどうか。
2012年5月までに肺炎球菌とヒブワクチンの同時接種で13人が死亡しています。しかし、他に原因が見つからないのに、原因不明とか乳幼児突然死症候群の紛れ込み事故として処理され、副反応としてなかなか認定してくれません。
国内臨床試験では、注射部の紅斑80~71%、注射部の硬結・腫脹71.8~64.5%、発熱(37.5℃以上)24.9~18.6%、易刺激性20.4~11.2%、傾眠状態21.5~10.7%、注射部疼痛・圧痛12.7~7.5%と言います。副反応の研究は極めて弱く、常在菌のため、重症の副反応の判定が難しいのです。
どういうワクチンか。
T細胞非依存性抗原であるので、B細胞は抗体を産生しますが、乳児や低年齢児ではその働きがまだ弱く、十分な免疫を誘導できないこと。また免疫学的記憶を持たせることができず、接種により獲得された免疫は数年後には減弱し、追加接種によるブースター効果(免疫の強化効果)は認められません。気道粘膜での菌定着を防ぐ効果はあまり期待できず、集団免疫効果に乏しいです。
中野貴司によれば、今使われているワクチンは、「乳児に対しても十分免疫を作り、生後2か月からの接種が可能である。基礎免疫後の追加接種によるブースター効果が認められた。免疫学的記憶機能も誘導することも確認された。」というが、根拠となるデータは公表されていません。
またハイリスクグループへの抗体形成は不良であると言います。
ワクチンが普及するとどうなるか。
肺炎球菌ワクチンが普及した国では、ワクチン株以外の肺炎球菌感染症が相対的に増加しています。イギリスやアラスカ先住民では、ワクチンがカバーしている侵襲性肺炎球菌感染症の頻度は減少していますが、その減少を相殺する程、ワクチンの株(血清型)と異なる侵襲性肺炎球菌感染症の頻度が明らかに増加しています。アメリカ、カナダ、オーストラリアでは、その増加はまだ少ないと言います。
ワクチン株は当初7株で、次いで13株になりました。アメリカでは7価ワクチンが普及したら、それに含まれない肺炎球菌の株が流行したのです。それでそれを含めて13価ワクチンが作られました。成人用は23株です。成人用は2歳未満には使えません。アメリカのハリソン内科書によると、アメリカのデータでは、23価ワクチンは5歳未満では84%に有効であったが、18~64歳では76%、65歳以上では僅か65%にしか有効では無かったと言います。
「必要なワクチンとは」と「免疫が低下する時とは」は、ヒブワクチンの項をお読みください。
最後に、
ヒブワクチンと肺炎球菌ワクチンが早くから導入されたアメリカでも、乳幼児死亡率はようやく導入された日本より高いのです。ワクチンを導入しなくても、全体の乳幼児死亡率を見たら、導入する必然性はあるのかどうかは判りません。個々の病気で判断するよりも、全体の罹患率、死亡率で判断すべきと思います。侵襲性感染症は、前述のように、日本はアメリカの10分の1です。
常在菌のため、撲滅は期待できず、ワクチンの影響による疾患の交替現象から、際限ない接種や成人への接種拡大が予想されます。
私の病原環境論では、人と細菌やウイルスは、共存していて、抵抗力の落ちた時に発病するのです。のどの常在菌をワクチンで抑えてしまうと、別の菌が入り込んできて棲みこみます。そしてまた、抵抗力が落ちた時に発病するのです。これをまたワクチンで防ごうとすると、また新たな菌が入り込んできます。常在菌は、人間の同盟軍なのです。それを排除してはいけないのではないでしょうか。


















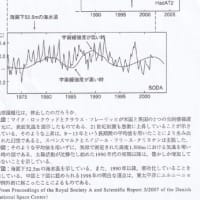
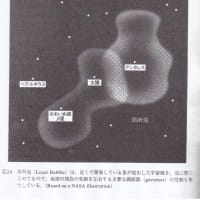






※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます