子ども医療講座 改訂版
子 ど も 医 療 講 座 (改訂版)
第1回「 健 康 は 自 分 で 守 る も の 」
1)医療は病気をなおす技術であり、医者は医療の専門技術者である。
➀医師は多くは、細分化された分野の専門家である。
医者は、素人から見れば医学医療全般の専門家に見えるが、内科、外科、小児科などの多くの科に分かれており、その上小児科を始めすべての科が、皆それぞれ更に細分化した専門分野に分かれている。
小児科は、普通は小児内科を指し、新生児・未熟児科、循環器科(心臓)、呼吸器科、血液・悪性腫瘍科、感染症科、アレルギー科、内分泌科、神経科、腎臓科、肝臓または消化器科などに分かれている。外科系も、小児外科、小児整形外科、小児眼科、小児耳鼻科、小児皮膚科、小児泌尿器科、小児婦人科、心臓外科先天性部門、小児形成外科、更に小児精神科、小児放射線科、小児歯科があり、さらに矯正歯科、脳外科、麻酔科、移植外科なども子どもの医療にかかわっている。
専門医としては、日本ではまだ麻酔科だけが信頼されている制度になっている。認定医とか専門医という制度は他の科でも実施されているが、博士号と同じで、信頼度が低い。現在は、専門に勉強し、専門に患者の診療にあたることで、専門医になることが多く、試験はあるが、専門医の資格をとったからといって、標準化された医療をしている保証はない。日本の医療が標準化されていないことにも問題があるし、専門医を養成する制度ができていないことにも問題がある。すべて個人の努力に負っていては、標準化されない。
さらに日本では、勝手に専門科名を名乗れるので、病院の小児科は小児科専門医であるが、診療所の小児科のほとんどは小児科専門医ではない。小児科しか名乗っていないか、小児科内科と名乗っていれば、小児科専門医であると考えてよいが、内科小児科というのは内科医である。小児科だけでは診療所の経営が成り立たないので、小児科医になりたがらないので、小児科医だけでは日本の子どもの2割くらいしかカバーできないためである。
しかも小児科専門医と言っても、さらに細分化されて未熟児・新生児、呼吸、循環、腎臓、内分泌などの専門分野に分かれます。それが大学病院で生み出されています。大学病院に残ると必ずどこかの分野に配属され、細かく細分化されるのです。
私は、総合小児科医であり、子どもの病気を浅く広く知っていて、小児の耳、鼻、目、口の中、泌尿器などの簡単な病気を治療します。アトピー性皮膚炎、花粉症、気管支喘息などのアレルギーの病気の治療をします。大人を専門とする耳鼻科、眼科、皮膚科より、子どもの病気に関しては上手に治してきました。総合小児科医は、日本では教育システムがなく、ほとんどいません。
専門医の中でも腕の上手下手はあるし、よく説明してくれるか否か、優しいか否かなどの違いもある。しかし小児の専門医で腕の良い医者は、何科にかかわらず子どもを扱うのが上手で優しい。病気がよくならない時や、専門的な治療を要する時は、子ども専門の医者にかかることをお薦めする。良い専門医を知っていることが、医者の腕である。あくまで選ぶのは医師個人であり、病院ではない。
知識というものは、誰を知っているかが、何を知っているかである。自分では知らなくても、知っている医者を紹介するか、電話などで相談することができれば、知っているうちに入る。良い医者は良い医者を紹介してくれる。しかし、必ずしも近い所に居るとは限らないのが難点である。
➁当たりはずれのある医療
一般に医者は、専門医として教育され、大病院に勤務するので、自分の専門分野以外については詳しくは知らないことが多い。そういう専門医が、開業したり、一般病院に勤めたりする。そこで同じ科を標榜していても当たりはずれがある。これは日本の医師の卒業後の教育制度の欠陥からくる問題でもあるし、日本の医療が標準化されていないことにもよっていて、当たりはずれのある医療を生んでいる。アメリカでは、1970年代に医療の標準化が進み、一般的な日常の医療に関してはどこでもいつでも最高の水準の医療が受けられるようになっている。
日本は当たりはずれがあり、開業医でも良い医者にあたれば、良い医療を受けられる利点もあるし、大学病院、小児医療センターや大病院に行っても良い医者に当たるとは限らず、はずれの医者もいる。結局は、どこにかかるかではなく、医者個人の腕に左右される。どの医者が本当によく知っていて、腕が良いか、優しいかは、会っただけでは医者でも判らない。一緒に診療をしたり、患者さんを紹介して初めて判ることもあるし、上手な医師や上手な診療を知って、判ることもある。
元日本医師会長だった故村瀬敏郎先生は、出身は外科医だったが、開業してから内科を加え、さらに小児科も始めた。私のアイスホッケー部の先輩で、部のOB会長だったので、小児科を始めた時に部のOBの小児科医たちが、いろいろ質問したがすべてに正しく答えたので、その後は誰も何も言わなくなった。先生はその後育児書を書き、医師会に予防接種センターを作り、日本小児科学会の予防接種専門委員会の委員にまでなった。後に日本医師会長になったが、医師会長としての評価は知らないが、医者としてはよく勉強していた。
私自身は、大学における医局講座制度(医師と関連病院の人事を左右している、教授を頂点とする制度)を批判し、小児科の中の細分化された専門家にならず、小児医療全般に浅く広く知識を持つ総合小児科医(小児科総合科医師)を目指してきたので、小児医療(小児内科でなく、子どもの医療全般)を浅く広く知っているが、細かい専門的なことはその分野の専門医に依頼している。
だから私は専門医資格を持っていないし、博士号も持たない。私の腕が勝負である。
予約制の小児科が多いが、私のいた診療所は予約制ではなかった。子どもの病気は、ある日突然起きることが多いので、予約しないと診てもらえないのはおかしいし、私の外来はそれほど混雑しなかった。それは何度も来なくて治るからです。例えば、アトピー性皮膚炎や喘息様気管支炎の乳児なら2~3回、かぜなら1回、気管支喘息なら年数回、大抵の病気は1回で済みました。それは薬だけでなく、予防や食事療法など教えていたからです。最初にいた吹上共立診療所時代には治ってしまうし、予防を教えますから、患者さんがどんどん減ってしまい、経営的には苦労しました。
知識というものは、知っているか知らないかであって、知っていれば100%、知らなければ0%である。知らない医者にいくら聞いても、答えないか、またはいい加減なことを知ったかぶりで言うだけである。専門家やプロの人たちは、素人にやさしく判りやすく説明してくれるものである。よく知っているからそうできるのであって、生半可な知識では上手に説明できない。だから医者に、よく質問することである。答えてくれない医者は敬遠しよう。
医者の言うなりになってはいけない。言うなりではなく、納得することが大切である。医師の言うことに納得したら、医師の言う通りにしてよい。
➂人はなぜ病気になるのか
私は「人はなぜ病気になるのか」について、「人は環境にうまく適応できない時に、その遺伝的に持つ弱点に病気が出る」と考える。この説はアメリカのロックフェラー大学環境医学の故デュボス教授の説で、欧米でも日本でも基礎医学者や精神科医に支持者が多く、臨床医にはほとんど支持者がいません。私はデュボスの本を読んで、病原環境説の方が病気をうまく説明できるし、病気の治療に応用するとうまく行くので考え方が変わりました。この考え方は、「ヒポクラテスへ帰れ」というデュボスの言葉の通り、世界ではネオヒポクラテス学派と呼ばれています。
➃自分自身で健康を維持しよう。
自分で自分の健康を守ろう。病気を治すよりも、病気を予防する方がやさしい。
病気にかかった時には、医療技術は医者に学ぶが、実際に治すのは自分であるから、自分で病気を治すようにしよう。薬をもらっても、きちんと薬を飲み続けるのも、食事療法をするのも、リハビリをするのも自分の意志である。
北野(ビート)武に学ぼう。彼は医者にとっては不可能と思われた顔面の麻痺を、信じられない程の努力で治してしまった。彼は、外傷による顔面神経麻痺を、努力して自分で治した。普通では回復は困難と思われる程の神経症状でしたが、毎日毎日自分の努力で、動かない顔の筋肉を動かし、ついにほとんど判らないくらいに治してしまった。始めは顔の一部がピクピクしていたが、それも今はほとんど見られない。私は、その努力をしたというだけで敬意を表する。
医者は、人が豊かな人生を送るためのお手伝いや援助をするだけで、自分の健康を守り、病気を治すのは自分自身である。その為のノウハウを教えましょう。但し自己過信はけがのもと。一度は腕の良い医者に診てもらい、治療法を教えてもらうこと。
2)病気は人間の生物学的過程だけで起きる訳ではない。
①病気は、人間と環境(自然環境と社会環境)の相互作用の中で発生する(病原環境論=ネオヒポクラテス医学)。人間は、他の動物や植物と違って、地球のすべての場所に適応して生きていける力がある。そして人間は、地球の自然環境を変えてきたが、地球が変わると人間も変わっていく。
人は南極も北極も、熱帯も、3000メートルを超える高山地帯にも住んでいます。
人が環境にうまく適応できない時に、病気になる。自然環境に適応できない時も、社会環境に適応できない時にも、病気になる。
ウィルスや細菌に違いがないのに、軽く済んだり重症化したりする違いがあるのは、人間の側に違いがあるからで、その違いは、環境によって人間が変化してつくられたのである。
②人は身体とこころを持つ社会的存在である。
人間は身体とこころ(精神)をもち、社会的に左右される存在である。社会の最小単位は家庭である。社会は地域、職場、学校、民族、国、世界と拡大される。
こころは社会的に左右される。特に赤ちゃんから幼児の頃のこころの成長が、人間のこころを左右する。そして人間の社会的な生活がこころを左右し、それが病気を左右する。一般には物心がつく頃と思われてきたが、記憶にない乳幼児期のこころが人生を決めることが分かってきた。
一般の精神科医や児童精神科医も、記憶にない時代を取り扱わないが、乳幼児精神科医は乳幼児期の心を大切に考えている。特に虐待を受けていると、脳の発達が変化する。でも成長が止まる25歳頃までは、変わることが容易である。それを過ぎるとかなりの努力がないと、人は変われない。
心身共に充実している時には、風邪をひきにくい。身体がいくら充実していても、精神面に問題があると病気になる。
子どもを上手に育てると、病気をしなくなります。「病気をするたびに免疫ができて強くなる」と言うことは間違いです。人間は自然に免疫システムを完備し、それを上手に働かせれば病気をしないし、かかっても軽く済むのです。それを利根川進さんが証明してくれました。利根川さんは「人は1億もの抗原(病原体や異物)に対し、抗体を作る能力を持つことを証明したのです。ウイルスや細菌が入ると必ず病気になると考えている医師が多いですが、そうではなく、その時に体力や抵抗力が落ちている時に病気になるのです。
WHO(世界保健機構)の健康の定義では、「健康とは」「病気でないだけでなく、身体的にも精神的にも、さらに社会的にも調和のとれて完全に良好な状態をいう」
③精神神経免疫内分泌学
こころと免疫の働きが連動していて、さらにホルモン分泌などの内分泌にも影響することが、近年証明されました。ホルモンの働きも免疫と共に、こころと連動することも判ってきたのです。この30年位前からアメリカのハーバード大学の精神科を中心とした「精神神経免疫学」の動きで、ストレスによって免疫の働きが低下することも、動物実験で証明されました。その後ホルモンの分泌も心に左右されることも、動物実験で証明されたのです。
そのために、ストレスがあると抵抗力が落ち、その時に病気になりやすくなる。よく幼稚園や学校の行事があると、その前後に子どもが病気になるのもその例である。インフルエンザにかかるのは、通常10%と言われ、受験などのストレス状態にある子どもがかかりやすい。こころと体の健康を維持していれば、かかることはない。また病気を怖がったり、不安があると病気が悪くなり、重症化しやすい。
◇マウスの実験では、過密の状態で飼うと、妊娠し難く、まばらに飼育するとすぐ妊娠するという。不妊症もストレスが関与しているのである。
◇犬の実験では、ストレス状態におくと病気になりやすいことも判った。
◇重症の火傷を負った時に、病気と闘うように催眠をかけると回復が早いことも判っている。
④自然治癒力。人は誰でも自然免疫のシステムを持っている。
人間には、病気を治す力がある。それが妨げられた時が病気である。
昆虫の研究では、蠅(はえ)の一種は体内で抗細菌、抗真菌の蛋白質を作り、抗ウィルス性や抗がん性の蛋白質も作っていると見られることが判ってきた。進化の過程で自分に有利な機能を落とすことはないから、人間はそれに替わるもっと進んだ生体防御機構を持っていると考えられる。そこから「人間には元々病気を治す力(自然治癒力)が備わっていて、その力が妨げられ、発揮されない時に病気になる。」と考える。この考えだと、宗教によって病気が治ったり、癌の自然治癒なども説明がつく。免疫の仕組みには、自然免疫と獲得免疫がある。
3)文明は人間の病気を発生させた一つの要因である。
人間が自然の中で暮らしている方が病気は少なかった。文明が社会を変え、社会が変わることによって、病気が増えてきた。交通機関が発達するに連れて、地方の土着病が世界的な病気になり、また薬害、公害などが登場してきて、ますます増加している。アマゾンのピダハン族やアフリカのブッシュマン族は、現在でも平等で争いのない社会を作っていて、病気がない。ピダハン族は、外部から隔絶されて守られている。
社会が進むに連れて新しい病気が増える。放射線や発癌物質の増加により癌が増え、人間社会の入り組んだ関係からストレスが増え、精神病、心身症、アレルギー性疾患が増加している。その為先進国の方が病気が多く、医療費が増えて国の財政を圧迫している。
文明は健康を増進させてもくれたが、その武器の一つが医学であるが、武器は医学だけではない。社会が変化したことによって病気に打ち勝ったものもある。
天然痘が撲滅されたことや、伝染病が減少したのは、医学の力と共に、検疫や隔離など社会的施策によることも大きい。結核やライ病の減少は、主に社会的対策による所が大きい。
4)長寿日本一は・・・。日本一の長寿県は長野県です。昔は日本一の医療過疎県、沖縄県でした。
令和三年の平均寿命は、女性87.57歳、男性81.47歳ですが、都道府県別では、女性は長野県が1位、2位は岡山県。男性は滋賀県が1位、2位は長野県。
自然環境や質素な食事が寿命を延ばすのか。
人間の寿命に医療はほんの僅かしか寄与していない。寿命が大きく延びたのは、赤ちゃんや子どもや青少年。江戸時代には五歳までに25%以上が死んでいた。これは現代では難民キャンプの乳幼児死亡率に匹敵する。新生児や乳児の死亡や青少年の死亡が少なくなった分を中心に平均寿命が延びていた。日本の乳児死亡は世界一少ないから、平均寿命も世界一になった。ひと昔前まで、男の子の死亡率が高く、生まれた時には男が多く、20歳では女の方が多くなっていたが、今は20歳でも男が多い。
老人の寿命も延びている。老人は環境の変化に弱く、暑さ寒さの気候の変化や、土地や家が変わったりすると変化について行けないが、冷暖房の普及や住居の改善、また食料の充足や老人の趣味なども広がり、寿命が延びている。しかし、中年の男性を中心として癌、心筋梗塞、脳梗塞などの成人病による死亡が増加し、平均寿命の延びを鈍らせている。
5)健康を守る方法について。
健康を守るには、第一に暮らしやすい社会にすること。それには自分の住んでいる地域から変えていくこと。暮らしやすく、住みやすい町にする。世界の町を見て、住みやすい町にしていこう。なぜなら自分のこころが落ち着くからである。人間は一人だけでは生きていけず、社会があって初めて人間として生きていける。
人間は生まれながらにして、人間ではない。人間に育てられて初めて人間になる。狼に育てられれば狼に、犬に育てられれば犬になってしまう。1990年11月、南アフリカで2年余にわたり犬に育てられていた2歳半の男の子が見つかったが、行動は犬であった。子どもはまず家庭と言う社会で育てられる。そして保育所や幼稚園、地域社会へ出て行き、育っていく。うまくその環境に適応していれれば、病気をしないで育つが、適応できないと病気になる。だから、集団生活に入るとしばらく病気を繰り返すことが多いが、慣れて来ると病気をしなくなる。でも、くよくよしないタイプの子どもは病気をしない。
健康を守る第二は、くよくよしないことである。不安があれば、不安を無くすか、不安を忘れること。これがなかなか難しい。いつも楽しいことを考え、嫌なことは棚上げすること。
第三は、健康に良いと言われることを実践してみること。禁煙、節酒、体重のコントロール、運動など。でも無理せず、健康に悪いことでも、好きでやめられなければやめなくてよい。運動もし過ぎると体をこわす。
第四は、生きがいをもつか、生活の中での楽しみをもつこと。
6)以上に関連したいろいろな感想
◇新生児・未熟児科の医師は、500グラムの未熟児でも救命したりするし、750グラムの未熟児ならそんなに難しくないというのだが、小学生以上になると体も大きいし、薬の量も多いので、診療するのが不安になるという。500グラムの未熟児は大人の手のひらに乗ってしまう大きさである。
ところがその医師が、退院後の指導が上手でない。入院中の医療は世界の最先端を行っているのに、退院後の外来での診療は大きく先進国に遅れている。それは離乳食の指導にある。日本の離乳食は先進国では一番遅い。その為食事が原因でのいろいろな病気が絶えない。指しゃぶり、物をすぐ口に入れる、少食、偏食、過食、甘い物好き、子どもの肥満、食事アレルギーなど食事関連の病気が少なくなく、その多くは適切な離乳食指導で予防できる。
◇ある子どもが、転んで前歯が折れてしまった。近くの歯科(一般歯科)に行ったら、取るしかないと言われたという。母親はちゅうちょしていたが、たまたま風邪で私の所へ来たので見たら、折れ曲がっているがまだついたままなので、これならつくはずだと思い、知り合いの矯正歯科医を紹介した。その結果、その子の前歯はうまくついて元どおりになり、取らずに済んだ。
◇麻酔科が未熟児の呼吸管理をしていることが、余り知られていない。麻酔科は、現代では呼吸と循環の管理が専門であり、痛みをとることもしている科と考えた方がよい。国立成育医療センターでは、院内の呼吸管理はすべて麻酔科医がしている。子どもの麻酔は、どんな麻酔でも全身麻酔がよく、麻酔科専門医に任せた方がよい。麻酔に大きい小さいはない。心臓の手術でも、扁桃摘出の手術でもすべて同じ麻酔である。
◇麻酔科の専門医制度が信頼されているのは、きちんとした教育のシステムと専門医試験の公正さにある。元々麻酔科は、アメリカでの教育を受けてアメリカの専門医の資格を取った医師が日本へ戻り、各大学の麻酔科教授になって、日本の麻酔科を作った歴史がある。それで、アメリカの教育システムを導入し、専門医試験も私的感情を入れずに判定する仕組みが作られて維持されている。それで信頼されている。
日本の他の学会の専門医や認定医は、博士号と同じで、適当に作られ、資格を持っていると言っても信頼できない。教育のシステムができていないのでペーパーテストに偏りやすい。
◇小児外科医は、離乳食も知っているし、子どもへの注射が一番うまい。それは新生児外科が多いし、入院する子どもの全員に注射点滴をするから、注射点滴が上手になるのである。大人と違って子ども特に乳幼児、さらに新生児未熟児の注射点滴は至難で看護師にはできない。未熟児科医師は500グラムの未熟児にも注射点滴をする。大人用よりも極めて細いと言っても、未熟児の血管の太さより太い注射針を血管に入れるのであるからすごい。若い時にしかできない技術である。
◇私は、今までの実績から国立成育医療研究センター、都立小児医療センター、埼玉県立小児医療センターや各府県の小児医療センターに紹介している。しかし、開業の医師を紹介することもあるが、私が信頼する医師だけである。紹介するのはすべて医師個人が対象であるべきだが、最近はなかなかうまく見つからず、次善の病院へ紹介せざるを得ない時もある。
◇私の後輩に、優れた内科医がいて、先輩を追い越して内科講師になり、40代で某大学の内科教授になったのに、突然辞めて開業してしまった。内科はどこの大学でも、トップクラスがいく科であり、内科教授にはなかなかなれない。(私の同級生でも、定年まで内科助教のままの人がいた)私が信頼する後輩であったが、何があったのか、教授を辞めて開業してしまった。彼が開業した土地の人は、期せずして優秀な内科医に診てもらうことになったのである。一般には、教授が良い医者とは限らないが、開業医の息子であったから上手にしていると思う。周りの住民は幸運である。
◇小児科の先輩で、慶応の講師から愛知県の私立大学の教授になった人がいた。しかし、赴任すると当初の約束と違って、研究設備はほとんど揃っていないし、外来を毎日させられるし、一番怒ったのは連れて来た自分の弟子の研究ができないことであった。しかし、それでも我慢していたが、丁度その時に名古屋大学小児科教授が退職するので、後任の教授選が始まった。たまたま名古屋で開業していた慶応の先輩が、兄弟が名古屋大学の小児科を出ていたので、実績や人柄から名古屋大学小児科の教授に推薦し、名古屋大学も受け入れて最終選考にあたって母校の推薦状が必要になった。ところがなぜか慶応小児科教授が推薦状を出さなかったので、最終選考からはずれてしまった。 彼は激怒して、勤めていた大学教授の職を辞めて開業してしまった。その後某私立医大の客員教授になった。ところが、その反響はどうかというと、善し悪しは半々であった。何故なら、小児科の教授を定年退職した後の就職先がないことが多く、現役時代はよくても退職後は惨めになることが少なくないからで、開業だったら年齢に関係なく自分の働けるまでできるから、その方が良かったという声が教授クラスに少なくなかったという。
◇一般に医師は、診断や治療が難しい病気はよく勉強するが、日常にありふれた病気や自然に治ることの多い病気は、軽視して勉強しないことが少なくない。だから難病や癌は日本やアメリカの専門書を読んだりするが、風邪やインフルエンザ、胃腸炎などの診断や治療がおろそかになっていることが多い。診断や治療が適切で無くても、患者の方が自然に治ってしまうから、医者に反省させることがないからである。
これはどの科でも同じである。小児科以外の科は、主に大人が対象のため、子どもの扱いも、子どもの病気の治療も上手で無いことが多い。どうしても大人の治りにくい病気の治療が主で、子どもの病気が軽視される。
例えば、蓄膿症(副鼻腔炎)、滲出性中耳炎、斜視、弱視、包茎、亀頭包皮炎、とびひ、水いぼ、蕁麻疹、アトピー性皮膚炎など。
耳鼻科では、耳鼻科医と小児科医向けに、小児耳鼻科の本が出ているくらいである。
内科医に子どもがかかった時の問題点は、すぐ解熱剤やステロイドの内服を使う医師が多いこと。子どもの病気を充分には知らないから、説明が不十分だし、診断も当てになら無いことが少なくない。特に突発性発疹、風疹、おたふく風の診断があてにならない。
小児科医でも、一般に嘔吐下痢症の治療が下手である。私の知人の小児科医の中には、診察室の隣に点滴部屋というのを作って、6ベッドも置き、多いとそこが満員になるくらい点滴をしているという。私の診療所で大人も含めて最大で同時に点滴をしたのは二人で、子どもの点滴は滅多にありません。他の医者は嘔吐の初期治療が下手なので、脱水にしてしまうからである。それを私はマッチ・ポンプだと思っている。(マッチで火をつけて、その火をポンプで消すこと。政治家を揶揄する例えから来ている)
◇知識というものは、丸い球の様なもので、知識が少ない時は、球は小さくその表面積は少なく、知らないことも少なく、知識が増えると、球が大きくなると表面積も広がって、知らないことも広がる。知識が少ないと、何でも知っている気持ちになり、知識が増えるとほんの僅かしか知らないという気持ちになり、謙虚になる。
◇こころと身体はメタルの裏表である。こころが動けば、体も動揺する。体の具合が悪ければ、こころも健康ではなくなる。
◇アメリカの医療の標準化とは、例えば時差が3時間ある東海岸から西海岸へ移っても、同じ治療をするから、看護師は就職してもすぐ翌日から、何年も前から働いていたかのように、仕事ができる。アメリカは看護師も専門化し、自分の専門の科に勤務することが普通である。だから手術室の看護師は手術室に勤務する。しかも地域や病院や医師が替わっても、手術の方式も、注射や投薬の仕方も、伝票の形式も同じになっている。病院ごとの違いや、医師が変わると方法が変わるというような日本とは全く違う。だから就職の翌日から、他の同僚と同じように仕事ができる。
その背景には、専門医制度の確立と医療保険制度の違い、それに消費者運動の要求と盛り上がりがある。専門医制度は、一般に4年くらいだが、日本の十年に相当するくらい密度の濃い勉強と経験を積むことができるシステムになっている。
医療保険も任意加入制が中心で、手術もいろいろな病気の治療も、病気ごとにこのレベル以上の医師というような条件があり、ほとんどの手術は専門医でないとできないし、その方法も決められていることが多い。その条件を満たさないと、保険金の支払いが得られないので、みなそれに従うことになる。
消費者運動もラルフ・ネーダーを中心に活発で、議会対策も行われ、医療費が高いことからも、医師に対する要求が強いと思われる。
◇腕の良し悪しは、かかって見なければ判らないのが、日本の現実である。アメリカでは金を出しさえすれば良い医療が受けられるが、日本では金を出しても最高の医療が受けられる保証はない。大学教授であっても、良い医師とは限らないのが日本の現状である。私の同級生もかなりいろいろの大学の教授になってはいるが、私がかかりたいと思う人はわずかであり、だから紹介しない。私が出身は慶応でも、慶応に紹介しないのは信頼できる医師が少ないことと、いても遠いことである。
◇しかし慶応小児科の松尾名誉教授は信頼できる人で、若い時から優秀でひらめきがあり、私の小児科医になりたての頃に教えていただき、私の医療技術と医療理念の形成を大きく左右した人で、慶応小児科から干されていた時にも分け隔てなく応援してくれた人です。
私が、子どもが病気になった時に、安静も栄養も保温も必要ないと言っているのは、実は松尾名誉教授が卒業後四年目頃に言っていたことで、私はその時小児科1年目で、それに感心してその後ずっとそれでやって来たが、本当にその方がうまくいくので続けている。
当時松尾先生は、小児科の看護師の病棟主任が小児看護の本を書いていた時にその医学面のチェックを頼まれて、その文の中の「安静、栄養、保温」という言葉を全部削除していた。その時それがアメリカの文献に裏打ちされていることを知ったのである。
◇札幌の麻布脳外科病院の話がNHKテレビで2度放送されたが、ほとんど全身麻痺で植物状態と思われる患者さんを受け入れて、ほんの僅かに残されている機能、例えば目を動かすことや口を開けることなどを使って、話しかけたり、紙に書いた字を見せたりした、それに対する返事をイエス・ノーで答えさせ、意思の疎通をはかって、リハビリをさせ、努力して体を動かすようにさせ、半年1年かかって車椅子で生活できるようにさせ、驚異的な回復をさせる。この時の病棟の師長はその後筑波大学教授になりました。それを指導した院長を始め脳外科の医師たちも大したものである。
◇だから私は、脳死をもって人の死とすることに異論がある。生きる意思があるから生きているのではないのか。それが外から判らないだけではないのか。
と言うのは、私の経験では、意識がなくなると急速に抵抗力が落ちて、外からの細菌やウィルスに対する感染を起こしやすくなり、死に到ることが多い。
またいろいろな事故や遭難事件での生存者に共通することは、生きることに対する執念であった。こんなことでは死ねないという一念が生還に繋がるのだと思う。「もうだめだ死んでしまう」と思う人は、すぐに死んでしまいやすい。
◇気管支喘息で突然死があるが、ある心療内科の医師の話では、パニックになるからだという。パニックになって、「呼吸が苦しい、呼吸が止まってしまう、もう死んでしまう。ああもうだめだ。」とどんどん悪化し、呼吸が止まってしまうのだという。確かに乳児は別にして、幼児の突然死は少なく、年齢が高くなるに従って突然死が増え、成人になってピークになる。子どものパニックは、母親がパニックになるとなるようで、母親が冷静になって子どもを励まし、必要なら救急病院へ連れて行くようにすると突然死にはならない。


















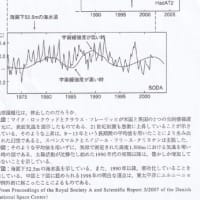
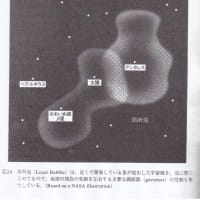






※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます