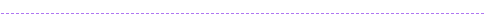農村の家の味噌汁は、「汁」であり「おかず」だった。
汁よりも「具」が主役だった。
イモや団子やアサリや河豚や麩や、いろんな野菜も入っていた。
味噌汁を作るのは母であり、
味噌を作るのは父母で、
麹を作るのは母、
大豆を作り、米を作るのも父母だった。
味噌作りで購入品は塩だけ。
味噌作りの日は天気のいい日で、
餅を搗くのと同じように、父母は木臼で味噌をつくった。
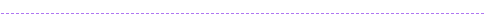
「岡山の食風俗」 鶴藤鹿忠 岡山文庫 昭和52年発行
味噌
味噌の原料は、米の麹、大麦の麹、裸麦の麹で、
大豆と塩を用いる。
麹は納屋の土間に青草を敷いて、そのうえに蓆(むしろ)を敷き、
蓆に大豆、膚麦、麹のモトをまぜて、ねさせる。
麹を作るのに技術がいる。
笠岡市吉田では秋の彼岸に搗く。
南部地方では味噌は六十日味噌といって、60日すると食べ始め、翌年また新しい味噌を作って食べる。
吉備高原地方では三年味噌といって3年経過した味噌を重宝がる。
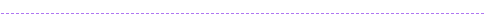
「金光町史民俗編」 金光町 平成10年発行
調味料
味噌は手作りであったが、醤油、酢、塩、砂糖、油など味噌以外のものは購入した。
また、だしの材料となる煮干しは年中切らしたことはなく、普段のおかずの味付けは、味噌と醤油が中心であった。
味噌
米味噌と麦味噌の両方が作られていたが、終戦後の農地改革で米が比較的自由に使えるようになってから、だんだんと米味噌中心になった。
寒に作った方がカビが生えないといって、味噌作りは主に冬の仕事であった。
庭が上がったら(米の収穫が終わると)すぐに味噌を作った。
米味噌には、小米を使うことが多かった。
まず、米か裸麦を蒸し、麹の素を混ぜ紙袋に入れた。
藁で編んだおひ つに入れてコタツに入れたり、風呂の湯を沸かし、蓋の上へおいて温度を上げ、麹を作った。
また、青草のある時期には、刈り取った青草の上に筵を敷き、
蒸した米を広げて上に筵をかけて家の中の風が当たらないところに置き、
青草の発酵熱を利用して麹を作ったこともあったという。
麺は味噌の花とも呼ばれた。カビがここまでという時に塩を混ぜ、カビがこれ以上生えるのを止めた。
次に味噌用の五升も入る平釜で大豆を炊き、麹と豆と塩を混ぜて搗いた。
麹と豆と塩は同じ量だけ三つ山にして混ぜた。
昔は腐らないように塩は 三合塩でからい味噌であったが、今は一合から一合五勺程度である。
一斗も入る味噌瓶に二つも三つも作った。
大きなしゃもじでしっかり詰め込み、風が当たらないように新聞紙で覆い蓋をした。
三年味噌といって 三年経ったものから食べていったが、三ヵ月から半年ぐらい経つと食べる家もあった。
味噌がなくなった家ではまだ花のにおいがするころから食べた。
味噌搗きは一日がかりであったが、日が経つにつれだんだん甘みが増し、家で作った味噌が一番おいしい。
高度経済成長期以後、各家での味噌作りはだんだんと廃れていった。
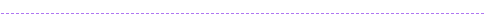
「鴨方町史民俗編」 鴨方町 昭和60年発行
日常のおかず
味噌
かつては味噌で味付けをすることが多く、また、おかずでもあったので、重要な調味料であり、保存食であった。
原料は、大豆と裸麦の麹・塩である。
いっちょう(一畳)台の上へ莚を二枚敷く。
そこに蒸した裸麦を移し広げる。タネといって麹菌を加えてまぜる。
上へ筵をかけてねかせる。
大豆を風呂または釜で煮て、からうすでついてつぶす。
これに裸麦の麴をまぜる。
両手でもみほぐしながらまぜ、味噌樽に仕込む。
一年に一回、春秋の彼岸ごろにつく家が多い。
気温の上から、麴をねかせる(発酵)のに骨が折れない。
60日味噌といって、味噌の仕込みをして60日たつと食べられるというが、一年たって食べ る。
味噌つきをして三年経過したものを三年味噌といい、三年味噌はおいしいという。
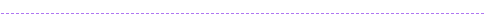
「聞き書 広島の食事」 神田三亀男 農山漁村文化協会 昭和62年発行
味噌
味噌は、毎日つくる味噌汁に欠かせない。
そのほか、あえものに使ったり、いりみそ(味味噌)をつくったり、漬物と一緒に焼いたりと、なくてはならないものである。
家族でつくる家が多い。
味噌も醤油も買って食べる人はいない。
毎年仕込むので、味噌倉には三、四本の味噌樽が並んでいる。
長くおくほどよい味になるといわれ、三年から四年おいて、あめ色になったものを自慢する。
醤油も毎年仕込み、一番醬油、二番醬油としぼる。
醤油 の実も、ふだんよくごはんに添えて食べる。
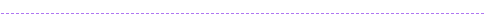
「岡山県史第15巻民俗Ⅰ」 岡山県 昭和58年発行
味噌の原料は大豆で、中国山地では米、吉備高原では大麦、南部地方では裸麦の麹を用いた。
笠岡市吉田では、裸麦を甑で蒸したものをネサシてハナ(麹)を作る。
ハナ作りは納屋の土間に青草を敷いて、その上に蓆を敷き、蓆に大豆・裸麦・ハナのモトをまぜてネサセル。
青草のクミ(発酵)の熱を利用する。
大豆は平釜で煮る。
大豆の煮え具合は親指と小指でつぶしてみて、よくつぶれたらよい。
塩の割合は、三合塩といって 裸麦のハナ一升に対して塩を三合いれる。
ハナは大麦のほか、大麦に小麦粉をまぜるとか、小麦だけでハナを作ることもあった。
ハナも自家でネカシていたので、春・秋の彼岸ごろに作れば温度をかけなくてもネルので楽である。
秋の収穫後とか、十二月下旬の正月用の餅搗きのあと搗くことが多い。
寒水で搗くと、味噌が痛まなくてよいということもある。
寒い時期にハナをネカセルのはむつかしい。
ハナは蓆にいれ、炬燵でネカセタという。
南部地方では味噌は六〇日味噌といって、六〇日すると食べ始め、
だいたい誕生(一年) 味噌を食べ、翌年また新しい味噌を作る。
たいていの家に四斗樽二本を用意していて、一年で一本食べ終わると、
もう一本の樽のを食べ、空いた樽に新しい味噌を搗く。
かつて、味付けは醤油よりも味噌の方が多かったので、重要な調味料であった。
飯にそえておかずとし、また、焼き魚などつけて食べる。
「味噌がくさる」とかいって、味噌にまつわる縁起は多い。
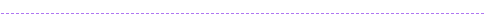
「江戸の町くらし図鑑」 江戸人文研究会 廣済堂 2018年発行
味噌。発酵食品の大関。
昭和の頃、《塩分は健康の敵》 とばかりに嫌われ、塩分の多い味噌も醤油も漬け物も、悪者にされましたが、
平成になって塩分が単純に高血圧の原因だということが誤りだと、医学的に証明されました。
古来の知恵を見てみましても、味噌が身体に良いことが、いろいろと書かれています。
江戸前期の『本朝食鑑』では特に味噌の効能が語られます。
一:味噌は昔から朝夕に食べ、粗食の補助食である。
二:味噌は一日もなくてはならない食品である。
三:大豆の甘さや温かさは、気を穏やかにして、血を生かし百薬の毒を消す。
四:麹の甘みと温かさは胃のつかえを取り、消化を助け、詰まりを正す。
五:元気をつけて、血の巡りをよくする。
六: 髪を黒くし。肌を潤す。
江戸中期の『養生訓』でも、「味噌の成分は身体に優しく、胃腸の動きを補う」と、これもまた肯定的に書かれています。
そればかりか、国立がんセンターの研究では、味噌を毎日飲む人は50%も、
胃がん、心筋梗塞、肝硬変になる確率が低く、
厚生労働省は毎日三杯ずつ飲む人は乳がんの発生率が40%減少するとしています。
また、高血圧防止に役立つペプチドが含まれ、血圧を下げる効果もございます。
さらに、放射能による康被害を抑える効果も、見出されています。