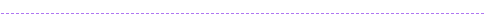高校生の時、クラスにとびきり美人の同級生がいた。
美人なので、その人に思いを打ち明けることは(絶望的な結果しかないので)思いも及ばず、ただ憧れの雲の上の存在の人であることで満足していた。
ある日、国語(古文)の授業で「今昔物語」があり、
男性の先生が、
「今昔物語にはいろいろな説話が載ってあり、その一つをこれから紹介します。」
それが「平中が侍従の君に懸想した話」だった。
先生が授業中に密かに笑う声がおこった。
男子生徒が2~3人、
女子生徒も2~3人。
途中で笑う声が1人、2人とさらに増えて行った。
我が憧れの君からは笑い声が漏れなかった。
当然だと思った。
こういう話は彼女には縁のない、
もともとあり得ないことだから、と至極納得し、かつほっとしていた。
けれど、やはり、なにか、それも違うのでないかとも思った。
あのとき、彼女の表情はどうだったんだろう?
内心、だまって笑いをかみ殺していたのだろうか?
旅の場所・京都市上京区・京都御苑
旅の日・2017年2月15日
書名・「今昔物語」
原作者・未詳
現代本・「今昔物語・宇治拾遺物語」 世界文化社 1975年発行
訳者・古山高麗雄

平中が侍従の君に懸想した話
むかし、兵衛の佐平定文という人がいた。通称を平中といった。
人品賤しからず、容貌風采うるわしく、物腰、話術も優雅であり、当時、第一等の美男子であった。
それほどの男だから、人妻、娘、まして宮仕えの女房で、 言い寄れない者はいないという。
その頃、本院の大臣で藤原時平という人がいた。
その屋敷に、侍従の君と呼ばれる若い女房がいた。
眉目容姿まことに美しく、心ばえすぐれた女性であった。
平中は、常々、本院の大臣の屋敷に出入りしていて、 この侍従の君の噂を聞いていて、 年来、 心のたけをつくして言い寄ったのだが、ままならぬ。
侍従の君は、恋文を送っても、返事をくれないのである。
平中は、なんとかして、
あの女のいやらしいところを聞いて、うとましい女だと思う心を持ちたいと思った。
そうだ、と気がついた。
君がいかに才媛であろうとも、おまるに入れる物は、われわれと変わりはない。
それを手に入れて玩弄すれば、銀蔵を感じて、未練も断てるだろう。
そこで、平中は女の童が、侍従のおまるを洗いに行くところをねらって、奪い取ることにしたのである。
すると、年は十七、八で、容姿端麗、薄物で、濃い紅の袴をしどけなく引き上げた女の華が、
香染めの薄物におまるを包んで、赤い色紙に絵をかいた扇で顔を隠して、女の局から出て来たのであった。
平中はそれを見て、しめたと思い、見え隠れにあとをつけて行き、
人のいない所を見すまして、走り寄って、おまるを奪う。
女は、泣いて抵抗したが、容赦なく取り上げて逃げて、人のいない部屋に駆け込んで、掛金を掛けた。
奪ったおまるは、金漆塗りであった。
なんともみごとなおまるで、開けるのがもったいないくらいである。
中身はともかく、おまるについては、他の人のものより格段に立派である。
開けて幻滅を感じるのが惜しいような 気になって、しばらくはそのまま鑑賞していたが、
いつまでもこうしてはいられないと心を決めて、そっと、蓋を開けてみた。
丁子の香が、ぷんと匂った。
これはどうしたことか。
平中が、首をひねっておまるをのぞき込むと、淡黄色の 水が半分ほど入っている。
その中に、親指ぐらいの太さで、長さ二、三寸ほどの黒ずんだ黄色の物が三切れほど、転っている。
これが、女の糞だと思って眺めたが、匂いがよすぎるので、木片で突き刺して、鼻にあてて嗅いで みると、
なんとそれは、馥郁たる黒の香であった。
考え及ばぬにくい仕業であった。並の女ではない。
そう思って、それを見るにつけても平中は、侍従の君とねんごろになりたい心が、またも燃えさかるのであった。
おまるを引き寄せて、少し、すすってみた。
丁子の香が染みわたっていた。
木片に刺して取り出した物の端を、少し舐めてみた。
苦くもあり、甘くもあり、香ばしさがこの上もない。
なにからなにまで、心の行き届いた女ではないか。
尋常の女ではない。
ああ、なんとかして、思いを遂げたい。
と悶々としているうちに、平中は病気になり、悩みに悩んだあげく死んでしまった。
益なきことだ。
女には、やたらに夢中になるものではない。
と、世人は、くさしたということである。 (巻三十第一)