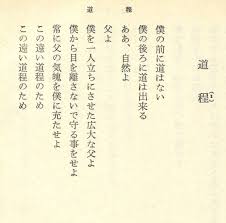カーテンを開け、外に目を凝らすと霧雨であった。
まだ明けやらぬ6時少し前。おまけに雲に覆われた空は薄暗い。
霧雨は見えるか見えぬほど、音もなくあたりを包んでいた。
それでも庭木は濡れそぼり、しずくが葉っぱを転がり落ちている。
夏は去り、季節は移ろう。
そう言えば、あの日もこのような天気だった。
まだ小学生にもなっていなかった頃、八つ上の姉は
僕を抱きかかえるようにして一本の傘で霧雨を避けながら、
路面電車の停留所近くにあった一軒の家に僕を連れて行った。
出迎えたのは母だった。母はなぜ、
父や僕たち兄弟姉妹が暮らす家とは違うところに一人いるのだろう。
かすかな、たったこれだけの記憶で、小学生も高学年になると、
父と母は一時期、別居していたのだということが分かった。
ただ、どんな理由だったのか未だに知らない。
兄や姉たちが、「実はこんなことがあってね」などと
教えてくれるはずもなく、兄や姉にしても
寂しくて、悲しくて胸を痛めていたに違いない。
姉が僕を母さんの所に連れて行ったのは、
自分も母に会いたさに父には内緒で僕の手を引いたのではなかったのか。
思えば父と母はあまりにも境遇が違う者同士だったと思う。
父は官立の高等商業学校、今で言えば国立大学の経済学部の出身なのに、
対する母は、定かではないが尋常小学校、
あるいは高等小学校の出だったのではあるまいか。
仮に恋愛であったのであれば学歴は関係ないことだと言えなくもないが、
それでもどんな出会いであったのか想像するのは難しい。
また父方は天理教、母方はキリスト教だ。
宗教が違う者同士の結婚は、ややこしい障害がいろいろあったはずで、
二人が結婚した時には、父がキリスト教に転宗し、
母以上に熱心なキリスト教信者になっている。
その時、父には何の咎めもなかったのだろうか。
そう言えば、父方の祖父母はもちろん、その親族をほとんど知らない。
面識があったのは父の弟唯一人だった。
もう一つ。これは笑い話みたいなものだが、
父はまったくの下戸なのに、母方は酒豪の家系だ。
母もそうで、夕食時の食卓に杯が置かれるのは母の席だけだった。
母の兄や弟がよく我が家に遊びに来ていたが、
父は笑顔を作って出迎えたものの、酒席の長さに癖癖した表情を見せたりした。
そんな違い過ぎるとも思える二人が、
どのような縁があり結婚することになったのか。
そして二人の結婚生活には何の問題もなかったのであろうか。
僕には知りようのない父母の〝秘密〟である。
平成七年だったから、母が逝ってもう二十七年になる。
八十四歳だった。
母の葬儀の日の写真が、A4の紙を半分に折ったものよりやや小さい
角形7号の、茶の封筒の中にあった。
僕の若い頃のモノクロ写真が五十数枚、実に無造作に入っており、
葬儀の写真はその中に紛れ込んでいた。
この写真には、父はすでにない。
長男、次男、それに長女、次女、そして末っ子の僕、
五人の兄弟姉妹が並んで写っている。
僕の二つ違い、三男の兄だけがいない。
彼はすでに母より五年早く他界していた。
五十歳ちょっと手前の不幸だった。
一人欠けているとはいえ兄弟姉妹が一緒に写っているものは
おそらくこの一枚だけだろう。
母の葬儀というのに、なぜか皆笑顔である。
今、マリア像の横に置かれた写真の母も柔和な笑みを浮かべている。
生きていくことの辛さや悲しさとはおおよそ無縁と思える、
ぽっちゃりとしたかわいい顔だ。
さだまさしは『無縁坂』という曲の中で、
「(母には)悲しさや苦しさはきっとあったはず。
(でも、それらを) すべて暦に刻んで流してきたんだろう」
と歌っている。
母もそうではなかったのか。
父とは一時別居はしたものの、すべて暦に刻んで流し、
別れることなくいてくれた。
僕たち兄弟姉妹にとって、それは何よりの幸せであった。
二人は今、同じ墓の中で一緒に暮らしている。
仲良くしているだろうか。
「末っ子が余計な詮索はよしなさい」母が苦笑しているかも知れない。
母の晩年、五年ほどは病院暮らしだった。
脳梗塞から始まった。
症状は軽く、言葉もしっかりしていたし、
体もさほどのダメージを受けていなかったのだが、
どうしたことか入院中に転倒し、大腿骨を骨折してしまったのである。
年寄りが足腰を骨折すると、それが引き金となって
寝たきりになるとよく言われるが、その通りであった。
母を見舞ったある日。その日はちょうど昼食時だった。
歩けないのでそのままベッド上で食事をしようとしている。
母の側に寄り、ベッドの端に少しだけ尻を乗せた。
おかゆみたいな流動食、それをスプーンで母の口に運んでやった。
すると、それを見た看護師が「やめてください」と咎めるのである。
「なぜ?」と語気を強めた。ささやかな孝行を邪魔された思いだった。
「手助けすると、もう自分では食べようとしなくなりますよ」
……母の手を取り、そっとスプーンを握らせた。
他に悪いところはなかったが、日に日に衰えていくのが分かった。
おまけに認知症みたいな症状も出てきた。
病室に入り顔を見合わせると「遠いところをよく来てくれたね」と、
福岡から入院先の長崎まで高速道路で二時間かけてやって来た僕を
労ってくれるようなことを言うので安心したら、
その後の会話は誰と話しているのか、
まったく分からないものになってしまう。
唖然とし、そしてたまらず、「トイレへ」と飛び出すように
病室のドアを開けたとたんに涙が零れ落ちた。
「もっと見舞いに来てあげたらよいのに……」そう言う妻には、
「そうだね」と気のない返事を繰り返すだけ。
そんな母を見るのが忍びなかった。
何とか笑顔を戻し病室に入った。
すると、母の人差し指が僕の額の方へすーっと伸びてきた。
でも途中で力をなくした。ポトリと落ちるのと同時に、母は目を閉じた。
それから一カ月ほど後だったろうか、
「おふくろの状況があまり良くない。
医者が状況を説明するらしいのでお前も来てくれ」長兄からの電話だった。
僕を待ち構えたように医師は、
右半分が真っ黒の母の頭部のレントゲン写真を見せた。
「そんな切ないものを見せないでほしい」心中そう叫んでみても、
医師は素知らぬふうに「一年後かもしれないし、明日かもしれません」
そう冷たく告げたのである。その悲しみは一週間後のことだった。
一歳になるかならないか、泣きじゃくる僕を母は膝に乗せ、
抱きしめるようにあやしている、あの写真はどこにあるのだろうか。
封筒の中にはなかった。
記憶に残る幼児期の写真は、あれだけだというのに
二度と見ることは出来ないのか。
おそらく、母の手元にあったに違いないと思うが、
亡くなった際、家財道具を整理するのに取り紛れてしまったのかもしれない。
あるいは母が胸に抱いて持っていったか。
少しばかりの寂しさはあるが、でも、あの写真の情景は、
八十歳となっても、母の温もりをしっかり感じさせてくれている。
少し大きくなった小学二年生の、ある真夏の昼下がり、
遊び疲れ倒れるように畳に寝そべった僕の傍らに座った母は、
今度はうちわで風を送りながらこう言った。
「子どもはね、親を選んで生まれてくるのだそうよ。あなたは私を選んでくれたんだね。本当にありがとう」
そして、こう続けた。
「ほれ、眉が下がっているよ。眉が下がっていたら男前が落ちるからね。
指を湿らせ、それで眉をぎゅっと上げなさい」
髭を剃ろうと鏡を覗き込むと、母がすーっと出てきて、
人差し指を眉に向かって伸ばしてくる。
鏡に映したわが顔をしげしげと見つめてみると、
確かに長く伸びた眉が二、三本あり、それらがたらりと垂れている。
シワ、シミに加えて目尻が下がり、おまけに眉が垂れてくると
人相はやっぱり老人そのものである。
小さい頃は、母に言われるままに指を湿らせ横に引くと、
眉は一文字に近くはなった。だが今はもう、あの頃とは違う。
同じようにやってみても、そうはいかない。
でも、母は今もしつこい。
「ほれ、ほれ」と人差し指を伸ばしてくる。
幼い日に戻り指先を舌で湿らせ、眉を横にきっと引いた。