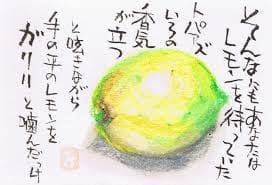オリンピックの熱戦にも劣らぬ激しい戦いだ。
10時に開店したばかりの近くのスーパーマーケット。
その野菜売り場の一角が戦いの場だった。
おそらく、朝刊のチラシを見て駆け付けたのであろう
奥さんたちが早くも群がっている。
目当ては「詰め放題100円のキュウリ」だ。
我が家もこの道にかけては腕に自信の妻を参戦させた。
と言うより、妻自ら望んで駆け付けたのである。

さて、ビニール袋に何本のキュウリを詰め込めるか。
隣に陣取った奥さんは、早くもぎゅうぎゅうに詰め込んでいる。
シニア、シルバー世代の女性の、
こうしたことに対するパワーは凄まじい。
これでもかこれでもかとばかり、キュウリを詰め込んでいく。
「今、何本ですか」と尋ねれば、
「えーと」と数え始め、「15本ね。まだまだ」。
さらにキュウリが気の毒と思えるほど
隙間にぎゅうぎゅうねじ込んでいく。
そこに店員さんがやって来て、
「手で押さえてレジまで持っていけるものもOKですよ」
そう言われて、「それでは」と一層熱を上げ、
その結果、ビニール袋からこぼれ落ちそうになっているものまで
手で押さえてレジまで持ち込んでいた。
なんと21本ゲットされていた。

こちらとて負けてはいられない。
妻の手さばきがスピードアップする。
「18本までなんとか入ったわ。
あとは、手で押さえてOKのものを何本足せるか」
妻もオリンピック選手並みに最後の力を振り絞る。
「やった! 22本になった」見事な金メダル。
意気揚々と我が家に凱旋だ。
だが、待てよ。
こちとらは、キュウリが大の苦手なのだ。
絶対に食べない。
それなのに、これほどのキュウリを一体どうする気だ。
もちろん、妻は知っている。
そして、唯一の例外があることも知っている。
しば漬けだと何の苦もなく、むしろ美味しく食べられるのだ。
その夜、妻のしば漬け作りが遅くまで続いた。
こちらは、オリンピックのテレビ観戦である。
いやはや、ご苦労様。
そして、ありがとうございます。