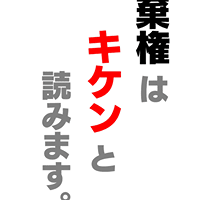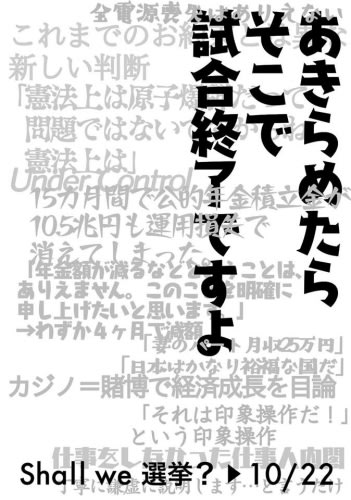10月14・15日に出かけた京都旅の二日目は、千本釈迦堂大報恩寺と相国寺の見学です。
今回私を京都に誘ってくれたサライ秋の特集号には、国宝展と共に‘歩けばわかる応仁
の乱’という記事がありました。文化財の宝庫たる社寺仏閣だらけの京都を一面の焼け
野原にしてしまった応仁の乱。
勃発したのが1467年としか記憶はありません。サライによれば室町幕府の管領職につく
事ができる三家の内の畠山家の家督争いがはじまりで、それが当事者を補佐する細川勝
元・山名宗全の対立につながり、都に居た多くの守護大名を巻き込んで10年に及ぶ戦乱
の世に突入していったのだそうです。
一日で全ては歩けませんから、精選して2か所に絞りました。
まずは千本釈迦堂大報恩寺、時間を有効に使いたいのでタクシーで一目さんに向かい
ました。下ろされた千本釈迦堂の石塔のある参道から向かう山門は意外に小さいです。

当時は現在の10倍もの広さがあり、境内にはイチョウやクスノキが鬱蒼とするほど植え
られていて、それが防火の役目を果たし戦乱の京都市内で唯一焼失を免れたそうです。
鎌倉時代創建の儘の本堂は国宝に指定されています。端正で美しいです。
↓撮り忘れたのでネットからの借用写真です

ここで見たかったのは↓これ、戦乱の刀傷や槍・弓矢の痕です。斜めに走っているのが
刀傷、小さな穴が弓矢の跡、深く大きな穴が槍の跡だそうです。一説によると、元は
外部に合ったこの柱、解体修理のときに堂内に移されたとも云われています。長い時間
の中で風化してはいますが、激しい戦闘がまさにここであったことがわかりますね。

戦乱に巻き込まれなければこうして何百年、千年と残っていく貴重な文化財を、一瞬に
焼失させてしまう戦、なんて愚かなことなんだろう・・・。
創建当時の逸話からおかめ信仰発祥の話も興味深く楽しめましたが、何といっても見忘
れてならないのは霊宝殿に安置された仏像たちです。定慶作の六体の観音像、快慶作十
大弟子像は必見です。とりわけ弟子像のリアルさには驚きを禁じ得ませんでした。思わ
ず離れた所に居た娘に声をかけると、「ホントだイケメンと定評の○○が本当にイケメン
に作られてる!」と喜んでいました。
そして、どうして○○について詳しいのか、私が疑問を持つと思ったか、自身で照れくさ
かったのか、その知識は漫画情報だと打ち明けてくれました。漫画も侮れません^^;
一か所目を見終えて2か所目に行く前に、今宮神社門前のあぶり餅屋『一和』に寄ります。

一皿13本の数字に取りあえず一皿だけ注文しましたが、ほんのり甘いみそ味のお餅
ペロッと行けそうだったので慌ててもう一皿追加、ついでに焼く所も見学させて
もらいました。

年季の入った扇風機で風を送りながら、注文を受けてから手に持ち、火にあぶり焼かれ
る串の先の小さなお餅、創業は応仁の乱勃発よりさらに数百年以上も前と言うから凄い
です!戦乱時には、今宮神社に集まってきた避難民に、このあぶり餅を総出でふるまっ
たのだそうです。
お餅で空腹をしのいで2か所目の相国寺に行きます。ここは応仁の乱の戦跡としては
無論外せませんし、去年紅葉の京都を訪ねた最後に、閉館間近の承天閣美術館をバタ
バタ見学した心残りから是非再訪したかったし、未体験の鳴き龍見学がとても楽しみ
でした。
今出川通りから入って行き山門を過ぎるとすぐ左手に、戦乱の折大勢の西軍が溺れ死
んだという蓮池がありました。蓮はことし韓国のプヨで十分観賞したので、ちら見だけ
で通り過ぎてしまいました。当時よりはかなり縮小されているだろうと思いながら~~。
蓮池から法堂までは松林が続きます。この松林を見て、境内に松林の多い韓国のお寺や
書院を思いだしました。

さて楽しみにした鳴き龍体験、娘が叩いた時は確かに聞こえた気がしたのですが、自分
の時はよくわからず、待っている人に交代しながら何度も挑戦してしまいました。
方丈の前庭

方丈の裏庭

お庭が深山渓谷の様にしつらえてあって、方丈の立派さと共にこのお寺の格式の高さが
思われました。
承天閣美術館、足利三代将軍義満創建の相国寺は金閣寺・銀閣寺を塔頭寺院として抱え
るだけに国宝や重文等沢山の宝物を所持し、ここに展示しています。
茶道をたしなんでいるわけではありませんが、茶道の道具類が多く、意外にたくさんの
お茶碗を見られるのが嬉しい美術館です。
今回私を京都に誘ってくれたサライ秋の特集号には、国宝展と共に‘歩けばわかる応仁
の乱’という記事がありました。文化財の宝庫たる社寺仏閣だらけの京都を一面の焼け
野原にしてしまった応仁の乱。
勃発したのが1467年としか記憶はありません。サライによれば室町幕府の管領職につく
事ができる三家の内の畠山家の家督争いがはじまりで、それが当事者を補佐する細川勝
元・山名宗全の対立につながり、都に居た多くの守護大名を巻き込んで10年に及ぶ戦乱
の世に突入していったのだそうです。
一日で全ては歩けませんから、精選して2か所に絞りました。
まずは千本釈迦堂大報恩寺、時間を有効に使いたいのでタクシーで一目さんに向かい
ました。下ろされた千本釈迦堂の石塔のある参道から向かう山門は意外に小さいです。

当時は現在の10倍もの広さがあり、境内にはイチョウやクスノキが鬱蒼とするほど植え
られていて、それが防火の役目を果たし戦乱の京都市内で唯一焼失を免れたそうです。
鎌倉時代創建の儘の本堂は国宝に指定されています。端正で美しいです。
↓撮り忘れたのでネットからの借用写真です

ここで見たかったのは↓これ、戦乱の刀傷や槍・弓矢の痕です。斜めに走っているのが
刀傷、小さな穴が弓矢の跡、深く大きな穴が槍の跡だそうです。一説によると、元は
外部に合ったこの柱、解体修理のときに堂内に移されたとも云われています。長い時間
の中で風化してはいますが、激しい戦闘がまさにここであったことがわかりますね。

戦乱に巻き込まれなければこうして何百年、千年と残っていく貴重な文化財を、一瞬に
焼失させてしまう戦、なんて愚かなことなんだろう・・・。
創建当時の逸話からおかめ信仰発祥の話も興味深く楽しめましたが、何といっても見忘
れてならないのは霊宝殿に安置された仏像たちです。定慶作の六体の観音像、快慶作十
大弟子像は必見です。とりわけ弟子像のリアルさには驚きを禁じ得ませんでした。思わ
ず離れた所に居た娘に声をかけると、「ホントだイケメンと定評の○○が本当にイケメン
に作られてる!」と喜んでいました。
そして、どうして○○について詳しいのか、私が疑問を持つと思ったか、自身で照れくさ
かったのか、その知識は漫画情報だと打ち明けてくれました。漫画も侮れません^^;
一か所目を見終えて2か所目に行く前に、今宮神社門前のあぶり餅屋『一和』に寄ります。

一皿13本の数字に取りあえず一皿だけ注文しましたが、ほんのり甘いみそ味のお餅
ペロッと行けそうだったので慌ててもう一皿追加、ついでに焼く所も見学させて
もらいました。

年季の入った扇風機で風を送りながら、注文を受けてから手に持ち、火にあぶり焼かれ
る串の先の小さなお餅、創業は応仁の乱勃発よりさらに数百年以上も前と言うから凄い
です!戦乱時には、今宮神社に集まってきた避難民に、このあぶり餅を総出でふるまっ
たのだそうです。
お餅で空腹をしのいで2か所目の相国寺に行きます。ここは応仁の乱の戦跡としては
無論外せませんし、去年紅葉の京都を訪ねた最後に、閉館間近の承天閣美術館をバタ
バタ見学した心残りから是非再訪したかったし、未体験の鳴き龍見学がとても楽しみ
でした。
今出川通りから入って行き山門を過ぎるとすぐ左手に、戦乱の折大勢の西軍が溺れ死
んだという蓮池がありました。蓮はことし韓国のプヨで十分観賞したので、ちら見だけ
で通り過ぎてしまいました。当時よりはかなり縮小されているだろうと思いながら~~。
蓮池から法堂までは松林が続きます。この松林を見て、境内に松林の多い韓国のお寺や
書院を思いだしました。

さて楽しみにした鳴き龍体験、娘が叩いた時は確かに聞こえた気がしたのですが、自分
の時はよくわからず、待っている人に交代しながら何度も挑戦してしまいました。
方丈の前庭

方丈の裏庭

お庭が深山渓谷の様にしつらえてあって、方丈の立派さと共にこのお寺の格式の高さが
思われました。
承天閣美術館、足利三代将軍義満創建の相国寺は金閣寺・銀閣寺を塔頭寺院として抱え
るだけに国宝や重文等沢山の宝物を所持し、ここに展示しています。
茶道をたしなんでいるわけではありませんが、茶道の道具類が多く、意外にたくさんの
お茶碗を見られるのが嬉しい美術館です。