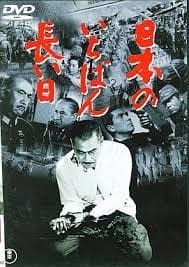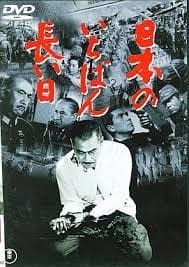
8月15日は終戦記念日ということもあって、
「日本のいちばん長い日」(岡本喜八監督 1967年 東宝)
を観ました。半藤一利のノンフィクションを基に映画化されたものです。
(原作本には大家壮一著とありますが、実際は半藤一利の作品だそうです)
2時間半という長尺の映画ですが、展開が早く、全く飽きることなく一気に見てしまいました。
制作に田中友幸が入っており、初代「ゴジラ」を彷彿とさせます。これを見ると「ゴジラ」はそもそも戦争映画だったのだ、ということが改めてよくわかります。
すごい映画です。
なんで今まで観なかったんだろう。タイトルは知っていたし有名な映画だということもわかっていたのですが、観てなかった。こういう映画まだたくさんあるんだろうな。
これは、昭和20年(1945年)8月の終戦前夜の話です。
正確に言うと8月14日の正午から15日の正午にかけての24時間の物語。
この24時間に起きたことが、日本の運命を決めたわけですから、実際「日本のいちばん長い日」だったことは確かです。
ポツダム宣言受諾については、7月28日に鈴木貫太郎首相が「黙殺」と決めたものの誤訳され連合各国からは「拒否」と受け取られ、この間に8月6日広島、8月9日長崎と二度も原爆を落とされます。
長い議論の末、8月10日天皇の判断により、受諾が決まりますが、正式に決まったのは14日のこと。
受諾に真っ向から反対した陸軍大臣阿南惟幾(あなみこれちか)は本土決戦と徹底的な水際撃滅論を展開し、ポツダム宣言受諾を主張した東郷茂徳外相と対立します。
しかし天皇の英断により、受諾が決定。
「これ以上戦争を継続することは、我が民族を滅亡させることになる。すみやかに終結せしめたい」
「私自身はいかようになろうとも、国民にこれ以上苦痛をなめさせることは私には忍び難い。できることは何でもする・・マイクの前にも立つ・・陸海軍に説得もする・・」
この時の天皇の決断は生半可なものではなかったことがわかります。だからこそ阿南陸軍大臣も納得したのでしょう。
その裏で、秘かに陸軍の若手将校たちがクーデターを企てていたのです。
天皇による終戦の英断、そして玉音放送の準備と着々と終戦準備が進む中、一方では、クーデター計画も進んでいた。
近衛兵(天皇を守る兵隊)である若い将校たちが天皇の英断に逆らって本土決戦に持ち込もうとするのですから、狂気の沙汰としか思えません。
最後まで突っ走った畑中少佐(黒沢年男)の血走った眼は、カルトに洗脳された若者の狂気を彷彿とさせます。
この戦争に負けるわけにはいかない、本土決戦に持ち込んで玉砕するのだ!と叫ぶ畑中少佐のエネルギーのすさまじさ。
彼はクーデターに反対する近衛師団長森中将を殺害し、宮城に向かいます。
2,26 事件の再来が起きようとしていた。
この後半の展開がすさまじく、日本で実際にこんなことがあったのか、と驚くばかりの展開です。
考えてみれば、戦争そのものが狂気の沙汰なので、どんなことだって起こりえるのでしょう。
まして、若い兵士ならなおのこと。子どもの頃から軍国教育を受けて育ち、天皇は神だの国体が大事だのと洗脳され続けてきたのですから、それをいきなり放棄するのは無理難題というもの。
体を張ってでも阻止したいと願うのは当然のこと。それを思いとどまらせることは、陸相の阿南惟幾にもできなかった。阿南は天皇の英断を聞くと、静かに去っていきます。
阿南はクーデターに反対し、不服な者はこの阿南を切れ、と兵士たちをなだめるのですが、兵士たちは聞かず。
心理戦も凄い。阿南陸相はなかなかの人物だったと思われます。玉音放送が決まった後に、彼は切腹します。
まさに武士の生きざま、といったところでしょうか。「切腹」がまだ残っていた、というあたりに非常に前近代的なものを感じます。
良いか悪いかは別として、そうして生きざるを得なかった当時の人達のすさまじさを思います。人ひとりの人生の重みのなんて違うことだろうか。
政府や軍の中枢部にいる人たちは、その配下にいる多くの国民や兵士の命をも代表している・・その自覚の在り様が今とはえらく違うなあとも思います。
畑中少佐は近衛師団長森中将を殺害した後、宮城になだれ込み、玉音放送を録音したレコードを探しますがみつからない。この時レコードが見つかっていたら、今の日本はなかったかもしれない・・
歴史って紙一重のところがあるのだなあ。
あるいは、ひょっとすると、この時クーデターが成功し違う世界線に移行した世界もあったりして・・
それはともかく、15日未明の若手将校によるクーデターは失敗し、15日正午、天皇の玉音放送が全国に流され、日本国民は戦争に負けたことを知らされたのでした。
歴史って、当時の人々には自分事なので切実ですが、こうして時間がたってみると非常に興味深い。
私は父のことをほとんど知らずに大人になり、すぐに実家を出たので、父がどういう人生を歩み、どういう思想を持っていたのかよくわからないところがありました。
父も戦争に行ったので、もしかすると畑中少尉のように過激な思想に染まっていたのかもしれず、あるいはもっと平凡な兵士だったのかもしれません。
私が「ゴジラ」が大好きなのも(おそらく日本人の多くが大好きだと思いますが)、やはり戦争の影響が大きいだろうと思います。
次回は2015年版の「日本のいちばん長い日」を見てみたいと思っています。
《追記》NHKスペシャルで「一億特攻への道」を観ました。その中で特攻について天皇が言われた言葉がこれです。「そのようにまでせねばならなかったか・・。しかし、よくやった」NHKスペシャル、時々いいのやるよね》