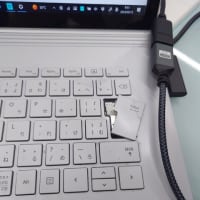おはようございます!
今日も快晴。こういう気持ち良い日々がずっと続けばよいのにと思う今朝の@湘南地方です。
さて、知財動画第7回、先ほど公開しました。
今回は「他人との関係でできること、気を付けること」です。ぜひご覧ください
さてさて、掲題の件。
4年ほど前にあれこれ取り沙汰されて現在に至るわけですが、
今のところまだ、そこまで目に見えて業務上の大きな変化があった、ということはありません。
・商標画像検索で使ってみる とか
・お試しで特許調査をやってみる(お客様への納品物ではなく) とか
くらいですかねー。
あと、お客さんがセカンドオピニオン求めにAIの調査結果片手に相談に来た、とか(調査結果の精度についてはここではコメントしません)。
現時点で、影響は皆無ないし軽微です。
いや、だから
“AIなんて関係ないよ、何も変わらない”
とは思っていません。きっと変わります。
ただ、例えばこの記事とかこの記事とかで書かれてたようなかたちではないのではないかな、と。
もちろん、従来型の「保護されてきた専権業務」だけに恋々と固執する自称「専門家」は、生きていくのが難しいかもしれません。
そこがまさに代替可能な業務要素なわけだし。
でも、じゃあ「コンサルに傾斜」とか「徹底したコストダウン」に向かっていくかというと、どうも違うようで。
一つには、「みんながみんなコンサルやりたいわけでもできるわけでも、或いは求めてるわけでもない」ということ。
クライアントが求めているものが「解決」或いは「意思決定」である場合、
必要なのは「情報の選別と結論へのルート説明、及びその合理性/妥当性の担保」。
そのプロセス自体はいわゆる「コンサル」ではない。ただの「アドバイス」。
“ただの”と書いたけど、この「アドバイス」の部分に最も必要なのが「納得感」。
「納得感」って、結局「信頼感」に依存するものでは?と思うのです。
誤解を承知で言えば、「納得感」を生み出すのにはIntelligenceだけでは無理で、Emotionの要素が少なからずあるわけで。
人が人と仕事をする以上、そこは捨象できない。
どれだけ優秀で卓越したスキルをお持ちの方でも、何だか当社とはソリが合わないんだよなぁ…
というケースもあると思う。そこはIではなくEの部分。
非効率?不合理? そう。人間なんて非効率で不合理で独善的でそのときどきで言うことの変わる不安定な存在。
ある種「感情ビジネス」的な側面は、専門領域だからこそ重要。
もっと時代が進んで、
“へー、昔はそんなことを人間がやってたんだねー”
なんて思い、AIが出す結論に何の不安もなく「納得感」を持つ層が現役世代の中心になったら、
その時初めて変わるのかも。
まあ、たぶんその入り口くらいの時期にはまだ自分も現役なのだと思うので、
結局避けて通れないところではあるわけですが…その時はどうしましょうかね。
“あの人昭和生まれだから”と言われても自己流を貫き通しますかね。。
「踊る大捜査線」の和久さん的な感じで。
今日も快晴。こういう気持ち良い日々がずっと続けばよいのにと思う今朝の@湘南地方です。
さて、知財動画第7回、先ほど公開しました。
今回は「他人との関係でできること、気を付けること」です。ぜひご覧ください
さてさて、掲題の件。
4年ほど前にあれこれ取り沙汰されて現在に至るわけですが、
今のところまだ、そこまで目に見えて業務上の大きな変化があった、ということはありません。
・商標画像検索で使ってみる とか
・お試しで特許調査をやってみる(お客様への納品物ではなく) とか
くらいですかねー。
あと、お客さんがセカンドオピニオン求めにAIの調査結果片手に相談に来た、とか(調査結果の精度についてはここではコメントしません)。
現時点で、影響は皆無ないし軽微です。
いや、だから
“AIなんて関係ないよ、何も変わらない”
とは思っていません。きっと変わります。
ただ、例えばこの記事とかこの記事とかで書かれてたようなかたちではないのではないかな、と。
もちろん、従来型の「保護されてきた専権業務」だけに恋々と固執する自称「専門家」は、生きていくのが難しいかもしれません。
そこがまさに代替可能な業務要素なわけだし。
でも、じゃあ「コンサルに傾斜」とか「徹底したコストダウン」に向かっていくかというと、どうも違うようで。
一つには、「みんながみんなコンサルやりたいわけでもできるわけでも、或いは求めてるわけでもない」ということ。
クライアントが求めているものが「解決」或いは「意思決定」である場合、
必要なのは「情報の選別と結論へのルート説明、及びその合理性/妥当性の担保」。
そのプロセス自体はいわゆる「コンサル」ではない。ただの「アドバイス」。
“ただの”と書いたけど、この「アドバイス」の部分に最も必要なのが「納得感」。
「納得感」って、結局「信頼感」に依存するものでは?と思うのです。
誤解を承知で言えば、「納得感」を生み出すのにはIntelligenceだけでは無理で、Emotionの要素が少なからずあるわけで。
人が人と仕事をする以上、そこは捨象できない。
どれだけ優秀で卓越したスキルをお持ちの方でも、何だか当社とはソリが合わないんだよなぁ…
というケースもあると思う。そこはIではなくEの部分。
非効率?不合理? そう。人間なんて非効率で不合理で独善的でそのときどきで言うことの変わる不安定な存在。
ある種「感情ビジネス」的な側面は、専門領域だからこそ重要。
もっと時代が進んで、
“へー、昔はそんなことを人間がやってたんだねー”
なんて思い、AIが出す結論に何の不安もなく「納得感」を持つ層が現役世代の中心になったら、
その時初めて変わるのかも。
まあ、たぶんその入り口くらいの時期にはまだ自分も現役なのだと思うので、
結局避けて通れないところではあるわけですが…その時はどうしましょうかね。
“あの人昭和生まれだから”と言われても自己流を貫き通しますかね。。
「踊る大捜査線」の和久さん的な感じで。