【この記事のポイント】
・世界の新薬、日本では72%が未承認
・小規模病院が多く、必要な治験のデータ集まらず
・遠隔地からの「リモート治験」で裾野広げる動きも
世界で生まれる画期的な新薬の7割が日本で治療に使えない事態となっている。薬の実用化に必要な臨床試験(治験)に課題がある。
製薬会社や医療機関が必要な数の被験者を即座に集めることができないため、欧米に比べて長期化しやすい。治験の費用もかさむため、国際共同治験の対象国から外される例もある。難病患者の不利益となっている。
<picture class="picture_p166dhyf"><source srcset="https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO4716759016042024000000-2.jpg?ixlib=js-3.8.0&w=425&h=799&auto=format%2Ccompress&fit=crop&bg=FFFFFF&s=75c5bf5ff6648f867cce77ff019cab02 1x, https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO4716759016042024000000-2.jpg?ixlib=js-3.8.0&w=850&h=1598&auto=format%2Ccompress&fit=crop&bg=FFFFFF&s=c9081993567c9c7b4b42e56e2c733bf5 2x" media="(min-width: 1232px)" /><source srcset="https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO4716759016042024000000-2.jpg?ixlib=js-3.8.0&w=425&h=799&auto=format%2Ccompress&fit=crop&bg=FFFFFF&s=75c5bf5ff6648f867cce77ff019cab02 1x, https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO4716759016042024000000-2.jpg?ixlib=js-3.8.0&w=850&h=1598&auto=format%2Ccompress&fit=crop&bg=FFFFFF&s=c9081993567c9c7b4b42e56e2c733bf5 2x" media="(min-width: 992px)" /><source srcset="https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO4716759016042024000000-2.jpg?ixlib=js-3.8.0&w=425&h=799&auto=format%2Ccompress&fit=crop&bg=FFFFFF&s=75c5bf5ff6648f867cce77ff019cab02 1x, https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO4716759016042024000000-2.jpg?ixlib=js-3.8.0&w=850&h=1598&auto=format%2Ccompress&fit=crop&bg=FFFFFF&s=c9081993567c9c7b4b42e56e2c733bf5 2x" media="(min-width: 752px)" /><source srcset="https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO4716759016042024000000-2.jpg?ixlib=js-3.8.0&w=425&h=799&auto=format%2Ccompress&fit=crop&bg=FFFFFF&s=75c5bf5ff6648f867cce77ff019cab02 1x, https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO4716759016042024000000-2.jpg?ixlib=js-3.8.0&w=850&h=1598&auto=format%2Ccompress&fit=crop&bg=FFFFFF&s=c9081993567c9c7b4b42e56e2c733bf5 2x" media="(min-width: 316px)" /><source srcset="https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO4716759016042024000000-2.jpg?ixlib=js-3.8.0&w=425&h=799&auto=format%2Ccompress&fit=crop&bg=FFFFFF&s=75c5bf5ff6648f867cce77ff019cab02 1x, https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO4716759016042024000000-2.jpg?ixlib=js-3.8.0&w=850&h=1598&auto=format%2Ccompress&fit=crop&bg=FFFFFF&s=c9081993567c9c7b4b42e56e2c733bf5 2x" media="(min-width: 0px)" />

</picture>
「(グローバルに治験をする上で)日本を選択するメリットがないと世界が判断してしまう」――。
世界の主要な製薬会社が加盟する米国研究製薬工業協会(PhRMA)と欧州製薬団体連合会(EFPIA)が2023年に岡山市で共催したセミナーでは、日本の治験を巡る体制に対して厳しい意見が相次いだ。
「臨床試験のあり方を考える会議」と銘打ったこのセミナーで、両協会が公表した日本の治験の国際評価は「△」。いかに治験が効率的で速やかに進んでいるかを基準にした評価で、4段階のうち下から2番目の低さだ。
1つの薬の基礎研究から国の承認までの開発期間は9〜17年程度とされる。治験は実際にヒトに投与し、安全性と有効性を確認する開発の最終段階に当たる。
実施期間は3〜7年で、一定数の健常者や患者の協力が必要となる。
世界の新薬、日本では7割が未承認
欧米の製薬大手各社が指摘する問題点が「治験の進めにくさ」と「コストの高さ」だ。
日本では多くの被験者を集めて治験を進める環境が十分に整っていない。一般的に病院など医療機関が治験の場となるが、日本は欧米などに比べて規模が小さい施設が多い。製薬会社は有意なデータを得るため、多数の病院にまたがって治験を実施しなければならなくなる。
病院ごとに治験を準備する必要がある。製薬会社の開発担当者の数も多くなり、事務負担も重い。治験の安全性や倫理性を審査する「治験審査委員会(IRB)」を個別に開く必要もある。
製薬会社は、複数の医療機関の治験審査を一括して実施する「中央IRB」と呼ぶ手法を採用しようとしているが、十分に浸透していない。
もともと日本では治験に参加したいという患者が少ない。安全性への根強い不安に加え、「国民皆保険」を実現している独自の公的医療制度が背景にある。
欧米は保険の未加入者が多く存在する。治験は高額となる高度医療を無料で受けるための一つの手段とみなす傾向がある。一方、日本は保険でカバーされるため個人の医療費負担が比較的軽い。治験に参加したいというインセンティブが起きにくい。
有望な新薬候補では、複数の国や地域で治験を同時並行で実施することも多い。日本は評価の低さから、こうした国際共同治験の対象国から外されるケースも目立つ。
医薬産業政策研究所(東京・中央)によると、00〜21年に日本が参加した国際共同治験の数は累計で2110。世界で23位にとどまる。
国際共同治験の少なさもあり、新薬の市場投入は滞る。同研究所の20年の調査では、直近5年間に欧米で承認された新薬のうち、72%が日本国内では未承認だった。16年(56%)から16ポイントも上昇した。
日本の医薬品市場は、米国や中国に次ぐ世界3位の規模を持つ。にもかかわらず、海外で使われている新薬が日本で生かせない「ドラッグ・ロス」の問題がかねて指摘されていた。日本での承認が遅れる「ドラッグ・ラグ」の問題もより深刻化している。
日本医科大学の松山琴音特任教授は「このままでは10年、20年後には海外の優れた薬がほぼ入ってこなくなってもおかしくない」と話す。
治験の裾野広げる「リモート」
「治験後進国」の現状を打破するため、デジタルトランスフォーメーション(DX)の活用が期待されている。従来の治験は都市部に集中していた。
地方にいる患者にも裾野を広げる手段として有望なのがパソコンやスマートフォンなどを活用して遠隔地からも治験に参加できる「リモート治験」だ。
<picture class="picture_p166dhyf"><source srcset="https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO4744525022042024000000-1.jpg?ixlib=js-3.8.0&w=638&h=425&auto=format%2Ccompress&fit=crop&bg=FFFFFF&s=022a578bf475cf6cffb88bd13fa7fc76 1x, https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO4744525022042024000000-1.jpg?ixlib=js-3.8.0&w=1276&h=850&auto=format%2Ccompress&fit=crop&bg=FFFFFF&s=9c0c1e5abd088a4e9b12a6300d6827c7 2x" media="(min-width: 1232px)" /><source srcset="https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO4744525022042024000000-1.jpg?ixlib=js-3.8.0&w=638&h=425&auto=format%2Ccompress&fit=crop&bg=FFFFFF&s=022a578bf475cf6cffb88bd13fa7fc76 1x, https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO4744525022042024000000-1.jpg?ixlib=js-3.8.0&w=1276&h=850&auto=format%2Ccompress&fit=crop&bg=FFFFFF&s=9c0c1e5abd088a4e9b12a6300d6827c7 2x" media="(min-width: 992px)" /><source srcset="https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO4744525022042024000000-1.jpg?ixlib=js-3.8.0&w=600&h=399&auto=format%2Ccompress&fit=crop&bg=FFFFFF&s=1d04255cab06efa5de5bcdc35a9ae88f 1x, https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO4744525022042024000000-1.jpg?ixlib=js-3.8.0&w=1200&h=799&auto=format%2Ccompress&fit=crop&bg=FFFFFF&s=55e39c5e13240feabeb8d975ddf701af 2x" media="(min-width: 752px)" /><source srcset="https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO4744525022042024000000-1.jpg?ixlib=js-3.8.0&w=600&h=399&auto=format%2Ccompress&fit=crop&bg=FFFFFF&s=1d04255cab06efa5de5bcdc35a9ae88f 1x, https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO4744525022042024000000-1.jpg?ixlib=js-3.8.0&w=1200&h=799&auto=format%2Ccompress&fit=crop&bg=FFFFFF&s=55e39c5e13240feabeb8d975ddf701af 2x" media="(min-width: 316px)" /><source srcset="https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO4744525022042024000000-1.jpg?ixlib=js-3.8.0&w=600&h=399&auto=format%2Ccompress&fit=crop&bg=FFFFFF&s=1d04255cab06efa5de5bcdc35a9ae88f 1x, https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO4744525022042024000000-1.jpg?ixlib=js-3.8.0&w=1200&h=799&auto=format%2Ccompress&fit=crop&bg=FFFFFF&s=55e39c5e13240feabeb8d975ddf701af 2x" media="(min-width: 0px)" />

</picture>
模擬のリモート治験でオンライン診療する大阪大医学部付属病院の忽那賢志医師(大阪府吹田市の大阪大)
新型コロナウイルス禍で「オンライン診療」が条件付きで解禁されたことを受け、リモート治験も技術的に可能となった。23年末には希少がんの治験で導入された。
塩野義製薬は大阪大学と組み、24年2月から新型コロナ治療薬「ゾコーバ」の投与効果について、国内の2000人を対象としたリモートでの臨床研究を始めた。
研究を主導する阪大の忽那賢志教授は「臨床研究にとどまらず治験としてもリモート活用が広がっていくだろう」と話す。
安全性の担保や個人情報の取り扱いなどで課題は残るものの、日本の治験のあり方を考える機会になるとみる向きも多い。
コロナ禍が促したデジタル革新
リモート治験では必要な手続きをパソコンやスマートフォンを使ったオンライン通信で進める。バイタル(生体情報)の測定、医師の問診などの治験の一部またはすべてを被験者の身近にある医療機関や自宅で実施する。
リモート治験の発想自体は従来からあったものの、安全性への懸念や費用対効果が見えにくいことなどから導入が進んでいなかった。
新型コロナウイルスの感染拡大によって外出自粛が広がった。医療機関への通院も難しくなり、リモート治験の必要性が増した。
日本は厚生労働省が20年春、コロナ下の治験の進め方の指針を公表し、製薬会社が導入しやすくなった。
中国、新薬開発でも「先進国」に
世界の製薬会社が注力する市場が中国だ。経済成長を背景に新薬のニーズは高い。
治験を実施する上で被験者を集めやすいなど、比較的スムーズに新薬投入ができる環境が整っていることも市場の成長を促している。
<picture class="picture_p166dhyf"><source srcset="https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO4716761016042024000000-1.jpg?ixlib=js-3.8.0&w=638&h=574&auto=format%2Ccompress&fit=crop&bg=FFFFFF&s=e509af897bfaa689f9aa77eeee1767f6 1x, https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO4716761016042024000000-1.jpg?ixlib=js-3.8.0&w=1276&h=1148&auto=format%2Ccompress&fit=crop&bg=FFFFFF&s=52eb29cba95081d15abcb0a7b25f0bd8 2x" media="(min-width: 1232px)" /><source srcset="https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO4716761016042024000000-1.jpg?ixlib=js-3.8.0&w=638&h=574&auto=format%2Ccompress&fit=crop&bg=FFFFFF&s=e509af897bfaa689f9aa77eeee1767f6 1x, https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO4716761016042024000000-1.jpg?ixlib=js-3.8.0&w=1276&h=1148&auto=format%2Ccompress&fit=crop&bg=FFFFFF&s=52eb29cba95081d15abcb0a7b25f0bd8 2x" media="(min-width: 992px)" /><source srcset="https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO4716761016042024000000-1.jpg?ixlib=js-3.8.0&w=600&h=539&auto=format%2Ccompress&fit=crop&bg=FFFFFF&s=71a8279bc0bc082303c750391a0139d1 1x, https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO4716761016042024000000-1.jpg?ixlib=js-3.8.0&w=1200&h=1079&auto=format%2Ccompress&fit=crop&bg=FFFFFF&s=20724d3ad896be1f6e3c220e540d2898 2x" media="(min-width: 752px)" /><source srcset="https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO4716761016042024000000-1.jpg?ixlib=js-3.8.0&w=600&h=539&auto=format%2Ccompress&fit=crop&bg=FFFFFF&s=71a8279bc0bc082303c750391a0139d1 1x, https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO4716761016042024000000-1.jpg?ixlib=js-3.8.0&w=1200&h=1079&auto=format%2Ccompress&fit=crop&bg=FFFFFF&s=20724d3ad896be1f6e3c220e540d2898 2x" media="(min-width: 316px)" /><source srcset="https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO4716761016042024000000-1.jpg?ixlib=js-3.8.0&w=600&h=539&auto=format%2Ccompress&fit=crop&bg=FFFFFF&s=71a8279bc0bc082303c750391a0139d1 1x, https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO4716761016042024000000-1.jpg?ixlib=js-3.8.0&w=1200&h=1079&auto=format%2Ccompress&fit=crop&bg=FFFFFF&s=20724d3ad896be1f6e3c220e540d2898 2x" media="(min-width: 0px)" />

</picture>
国際共同治験の実施数は少ないものの、中国国内のみを対象とした治験の数は増えている。
医薬産業政策研究所によると、単一国の臨床試験で比較すると中国は21年に739と日本の約6倍だった。
中国は都市部に大病院が集中しており、被験者を集めやすいとされる。治験に関わる開発担当者の人件費も比較的安く、製薬会社にとっても開発コストが増えにくい。
当局も治験の迅速化に向けてデータの評価などの審査期間を短縮化しようとするなど新薬投入を後押ししている。
米調査会社のIQVIAによると医薬品の市場規模は13年に日本を抜き世界2位となった。
日本の医薬品市場が23年から28年にかけてほぼゼロ成長を見込むのに対し、中国は21%増の1970億㌦(約30兆円)まで拡大する見込み。日本の2.7倍となる。
治験では中国独自のルールに沿った書類を用意する必要などもあるが、製薬各社も実績を積むことでよりスムーズに工程を進めることができるようになっている。
日本医科大の松山特任教授は「中国の現地製薬会社も治験をうまく設計できるようになり、有望な新薬を独自に開発できる技術力がついてきた」と指摘する。
(三隅勇気)
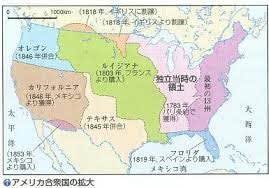











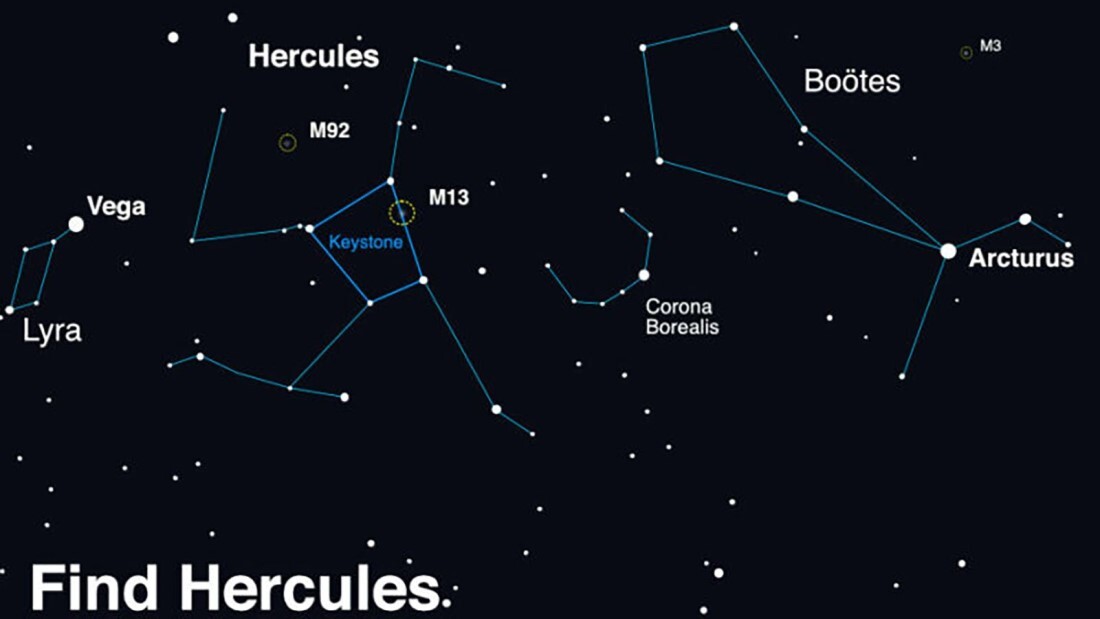
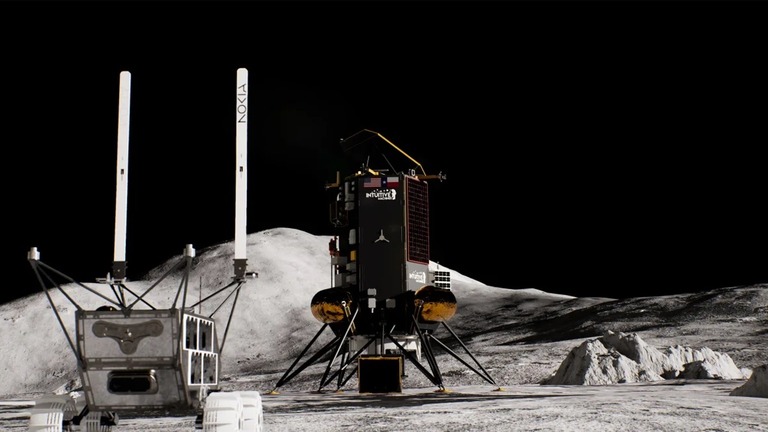

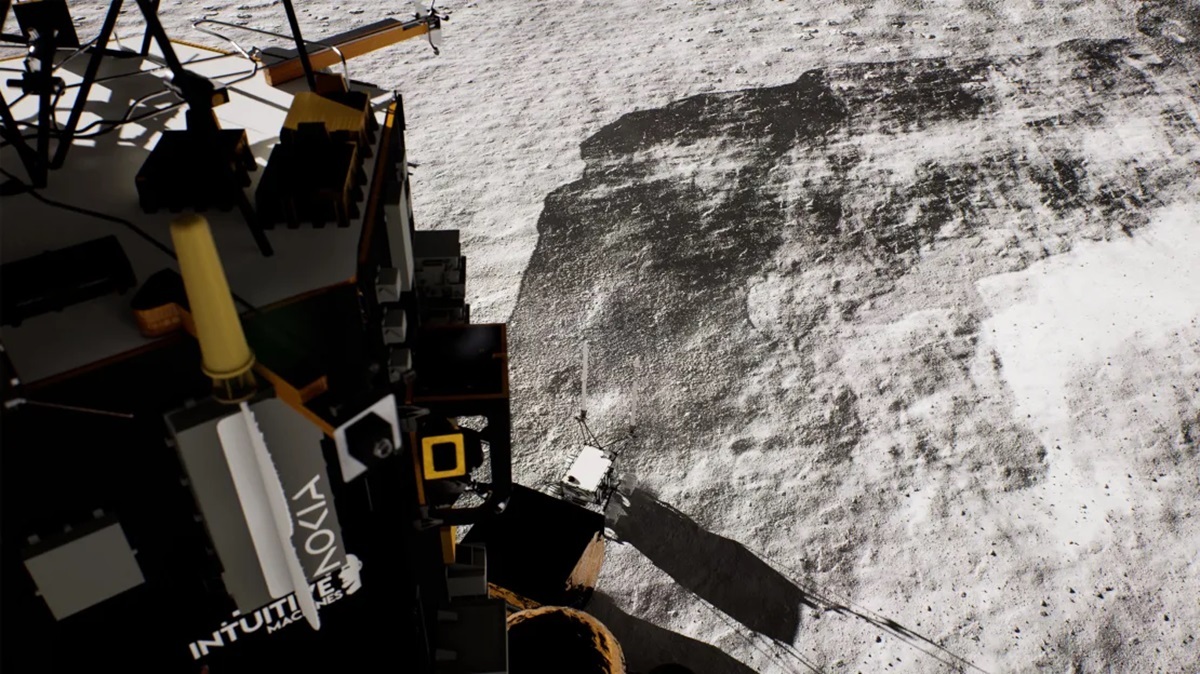
 </picture>
</picture> </picture>
</picture> </picture>
</picture>

