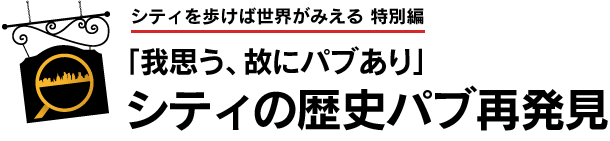英金融街シティーが再起動している。英国の欧州連合(EU)離脱から1月末で4年を迎える中で、英国内外の金融機関による大型買収や拠点新設といった事業拡大の姿勢が鮮明だ。
金融史の舞台として長年築き上げた金融サービスの集積と文化力が、にぎわいを支えている。
大型買収・拠点新設相次ぐ
「M&A(合併・買収)のアドバイザリーや株式発行といった投資銀行業務にEU離脱の影響はなく、欧州における英国の主導的地位は今後も揺るがない。
英国の法人顧客との深いネットワークを手に入れることで、ドイツ銀行の成長は加速する」。
ドイツ銀行のファブリツィオ・カンペリ取締役(法人・投資銀行部門担当)はシティーのオフィスでの取材で強調した。

EU離脱の交渉では英国への強硬姿勢をとったEUの盟主ドイツと対照的に、独金融大手のドイツ銀行はシティーでの事業拡大を鮮明にしている。
23年10月には英投資銀行ヌミスの買収を完了した。買収金額は約4億1000万ポンド(約760億円)と同行として過去10年で最大規模の買収とみられ、英国で有数の投資銀行部門の陣容をそろえた。
24年には新オフィスの移転も進める。ロンドンの5拠点を統合し、計14フロアで従業員5000人以上がシティーに勤務することになる。
1873年にドイツ銀行が英国での営業を始めた歴史的な地の近くへ戻る。
EU離脱から4年
EU離脱から24年1月末で4年が経過する。離脱前にはシティーの金融街としての地位は低下すると懸念もあった。
確かに英国の拠点からEUでの取引が制限される株式営業の分野などで悪影響は発生した。
アーンスト・アンド・ヤング(EY)によると、16年の国民投票から22年3月までの英国からEU圏内へ流出した金融業の就業者数は7000人強となった。
ただシティー全体の就業者数は国民投票前の15年の43万8100人から22年に59万8900人と4割弱増の約16万人増えた。
伸び率は英国全体の5%増を大きく上回る。「シティーが長年にわたって築き上げた金融業や、会計や法律、コンサルティングといった金融専門サービスのネットワークの優位性は揺るがない」とシティーの大手会計事務所幹部は話す。
ロンドンの中でもシティー回帰が進んでいる。英金融大手HSBCは23年、27年にも新金融街「カナリーワーフ」を象徴する存在だった超高層ビルから、シティーで改築中のビルへ本社移転する計画を明らかにした。
経営不安に陥ったクレディ・スイスの従業員も、買収したスイス金融最大手のUBSがシティーで構える本社へ移っている。
港湾街の再開発でできたカナリーワーフは1980年代のサッチャー政権の金融ビッグバンによる外資系金融の流入ともに成長。これまでシティーから金融機能が移っていた場所だった。
シティーの追い風になったのが、新型コロナウイルスの感染拡大をきっかけとした在宅勤務の定着だ。
従業員の出社頻度が減り、交通の便が悪いが広いオフィススペースを確保できるというカナリーワーフの利点が乏しくなった。同地のビルで働く靴磨きの男性は「いまだに日中の人通りと売り上げはコロナ前の2分の1から3分の1にとどまる」と嘆く。
EU離脱後も人材を吸引
出社の意味が問われる中で、幅広い金融関連のプレーヤーが集積し、対面で会って交流しやすいシティーの魅力が増した。
シティーの起源は、ローマ帝国が3世紀ごろに現在のロンドンのわずか約3平方キロメートルを防壁で囲んだことだ。
その狭い地域の中で、近世以降に保険市場や証券取引所といった金融インフラが相次いで生まれ、今日まで拠点を構え続けている。
アイデアの交換が生まれやすい空間は新しい人材も引き付ける。EU離脱後に急成長を遂げたフィンテック企業の本社はいずれもシティーにある。
18年に新規株式公開(IPO)した融資プラットフォームの英ファンディングサークルや英デジタルバンクのモンゾなどだ。
シティーの金融機関勤務の傍らで同地の公認ガイドとして活動する坂次健司さんは「シティーは外に開かれているのが特徴だ。
現在の就業者の4割強が英国外出身で、6割が20〜30代の若者世代だ。最近では東欧からのフィンテック人材の流入が目覚ましい」と話す。

中世には外部人材を担い手として商業街として発展していったという歴史もある。
11世紀には現在のフランスから征服したウィリアム1世が、金融の担い手としてユダヤ人を招いた。
13世紀のユダヤ人追放令の後には、イタリアのロンバルディア商人が活躍して現在まで続く中心部の「ロンバード街」の名前の由来となっている。
EU離脱や新型コロナウイルスといったここ10年弱の試練に対して、過去約2000年にわたり積み重ねた歴史が、シティーの底力を生み出している。

シティーの中心部から東に向かうと、建物の外側に配管や階段をむき出しにした奇抜なデザインの「ロイズビル」が姿を現す。
このビルの内部には、現存する最古とみられ、世界最大級の取引規模を誇る保険市場がある。その市場を運営するのが英ロイズ保険組合だ。
建物の内部に入ると、取引フロアにずらりと並ぶ数百個の机に向かって、保険を引き受けるアンダーライターと呼ばれる担当者が座っていた。保険をかけたい企業からの依頼を受けたブローカーが通路を歩き回って、アンダーライターに話しかけ、どのぐらいの金額や条件であれば引き受けが可能かを交渉する。
保険の担当者は複数のアンダーライターが控える机へ足を運び、企業が希望する保険金額全体の引き受けが完了するまで何度も話し合いが続いていた。
ロイズ保険組合は17世紀後半に相次いでシティーで開かれたコーヒー店「コーヒーハウス」の「ロイズ」が発祥だ。紅茶のイメージが強い英国では、実はコーヒーの流行の方が早かった。
新聞などのマスメディアが未発達な時代に、船主や投資家が集まって情報交換をし、さらに海上保険が売買されるようになって今に至る。
現在でもアンダーライターが控える机は「ボックス」と言われ、当時と同じ呼び方が残る。
あるロイズ保険組合の有力メンバーの男性社員は「新型コロナウイルス禍で一部で電子取引や在宅勤務が進んだが、『コーヒーハウス』の雰囲気が残る対面取引も根強い。
顔を合わせた信頼関係が取引の肝となるのは何百年たっても変わらない」と話す。
コーヒーハウスは数々の金融インフラを生み出した。1698年にコーヒーハウス「ジョナサン」で株価やコモディティーのリストが発表されて投資家が集ったのが、ロンドン証券取引所の発祥だ。
同様に1744年にも「バージニア&バルチック」でバルト海の商品取引がされたのがバルチック海運取引所の起源となる。
シティーで1652年に初めてできたコーヒーハウスは、ジャマイカなどでのラム酒や砂糖の貿易の場となった。
その跡地は現在「ジャマイカ・ワインハウス」というパブとなり、今でも金融機関で働く人たちが立ち飲みをしながら、情報交換をいそしみ活気づいている。
16世紀後半に設立された「王立取引所」は為替とコモディティーの取引所として機能した。
「悪貨は良貨を駆逐する」というグレシャムの法則で知られるトーマス・グレシャムが設立。王室の金融代理人として仕え、女王エリザベス1世から認められて「王立」の名が冠された。今では高級ブランド店が並びにぎわう。
そもそもシティーが国際金融センターとしての地位を確立したのは、19世紀前半のフランスのナポレオンとの戦争以降となる。
現在のオランダのアムステルダムなど、荒廃した欧州大陸から金融機能の移行が進んだ。
ワーテルローの戦いでナポレオンを破った国民的英雄で、のちに首相を務めたウェリントンの像が、それを象徴するかのようにシティーの中心部の広場に鎮座する。
王立取引所の裏手には、ロイター通信や現在はLSEG傘下の金融・相場情報サービスの創業者であるポール・ジュリアス・ロイターが1851年に同地で創業したとの石碑が建つ。
伝書バトでやり取りした相場情報を、英仏海峡間に敷設した海底電信ケーブルを使って伝達するというイノベーションを起こした。
こうした金融インフラはいまも、人々の活動を支える。独自の生態系と周辺に集まる金融業者へのメリットを生み出している。
「劇場」としての存在価値は不変
シティー公認ガイド 坂次健司氏
<picture class="picture_p166dhyf"><source srcset="https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO4313508012012024000000-1.jpg?s=01fc2a5fc16599e31a2c05214f5f139f 1x, https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO4313508012012024000000-1.jpg?s=01fc2a5fc16599e31a2c05214f5f139f 2x" media="(min-width: 1232px)" /><source srcset="https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO4313508012012024000000-1.jpg?s=01fc2a5fc16599e31a2c05214f5f139f 1x, https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO4313508012012024000000-1.jpg?s=01fc2a5fc16599e31a2c05214f5f139f 2x" media="(min-width: 992px)" /><source srcset="https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO4313508012012024000000-1.jpg?s=01fc2a5fc16599e31a2c05214f5f139f 1x, https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO4313508012012024000000-1.jpg?s=01fc2a5fc16599e31a2c05214f5f139f 2x" media="(min-width: 752px)" /><source srcset="https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO4313508012012024000000-1.jpg?s=01fc2a5fc16599e31a2c05214f5f139f 1x, https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO4313508012012024000000-1.jpg?s=01fc2a5fc16599e31a2c05214f5f139f 2x" media="(min-width: 316px)" /><source srcset="https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO4313508012012024000000-1.jpg?s=01fc2a5fc16599e31a2c05214f5f139f 1x, https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO4313508012012024000000-1.jpg?s=01fc2a5fc16599e31a2c05214f5f139f 2x" media="(min-width: 0px)" />

</picture>
シティーの成長のきっかけを作ったのは16世紀の国王ヘンリー8世の宗教改革だ。
カトリック教会から離脱して英国国教会を創始したことを、私は「ファーストブレグジット」と呼んでいる。
カトリックの資産を民間に払い下げて得た巨額の資金を、私腹を肥やすのではなく海軍の創設に使って英国の国力を高めたと評価している。
17世紀後半の名誉革命によって金融街としての躍進が始まった。オランダから迎え入れたウィリアム3世とメアリ2世のもとで「権利の宣言」が制定された。議会主義や私有財産制が確認されたことで、安心して金融活動ができる自由経済の土台ができたことが大きい。
長年にわたりシティーは欧州の片隅の商業街に過ぎず、同じローマ帝国下で成立したパリやウィーンに比べておまけのような存在だった。それが急にぐっと商業と貿易の神が手を組んで繁栄を遂げたイメージだ。
転んでもただでは起きない。第2次世界大戦後に英国は多くの植民地を失ったが、英領をケイマン諸島やバミューダなどオフショアのタックスヘイブン(租税回避地)として活用して金融業を支えた。
1950年代に冷戦が激化する中、米国による資産凍結の懸念からソ連や東欧が保有する米ドルをロンドンの銀行に預け替えたことでユーロダラー市場ができあがった。
シティーは最高の「劇場」というのが私の見方だ。常に入れ替わりはあるが、一流の役者に一流の演技をしてもらう場所であり続けている。
近年でも1980年代のサッチャー政権の金融ビッグバンで英国内の金融機関に大打撃を与えながらも、世界の有数の金融機関を招くことで金融街として再び成功することができた。
アジア時間と米国時間の中間にあり、トレーダーや投資家が世界全体を見渡して取引ができる地球上の特権的な場所でもある。金融街としての存在価値は不変だ。
いわば「セカンドブレグジット」となる英国のEU離脱がシティーをさらに成長させるかどうか。
それは金融規制の緩和とデジタルトランスフォーメーション(DX)でどれだけ大陸側に対する優位性を出せるかにかかっている。
(ロンドン=大西康平が担当した。グラフィックスは田口寿一)
日経記事2024.01.19より引用
<picture class="picture_p166dhyf"><source srcset="https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO4280413002012024000000-1.jpg?ixlib=js-3.8.0&w=638&h=436&auto=format%2Ccompress&fit=crop&bg=FFFFFF&s=33950771673bec3cc96783f5b3eb769b 1x, https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO4280413002012024000000-1.jpg?ixlib=js-3.8.0&w=1276&h=872&auto=format%2Ccompress&fit=crop&bg=FFFFFF&s=f4711deb989d314b55bae920e9d082f1 2x" media="(min-width: 1232px)" /><source srcset="https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO4280413002012024000000-1.jpg?ixlib=js-3.8.0&w=638&h=436&auto=format%2Ccompress&fit=crop&bg=FFFFFF&s=33950771673bec3cc96783f5b3eb769b 1x, https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO4280413002012024000000-1.jpg?ixlib=js-3.8.0&w=1276&h=872&auto=format%2Ccompress&fit=crop&bg=FFFFFF&s=f4711deb989d314b55bae920e9d082f1 2x" media="(min-width: 992px)" /><source srcset="https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO4280413002012024000000-1.jpg?ixlib=js-3.8.0&w=600&h=410&auto=format%2Ccompress&fit=crop&bg=FFFFFF&s=000dfab6fc073f7eb7cbdf2ca4a8dd6c 1x, https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO4280413002012024000000-1.jpg?ixlib=js-3.8.0&w=1200&h=820&auto=format%2Ccompress&fit=crop&bg=FFFFFF&s=55e95c13ad2aff5a23b7eeafbd5386e2 2x" media="(min-width: 752px)" /><source srcset="https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO4280413002012024000000-1.jpg?ixlib=js-3.8.0&w=600&h=410&auto=format%2Ccompress&fit=crop&bg=FFFFFF&s=000dfab6fc073f7eb7cbdf2ca4a8dd6c 1x, https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO4280413002012024000000-1.jpg?ixlib=js-3.8.0&w=1200&h=820&auto=format%2Ccompress&fit=crop&bg=FFFFFF&s=55e95c13ad2aff5a23b7eeafbd5386e2 2x" media="(min-width: 316px)" /><source srcset="https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO4280413002012024000000-1.jpg?ixlib=js-3.8.0&w=600&h=410&auto=format%2Ccompress&fit=crop&bg=FFFFFF&s=000dfab6fc073f7eb7cbdf2ca4a8dd6c 1x, https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO4280413002012024000000-1.jpg?ixlib=js-3.8.0&w=1200&h=820&auto=format%2Ccompress&fit=crop&bg=FFFFFF&s=55e95c13ad2aff5a23b7eeafbd5386e2 2x" media="(min-width: 0px)" /></picture>



 </picture>
</picture>