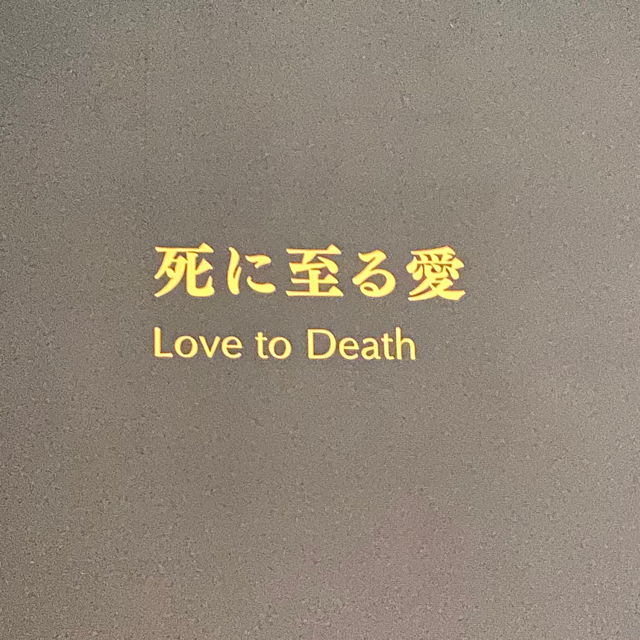そしてもう一つ、わたしの心の底にあったもの。
それは
「彼は結婚したかったから、結婚してくれるのなら誰でも良かったのではないか」
ということでした。
なぜわたしがそう思うようになったか。
それはやっぱり展開がすごく早かったこと
彼は5年近くまったく音信普通だったわたしに電話をかけてきたのが7月あたま。
そして入籍したのは11月でした。
一度破談になって、家を出て一人暮らしをしていた彼は、相当寂しかったんだと思います。そして、家事をやってくれる人が欲しかったんだと思います。
1年位前、わたしは彼の古い携帯メールを見たことがありました。
それで前の彼女のことについての嘘も分かったのですが。
彼が他に昔かかわりがあった女性に送っていたメールがありました。
それは、わたしに連絡を取る前の1,2ヶ月前に送信していて、かなりの部分、わたしに送ってきたメールと同じ文面のものだったのです。
それを見た一年前。
「ああ、誰でもよかったのか・・・結婚したかったんだな。結婚してくれる人を、彼は探していたんだな」
と思いました。
そこでわたしが引っかかってきた。
東京に行って、テレビでも取り上げられるような仕事をするようになっていた。
これはいい、と思ったんでしょう。
でも、あとからいろいろ、母のこととか面倒なことが出てきて、破談になりかけたけど、まあここまできたら仕方ない、と思ったのか結婚にこぎつけた。
二度も破談は世間的にもまずいし。
そう思いました。
でももう結婚してしまったし
何より彼のことが好きだったから。
それでもいいと思っていた。
「結婚してくれるなら、誰でも良かったんだ」
という思いは、ずっとそれからわたしのなかにあったのです。
でも、今、夫と、夫の両親が憎くて仕方なくなってしまった。
誰でもいいなら、別に私じゃなくていいなら、わざわざ大事なものをすべておいて来ることなんてなかった。
そういう思いがわき上がってきたのです。
夫は、わたしが携帯をみたことも知りません。
普段は夫の携帯なんて、まったく興味がないので見ることもないです。
忘れていた、忘れようとしていた思いが、表面に出てきてしまった。
不思議なことに、夫への変わることがないと思われた愛情が、わたしのなかから消え失せてしまったのです。
まるで、最初からなかったもののように。
夫の姿は何よりも愛しいものだった。
夫が寝ている顔を、なんとしても守りたいと思った。
夫が喜ぶ顔が見たいと思った。
夫の喜びが、わたしの喜びだった。
それが、わたしの生きていく、行動する基準だった。
生きていくうえの、決してなくなることがない気持ちだった。
それが、ある朝、わたしにとって、夫はただの男になってしまったのです。
それは
「彼は結婚したかったから、結婚してくれるのなら誰でも良かったのではないか」
ということでした。
なぜわたしがそう思うようになったか。
それはやっぱり展開がすごく早かったこと

彼は5年近くまったく音信普通だったわたしに電話をかけてきたのが7月あたま。
そして入籍したのは11月でした。
一度破談になって、家を出て一人暮らしをしていた彼は、相当寂しかったんだと思います。そして、家事をやってくれる人が欲しかったんだと思います。
1年位前、わたしは彼の古い携帯メールを見たことがありました。
それで前の彼女のことについての嘘も分かったのですが。
彼が他に昔かかわりがあった女性に送っていたメールがありました。
それは、わたしに連絡を取る前の1,2ヶ月前に送信していて、かなりの部分、わたしに送ってきたメールと同じ文面のものだったのです。
それを見た一年前。
「ああ、誰でもよかったのか・・・結婚したかったんだな。結婚してくれる人を、彼は探していたんだな」
と思いました。
そこでわたしが引っかかってきた。
東京に行って、テレビでも取り上げられるような仕事をするようになっていた。
これはいい、と思ったんでしょう。
でも、あとからいろいろ、母のこととか面倒なことが出てきて、破談になりかけたけど、まあここまできたら仕方ない、と思ったのか結婚にこぎつけた。
二度も破談は世間的にもまずいし。
そう思いました。
でももう結婚してしまったし

何より彼のことが好きだったから。
それでもいいと思っていた。
「結婚してくれるなら、誰でも良かったんだ」
という思いは、ずっとそれからわたしのなかにあったのです。
でも、今、夫と、夫の両親が憎くて仕方なくなってしまった。
誰でもいいなら、別に私じゃなくていいなら、わざわざ大事なものをすべておいて来ることなんてなかった。
そういう思いがわき上がってきたのです。
夫は、わたしが携帯をみたことも知りません。
普段は夫の携帯なんて、まったく興味がないので見ることもないです。
忘れていた、忘れようとしていた思いが、表面に出てきてしまった。
不思議なことに、夫への変わることがないと思われた愛情が、わたしのなかから消え失せてしまったのです。
まるで、最初からなかったもののように。
夫の姿は何よりも愛しいものだった。
夫が寝ている顔を、なんとしても守りたいと思った。
夫が喜ぶ顔が見たいと思った。
夫の喜びが、わたしの喜びだった。
それが、わたしの生きていく、行動する基準だった。
生きていくうえの、決してなくなることがない気持ちだった。
それが、ある朝、わたしにとって、夫はただの男になってしまったのです。











 と。
と。 」
」



 わたしにとって。
わたしにとって。