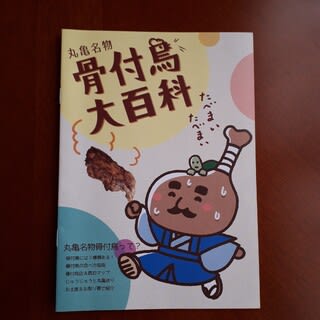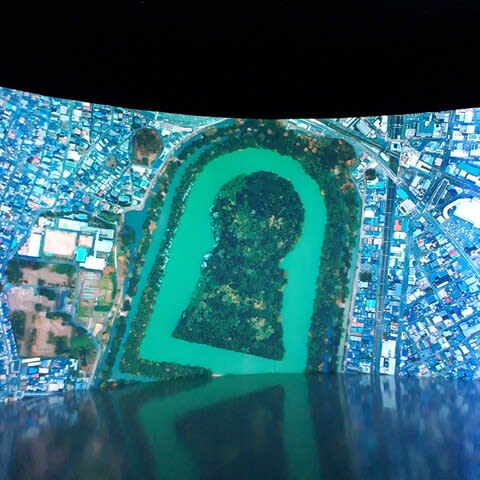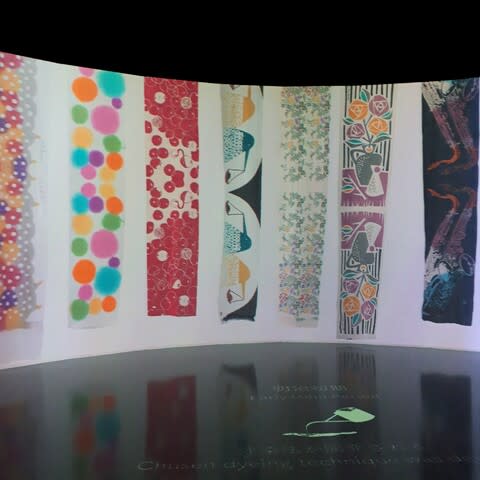前回の続きです。
西院伽藍と大宝蔵院を見学し、東大門を出て東院伽藍に向かいます。
東大門を内側から見た写真です。
奈良時代を代表する三棟造りの門です。

東大門を外側から見た写真です。
両脇は空いていますが、何か像が立っていたりしたのでしょうか。

美しい築地塀を見ることができます。

向こうに見えるのが東院伽藍です。
西院伽藍と東院伽藍は少し離れています。

夢殿は東院の本堂で、聖徳太子を供養するための殿堂です。
八角形の形をしています。

頂には立派な宝珠。

鬼瓦も立派です。

法隆寺をゆっくり拝観していると、2時間以上たっていました。
とっても広く見どころの多いお寺でした。
さて、法隆寺のすぐお隣には中宮寺があります。
こじんまりとしたお寺ですが、こちらには有名な国宝 菩薩半跏像が安置されています。

 中宮寺のホームページhttp://www.chuguji.jp/
中宮寺のホームページhttp://www.chuguji.jp/
とっても優しいお顔で、いつまでも見ていたいと思います。
お堂の中は畳敷きになっているので、座ってゆっくり仏像と向き合うことができます。
椅子も用意されていました。
エジプトのスフィンクス、レオナルド・ダ・ヴィンチのモナリザと並んで「世界の三つの微笑像」と呼ばれているそうです。
法隆寺に行った際は、ぜひ中宮寺も訪れてください。
法隆寺と中宮寺を訪れ、大満足の一日でした。
続いて、法隆寺境内を歩いていて、私が気になったものです。
それは瓦。
鬼瓦の隣にあるものです。
桃

菊

蓮?

獅子(見にくいですが)

これ、留蓋瓦と言うそうです。
雨水が入るのを防いだり、風で飛ばされないようにするためのものだそうです。
こんな彫刻を施すなんて、おしゃれですね。
波に乗ったウサギや、亀もいるそうですよ。
次回行ったときは探さねば。
もう一つ気になったのが、このすごい形のクスノキ。


中がえぐれていて、根元だけ見ると死んでそうですが生きています。
こんな形になってしまうなんて、いったい何があったんでしょうか。
気になります。
この日のランチは中宮寺近くの「和CAFE 布穀薗」でいただきました。

幕末・維新期の尊攘運動家、明治期の司法官である北畠治房が晩年隠棲していた屋敷だそうです。
屋敷の長屋門がカフェになっています。
こちらで斑鳩名物 竜田揚げランチをいただきました。

竜田揚げの竜田は、斑鳩町を流れる竜田川に由来するとのこと。
百人一首にも竜田川が出てきますが、昔から紅葉が有名な場所だそうです。
揚げたときの赤くなる醤油の色や、片栗粉がところどころ白く浮かぶさまを、紅葉が流れる竜田川に見立てて、その名がついたそうです。
店内からは母屋が見えます。

のんびり一人ランチ。
たまにはこういう時間もいいものですね。

久しぶりに法隆寺と中宮寺を訪れましたが、新しい発見がいろいろあり楽しかったです。
ぜひまた訪れたいと思います。

…おまけ…
法隆寺駅前でポケモンマンホール見つけました

西院伽藍と大宝蔵院を見学し、東大門を出て東院伽藍に向かいます。
東大門を内側から見た写真です。
奈良時代を代表する三棟造りの門です。

東大門を外側から見た写真です。
両脇は空いていますが、何か像が立っていたりしたのでしょうか。

美しい築地塀を見ることができます。

向こうに見えるのが東院伽藍です。
西院伽藍と東院伽藍は少し離れています。

夢殿は東院の本堂で、聖徳太子を供養するための殿堂です。
八角形の形をしています。

頂には立派な宝珠。

鬼瓦も立派です。

法隆寺をゆっくり拝観していると、2時間以上たっていました。
とっても広く見どころの多いお寺でした。
さて、法隆寺のすぐお隣には中宮寺があります。
こじんまりとしたお寺ですが、こちらには有名な国宝 菩薩半跏像が安置されています。

 中宮寺のホームページhttp://www.chuguji.jp/
中宮寺のホームページhttp://www.chuguji.jp/とっても優しいお顔で、いつまでも見ていたいと思います。
お堂の中は畳敷きになっているので、座ってゆっくり仏像と向き合うことができます。
椅子も用意されていました。
エジプトのスフィンクス、レオナルド・ダ・ヴィンチのモナリザと並んで「世界の三つの微笑像」と呼ばれているそうです。
法隆寺に行った際は、ぜひ中宮寺も訪れてください。
法隆寺と中宮寺を訪れ、大満足の一日でした。
続いて、法隆寺境内を歩いていて、私が気になったものです。
それは瓦。
鬼瓦の隣にあるものです。
桃

菊

蓮?

獅子(見にくいですが)

これ、留蓋瓦と言うそうです。
雨水が入るのを防いだり、風で飛ばされないようにするためのものだそうです。
こんな彫刻を施すなんて、おしゃれですね。
波に乗ったウサギや、亀もいるそうですよ。
次回行ったときは探さねば。
もう一つ気になったのが、このすごい形のクスノキ。


中がえぐれていて、根元だけ見ると死んでそうですが生きています。
こんな形になってしまうなんて、いったい何があったんでしょうか。
気になります。
この日のランチは中宮寺近くの「和CAFE 布穀薗」でいただきました。

幕末・維新期の尊攘運動家、明治期の司法官である北畠治房が晩年隠棲していた屋敷だそうです。
屋敷の長屋門がカフェになっています。
こちらで斑鳩名物 竜田揚げランチをいただきました。

竜田揚げの竜田は、斑鳩町を流れる竜田川に由来するとのこと。
百人一首にも竜田川が出てきますが、昔から紅葉が有名な場所だそうです。
揚げたときの赤くなる醤油の色や、片栗粉がところどころ白く浮かぶさまを、紅葉が流れる竜田川に見立てて、その名がついたそうです。
店内からは母屋が見えます。

のんびり一人ランチ。
たまにはこういう時間もいいものですね。

久しぶりに法隆寺と中宮寺を訪れましたが、新しい発見がいろいろあり楽しかったです。
ぜひまた訪れたいと思います。

…おまけ…
法隆寺駅前でポケモンマンホール見つけました