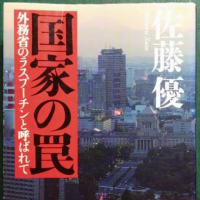佐藤優氏を知るために、初期の著作を読んでみました。
まずは、この本です。
佐藤優『国家の罠 ―外務省のラスプーチンと呼ばれて』

ロシア外交、北方領土をめぐるスキャンダルとして政官界を震撼させた「鈴木宗男事件」。その“断罪”の背後では、国家の大規模な路線転換が絶対矛盾を抱えながら進んでいた―。外務省きっての情報のプロとして対ロ交渉の最前線を支えていた著者が、逮捕後の検察との息詰まる応酬を再現して「国策捜査」の真相を明かす。執筆活動を続けることの新たな決意を記す文庫版あとがきを加え刊行。
国家の罠 ―外務省のラスプーチンと呼ばれて
□序 章 「わが家」にて
□第1章 逮捕前夜
■第2章 田中眞紀子と鈴木宗男の闘い
■「小泉内閣生みの母」
□日露関係の経緯
□外務省、冷戦後の潮流
□「スクール」と「マフィア」
□「ロシアスクール」内紛の構図
□国益にいちばん害を与える外交官とは
□戦闘開始
□田中眞紀子はヒトラー、鈴木宗男はスターリン
□外務省の組織崩壊
□休戦協定の手土産
□外務官僚の面従腹背
□「9・11事件」で再始動
□眞紀子外相の致命的な失言
□警告
□森・プーチン会談の舞台裏で
□NGO出席問題の真相
□モスクワの涙
□外交官生命の終わり
□第3章 作られた疑惑
□第4章 「国策捜査」開始
□第5章 「時代のけじめ」としての「国策捜査」
□第6章 獄中から保釈、そして裁判闘争へ
□あとがき
□文庫版あとがき――国内亡命者として
※文中に登場する人物の肩書きは、特に説明のないかぎり当時のものです。
「小泉内閣生みの母」
「自民党をぶっ壊す」――。
そんなスローガンを掲げて小泉純一郎内閣が誕生したのは、2001年4月26日のことだった。発足時の支持率は80パーセントを超え、森前内閣の不人気で崩壊の危機に瀕しているとすら言われた自民党は、小泉総理の言葉とは裏腹に奇跡的な復活を果たしたのだった。
小渕恵三(おぶちけいぞう)総理の緊急入院を受けて、自民党の実力者5人の指名により後継総裁となった森喜朗(よしろう)氏だったが、密室で誕生したと批判された森内閣は低支持率に苦しみ、わずか1年で崩壊。同時に自民党自体も危機的な状況に陥ってしまう。
進退窮まった自民党執行部が目をつけたのが、政界では「変人」といわれた小泉氏だった。少なくとも当時は妥協を許さないといわれた小泉氏の政治姿勢は、多くの国民から強い支持を受けた。そして、この時「小泉内閣生みの母」の役目を果たしたのが、田中眞紀子女史だった。
従来の永田町政治のメインストリームからは“異邦人”だと見られており、それゆえ人気も高かった小泉・田中の二人が手を組んで登場してきたことで、国民的な熱狂は一大ブームとまでなる。それは、1993年に日本新党ブームを巻き起こし、自民党を政権与党から引きずり下ろした細川護熙(もりひろ)内閣誕生の再現を見ているかのようだった。異常な興奮は田中眞紀子女史が小泉新政権において外務大臣という重要閣僚のポストに就いたことで、最高潮に達する――。
それから、約4年を経た今日。小泉首相と田中女史とのコンビは早々に解消され、田中女史の姿は政権内どころか、自民党にすらない。そして、支持率維持を“最優先課題”にして場当たり的な印象の強い政治を行ってきた小泉首相の人気にも、いよいよ本格的にかげりが見え始めてきている。
「構造改革なくして景気回復なし」――。
就任当時、小泉首相が何度となく繰り返したこのスローガンを今思い返すと、多くの人々は空々しい気分になるかもしれない。「改革などほとんど実現しなかったではないか」、「小泉政権の公約は空約束のオンパレードだ」という声も聞こえてくる。
確かにそれはその通りだ。小泉首相が改革の俎上にあげた個別の組織や制度に関しては中途半端な点が目立つのも事実である。
しかし、日本という国の根本的な方針が、小泉政権の登場前と後では大きく変貌を遂げたというのが、私の分析である。歴史を振り返った時、あの時がターニングポイントとなったという瞬間がある。
「小泉内閣の誕生」は、日本にとってまさにそんな瞬間だったのではないだろうか。
それではいったい、何がどう変わったのだろうか。
外務省に話を移そう。
小泉政権がスタートしたとき、自民党同様に外務省もまた、未曾有の危機に瀕していた。年明け早々に松尾克俊元要人外国訪問支援室長の内閣官房報償費(機密費)詐取事件が明るみに出たのをきっかけに、「組織ぐるみ」の機密費流用や首相官邸への機密費「上納」などの疑惑は芋づる式に広がった。こうした「腐敗」は世論の猛烈な怒りを買った。
一方、この時期、本業である外交活動でも停滞が目立っていた。特に森前総理とプーチン大統領の間で行われた日露首脳会談について、北方領土問題の解決を遠ざけたのではないかという批判が強まった。2000年までに日本とロシア間で平和条約を締結するという外交目標があったのに、結局はその具体的な道筋をつけることができなかったからである。
そんな状況に置かれた外務省に、世論の圧倒的な後押しを受けて、意気揚々と乗り込んできたのが田中眞紀子女史だったというわけだ。
2001年4月。外務大臣に就任した田中女史は、自民党守旧派の幹部として、また、外交族として同省に影響力を持っていた鈴木宗男氏と鋭く対立。二人は「天敵」同士として泥仕合を繰り広げ、外務省を大混乱に陥れた――。
田中女史が外相のポストにあった約9ヶ月の間、新聞、テレビや週刊誌など多くのマスコミは基本的にこの構図で二人の関係を取り上げた。しかし、実態はそう単純なものではなかった。そこには外務省内部の権力闘争、「知りすぎた」政治家を排除したいという外務省の思惑、自民党内の内部抗争、また、支持率維持を最優先とする官邸の思惑など、さまざまな要素が複雑に絡み合っていたのである。
当初、鈴木氏は田中女史と対決する気持ちを全くもっていなかった。
実は、後に「宗男対眞紀子の対決」としてマスコミが取り上げた抗争の始まりは、最初の段階では外務省内のひとつの部署のゴタゴタに過ぎなかったと言えるだろう。
4月26日深夜、田中眞紀子女史が外相就任会見を行った後、私と東郷和彦欧州局長は、鈴木宗男氏を訪ね、ざっくばらんに話をした。因みに外務省では01年1月6日 に機構再編が行われ、オーストラリアやニューギニアなどの太平洋州諸国が欧亜局からアジア局に移管され、名称もそれぞれ欧州局、アジア大洋州局に変更された。
田中女史は記者会見で、今後の日露関係について「1973年の田中(角栄)・ブレ ジネフ会談が原点だ。(中略)当時は四島一括返還でということだったが、途中で二島先行して返還してもらうのがいいのではと方向転換している。もう一度原点に立ち返り、しっかり検討したい」と述べたのだが、そのことは、既に日露外交専門家の間では日本政府の外交方針転換に繋がると大きな波紋を呼んでいた。深夜であるにもかかわらず、在京ロシア大使館幹部からも私のところに「田中外相の真意をどのように理解すればよいのか」と照会の電話があった。
鈴木氏は「東郷さん、田中大臣は事情をよくわからないで、田中角栄に対する強い思い入れであのような発言をしているのだから、あんた、事情を丁寧に説明してやってくれ」と言った。東郷局長は、「私は以前から田中大臣とは面識があるので、私が説明すればきっと理解してくれるでしょう」と楽観的だった。しかし、後になって考えると東郷氏の「説明」が田中眞紀子女史の鈴木宗男氏、東郷和彦局長、私に対する心証を悪化させる端緒になった。
深夜、東郷局長は説明用の書類を作り、翌日、外務大臣室を訪れ、田中眞紀子女史に日露関係について説明した。東郷氏は話術が巧みで、特に政治家に対して複雑な外交案件をわかりやすく説明する才能がある。ただし、気分が高揚すると声が大きくなり、時に机を叩いたりして熱を込めて説明することがある。このときはそれが裏目に出た。この説明の直後、東郷氏から私のところに電話がかかってきて、「田中大臣は忙しく、今日は十分時間をとることができなかったので、2、3日中にもう一度時間を作ってもらう」と言っていたが、結局、東郷氏が北方領土問題について田中女史に説明する機会はその後永遠にやってこなかった。
その数日後、私は外務省幹部に呼ばれた。この幹部は、ロシア専門家ではないが、戦略的思考に優れているのみならず、口が堅く、腹も据わっているので、私も気を許して、日露関係や情報の世界の話だけでなく、日本の国内政局動向についても見立てを率直に言うような関係だった。
「東郷の大臣への説明はまずかったな。田中大臣は東郷に恫喝されたと言いふらしているよ。それから、誰が吹き込んだのかわからないが、田中さんは君のことを『ラスプーチン』と呼んでいて、『ラスプーチンを早く異動させろ』と言うんだ。田中さんは『世の中には、家族、使用人と敵しかいない』と公言しているんだけど、君や東郷に対する目つきは敵に対する目つきだ」
私は「仕方ありませんね。現代心理学でも、ある人が何かを考えることを外部から禁止できないというのが基礎理論ですから、田中さんがそう思っているならば、私はいつでも異動しますよ」と答えると、その幹部は、こう言った。
「まあ、そう言うなよ。君にしたって俺にしたってお国のために仕事をしているんだからな。大臣の使用人じゃないよ。とにかく田中さんは自分のお父ちゃん(田中角栄)は偉い。だから、日露関係でも田中・ブレジネフ会談が原点なんだ。それから自分のお父ちゃんを裏切った経世会(橋本派)は許せないという、この二つの想いで動いている。鈴木(宗男)さんは、橋本派だし、どうも田中・ブレジネフ会談と違う流れを作ったので、絶対にやっつけてやるという気持ちになっている。まあ、うまく逃げ切ることだ。君が婆さん(田中眞紀子女史)の言うなりになったら、日本の国のためにならないよ」
【解説】
従来の永田町政治のメインストリームからは“異邦人”だと見られており、それゆえ人気も高かった小泉・田中の二人が手を組んで登場してきたことで、国民的な熱狂は一大ブームとまでなる。(中略)異常な興奮は田中眞紀子女史が小泉新政権において外務大臣という重要閣僚のポストに就いたことで、最高潮に達する――。
外交に無知で、「自分と家族と使用人以外は敵だ」という考えの田中眞紀子女史が外務大臣になったことが悲劇の始まりでした。
獅子風蓮