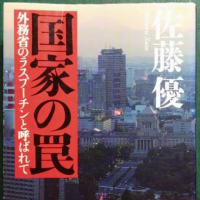佐藤優氏を知るために、初期の著作を読んでみました。
まずは、この本です。
佐藤優『国家の罠 ―外務省のラスプーチンと呼ばれて』

ロシア外交、北方領土をめぐるスキャンダルとして政官界を震撼させた「鈴木宗男事件」。その“断罪”の背後では、国家の大規模な路線転換が絶対矛盾を抱えながら進んでいた―。外務省きっての情報のプロとして対ロ交渉の最前線を支えていた著者が、逮捕後の検察との息詰まる応酬を再現して「国策捜査」の真相を明かす。執筆活動を続けることの新たな決意を記す文庫版あとがきを加え刊行。
国家の罠 ―外務省のラスプーチンと呼ばれて
□序 章 「わが家」にて
□第1章 逮捕前夜
□第2章 田中眞紀子と鈴木宗男の闘い
□「小泉内閣生みの母」
□日露関係の経緯
□外務省、冷戦後の潮流
□「スクール」と「マフィア」
□「ロシアスクール」内紛の構図
□国益にいちばん害を与える外交官とは
□戦闘開始
□田中眞紀子はヒトラー、鈴木宗男はスターリン
□外務省の組織崩壊
□休戦協定の手土産
■外務官僚の面従腹背
□「9・11事件」で再始動
□眞紀子外相の致命的な失言
□警告
□森・プーチン会談の舞台裏で
□NGO出席問題の真相
□モスクワの涙
□外交官生命の終わり
□第3章 作られた疑惑
□第4章 「国策捜査」開始
□第5章 「時代のけじめ」としての「国策捜査」
□第6章 獄中から保釈、そして裁判闘争へ
□あとがき
□文庫版あとがき――国内亡命者として
※文中に登場する人物の肩書きは、特に説明のないかぎり当時のものです。
外務官僚の面従腹背
外務省内部での田中女史と事務方(官僚)の対立も、2001年8月10日の川島裕事務次官の退官、野上義二新事務次官の就任により新たな局面に入った。
退任記者会見で川島次官が外務省員に「グッドラック(うまくやれ)」と呼びかけたのは、どんなに厳しい状況でもユーモアを忘れない川島氏らしかった。
野上体制の成立と共に田中女史を所与の条件とみなし、外務省幹部の中で田中大臣と折り合いをつけようとする雰囲気が強まってきた。「田中眞紀子はインフルエンザだが、鈴木宗男は癌だ。この機会に治療しておかないと命にかかわる」との話が私の蜘蛛の巣にも引っかかってくるようになった。他方、外務省は怪文書を継続的に作り、鈴木宗男氏に田中女史に関する否定的情報を流し続けた。
田中外相の長期登板が確実との見通しが強まると、外務省の機能低下が著しくなった。01年1月に発覚した内閣官房報償費(機密費)詐取事件に関する捜査が進み、腐敗の構造が明らかにされるにつれて、外務省課長クラス以下は、上層部に対する不信感を強めた。外務省内の権力抗争は複雑なモザイク画を作った。
親田中眞紀子の立場を公言する官僚は少なかったが、外務省の腐敗構造を暴き、膿を出し切るには田中女史の破壊力に頼るしかないと考える者は少なからずいた。それに自らの立身出世のために田中女史に擦り寄る人々が加わった。これらの人々にとって、第一の敵は鈴木宗男氏であり、その「御庭番」であるラスプーチン、つまり私だった。そのため、私の信用失墜を図る動きも活発になった。
親鈴木宗男の立場を公言する外務官僚は、私を含め少なからずいた。主として、これまで鈴木氏と外交案件を共に進め、鈴木氏の外交手腕と政治力に一目置いている外務官僚だった。しかし、この中にも温度差があった。カラオケバーで、ある後輩が酩酊して、私に絡んできた。
「僕だって鈴木さんは重要と思いますよ。しかし、あの人は総会屋だ。総会屋は病理のある企業に巣食う。だから病んだ外務省にとって与党総会屋の鈴木さんは重要なんです。佐藤さんは総会屋担当の係長だったんだけれども、今や鈴木さんの利益を体現する企業舎弟になってしまった。佐藤さんを慕っている後輩は多いんですから、少し鈴木さんと距離を置いてくださいよ。身内では鈴木さんに対する批判もきちんとすべきですよ」
私はその間には答えずに、「飲み足りないようだな。もっと飲めよ」と言って、ロックグラスにウイスキーをなみなみと注ぎ、ロシア風に右手を組み合わせて(ブンデルシャフト)、後輩と一気のみをした。そして、頬に3回キスをした。後輩は絨毯の上に倒れ、激しく嘔吐した。
私が見るところ、外務官僚の最大公約数は以下のようなことを考えていた。
「田中が狼なら鈴木は虎、眞紀子が毒蛇ならば宗男はサソリ、お互いに噛みつき合って、両方とも潰れてしまえばよい。そして、外務官僚によって居心地のよい『水槽』の秩序を守ることができればよい」――。
もちろん外交官が自己保身だけに走っていたということではない。外交を機能的に行うためには「水槽」がきれいになって、熱帯魚(外交官)たちが「水槽」の中で安心して生活することが不可欠と考えたのである。
外交政策上の観点からは、前述したようにアーミテージ国務副長官との会談をドタキャンし、その後、アメリカのミサイル防衛政策に批判的発言をする田中女史に外務省内「親米主義者」は危惧を強めた。一方、「アジア主義者」は、中国への思い入れの強い田中女史を最大限に活用しようとした。「地政学論者」は、田中女史がいる限り、戦略的外交は展開できないと、半ば諦めの気持ちでやる気をなくしていった。
こうした状況のなかで、これまでの鈴木宗男氏との距離関係、外務省内部の人脈が複雑に絡み合い、混乱状態に陥った外務省内では誰が敵で誰が味方か全くわからなくなっていた。
たとえば、中国語専門のある中堅幹部の例をとってみよう。
「チャイナスクール」の一員としては、田中女史が外務大臣にとどまることは好都合である。但し、中国は政府開発援助(ODA)の主要対象国であるのに、田中女史のODAに対する理解は薄い。鈴木氏は中国とも良好な人脈をもつ。外務省はODA予算で以前から鈴木氏の応援を受けてきた。鈴木氏の専門知識に裏打ちされた政治力の重要性もよくわかっている。
以上の要素を総合的に考慮すると、この中堅幹部は自らの立場を一方の側に置くことはできないのである。従って、田中女史、鈴木氏の双方と良好な関係を維持しようとする。外務省執行部は、この中堅幹部がもつ田中女史と鈴木氏との良好な関係を組織維持のために使おうとする。知らず知らずのうちに、中堅幹部は、危険な政治ゲームに巻き込まれて、イソップ物語の蝙蝠の機能を果たすことになる。私の場合は、田中女史にとって私は「使用人」ではなく、「敵」であったから、蝙蝠になる運命からは免れていた。これは私にとって幸せなことだった。
【解説】
私が見るところ、外務官僚の最大公約数は以下のようなことを考えていた。
「田中が狼なら鈴木は虎、眞紀子が毒蛇ならば宗男はサソリ、お互いに噛みつき合って、両方とも潰れてしまえばよい。そして、外務官僚によって居心地のよい『水槽』の秩序を守ることができればよい」――。(中略)
こうした状況のなかで、これまでの鈴木宗男氏との距離関係、外務省内部の人脈が複雑に絡み合い、混乱状態に陥った外務省内では誰が敵で誰が味方か全くわからなくなっていた。
当時の外務省内の複雑な人間関係を分かりやすく記述しています。
ある意味、とても貴重な記録です。
獅子風蓮