坪谷ニュウエル郁子(東京インターナショナルスクール理事長)さんがブログに下記の内容を紹介されていました。(出典を確かめていますが、たぶん記憶に間違いはないと思いますが?・・・)
「アメリカ国務省職員の世界各国派遣駐在員研修の言語に関して、速習プログラムがあるそうです。その研修時間は、日常会話レベルまで習得させるケースで、アメリカ人が比較的習得が易しい言語でおよそ480時間。アメリカ人から見て最も難しい日本語は、およそ2760時間で、研修時間は6倍弱になります。1日8時間研修に当てても、345日。ほぼ1年間ということです。逆に日本人がネイティブレベルの英語を操るには、345日の倍の690日はかかる」とのこと。
かように英語と日本語とは構造やつくりやルール等、振り子でいうところの端から端で一番離れているようで、ですから習得するのは難しく時間もかかるわけです。
ちなみに、英語と日本語の文の構造・ルール(文法)は、次に示すとおりで、日本語は察する文化と言われていることから述語(動詞)が最後にくる文の組み立てになっています。さらに、主語が明記されていない文も目立ちます。
◎主語(S)+述語(動詞V)+目的語(O)+飾り等(修飾語)
英語、中国語、仏語・スペイン語・ポルトガル語等のヨーロッパ語
◎ 主語(S)+飾り等(修飾語)+目的語(O)+述語(動詞V)
日本語等
立教大学名誉教授鳥飼玖美子さんが語っていました(朝日新聞2019年11月18日朝刊)。
「英語の4技能、読む、聞く、書く、話す、の土台は読解力、つまり『読む』こと。読むことによって、単語の使い方や文章の組み立てを学び、それをもとに書くことを学ぶと、聞いて分かるようになる。そして話せるようになるのです。さらに高校までは英語の基礎を作り、その上で高校卒業後に、大学や社会で話す力を磨けばいいと考えます。そのためには、中学校の英語教育に資源を投入すべきです。中学生は記憶力や吸収力が抜群で、母語を土台に分析的に学ぶこともできます。少人数クラスにして、教員の質と数を確保すれば、成果は出るはずです。」
「アメリカ国務省職員の世界各国派遣駐在員研修の言語に関して、速習プログラムがあるそうです。その研修時間は、日常会話レベルまで習得させるケースで、アメリカ人が比較的習得が易しい言語でおよそ480時間。アメリカ人から見て最も難しい日本語は、およそ2760時間で、研修時間は6倍弱になります。1日8時間研修に当てても、345日。ほぼ1年間ということです。逆に日本人がネイティブレベルの英語を操るには、345日の倍の690日はかかる」とのこと。
かように英語と日本語とは構造やつくりやルール等、振り子でいうところの端から端で一番離れているようで、ですから習得するのは難しく時間もかかるわけです。
ちなみに、英語と日本語の文の構造・ルール(文法)は、次に示すとおりで、日本語は察する文化と言われていることから述語(動詞)が最後にくる文の組み立てになっています。さらに、主語が明記されていない文も目立ちます。
◎主語(S)+述語(動詞V)+目的語(O)+飾り等(修飾語)
英語、中国語、仏語・スペイン語・ポルトガル語等のヨーロッパ語
◎ 主語(S)+飾り等(修飾語)+目的語(O)+述語(動詞V)
日本語等
立教大学名誉教授鳥飼玖美子さんが語っていました(朝日新聞2019年11月18日朝刊)。
「英語の4技能、読む、聞く、書く、話す、の土台は読解力、つまり『読む』こと。読むことによって、単語の使い方や文章の組み立てを学び、それをもとに書くことを学ぶと、聞いて分かるようになる。そして話せるようになるのです。さらに高校までは英語の基礎を作り、その上で高校卒業後に、大学や社会で話す力を磨けばいいと考えます。そのためには、中学校の英語教育に資源を投入すべきです。中学生は記憶力や吸収力が抜群で、母語を土台に分析的に学ぶこともできます。少人数クラスにして、教員の質と数を確保すれば、成果は出るはずです。」










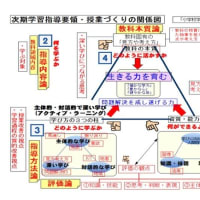
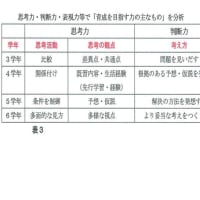
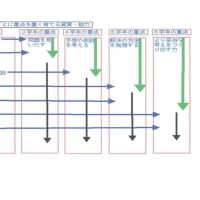
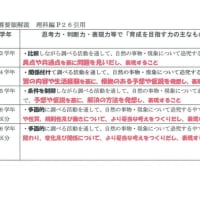
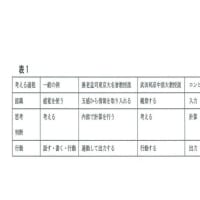
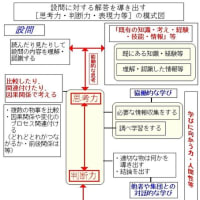
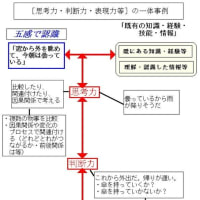
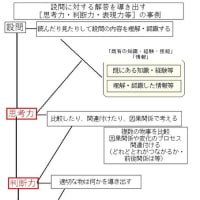
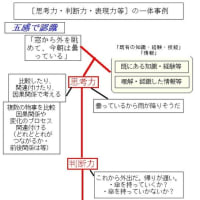
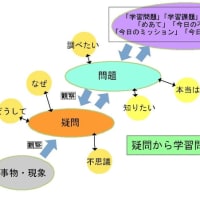
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます