71歳で心臓弁膜症を患い手術退院と同時に49年余り続いた仕事から解放。現在後期高齢者の仲間入り。「人生100年時代」を声高に語る自信が持てない自分がいる。だが、いま手元にある書名「100年学習時代」サブタイトル(はじめての「学習学」的生き方入門)本間正人著を読み始め、訝っている内心に変化が生じている。
著者は学校等で学んだ「最終学歴」はもちろん重要だが、100年学習社会では「最終学習歴」がその人物の真の実力を表していることになると主張している。であるから「最終学習歴」のアップデートが人生においては極めて重要になると強調。人生100年時代は常に「学び・学習」し続けなければ満足した人生を送れないことへの警鐘を鳴らしている。
国際社会の展開が加速度的に進行し、それを少なからず支えている半導体等の技術がAIに代表される人工知能の登場を促がしている。よって人々の生活スタイルや思考等のものの見方や考え方、扱い方の変容を助長している。
「最終学歴」で身に付けたことを活かして仕事等が満足にできる期間が極めて短くなっていると素朴に思う。世の中の事物や現象がブラックボックス的なことが多くなっていることに驚く。コンピュータの原理は知らなくても操作方法を会得すると文字は打てるが、詳しい扱いは深くコンピュータの原理や操作を学ばないとその域に達することができない。同様に現象面においては、新聞やテレビなどのマスコミ等から流れるニュースや情報の信憑性を見分けるには、一定程度の前もっての情報や知識の定着が判断の眼力になる。
これらを仕事の生業にするためには、その数十倍、数百倍の情報収集や知識や技能の習得が必須になる。であるから学校で学んだ内容(「最終学歴」=「最終学校歴」)よりも、キャリアを積みながらセミナーや講座、通信、読書、再入学等々(「最終学習歴」)がものを言う時代になっていると著書は語っている。
ところで、地球の歴史を一日で表したら今は何時何分かという身近な時間軸に類推する表し方があるが、著書に「人生100年を1日24時間に比べてみる」と紹介されている。例えば、
・15歳・・・午前3時36分 ・20歳・・・午前4時48分
・25歳・・・午前6時 ・還暦60歳・・・14時24分
私の年齢である後期高齢者75歳は夕飯時の18時に当たる。日本酒で喉を潤しつまみを美味しくいただき、今日の疲れをいやすひと時。まだ6時間もあると思うとなぜか身体か熱くなり、新しい想いが湧き出てくる。










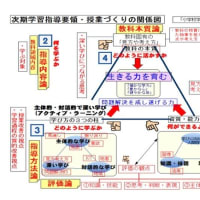
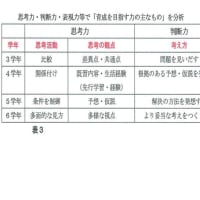
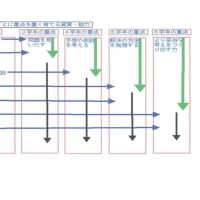
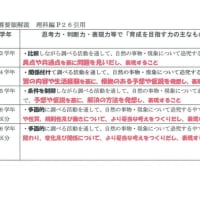
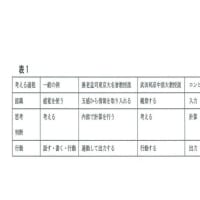
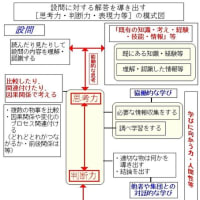
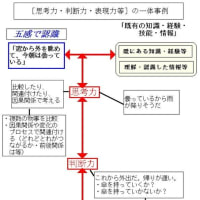
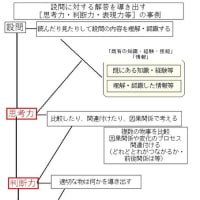
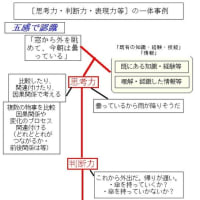
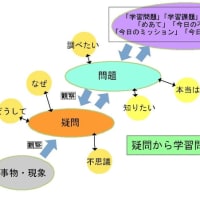
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます