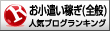このコルト600は白銀色に輝いている。啓太は車に乗り込むとギアやブレーキなどを点検したあと、駐車場からゆっくりと出発した。初めての路上運転なので緊張する。絶対に「安全第一」と自分に言い聞かせながら、コルト600を走らせた。そうは言っても、自分の車だと思うと胸が高鳴ってくる。自然に誇らしい気持になるのだ。
ところが、彼が山手通りに出て北へ向かう途中の西池袋付近だったか、車が何かの拍子で突然 エンスト(エンジンストップ)を起こした。焦って何度もエンジンをかけようとしたが、なかなかかからない。道路の真ん中で立ち往生になった。すると、後ろのトラックの運転手が怒鳴った。
「バッカヤロー! おんぼろ車に乗るな!!」
そう叫んで、トラックの運転手はコルト600を追い越していった。啓太は冷や汗が出る思いだった。当時の車はよくエンストを起こしたのである。ようやくエンジンがかかると、彼は気を取り直して運転を続けた。ギア操作を誤るとエンストが起きやすい。それに万全の注意を払いながら車は進んでいく・・・
ところが、今度は志村(板橋区)に近い中山道の交差点で、右から車が来る気配がして啓太は“急ブレーキ”をかけた。しかし、車は入って来なかった。明らかに誤認である。すると、追突しそうになった後ろのタクシーがけたたましくクラクションを鳴らし、車をコルト600の右前方に停車させた。運転手がもの凄い表情で啓太をにらみつける。彼はあわてて頭を下げた。
コルト600を遮ったタクシーはそのまま先に進んでいったが、啓太は度重なるトラブルにどっと疲れが出る感じだった。こうして初の路上運転は四苦八苦の連続だったが、彼はなんとか浦和の自宅にたどり着いたのである。しかし、車を無事に車庫に入れると、運転席でしばらく放心状態になっていた。
その日から、啓太は暇さえあれば車を動かした。父の送り迎えも適当にやった。親戚や知り合いの人が来ると、進んで浦和駅などへ送っていったりしたのだ。こうしてドライブに次第に慣れていったが、会社への通勤にはなかなか運転はできなかった。当時は車の通勤が許されていたが、都内を長時間 運転するには、まだ自信が持てなかったのである。それに、車だと渋滞や交通事故の余波で出勤時間に遅れることもあるからだ。
やがて、真夏の季節がやって来た。夏休みはまだ決まっていなかったが、ある日、五代厚子から電話がかかってきた。
「山本君、来週の土、日に辻堂の海の家へ行ってみない? 金曜日の夜に出発するの。わたしの車でどう? 何人か行くわよ」
「何人かって、誰と誰かしら?」
「え~と、森末君と知子さん。あとはまだ未定よ」
江藤知子の名前を聞いて、啓太はとたんに冷ややかな気持になった。どうしようか・・・行くかどうか決めかねていると、厚子がさらに言った。
「迷ってないで、いらっしゃいよ。知子さんとも久しぶりでしょ? 仲直りしなさい」
彼女がそう言うので、啓太はやっと応じる返事をした。いつも一緒に来る石黒は所用があって来ない。だいぶ気乗りがしなかったが、厚子の熱意にほだされた感じだ。それでも電話を切ると、啓太は厚子とのドライブを想像してようやく気を取り直したのだった。
1週間はすぐに過ぎて、辻堂へ行く日が来た。夕方、会社から厚子の車に乗り込むとまず四谷駅前に向かった。そこで森末と江藤知子を乗せたが、彼女が助手席に座った。2人はそれぞれの都合で四谷で待ち合わせていたのだ。
「山本君、久しぶりね。元気にしてる?」
知子が快活な声を上げて話しかけてくる。彼女は2カ月ほど前に、JOUCHI大学で同期の彼氏と結婚したばかりだった。気のせいか、余計に生き生きした感じに見える。
「ああ、なんとかやってるよ。知子は相変わらず元気がいいな。うらやましいね」
啓太がなんとか彼女の“口舌”をかわすと、今度は森末が口を出した。
「知子は毎晩、旦那からエネルギーを吸い取ってるんだよ。新婚の味はいいだろ?」
「まあ、いやらしい! 森末君の話はいつも下品に聞こえるわね!」
運転している厚子も啓太も苦笑した。森末はなんでもはっきりと言う質(たち)で、以前、啓太がしょっちゅうアナウンス室へ通った時は見かねて、「もう、あまり来るな!」と怒鳴ったりした。彼は部長やデスクの気持を代弁したのである。しかし、さっぱりした性格なので啓太は一目置いていた。森末に怒鳴られてから、啓太は用もないのにアナウンス室へ行くようなことは止めたのだ。
車は第一京浜道を通って横浜に入った。途中、厚子は知人の家に立ち寄って野暮用を済ませたあと、まっすぐに辻堂海岸へ向かった。
「報道の窪川さんも海の家に来ると思うわ」
えっ、窪川先輩も? 厚子の突然の話に啓太は面食らった。そんな話は聞いていないじゃないか。彼女が辻堂へ「何人か行く」と言ったのは、そういう意味なのか。
「窪川さんも来るの? それは賑やかになるね」
「あとは彼の友人が1人か2人かな」
啓太が相槌を打つと厚子は弾んだ声で答えた。海の家は辻堂海岸から少し奥まった所にある。ここはFテレビが契約した民宿で、夏になると社員やその関係者が利用するのだ。厚子のトヨペット・コロナは間もなく海の家に着いた。啓太と森末、厚子と江藤知子がそれぞれ部屋に入って休んでいると、やがて夜食の時間になった。
すると、ほどなくして窪川が1人の男を連れて現われた。その男は30歳を超えたぐらいか、長身で日に焼けたたくましい感じがする。
「やあ、皆さん、お待たせ。彼は私の友人で阿部君と言います。どうぞよろしく」
窪川が阿部を紹介したあと、6人で賑やかな酒盛りパーティーが始まった。みんなアルコールには慣れていて、啓太も入社後、自然に酒に親しむようになっていた。報道の連中とも飲むし、タバコも吸うようになった。だから酒盛りには何の違和感もない。みんなの話を聞いて楽しんでいたが、厚子がことさら窪川に話しかけるのだ。
「窪川さんはどうしてまだ“独身”なんですか?」
「ハッハッハッハ、どうしてって、女性に持てないだけだよ」
「そんなことはないでしょ。窪川さんは報道のエリートだもの」
酒が入るとざっくばらんになってくる。窪川は30を過ぎたのに独身だから、当時としては珍しかったのか・・・ こういう話は若い人たちの間では当たり前だが、啓太にとっては厚子が窪川におもねっているようで不愉快だった。
「この阿部君もまだ独身だよ。良かったら付き合ってみたら。そうそう、江藤君はこのあいだ結婚したばかりだな。そうすると、資格があるのは五代君だけか。良かったらどうぞ、ハッハッハッハ」
窪川は上機嫌で話をリードしていった。森末も江藤知子を冷やかしたりして、話に茶々を入れる。阿部君も入れてみんなは楽しそうにしていたが、この間、厚子は窪川に首ったけという感じで、啓太の方にはほとんど見向きもしない。彼だけが“のけ者”にされた感じだった。こうして3時間ぐらいがあっという間に過ぎ、みんなはそれぞれ自分の部屋に戻っていった。
翌朝、食事を済ませると6人は海水浴場へ向かった。じりじりとした夏の強い陽射しが照りつける。啓太は少し二日酔いだったが、森末と並んで張り切って出かけた。水泳は森末と阿部君が得意で、啓太と窪川はあまり泳げない。2人の女性も泳ぎは不得手だが、みんな更衣室で水着に着替えるとわれ先に海辺へと出た。
厚子は色白ではないが、江藤知子はもっと肌が浅黒く健康そうに見える。
「知子は本当にトランジスター・グラマーだな~」
森末が冷やかすと、彼女は満面に笑みを浮かべてやり返した。
「なに言ってるの! 森末君こそお腹がけっこう出てるわよ!」
「言ったな~! 新婚め」
森末が知子を追いかけると、彼女は笑い声を上げて逃げまわる。溢れんばかりの陽光の下で若者たちの楽しい海水浴が始まった。みんなは適当に泳いだり浜辺でわいわい騒いだりしていたが、そのうちにまた、厚子は窪川と談笑に打ち興じるようになった。啓太は2人の間に割って入ろうと思ったが、厚子がまったく相手にしないという態度だったのでだんだん嫌気が差してきた。
彼女は時おり啓太の様子をうかがうだけで声をかけてこない。軽い昼食の時間になっても、厚子と窪川だけが楽しそうに話し、啓太はまったく無視されているように感じた。そのうち森末と阿部君も談笑に加わり、にぎやかな会話が渦を巻く。啓太は自己中心的でわがままなのか、そういう雰囲気に耐え切れなくなった。
「僕はもう帰ります。明日の大宅壮一サンデーニュースの準備がありますから」
彼はそう言うと、みんなが不審に思う間もなくすぐに帰り支度を始めた。『サンデー・ニュースアワー』の準備だなんて単なる口実だ。ニュースは日曜夕方の放送だから、辻堂にもう一泊しても十分に間に合う。しかし、啓太はこれ以上 厚子と窪川の親密な様子を見たくはなかった。
「もう帰るのか? 山本は“せっかち”だな」
森末が声をかけるが、啓太は軽く会釈して逃げるようにその場を立ち去った。そのあと、彼はバスや電車を乗り継いで夕方には浦和の自宅に戻った。厚子に馬鹿にされた悔しさがじわじわと胸に広がってくる。彼女はわざと啓太を無視したのか。それとも、本当に窪川に好意を寄せているのか・・・ それらの疑問が沸き上がって、彼は悶々とした気持になったのである。
翌日の日曜日、啓太はよく睡眠を取って起きると、わりとさわやかな気分になっていた。辻堂のことは気にしないようにして昼前、コルト600に乗り家を出た。仕事があると気分転換になる。嫌なことは忘れて、運転に注意しながらテレビ局へ向かうだけだ。
1時過ぎにFテレビに着くと、早速、夕方のニュースの準備に取りかかった。星野ディレクターの指示に従い、フィルムやテロップ、フリップなど番組の素材を整える。そして、ニュース原稿を2~3本用意するのだ。残りの原稿は内勤整理班の何人かがまとめてくれる。こうして、夕方5時30分の『大宅壮一サンデー・ニュースアワー』の放送を待つのだ。
この日は何のトラブルもなく、30分の放送は無事終了した。大宅さんもようやくテレビに慣れてきて、コメントを要領よく伝える。彼の出社から退社までの面倒は、啓太がすべて受け持っているのだ。大宅さんを車で送り出して、啓太もコルト600で家路についた。夏の夕暮れは長く感じる。運転している間に、彼は何組ものアベックを見かけた。
すると急に厚子のことが脳裏に浮かび、啓太は辻堂海岸での苦い光景を思い出した。あのあと、厚子と窪川先輩はどうしたのだろうか。窪川はたしか鎌倉に住んでいるから、彼を車で送っていったのだろうか。いや、彼女の家は平塚だから彼とは逆方向になる。そこまでして窪川を送るはずはないが・・・ そんなどうでもいいことを啓太は考えていた。
家に着くと、母の久乃が声をかけてきた。
「お父さんが明日 出社するので、朝の送りを頼みますよ」
「ああ、分かった」
明日は自分は代休なのだ。父の国義が東京の某会社の非常勤取締役になっているため、時たま車で浦和駅などへ送ったりする。それは良いのだが、啓太は夜食を取るとどうしても厚子に電話をかけたくなった。思い立ったら我慢ができない質(たち)である。彼女はもう自宅に帰っている時間なので、啓太は受話器を取り上げた。
「もしもし、五代さんのお宅で・・・ ああ、厚子さん、山本です。昨日はお先にどうも」
電話の向こうには彼女がすぐに出てきた。
「山本君、ずいぶん早く帰ったのね。残念だったわ。あのあとも楽しかったのに」
厚子がそう言うので、啓太は日曜出勤の“口実”をもう一度話したあと、気になることを聞いてみた。
「そのあと窪川さんを送ったの?」
「ええ、辻堂駅まで送ったわ。そこで別れたの」
そうか、窪川を鎌倉の自宅までは送らなかったのだ。啓太は少しほっとしたが、やはり彼のことが気になる。
「厚子さんはずっと窪川先輩と話していたね。よほど気が合うんだ」
「ずっとじゃないわ。ほかの人とも話していたじゃないの。山本君は話に加わらなかったでしょ?」
「窪川さんと仲が良さそうだから遠慮したんですよ」
「それは“ひがみ”なの? それじゃはっきり言うわ。窪川さんはエリートだし、あなたよりずっと力があるのよ!」
そう言われた途端、啓太は逆上して頭の中が真っ白になった。返す言葉がない。彼は込み上げる悔しさに目頭が熱くなった。しばらく沈黙が続いたが、口を切ったのは啓太だった。
「分かりました! もう、これ以上話すのは止めましょう。失礼しました!」
彼が他人行儀な言葉を使うと、厚子が「ふん・・・」と鼻でせせら笑うような声を出した。啓太は馬鹿にされたように思い乱暴に電話を切った。そしてすぐに自分の部屋に戻ったが、先ほど、厚子が話した「窪川さんはエリートだし、あなたよりずっと力があるのよ!」という言葉が頭にこびりついて離れなかった。
そうだ。窪川先輩はたしかに優秀だし、今は自分なんか足元にも及ばない。そう考えると、啓太は彼に対し激しい劣等感を抱いた。そして、その感情は次第に嫉妬の念に変わっていったのである。しかし、嫉妬するということはこの場合、厚子への好意や恋心と“裏表”ではなかったのか。
啓太はそこまで深く考えなかったが、彼女との関係にしばらく冷却期間を置かざるをえなかったのだ。彼は好きなドライブをしたり、独りで旅行に出かけるなどして夏を過ごした。やがて、啓太にとって大きな転機となる秋を迎えたのである。
それからしばらくして、番組制作班が懸案の「報道討論番組」をスタートさせた。この番組は陣内社長の“鶴の一声”で誕生したものだが、放送が土曜日なので、啓太は土、日の出勤というハードな勤務態勢になった。しかし、その頃はほとんどの会社に週休2日制などはなく、代休を1日取れれば上出来という労働環境だったのである。
討論番組は新任の川崎ディレクターが担当したが、啓太はその下で多くの雑用をこなした。民放初と言ってもいい番組なのでスタッフは張り切ったが、問題はスタジオに一般のオーディエンス(聴衆)をいかに集めるかだった。そういう番組はこれまでになかったからだ。のちに“公募”が当たり前になったが、初めての試みなのでどうしたらいいのかよく分からない。
そこである時、石浜副部長が母校のWASEDA大学雄弁会に声をかけて、20人ぐらいの学生をオーディエンスに来てもらった。啓太も雄弁会の集まりに顔を出して関係をつくったのである。しかし、ある日の放送で、その学生たちが騒ぎすぎて問題になった。討論番組だから与野党の政治家が何人も出ている。ところが、社会党のある議員が話し出すと、猛烈なヤジが巻き起こった。
「やめろ!」「帰れ!」などの罵声に、ある議員はしばしば発言を妨害された。これはまずいと思ったが、放送中なので仕方がない。番組はそのまま続いて終わり、社会党の議員は怒って帰っていった。あとで聞くと、雄弁会の学生はほとんどが右寄りの“民族派”だと分かった。オーディエンスとはいえ、これは公平・中立の放送番組に反するものだ。以後、スタッフは大いに注意して番組づくりに取り組んだのである。
そんなある日、同期アナウンサーの石黒が啓太を喫茶室Fに誘った。2人は会社やレジャーなどたわいないことを話していたが、やがて石黒が五代厚子の話に触れてきた。
「厚子さんとはもうあまり付き合っていないの?」
「うん。このごろはとても忙しくて・・・」
啓太は忙しさを理由に適当に答えたが、厚子との電話のやり取りには一切触れなかった。あれは窪川先輩との件で揉めたから、恥ずかしくて表沙汰にはしたくなかったのだ。窪川の話は啓太にとって“タブー”である。
「今度、厚子さんと3人で飲みに行かないか?」 石黒がこう誘ってきた。
「えっ? ああ、いいよ」
啓太は気のない素振りで返事をしたが、内心は石黒の誘いが好都合だと思った。自分から厚子に言いにくいと感じていたのだ。石黒も満足した様子で、2人はなおしばらくコーヒーを飲みながら雑談していたが、やがてそれぞれの職場に戻っていった。
数日後、昼間に石黒から電話がかかってきた。
「今日は大丈夫だろ?」
「ああ、もちろん」
「それじゃ、厚子さんの車で歌舞伎町へ行くか」
「わかった、久しぶりだね」
電話を切ったあと、啓太は以前3人でジャズ・ライブハウスへ行ったことを思い出した。あのころは厚子にほとんど関心がなく、江藤知子が好きだったのだ。それから知子の婚約を知り、啓太は厚子に自然に惹かれていったような気がする。2人でお好み焼き店に行ったこともある。そうした思い出が湧いてきて、彼はなにか“甘い”気分に浸った。
夕方、仕事を終えると啓太はFテレビの正面玄関に出た。やがて厚子と石黒が現われ、彼女の車で新宿の歌舞伎町へ向かった。駐車したあと3人は狭い路地を数分歩き、あるスナックバーに入った。ここは厚子と石黒の馴染みの店だが、啓太は初めての所だ。厚子を真ん中にしてカウンターに座ると、彼女がすぐに声をかけてきた。
「山本君、辻堂の時はごめんなさいね。もう悪く思わないで」
「いや、いいんです。僕も少し“いらついて”ました。もう、ないことにしましょう」
「山本は気が短いからな。さあ、仲直りだ。ハッハッハッハ」
啓太が答えると石黒も笑い声で応じ、3人はビールとカクテルで乾杯した。啓太は学生時代、飲酒や喫煙、賭け事などにはいっさい関係なかったが、入社して1年半ぐらいたつと、さすがにそれらに慣れてきた。学生のころは極端に“嗜好”を避けていたが、その反動か、今では大いにたしなむようになっていたのだ。
酒量も増え、同期の石黒や小出よりも飲むようになっていた。啓太の父や兄も酒好きだから、それは血筋なのだろう。この日もはじめはビールで乾杯したが、やがてウィスキーのハイボールに手を出した。石黒は適当に飲んでいたが、啓太は3杯、4杯と飲んでいく。酔いがだんだん強まった。
石黒はそのうちマイクを手にし、立ち上がるとジュークボックスにコインを入れて歌い始めた。彼は歌が好きなのだ。
啓太はなおも飲んでいたが、途中でトイレに立った。用を足すとカウンターに戻ったが、その拍子に厚子の背中に右手を添えた。それはごく自然だったが、酔いで気分がおおらかになっていたのだろう。石黒は相変わらず歌っている。
「ねえ、山本君。わたしは結婚したら、いつでも夫を支えるわ。夫が金がないと言えば、いつでもお金を用意するの」
厚子がいきなり妙なことを言った。啓太はハイボールをもう一杯飲むと、彼女になにか甘えたい気分になってきた。彼は急に大胆になって、厚子の肩から背中にかけて手を回し撫で始めた。
「僕はいま厚子さんを触ってるぞ~。おい、石黒、よく見ろよ!」
“酔っぱらい”のたわ言に、石黒は歌うのをやめ大声を出した。
「山本、駄目じゃないか! 厚子さんに触るな!」
カウンターに戻った石黒が、啓太の手を払いのけた。
「この酔っぱらいが・・・」
「ハッハッハッハッハ」
啓太は大笑いすると、酔いつぶれたようにカウンターに顔を伏せた。
「困った奴だな、まったく。厚子さん、悪く思わないでね」
「ううん、いいの」
石黒も厚子もそれほど気にしていないようだった。彼らは啓太のこんなに酔った姿を見るのは初めてだ。やがて店に何人かの客が入ってくる。2人は啓太に水を飲ませたりして、しばらく酔いを醒ませるようにした。そのうち、啓太がようやく酩酊状態から醒めると、3人は割り勘で勘定を済ませスナックバーを出た。
厚子はそのままトヨペット・コロナに乗り込むと、窓から顔を出し別れを告げた。
「今夜は面白かったわ。2人とも気をつけて帰ってね」
彼女の車が走り去ると、啓太と石黒は近くのラーメン店に立ち寄ってから家路についた。
そうしたある日、石浜副部長が啓太に声をかけてきた。
「金森も入れて3人で熱海にでも行ってみるか。伊豆山(いずさん)の保養所に一泊するんだ」
この保養所は健保組合が運営しているもので、啓太も社員旅行で行ったことがある。また2年ほど前には、ここで新入社員研修を受けるなど馴染みのところなのだ。
石浜の誘いに啓太はもちろん応じた。金森を入れた3人はよく酒を飲みに行ったりしている。石浜は2人の若者と飲む時はいつもリラックスして、会社の話や昔話などに花を咲かせるのだ。啓太が承諾したので、金森がすぐに伊豆山保養所の予約を取った。3人が出かけるのは11月初旬の2日間と決まった。
実はその前に、石浜は金森を呼んでこう言った。
「山本は“童貞”だってな。24歳にもなって・・・ 熱海でも行って“筆おろし”をさせるか。君が面倒を見てやれよ。ハッハッハッハ」
そこで3人で伊豆山へ行く話になったが、金森は出発の前日に何も知らない啓太を3階の談話室に連れ出した。
「あす、熱海へ行ったら僕と一緒に遊ばないか?」
「えっ? 遊びって、石浜さんと3人で飲むんじゃないのか」
「それはそうだが、アレもしようということだよ」
アレと言われて、啓太はなんとなく合点が行った。日ごろ、金森がよく“女遊び”の話をしていたからだ。彼の方がその道では啓太よりはるかに通じていた。一方、啓太はまったく“うぶ”と言おうか、その方は一度も経験がなかった。金森からそういう話をされて、彼はすぐに返事ができなかった。
「うん、向こうへ行って考えるよ」
啓太がそう答えると、金森は満面に苦笑いを浮かべてつぶやいた。
「君は“純粋”だな。最近、そういう男は珍しいよ」
金森はそう言って笑い声を上げたが、啓太は無視した。
そして11月初旬、石浜ら3人は代休を利用して伊豆山へ向かった。熱海駅で降りるとタクシーに乗り、保養所には15分ぐらいで着く。そこで風呂に入ったり夕食を取ってくつろいだが、石浜はすぐにマッサージを頼んだ。
「俺は“按摩”をやってるから、君たちは町へ飲みにでも行けよ。ゆっくり遊んで来な」
そういう上司の“指示”で、啓太と金森はまたタクシーに乗り熱海の町中へ向かったのである。啓太は伊豆山保養所には2~3回来ているが、熱海の歓楽街は初めてだ。それに比べて、金森は何度も来ているという。2人は夜の熱海をぶらつき始めた。
「どこへ行く?」
啓太が聞くと金森が答えた。
「うん、糸川(いとがわ)の辺りへ行ってみよう」
糸川辺りというのは“旧赤線地帯”である。ここには旅館やホテル、飲み屋や風俗店などが沢山あり、昔から歓楽街として賑わっていた。こんなところは初めての啓太はキョロキョロと周囲を見回していたが、金森の案内でまず居酒屋に入った。
2人はビールなどで一時を過ごしたが、やがて金森が声をかけてきた。
「どう? これから遊びに行かない?」
「ああ、いいよ。君にすべて任せるさ」
啓太はその場の雰囲気にすっかり溶け込み、なんでもござれという気持になっていた。2人は勘定を済ませると歓楽街に出た。11月初旬にしてはどこか生暖かい気配がする。温泉街だからそう感じるのだろうか。歩いていくうちに○✕風呂(のちに「ソープランド」と言うようになる)の前にきた。こういう風俗店は最近とみに増えており、東京の新宿などでもよく見かけるのだ。
「ここに入ろう」
金森がそう言うので2人は店内に入った。料金を払って待合室にいると、オバサン風の女が2人現われた。どちらがどうということもなく、啓太は中年の小太りの女性について風呂場に入る。中にはスチームバスや湯船、マッサージ台があった。どうしていいか迷っていると、女が言った。
「○✕風呂は初めてなの?」
「ああ、そうだよ」
「なら、わたしが教えてあげる」
啓太は女の指示にしたがって服を脱ぎ、スチームバスに入った。蒸気が体中を熱くする。しばらくすると全身に汗をかいてきた。スチームバスを出ると今度は湯船だ。このあと、彼女が啓太の体を洗ってくれる。そして、マッサージ台へ・・・
「あんたはアレが初めてなの?」
「うん、初めてさ」
「それなら、わたしが上になってあげようか?」
女が言うことに啓太は少しためらったが、はっきりと答えた。
「いや、いいよ。ぼくが上だ」
2人はマッサージ台で“密着”した関係になる。自分の体の一部が女の体の中に入って、啓太はなにか妙な感じがした。
これが男女の交接なのか・・・なんだかピンとこない。機械的に体を動かすだけの感じだ。こんなことで自分の童貞が失われるとは情けない、と啓太は思った。そして、いくらか快感に達したと思ったら“液体”が放出されて終了。実に呆気ないものだった。
啓太がチップを払って待合室に戻ると、すでに金森が待っていた。2人は町に出て再びタクシーに乗り保養所に帰る。石浜はというと、好きなマッサージをたっぷり受けたらしく上機嫌で2人を迎えた。
「どうだった? 山本、楽しかったか?」
「ええ、まあ・・・」
上司の問いに啓太はあいまいに答えたが、石浜は察しがついているらしくニヤッと笑った。
「よしっ、3人じゃマージャンもできないし、飲みなおして唄でも歌おう!」
ということで、また酒やビールを飲みながら石浜が歌い出した。彼の十八番(おはこ)と言えば戦前の唄や軍歌だ。特に『大楠公・桜井の別れ』や『異国の丘』は好きなようでいつも歌うのだ(参考・異国の丘→ https://www.youtube.com/watch?v=9hkoI_r3MLM)。彼自身、終戦直後にシベリア抑留の体験があるのでこういう歌を好むのだろう。
だが、啓太や金森はいつも聞かされ、またかという思いである。しかし、石浜は歌い続け、やがて飽きると2人に歌を催促した。こうして、マイクはないものの小さな宴会が夜遅くまで続いた。
翌日、一行は伊豆山を後にしたが、啓太は糸川での初体験が心に重くのしかかった。なにか悪いことをしたという思い、ついに一線を越えたという思い、いや、あれは単なる“レジャー”に過ぎないという思い・・・それらが重なって複雑な心境になっていたのだ。
しかし、あれこれ考えたって仕方がない。もう済んだことだし、あとは仕事をしっかりやればいいのだと思った。それと同時に、五代厚子ら会社の普通の女性に対する印象が、なにか“希薄”になっていくような気がした。女性との交友は大事だが、レジャーはレジャー、遊びは遊びという割り切ったというか、自分勝手な考え方にとらわれるようになったのだ。
熱海への一泊旅行のあと、啓太は気持よく仕事に取り組んだ。「大宅壮一サンデー・ニュースアワー」をはじめ報道討論番組にも、また他の番組にも積極的に関わっていった。そうしたある日、母の久乃が車のことで啓太に言ってきた。
「お父さんが新しい車を買ってもいいと言ってるのよ。あの車は中古でしょ」
「いや、まだいいよ。中古でもよく走るし、親父が新車を買えば、僕に送り迎えばかりさせるかもしれないから」
啓太はそう言って笑ったが、内心はそろそろコルト600のことにケリをつけなければと思っていた。この中古車はタイトル係のA氏に15万円を貸した型に預かっており、Aさんが金を返せなければ自分のものになる。乗り心地もいいので、啓太は欲しいと思っていたのだ。
数日後、会社でAさんに会って聞くと、彼はいろいろな借金があるので車を手放してもいいと言う。そこで、啓太は15万円でこの車を買い取ることになった。その話を母にすると、久乃は笑って答えた。
「じゃあ、当分はいいのね。新車に替えたいなら、いつでも言って」
それで啓太はコルト600に乗り続けることになったが、この車に愛着心がいっそう湧いてきたのである。
そんなある日のこと、Fテレビの地下1階の社員食堂で啓太が金森と昼食を取っていると、五代厚子が同期の女子アナと食堂に入ってきた。ふだんなら啓太は気軽に声をかけるのだが、彼女を見かけるとなぜか“よそよそしい”気持になってくる。挨拶しようかどうか迷っていると、厚子の方が啓太に気がついた。
「山本君、久しぶりね。元気でやってる?」
「うん、まあまあ。けっこう忙しいよ」
「そう、また一緒にどこかへ行きたいな」
厚子はそう言ってにっこり笑うので、啓太も軽く手を挙げて応えた。以前なら、どこへ一緒に行こうかとすぐに考えるのだが、今はなぜか面倒くさいような気がしてくる。どうしてだろうか・・・ 熱海へ行って糸川で遊んだことが、厚子との距離感を広げたのだろうか。たぶん、そうに違いない。
これまで禁欲的な生活をしてきた自分が、あの糸川での体験からもっと自由に、もっと奔放に生きることを欲してきたのだろう。そう考えると、2歳年上の厚子はかえって“うっとうしく”感じるのか。啓太は自分の気持がまだよく分からないが、これまでと違った心境の変化を意識せざるを得なかった。
さて、報道番組の片隅に「ドキュメンタリー班」という部署があった。ここに数人の部員がいたが、そのほとんどがラジオ局から移籍してきた者たちだった。BUNKA放送とNIPPON放送の出身者だが、啓太ははじめ彼らが何をやっているのか分からないぐらいだった。いつも出たり入ったりして行方をくらましている。
だいたい、ドキュメンタリー班というのは制作でも報道でもどちらでもよい部署で、たまたま報道番組に籍を置いていたのだろう。啓太はそのうち、三雲大輔という2年先輩の部員と仲良くなった。三雲はBUNKA放送出身である。彼の作品のフィルム編集を手伝う機会があったが、それは麻薬に手を染めたある少年の更生物語であった。
「三雲さん、これはなかなかよくできた作品ですね」
「ありがとう。ところで、君はドキュメンタリーをやってみる気はないの?」
啓太が率直に褒めると、三雲は気分をよくして言い寄ってきた。その日、仕事が終わると2人はさっそく新宿のバーへ飲みに行った。三雲は酒が好きだ。ビールやウィスキーを飲みながら話し出す。
「報道にいたらやはり自分の足で取材し、それを発表するのがいいよ。だから記者でもいいし、僕らのようにドキュメンタリーを作るのもいい。山本君、スタジオにばかりいると、報道のやり甲斐や喜びが分からなくなると思うんだ。そう思わないかい?」
「それは分かりますよ。僕も早く記者になって、自分の足で取材してみたいですね。それと、ドキュメンタリーも面白そうだな~」
三雲の話に相槌を打つようになってしまったが、啓太は本心でそう思った。ニュースアワーや討論番組の担当も大切だが、若いうちに取材現場でばりばりと働く。それが報道マンの生き甲斐ではなかろうか。三雲はBUNKA放送ですでに報道現場の経験があり、それをとくとくと話し出した。ラジオは人が少ないだけあって、報道現場に行く機会が自然に多くなるのだ。
そんな話をしているうちに、時間がだいぶたったので2人はバーを出たが、啓太は心置きなく話せる先輩を知ったことに満足した。いずれ石浜副部長兼デスクに自分の希望を伝えようと思ったが、当面はスタジオ番組に全力を挙げなければならない。それは当然だが、三雲との会話で、啓太は自分の進路がおぼろげに見えてきた感じがしたのである。
季節はやがて12月に入った。師走になると、なんとなく気ぜわしくなる。テレビ局も年末や年始の番組作りで多忙になったが、啓太は三雲と話し合ったことも忘れて、またレジャー、つまり“享楽”の魅惑にはまっていった。彼は熱海の糸川にあったのと同じような「○✕風呂」の探訪を始めた。
おもに新宿の歌舞伎町が多かったが、足を延ばして都内のあちこちの○✕風呂に通い始めたのである。
啓太は自分の生活態度が大きく変わったことをそれほど気にはしなかった。彼は学生時代かなりの“堅物”だったが、社会人になって酒やタバコ、ギャンブルなど多くのレジャーを覚えた。しかし、妙に潔癖だったため「女遊び」だけは避けていたのだ。だが、これも糸川の体験から崩れていった。
いったん崩れ出すと、これまでの潔癖さの反動からか、見る見るうちに女遊びに“耽溺”していく。啓太はそれをむしろ自慢した。仲の良い川崎ディレクターや金森次郎に“馬鹿話”をするのだ。
「いや~、○✕風呂の遊びは最高に楽しいな。人生、こんなに素晴らしいことはないですよ。ハッハッハッハ」
そう言うと、川崎や金森もゲラゲラと大笑いしたが、こういう話はすぐに石浜副部長の耳にも入る。石浜は、啓太が年上の女子アナに熱を上げるのを牽制するために彼を熱海に連れていったのだが、啓太が女遊びにあまりに耽溺するのでかえって心配になってきた。
「困ったな。あいつは生(うぶ)だから、余計にはまってしまうんだ。なにか良い手立てはないのかな~」
石浜は川崎に相談したがこれといった手立てはない。しかし、金森と3人で話しているうちに、ある妙案が浮かんだ。
「そうだ、吉川さんになにか言ってもらおう。そうすりゃ、山本も少しは考えるだろう」
石浜が名前を挙げた吉川というのは、このところ報道番組によく出ているKYOTO大学の国際政治学者・吉川不二雄教授のことである。
そこで12月のある日、吉川教授が番組に出たあと、石浜は啓太を呼んで吉川に引き合わせた。啓太はむろん吉川を知っていたが、こうして膝を突き合わせて話をするのは初めてだ。
「吉川先生、これが山本ですが、どうぞなんなりと言ってやってください」
石浜が吉川に丁重に頼む。
「あなたが山本君ですか。話は石浜さんから聞きました。あなたは新宿などでいろいろ遊んでいるそうですが、そんなに遊ぶのが楽しいですか?」
吉川も丁寧に聞いてくる。だが、目つきは真剣で鋭い。40歳ぐらいだが、すでに貫禄は十分だ。
「ええ、楽しいですね。それに、他の人に迷惑はかけていないつもりです」
啓太は正直に答えた。すると、一呼吸おいて吉川が言った。
「報道の人間は、あまり見っともないことをしない方がいいですね」
啓太はすぐに返事ができなかったがこう答えた。
「分かりました。これから気をつけます。もちろん、他の人には迷惑をかけませんから」
すると吉川教授は初めてにっこり笑い、隣の石浜に語りかけた。
「石浜さん、山本君は大丈夫ですよ。ちょっとした若気の至りです」
「いや、ありがとうございました。山本、吉川先生の忠告をよく聞けよ」
こうして3人の話し合いは終わり、啓太はいちおう自粛しようという気持になった。報道の人間は、あまり見っともないことをしない方がいいという吉川の言葉が心に響いたし、年末年始の番組作りもかなり忙しくなってきた。啓太は仕事に全力を挙げるとともに、当面は自らの欲望を抑えることにしたのだ。