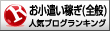そういう仕事を続けているうちに、いよいよ秋も本番となり素晴らしい季節になってきた。東京オリンピックの開幕が近づき、日本中が浮き立つような気分になってきた。聖火リレーが国中を回り、高速道路やモノレールが開通する。そして、10月1日には東海道新幹線も開通した。
これは超ビッグイベントで、国内外の注目を浴びた。テレビは中継に大わらわで、外国メディアももちろん絶賛する。こんなに速く走る列車は世界中どこにもないのだ! 日本中がなにか偉くなったような感じがした。そういう精神的興奮状態の中で、10月10日、ついに東京オリンピックの開会式を迎えたのだ。
その日は快晴に恵まれ、さわやかな秋らしい一日となった。啓太はむろん開会式の模様をテレビで見たが、正直言って感動した。古関裕而(こせきゆうじ)作曲の「オリンピックマーチ」が奏でられ選手団が入場すると、スポーツと平和の祭典がついに東京で開かれたと実感したのだ。(参考→ https://www.youtube.com/watch?v=m7GlLDgzI6E)
以後、10月24日までの大会期間中は、まさにオリンピック一色になった感がする。各競技にスター選手が出てきて大いに人気を博した。マラソンのアベベ(エチオピア)や陸上男子のヘイズ(アメリカ)、水泳のショランダー(アメリカ)などが大活躍したが、なんと言っても日本中を沸かせたのは女子バレーの“東洋の魔女”日本チームである。決勝でソ連チームを破って優勝した時は、多くの日本人が熱狂し拍手喝采したのだ。
また、最も美しかったのは体操女子のベラ・チャスラフスカ(チェコスロバキア)だったろう。彼女は個人総合など3種目で優勝したが、その“花”のような優美な演技は多くの人を魅了した。啓太もすっかり魅せられてしまったが、独身の先輩記者・窪川が「チャスラフスカと結婚するぞ!」と叫んだ時は、みんなが大笑いしたものである。
(3)五代厚子
こうして東京オリンピックは華やかな成功のうちに終わったが、大会期間中に不吉な出来事が2つ起きた。1つはソ連のフルシチョフ首相が政変で突然 解任されたため、ソ連選手らは大きなショックを受けていた。もう1つは大会不参加の中国が、初の核実験を行なったことである。これは明らかに東京オリンピックを念頭に置いてのことだろう。
オリンピックが終わると、祭りがようやく終わった感じがした。啓太はまた海外ニュースのトピックス原稿に集中することになったが、やはり気になるのはアナウンサー室の女性たちである。江藤知子との関係は“破局”に終わったが、五代厚子とは仲良くしている。ほかにも魅力のある素敵な女子アナが何人もいるのだ。啓太にとって、アナウンサー室は美しい“花園”のように見えるのだった。
11月に入ったある日、啓太はいつものように海外ニュース班で原稿を書いていた。夕方のニュース用トピックスを2本書き終わると、それを内勤整理班の稲垣デスクに届けたが、その時、椅子に座っていた五代厚子が啓太に声をかけてきた。その日は彼女が夕方のニュースの当番アナだった。
「山本君、今夜はなにか予定があるの?」
「いや、別にないけれど」
「それなら、わたしの友人と歌舞伎町のレストランで食事をしない? そんなに遅くならないと思うけど」
「・・・ああ、いいですよ」
少し考えて、啓太は承諾した。厚子の話によると、幼なじみの女の友人がオーストリアから帰ったばかりなので会うことになったという。彼女はオーストリアでスキーの特訓を受けたというのだ。海外でスキーの練習をするなんて、なんと贅沢な話かと啓太が思っていると、厚子がさらに言ってきた。
「今日はわたしの車に乗っていくのよ」
「えっ、厚子さんの車に・・・それでは、あとで」
そう答えて啓太は海外ニュース班の席に戻ったが、彼女の車に乗せてもらうのは初めてだ。なにかワクワクしてくる。彼はその時間が来るのが待ち遠しいような感じがした。そして、夕方のニュースが終わるやいなや、啓太はそそくさとFテレビの正面玄関に出て厚子を待ち受けた。
するとしばらくして、厚子が白い乗用車を運転して現われた。啓太が助手席に座ると車はゆっくりと発進する。この当時は社員も車での出勤が認められていたのだ。Fテレビのある新宿区・河田町から歌舞伎町まではそう遠くない。15分か20分ぐらいで着いてしまう。啓太はそわそわしながら聞いた。
「この車はなんて言うの?」
「トヨペット・コロナよ」
車種を聞いても、彼にはなんの知識も興味もない。乗せてもらう挨拶代わりに聞いたまでだ。ただ、この時から、啓太は“ドライブ”への意識にはっきりと目覚めたと言ってよい。自分も厚子のように、早く運転できるようになりたいと思ったのだ。白いトヨペット・コロナは、15分ほどして歌舞伎町のレストランに到着した。
駐車場に車を停めると、厚子と啓太はレストランに入った。鈴木某とかいう厚子の友人はもう来ていた。紹介された啓太は彼女に挨拶して着席したが、あとは厚子と鈴木某が話に夢中になり、啓太の出る幕はなかった。彼はビールを飲みながら適当に食事をしたが、なぜ厚子が自分を連れてきたのか解せなかった。
彼女は男友だちがいることを鈴木某に示したかったのか。それとも啓太を新車に乗せたかったのか。別に他意はなかったのか・・・そんなことを考えながら、2人の女性の会話を横で聞いていたが、話の中身はオーストリアでのスキーの特訓やヨーロッパアルプスへ行ったことなど大したものではなかった。
幼なじみだけあって、2人は最後に家族や住んでいる平塚(神奈川県)のことなどを話していたが、啓太は完全に聞き役だった。勘定を割り勘で払うと、厚子は鈴木某と車に乗り込んだ。2人で一緒に帰るのだ。彼女が別れぎわに声をかけてきた。
「山本君、こんど湘南の方へ遊びに来ない? 暖かくていいわよ」
「うん、ありがとう」
啓太は2人と別れて新宿駅へ向かったが、帰り道にいろいろ考えた。自分はやはり運転免許を取らなければならない。そうでなければ“厚子お姉さん”のようにはなれないのだ。実は啓太は学生時代に免許を取ろうと自動車教習所へ通ったことがあるが、指導員のあまりに傲慢な態度に腹が立って止めたことがる。
その頃は運転免許を取ろうと、多くの若者が教習所に殺到したためもの凄く混雑したのと、指導員が非常に横柄な態度を取ることがよくあった。同期の石黒達也も指導員に腹を立て、その男をぶん殴って教習を止めたことがあると語っていた。だから運転免許にはあまり未練はないが、厚子の影響でやはり免許を取らなければと啓太は思ったのである。
しかし、車は値段が高い。厚子は親の援助でトヨペット・コロナを買っただろうが、自分は親にそう甘えるわけにはいかない。となると、中古車か・・・ 中古車でもいいが、まずその前に運転免許を取るのが先決だ! そんな当たり前のことを考えながら、啓太は帰路についたのである。
当時の日本は急速に「車社会」になっていった時期だったと思う。啓太は学生時代に運転免許を取り損なったが、彼の同期でASAHI新聞に採用された友人は、自動車教習代をすべて新聞社が負担して運転免許を取らされた。地方勤務になると、新聞記者は特に運転が必要になるからだ。
強制的とはいえ、会社の全額負担で免許が取れるのは良い。啓太はその友人を羨ましく思ったが、動機はどうであれ、運転免許と中古車の取得が彼の当面の目標になったのだ。そのためには金がいる。啓太の月給は前にも言ったように約3万円だが、そのうち5千円は家に納めているから、手元に残るのは2万5千円である。そんな“薄給”ではなかなか中古車も買えない。
そこで、彼は思い切って在庫の本をほとんど古書店に売ることにした。○○全集や✖✖選集など文学書がやたらに多い。書棚からこぼれるぐらいだ。こういう本はもう必要ないと思った。今の仕事にはなんの役にも立たないのだ。ドライな考えかもしれないが、啓太はそう思って古本屋にどんどん売っていったのである。これを見て、母の久乃は嘆いた。
「もったいないじゃないの。せっかく買った本なのに」
久乃が苦情を言ったが、啓太は聞く耳を持たなかった。こうしてほとんどの本を売り払って、8万円あまりが手元に入った。彼はそれを元手に車関係の費用に充てようとしたのである。
ところが、冬がやってくるとFテレビの社員はにわかにスキーに夢中になりだした。この頃、スキー熱が盛り上がってきたのだ。先日、五代厚子と一緒に会った鈴木某も、それに煽られたのかオーストリアへスキーの特訓に出かけたほどだ。啓太も乗り遅れまいとして、車のことよりスキーに関心が移った。
報道でも高田(新潟県)出身の井上デスクが「みんなでスキーに行こう!」と呼びかけた。そうなると単純なもので、われもわれもとスキー場へ行くようになる。啓太はさっそく、小賀坂(おがさか)というメーカーのスキー板を買い、週末に先輩部員らについて苗場(なえば)などへ行くようになった。
日本人は特に“ブーム”に弱いのか。ちょうど同じ頃、ボウリングがブームになっていたが、少し前はフラフープやダッコちゃん人形などが大流行したことがある。「1億総○○」というのは、日本人にピッタシの特質だろう。啓太はそう考えていたが、自分も同じ渦の中に巻き込まれた感じがした。
12月のある日、彼は喫茶室Fでたまたま厚子と石黒達也に出会った。2人はどうも相性が合うようだ。すると彼女が声をかけてきた。
「山本君、わたしたちとスキーに行かない?」
「ああ、いいですよ」
啓太が気軽に答えると、石黒がすぐに付け加えた。
「小出にも声をかけてるよ。彼も大丈夫だろう。みんなで5~6人になるかな」
「よ~し、僕はまだ下手だけど頑張るかな」
「あんまり頑張りすぎないでね」
厚子がやんわりとした口調で言ってきたが、啓太は逆に勢いよく答えた。
「やるぞ~! 猛烈に滑るんだ!」
「まあ、いやね。まるで“イノシシ”みたい」
彼女の例えが面白かったのか、石黒が声を立てて笑った。
「ハッハッハッハ、山本はまったく“猪武者”だね。猪突猛進か。ケガでもされたら困るよ」
石黒と厚子が苦笑していたので、啓太も笑いながら喫茶室を後にした。翌日、3人は連絡を取り合って、12月の下旬に池の平温泉スキー場へ1泊で行くことを決め、小出や同期のもう1人のアナウンサー・森末太郎らにも声をかけた。啓太は白銀に“シュプール”を描くことを想像しながら、年末のスキーを楽しみにしていたのだ。ところが、ここで思わぬことが起きた。
それは小出が数日後にスキー場で脚を骨折したのである。彼は別のグループと新潟県・赤倉へ行っていたが、ゲレンデで人と衝突して転倒し、そのはずみで左脚を複雑骨折したのだ。この事故で小出は年末のスキーができなくなったが、さらに状況が悪くなる事態となった。
それは他にもケガ人が何人も出たため、会社が急きょ「スキー自粛」の業務命令を発表したのだ。報道でもアナウンス室でも管理職がそう告げた。こうなるとスキーどころではない。年末は仕事も立て込んでくるので、啓太たちはスキーを断念せざるを得なくなった。
彼と石黒は左脚の手術をした小出をさっそく見舞うことにした。
「彼も行けなくなったから、ちょうどいいかな。残念だけど」と石黒が言う。
「仕方がないさ。それより小出の状態が心配だね」
2人はタクシーに乗り込んで文京区・茗荷谷にあるS病院へ向かった。小出はここに入院して手術を受けたのである。2階の個室を訪れると、小出と大学生らしい女性がいた。啓太と石黒が手術後の容体を聞くと、彼はあと10日ほどで退院できそうだと答えた。あとは3人で会社のことなど雑談を交わしていたが、小出が急にその若い女性を紹介した。
「これは僕の妹だ。よろしく」
啓太と石黒が目を向けると、彼女は立ち上がって礼儀正しく挨拶した。
「妹の順子です」
大柄な彼女は背丈が162~3センチあるだろうか。ふくよかだが、どこか知的な感じがする。椅子にまた座ると雑誌などを読み始めた。順子は入院中の兄の看護で来ていたが、いたってリラックスした表情だった。小出誠一はベッドに座ったまま啓太らと話していたが、左脚にギプスをはめた姿は痛々しいものの、どこかのんびりした風情にも見える。正月前には退院して、あとはしばらく自宅で療養するという。雑談を交わしているうちに、小出がふと話題を変えてきた。
「ところで、山本は五代さんとの付き合いはどうなってるの?」
五代厚子の話が急に出てきたので、啓太は少し戸惑った。
「いや、別に・・・相変わらず付き合っているよ」
「そうか、五代さんともスキーに行けなくて残念だったな。でも、彼女は後輩の面倒もよく見るし、とても良い人だよ。石黒もそう思うだろ?」
話を振られて石黒達也は軽くうなずいた。五代のことから話は女子アナ全般に広がり、やがて報道局の女性も俎上に載った。社内結婚や女性の話題になると、会話が弾んでくる。Fテレビでは社内結婚が多い。「女子社員25歳定年制」というのがあるから、会社も社内結婚に積極的なようだ。
「でも、女性が25歳で定年というのはちょっと時代にそぐわないね」
「そうさ。時代遅れだよ」
石黒が言うことに小出が同調した。啓太も同じ思いだったが、それ以上は特に触れなかった。来年はどんな年になりそうかということで、3人の会話が続く。すると小出が言った。
「来年は、山本と五代さんの関係がどうなるか見ものだな。ハッハッハッハ」
「なるようになるさ。しかし、異動のことが気になるよ。いつまでも海外ニュース班にいるつもりはないし、早く記者クラブに出たいな。それに運転免許も早く取りたいし」
啓太が正直に本音を言うと、石黒が冷やかすように口を挟んだ。
「運転免許よりも厚子さんの“ハート”だろう。頑張れよ」
また五代厚子のことを言われ、啓太は気持が高ぶって思わず叫んだ。
「よしっ、北爆だ! 来年は必ずハノイを爆撃するぞ!」
これには2人は大笑いをした。その当時、アメリカと北ベトナムの戦闘が日に日に激しくなり、米軍の“北爆”がいつハノイ(北ベトナムの首都)に迫るかというのが最大の関心事だった。啓太のいる海外ニュース班にとっても、ベトナム戦争の報道は最重要事項であり、それに引っかけて言った彼の比喩が小出と石黒を笑わせたのだ。
3人の話に順子は聞き耳を立てていたようだが、特に反応はなかった。相変わらず雑誌などを読んでいたが、途中で兄がトイレに立つとかいがいしく彼を支えていた。小出は松葉杖を使ったが、まだ慣れないせいか歩き方が痛々しく見える。骨折した左脚を床に下ろせないので、彼は相当なケガをしたのだと啓太は思った。
正月明けの話をしているうちに、啓太がふと小出に尋ねた。
「お見舞いに行きたいんだが、君の家がどこかよく分からないのだ・・・」
すると、小出が妹に声をかけた。
「おい、地図を書いてやれよ」
その途端、順子の頬が見る見るうちに紅潮した。彼女は自分の居所を男たちに知らせるのを過剰に“意識”したのだろうか。順子は手帳の余白を切り取り、机に向かって地図を書き出した。まだ頬が紅潮している。少しぎごちない仕草で自宅の地図を書き終えると、彼女はそれを啓太に手渡した。石黒が横から覗き込んだ。
そんなことをしているうちに夜も遅くなったので、順子が軽く挨拶して帰っていった。
「あれは今年、TOKYO女子大に入ったんだよ」
小出が妹のことをさらりと言った。啓太も石黒もそろそろ帰る時間となり、彼に激励の言葉をかけると病室を後にした。帰りぎわに、啓太は順子のことでなにか清々しい気持になったのである。
年が明け、昭和40年・1965年を迎えた。スキー自粛の“お達し”が出ていたので、啓太は石黒から貰ったスケート靴を持って、新宿のスケートリンクなどによく出かけた。また、チャスラフスカに熱を上げた窪川先輩がボウリングが大好きなので、みんなで彼について青山のボウリング場などへ行った。
また、ようやく退院した小出を見舞うため、雑司ヶ谷の彼の家にもよく通った。こうしてわりと楽しい冬の日々を送っていたが、仕事関係では、アメリカ軍のベトナム介入や「北爆」がいよいよ本格化し、緊迫の度合いが一層強まったのである。海外ニュース班にいると、ベトナム戦争に関する外信記事や映像が一段と多くなった。
報道の仕事には大きな変化がなかったので、啓太は運転免許の取得に本腰を入れることにした。免許を持っている五代厚子らの体験談を聞いたりして、浦和の自動車教習所に通うことになった。ところが、教習所は免許取得希望者で大変な混雑になっていたのである。
「車社会」の到来で仕方がないが、こんなに混んでいるなら、ヒマだった学生時代に免許を取れば良かったのにと啓太は悔やんだ。しかし、愚痴を言っても始まらない。相当 長期になることを覚悟して、彼は教習所に通い出した。
(4)番組制作班に移る
ところが、3月上旬頃だったか啓太は急に「番組制作班」への異動を命じられた。新番組がスタートするので、人手が要るから行けということだった。せっかく海外ニュース班の仕事に慣れてきたのに、新人は簡単に動かされる。しかし、これも“修業”のうちだと思い、啓太は気持を切り替えて番組制作班に移ったのである。
「山本はよく動くな~。まあ、頑張れよ」
小出や石黒にそう言われたが、新しい職場に慣れるまで自動車教習所通いはほどほどにしなければならない。運転免許の取得はだいぶ先になりそうだった。報道番組の制作はアシスタント・ディレクター(AD)からの出発だが、これが種々雑多な仕事ばかりだ。要するに、雑務を全部やらなければならない。
スタジオに入ってフロア・ディレクター(FD)をしたり、ゲストの送り迎えや食事・お茶などの手配はもちろん、時には放送中にレコードを何枚もかけなければならない。レコードをかけるのを「皿回し」と言うが、これはディスク・円盤から来ている言葉だ。
不器用な啓太は「皿回し」が苦手で、放送中に何度も失敗した。音が出なかったり、時にはとんでもない音が流れたりしたのだ。番組担当の星野ディレクターは顔色を変えて、「やめろ!」と怒鳴ったりする。ある時、星野は放送が終わると啓太にこう言った。
「君は山本でなくて“ジャマ本”と呼ばれたんだってな」
星野ディレクターはそう言って大笑いをしたが、啓太は返す言葉がなかった。そんな苦しい日々を送っているうちに、ある日、彼は石浜副部長・デスクに呼ばれた。
「今度、うちで『サンデー・ニュースアワー』というのをやるが、君もそれを手伝ってくれ。キャスターは大宅壮一さんだ」
石浜はそう言うと、番組企画書のコピーを啓太に手渡した。
「えっ、あの大宅さんが・・・」
啓太は驚いて思わずその人の名を口に出した。大宅壮一といえば日頃、テレビを“一億総白痴化”の元凶のように言っている人だ。毒舌で有名な社会評論家である。<注・・・実際のタイトルは『大宅壮一サンデーニュースショー』だった。フジテレビの資料より>
大宅氏の登場に少し困惑したものの、啓太はすぐにこれは面白いなと考え直した。なにせ知名度の高い評論家である。視聴率は取るだろうし、彼のコメントが注目されるのは当然だ。ただ、大宅氏は以前 自民党のある実力者が亡くなった時に、「あんな政治家は早く死んでくれて、日本のために良かった」という趣旨の発言をして、大騒ぎになったことがある。注目されるのはいいが、あまり問題発言をすると番組担当者がその後始末に苦労することが心配だった。
しかし、視聴率を上げるにはそれもかえって好都合だろう。番組担当者は、何よりもまず視聴率のことを考えるのだ。こうして『サンデー・ニュースアワー』の準備が始まった。準備といってもスタジオの模様替えが主な仕事で、これは星野ディレクターが中心になって進めることだ。啓太は彼の助手として雑務をこなしていくだけだった。
そんな作業をしているうちに、ある日、五代厚子から彼のデスクに電話が入った。
「山本君、番組制作班の仕事はどう?」
「まあまあ、なんとかやってますよ」
「それならいいけど・・・ところで、運転免許の方はどうかしら」
「そちらの方は忙しくて、あまり進んでないな」
「あら、あんなにやる気満々だったのに」
「だって教習所が混んでいて、なかなか予約が取れないんですよ。まだけっこう時間がかかるみたい」
「そう・・・ところで、今日はお暇かしら」
厚子から久しぶりの誘いだった。啓太が暇だと答えると、彼女はさっそく夕食を共にしようと言う。2人だけの“ひと時”と聞いて彼はすぐに承諾した。そして夕方、厚子の車でFテレビを出ると新宿2丁目の方へ向かったのである。
彼女はよく駐車するビルの前に車を停めると、足早に啓太を連れて細い路地に曲がって行く。ここは初めての所だ。
「何を食べるの?」
啓太が背後から聞くと、厚子はぶっきらぼうに答えた。
「お好み焼きよ」
2人は5~6軒の店を過ぎて、間口の狭いお好み焼き店に入った。そのあと、靴を脱いで座敷に向かう時、先を行く厚子の顔を見て若い男の店員がクスッと笑った。彼女の表情がどうもおかしかったようだ。
厚子は啓太を先導して一番奥の隅の席に座った。
「お好み焼きは初めて?」
「ああ、初めてですよ」
正面にいる厚子はやや不愛想にも見える。まるで不機嫌な感じだと啓太は思った。料理の具材が来ると、彼女は魚介類や野菜などを鉄板の上に並べた。ジュジュジューッという音を出し具材が熱せられる。あとは厚子が独りで無言のまま調理していった。
頃合いを見て啓太は料理に手を出したが、厚子は彼の簡単な問いに答えるだけで押し黙っている。なにか気まずい雰囲気になってきた。こんな風に食事をしていても楽しいのだろうか・・・啓太は疑問を感じた。すると、かなり時間がたって厚子がふいに尋ねてきた。
「山本君は、わたしのことをどう思ってるの?」
「どう思うって、別に・・・あっ、ごめん。お姉さんのように思ってるよ」
啓太の答えに厚子は特に反応を示さなかった。また、無言が続いた。しばらくして、彼女は座布団の上で正面から脚を組み直した。その時、厚子の白い両脚が奥まで啓太の目に入った。彼はドキッとして息を呑んだが、素知らぬふりをして料理を味わっていた。
厚子は中肉中背で別にグラマーではないが、すっきりとした容貌をしていた。顔立ちは丸みを帯びてそれほど白くなかったが、知的な好奇心にあふれている印象だった。会社では啓太より1年先輩だが、大学受験で一浪したため年齢は彼より2歳上である。ということは、いま25歳になっているのだ。
Fテレビでは女子社員25歳定年制があるが、アナウンサーは別格で“契約”という形で1年ずつ延長が認められている。それでも、25歳になった女子アナは複雑な心境になるのだろう。厚子と啓太はほとんど無言で食事をした。1時間あまりがたっただろうか。彼女がつぶやいた。
「もう行くわ。ここはわたしが持つのよ」
「えっ、割り勘じゃないの?」
啓太があわてて言ったが、厚子は委細構わずといった様子で立ち上がると、伝票を持って店の出口へ向かった。結局、勘定は彼女が払って2人は外へ出たが、厚子はまた足早に駐車場の方へ歩いていく。そして、さっさとトヨペット・コロナに乗り込むと、啓太を無視するかのように夜の街の中へ去っていった。
俺は厚子を怒らせたのだろうか・・・啓太は自問したが、そんなに失礼な振舞いはしなかったはずだ。なんだか、彼女が“一人相撲”を取っていた感じで、彼は後味の悪い思いをしたのである。
それからしばらくして、『大宅壮一サンデー・ニュースアワー』が始まった。日曜夕方の放送で大宅氏は司会・キャスターだが、いわば“コメンテーター”ということでもちろん原稿は読まない。女性アナが読んだニュースにコメントを付けるだけだ。心配された問題発言もなく、放送はいちおう順調に進んでいった。
ちょうどそのころ、就任して間もない陣内春彦社長は番組制作班の一同を会議室に集め、新しい「報道討論番組」をスタートさせると抱負を述べた。陣内社長は日経連出身の“右寄り”の人だったが、民放ラジオ局の創設に成功して自信を深めていた。彼が言うには、Fテレビの報道はまだウィークで(弱くて)、何か目玉になるような報道番組が必要だというのだ。それを突破口にして、Fテレビは報道にも力を入れていることを世の中に訴えたいということらしい。
陣内社長は張り切っていて、「スポンサーは俺自身が見つけてくる」と述べた。この並々ならぬ決意に、番組制作班の一同は気が引き締まる思いだった。その当時、民放テレビが本格的な報道討論番組をやるのは珍しかっただろう。啓太もこれは面白いぞと思った。
仕事の方はなんとかやっていたが、彼の最大の関心事はやはり運転免許の取得である。浦和の自動車教習所はもの凄く混んでいたから、予約を取るのは大変だった。それでもようやく“実技試験”の日取りが決まったので、啓太はこの後、五代厚子に電話で報告した。
「そう、やっと実技試験ね。わたしも気になっていたのよ」
厚子はそう言うと、おかしそうにクスッと笑った。
「やっとですよ。なんとか頑張るから」
啓太は彼女に少しからかわれているような気がしたが、そう答えた。やがて実技試験の日がきた。苦手だった坂道発進はギアが上手く入って、エンストもなく上々の滑り出しだ。しかし、クランクとS字の試験では3~4回 縁石に乗り上げたり、脱輪して上手くいかなかった。結果は不合格である。
啓太はがっかりして厚子に報告した。
「ハッハッハッハッハ、それは残念ね~」
電話の向こうから高笑いが聞こえる。途端に啓太は悔しくなって言葉が出なくなった。厚子にバカにされた気がして、電話を切ったあと彼は不愉快でたまらなかった。しかし、どうしようもない。もう一度再挑戦するしかないのだ。そう思っているうちに、今度は交通法規など学科試験の番がやってきた。厚子にまるで“リベンジ”するような気持で啓太は取り組んだ。
運転免許については、父の国義も何度も促がしてきた。免許が取れれば車を買ってやると言っていたが、これは啓太が暇な時に駅までの送り迎えを彼にさせようという狙いがあったからだ。それは啓太も知っていたが、車社会ではとにかく免許は必要だと思っていた。
やがて学科試験の日がきたが、これは問題なく1回で合格した。そして2回目の実技試験で、彼は多少の運転ミスがあったもののなんとか合格したのである。啓太は今度は実技試験のことを事前に厚子に知らせなかった。もし万一また不合格だったら彼女になんと言われるか分からないし、それをとても恐れたからだ。
免許取得に合格した6月下旬のある日、啓太は厚子に電話をかけた。
「やっと受かりましたよ。永かったですね」
「そう、良かった! 今度はあなたの運転で車に乗りたいわ」
厚子は素直に喜んでくれた。彼女の正直な応答に、啓太もようやく肩の荷が下りた気分になった。これで思う存分車に乗れるぞ! 早く厚子を乗せて運転してみたい。ドライブの夢が一気に彼の心に広がった。また国義も喜んで、庭の一隅に車庫をつくることになった。彼は新車を購入するつもりだったのだ。
こうして運転免許の件は落着したので、啓太はまず中古車を手に入れようと考えた。それは国義が新車を買うと、車の送り迎えにいつも自分を使うのではと警戒したからだ。そうなると事実上の“運転手”である。好きなように車を使うことも難しくなる。ただし、自分の手で簡単に中古車が買えるのだろうか・・・
25万円も30万円もすれば、そんな貯金はないから中古車だって手に入らない。啓太はいろいろ考えたが埒(らち)が明かないので、しばらく成り行きに任せるしかなかった。そんなある日、石浜副部長が日頃の慰労ということで、啓太と同僚の金森(かなもり)次郎を新大久保の小料理屋に誘った。
石浜は筆頭デスクで身分は副部長だが、陣内社長に従って日経連からラジオのNIPPON放送を経てFテレビに来た人物だ。陣内の信任が厚く、いずれはFテレビの幹部になることは間違いないと見られていた。また、金森は高校卒で啓太より少し年下だが、番組制作班では熟練のディレクターである。
3人はビールやウィスキーの水割りなどを飲んでひと時を過ごしたが、そのうち石浜が思わぬことを言い出した。
「山本、君は五代という女子アナと付き合っているんだって?」
「ええ、それがなにか・・・」
啓太は意外なことを聞かれた気がして、石浜の顔を思わず凝視した。
「その娘(こ)はあまり評判が良くないようだな~。金森もなにか聞いてるだろ?」
そう問いかけられたが、金森は苦笑いを浮かべながら水割りを一口飲んだ。
「山本より年上の女じゃないか。大丈夫かな~」
金森は黙っていたが、石浜が冷やかすように言うので啓太は少しムッとなって答えた。
「ただ付き合っているだけですよ。年上じゃまずいんですか?」
「そうムキになるな。君は一途な男だからそれが心配になるんだよ」
そう言って石浜は笑ったが、啓太は男女の私的な交際は仕事とは関係なく、厚子との交友は続けていこうとの思いをさらに強くした。たしかに石浜は上司として立派だが、厚子への好意は別である。実は彼は啓太の兄・国雄の大学時代の先輩であり、それが縁でなにかとお世話になっていた。しかし、それと個人的な事柄とは関係ない。
厚子はあまり評判が良くないって? そんなことがあるだろうか。そんな話は他のアナウンサーから聞いていない。そういう噂さは金森が石浜に勝手に吹き込んだのではないか・・・ 啓太はそう自問自答していた。
石浜と金森の3人で小料理屋へ行った日からしばらくして、車の件で思いがけないことが起きた。啓太が免許を取ったことを聞きつけたのか、タイトル係りのA氏が、借金の返済に困っているので車を抵当に金を貸して欲しいと言ってきたのだ。「タイトル係り」とはテレビ画面の字幕を担当する人で、当時は“手書き”でニュースなどのテロップやフリップを作っていた。
このため、主に美術学校出身の若い人が多くA氏も同様の経歴を持っていた。彼は三菱・コルト600の中古車に乗っていたが、それを担保に15万円貸して欲しいと言う。そして半年間で返済できなければ、車を譲り渡すというのだ。啓太は15万円ぐらいの貯金はあったし、自分で車を持てば父の“運転手”にはならないで済むと考えた。それになんと言っても、車を持ちたかったのだ!
彼はA氏の申し込みを受け入れ、7月の上旬にコルト600を譲り受けることになった。当日、Fテレビの駐車場でコルト600を見ると、啓太は思わず歓声を上げた。
「素晴らしい! なんて格好がいいんだろう。車のオーナーになれるなんて夢みたいだな」
<参考・コルト600の映像→https://www.youtube.com/watch?v=EJEvRNClAHI>