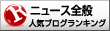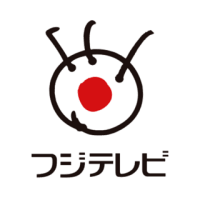「そうですか、蔵原さんはそういう人ですか・・・」
啓太はそれ以上は聞かなかったが、蔵原になにか不吉な予感を覚えた。そして、西尾と啓太は喫茶室を出たあとドラマ制作部に戻り、明日の予定を確認してから別れた。
翌朝、出社すると岡山ディレクターが嬉しそうな顔をして言う。
「放送予定日がようやく決まったよ。4月14日と21日の2回に分けて放送する。これで落ち着いてやっていけるね」
啓太も安堵した気分になって聞いた。
「時間枠はどこですか?」
「うん、夜のシオノギ劇場の枠だそうだ。よかったよ」
岡山はやっと安心して取り組めるといった表情を見せた。ほかのスタッフも約1カ月後の放送が決まって喜んだが、まだ心配なのは、ニッカツ映画社との交渉の行方である。これが決着しないかぎり、吉永ゆかりの出演は本決まりにはならないのだ。しかし、それは村山編成局長に任せるとして、啓太らスタッフは日々の制作に取り組んでいくしかない。
この日は、東京の墨田、江東などの撮影候補地を下見することにしていた。東京の下町は昭和20年・1945年の3月10日に、米軍による大空襲で壊滅的な打撃を受けたが、その日にドラマの主人公である田島三郎と小野瑩子(けいこ)が死亡したことになっている。
啓太もロケ班の一員として同行することになり、岡山ディレクターや植木AD、撮影クルーらと一緒に会社を出た。墨田、江東、荒川といった地域にはまだ昔の面影を残した所があり、その幾つかを下見してドラマづくりに役立てようというものだ。ロケの場所として選ぶものもあれば、事前にフイルム撮影して映像雑感に活かすものもある。
こうしてその日は半日、東京の下町を見て回ったが、啓太は植木ADとも仲良くなった。彼は西尾ADより1年後輩だが、啓太より2年先輩に当たる。
「ロケにふさわしい所が幾つかあったよ。特に中小企業の町工場はいいな。ああいう所の多くが焼き払われたんだよ。主人公はそこで焼夷弾に当たって死ぬ。そういうストーリーだね」
植木は快活な性格の男でよくしゃべる。
「そして最後に、三郎が瑩子の“懐”の中で死ぬというのはロマンチックでいいね!」
「それがロマン・ロランの原作のとおりですよ」 啓太が我が意を得たりと相づちを打った。
新進の脚本家・矢崎修(おさむ)の手で、ドラマは『また逢う日まで』と違って原作に近いものになっていた。それを2人は称賛したのだが、主役の蔵原圭一もそのストーリーに惹かれたらしい。啓太は気になって植木に尋ねた。
「蔵原さんはダイエーを辞めてまで出演するのは、相当の覚悟があってのことでしょうね?」
「よく知らんが、彼はユカリストだろう。一度、ぜひ吉永ゆかりと共演したかったのじゃないか。思い詰めると、何をするか分からん男のようだな」
そう言って植木は苦笑したが、啓太も同様の思いになっていた。あの蔵原はそういう男なんだと。
「恋人よ、あなたの腕に抱かれて死にたいとか、あなたの膝のうえで安らかに死にたいなどと、え~と、なんて言ったかな・・・そうそう、ロンサールとかいう詩人の詩をいつも口ずさんでるんだって。本当にロマンチックな奴だよ、あいつは」
「えっ! それはたしか『ピエールとリュース』の中に出てくる詩ですよ。蔵原さんはすっかりピエールになった気でいるんですね」
啓太がびっくりして話すと、植木がそれを遮るように言った。
「もう、よそう、こんな話は。それより下町を少し歩いてみないか」
「ええ」
そこで2人は本所(ほんじょ)界隈の街中を歩き始めた。隅田川に面したこの辺に啓太はほとんど来たことがない。珍しさもあって彼は景色を楽しんでいたが、突然あることを思い出して、つい植木に聞いてしまった。
「植木さん、ドラマ制作では労働組合をつくる話は出ていないのですか?」
「なんだい、急に・・・ いや、特に出ていないよ。出ていないけれど、今の会社はおかしいとみんなが思ってる。そうじゃないか、君はどう思ってるの?」
逆に植木に聞かれて、啓太は返事に困った。
「ええ、まあ僕もそう思ってます」
そう言いながら、彼は石浜報道部長の顔を思い出していた。石浜にドラマ制作部へ行ったら、組合結成の動きを探ってこいと言われたことが脳裏に浮かんだのだ。どうも場違いなことを聞いたかなと思っていると、植木が甲高い口調でしゃべり始めた。
「だいたい、普通の会社なのに労働組合がないって変だよ! だから女子25歳定年制なんて酷いものがあるんだ。まるで明治時代の会社だね。僕がいたBUNKA放送なんか、組合が3つも4つもあったんだぜ! いや、3つも4つも必要はない。1つあれば十分だ」
ここで一呼吸おいて植木はさらに続けた。
「山本君、君がいた報道なんか率先して組合をつくるべきではないか。報道部はこういうことにイニシアチブを取るべきだよ。そう思わないか?」
植木に言われても、啓太には返す言葉がなかった。こういう問題に最も関心を示すべき報道部は、表面上ほとんど動きが見られなかったと言える。植木と話を交わしているうちに時間が過ぎ、2人は車(ライトバン)のある待合い場所に戻った。
「お揃いで散歩か・・・下町の風情もいいもんだろう。これでロケ地の見当がついたな」
岡山ディレクターがにこやかに声をかけてきた。こうして一行は“ロケハン”を済ませて社に戻ったが、撮影場所などがほぼ決まり後半のドラマづくりが本格的に進んだ。啓太はおもにスタジオワークを担当したが、要するに雑多な仕事をすべてこなす“何でも屋”だった。このため、多くのスタッフやキャストとも自然に親しくなったのである。
そんなある日、3階のドラマ制作部でADの西尾と雑談を交わしていると、彼が気になることを言い出した。
「蔵原は本気で吉永ゆかりに言い寄っているそうだよ。岡山さんも心配しているんだ。もしドラマづくりの最中になにかトラブルでもあったら、面倒なことになる。ドラマ自体が壊れることもあるのだ。
山本君、君はみんなとだいぶ親しくなったそうだが、なにか気づいたことでもあったら知らせてほしい。この話は内々のことだよ」
啓太も心配していたことが、どうやら本当になったらしい。西尾に言われて彼は自分でも調べてみようと思った。記者本能が目覚めたらしい。しかし、蔵原とは顔見知りになったばかりだし、伝(つて)などは皆無と言っていい。岡山や西尾の方がよっぽど情報が入りやすいのではないか・・・
それでも啓太はスタジオワークをやっているので、カメラマンや音声係り、美術や照明係りなどのスタッフにそれとなく当たってみた。すると、大道具担当のA君が面白いことを言うのだ。
「この前、といっても2~3日前だったかな、蔵原さんが美術セットの裏で吉永さんにいろいろ話しかけていましたよ。吉永さんはなにか困ったような顔をしてたけど、4~5分たって別れたかな。蔵原さんはいつものように“むっつり”した顔をして出ていきましたよ。面白かったからなんとなく見ていたんだ」
啓太はこれは怪しいという思いが湧いた。
彼は機会をうかがっていたが、そのチャンスが数日後にめぐってきた。あるシーンのカメラリハーサルが終わったあと、啓太は思い切って蔵原圭一に声をかけたのである。
「蔵原さん、吉永さんとの息はぴったり合ってますね」
そう言っても蔵原は相変わらず不愛想で、啓太をチラリと見やるとうつむいてしまった。
「上々ですよ、本当に素晴らしい演技だ。ところで、つかぬことを伺いますが、吉永さんとは個人的に親しくされているんですか?」
蔵原は顔を上げると啓太をにらみつけて答えた。
「君はなにを言うんだね。僕らは単に仕事上の付き合いだ。つまらんことを聞くもんじゃない!」
彼はひどく不機嫌になり、顔をぷいとそむけると足早にその場を去った。図星(ずぼし)だったかな・・・啓太は手応えを感じた。蔵原は明らかに吉永に想いを寄せているのだ。間違いはない。そう思って、これらのことはすぐに西尾ADに報告し、岡山PDにも伝わったのだ。
しかし、こういう内密のことを吉永ゆかりに聞くチャンスはなかった。いつも周囲に人が大勢いるし、啓太と吉永は単に“顔見知り”程度である。なかなか聞けないまま、時間はどんどん過ぎていった。
そして、最大の問題であるニッカツ映画社との交渉も、村山編成局長が鋭意努力したがまったく進展がなかった。ニッカツ側は、吉永と専属契約を結ぼうとしている最中だから、彼女のテレビ出演は認められないという一点張りなのだ。しかし、そんなことにこだわっていたら遅れるばかりだから、ドラマ制作は予定通り進めた。
そして、ついに最終シーンの撮影と収録の段階が来た。4月に入ったある日、ロケがスタートする。担当ADの植木が叫んだ。
「さあ、最後のロケだ。みんな、頑張ろうぜ!」
「よしっ、行こう!」
岡山ディレクターも珍しく大きな声を出す。ロケ班一行は東京・墨田区の“下町”を目指した。昭和20年(1945年)3月10日、東京の下町界隈は米軍による大空襲で壊滅、焼け野原と化した。死者10万人以上! その中に、ドラマ『まためぐり合う時』の主人公・田島三郎と小野瑩子の2人がいたことになっている。
一行は墨田区内のある町工場にやって来た。そこはいろいろな機械部品を製造していたが、岡山も植木も撮影に最もふさわしいと考え選んだ所なのだ。
昭和20年3月にはここも軍需工場の1つとして稼働していたという。しかし、それとは関係なく最後のロケ現場になったわけで、蔵原圭一と吉永ゆかりがラストシーンに挑んだ。主人公の三郎と瑩子はこの場所に逃げ込んできたが米軍の空襲を受け、最後は焼夷弾の直撃により死亡するという想定で演技を始めた。
一連のセリフが終わったあと、蔵原は吉永の両腕に抱かれながら彼女の膝の上にうつ伏す。すると、吉永は蔵原の上に身をかがめ彼を覆い隠すように抱きしめる・・・ カメラマンが撮影を続けるが、それを見ていた啓太は蔵原がなんともうらやましく思えた。三郎は瑩子の懐(ふところ)で死に絶えていく。
それを演じる蔵原は“ユカリスト”として本望だろう。啓太は彼にある種の嫉妬を感じた。それは以前、付き合っていた五代厚子が、先輩独身記者の窪川に付きまとっていた時に感じたのと同じようなものだ。しかし、このシーンのなんと美しいことか。それは原作の『ピエールとリュース』のラストシーンとほとんど同じではないか!
啓太はディレクターや脚本家の意図に心から納得した。こうして最後のロケは終了したが、スタジオでも同じシーンを再現して撮影するという。岡山ディレクターはあらゆる角度から完璧なドラマをつくろうとしているのだ。あとは編集の段階で映像をいかようにも組み立てることができる。
帰りの車の中で、啓太は岡山と植木に語りかけた。
「すばらしいドラマができますね。僕はドラマづくりの現場に来てとても勉強になりましたよ」
「それはお世辞か? ハッハッハッハ。でも、やりがいを持ってもらえれば言うことはないさ」
植木が満足そうに答えた。
「山本君、いろいろご苦労さん。あと、もうひと踏ん張りだよ」
岡山も明るい声を出したので、啓太はさらに続けた。
「吉永ゆかりさんは素敵でしたね。やはり彼女はテレビでも映えるな~」
すると岡山は口が軽くなったのか、以前の話を始めた。
「あれはおととしだったか、彼女を連れてヨーロッパへ行ったことがある。向こうの若者たちの生活ぶりをフィルム構成で番組にしたのだ。僕がプロデューサーだったんだよ。その時、同行した吉永さんの父親にロンドンで、もしもチャンスがあれば次はぜひドラマに出てほしいと頼んだのだ」
「えっ、それじゃ今度の吉永さんの出演は、その時の話し合いの成果なんですね?」
「そう言えなくもない。しかし、吉永側はニッカツ映画社との専属契約が切れたから、いつでも堂々とテレビに出演できると思っているのだろう。それは当然だし、時の流れではないのか」
岡山は自分の成果を誇示するわけでもなく淡々と話した。これが啓太には、彼の謙虚な姿勢と映ったのだ。
「いや、岡山さんは立派だな。自分の手柄は二の次にしているもの」
「おいおい、君は報道で“おべんちゃら”でも習ったのか。ハッハッハッハ」
そばにいた植木が茶々を入れたが、啓太は岡山の態度に好感を抱いた。一行はその日 ロケを無事終了したが、2日後には、スタジオでラストシーンを再現して撮影を行なった。これはロケの補充みたいなものだが、完璧を期す岡山ディレクターの意向によるものだ。
撮影は特にクローズアップに力点を置くもので、“アップの太郎”と異名をとる岡山にふさわしい演出だった。主演の蔵原圭一と吉永ゆかりは役を見事に演じ切ったが、ことに蔵原の熱の入れ様は尋常ではなかった。彼の表情は恍惚として美しくさえ見える。フロマネ(フロア・マネージャー)をしている啓太は、すぐ近くからその様子をうかがい知ることができた。
蔵原は青白い優男(やさおとこ)で、石原裕次郎や小林旭のような“タフガイ”ではない。しかし、妙に女性に人気のある俳優だ。どこが良いのか知らないが、女の母性愛でもくすぐるのだろうか。その男が再び吉永にしっかりと抱かれるシーンを見ていると、啓太はまた軽い嫉妬の念を覚えた。
「おい、邪魔だよ~」
少し乱暴なカメラマンがケーブルの動きを遮っている啓太に注意した。フロマネとは、スタジオ内のいろいろな動きに注意しなければならないのだ(雑用係りはつらい)。最後のフロマネをなんとかこなしているうちに、ラストシーンの撮影が終わった。
「ご苦労さん!」
インターカムを通して、岡山の声が聞こえる。これですべてが終了した。啓太はホッとした気分になったが、このあとリハーサル室で簡単な“打ち上げ”が行われる。みんなで健闘を称えあい慰労するのだ。すぐにその準備に入ろうとしていると、蔵原がスタッフやキャストに声をかけた。
「僕は用がありますのでこれで失礼します。皆さん、ご苦労さまでした」
最後だけは丁寧な言葉遣いだったが、一礼すると彼はスタジオから足早に去っていった。
蔵原は相変わらず付き合いが悪いなと啓太は思った。しかし、それが彼の特徴であり、ふだん一緒にいても“必要最小限”のことしか話さないタイプなのだ。無口で内向的と言ってしまえばそれまでだが、あれでよく俳優が務まるものだと思ってしまう。そんなことを考えていると、2階のリハーサル室で打ち上げを始める時間になった。
社員食堂に連絡し、予約している立食パーティー用の簡単な飲食物を取り寄せた。村山編成局長らにも出席してもらい打ち上げが始まる。村山が挨拶したあとは和やかな団らんに移り、啓太は幾人ものスタッフにビールを注いで回ったりした。
吉永ゆかりは村山らと談笑していたが、やがて他のキャストやスタッフとも気さくに言葉を交わしている。蔵原がいないぶん、彼女はリラックスした雰囲気になっているのだろうか。特にカメラマンや音声係りとはすっかり顔馴染みなのだ。そのうち啓太とも目と目が合うと、吉永は打ち解けた口調で語りかけてきた。
「お疲れさまです。いろいろとありがとうございました」
そのとたん啓太は“どぎまぎ”したが、気になっていたことを一気に聞こうと思った。
「いえ、どういたしまして。ところで、蔵原さんからその後 特別なコンタクトはありましたか?」
一瞬、吉永の頬が少し赤く染まった感じがしたが、彼女は続ける。
「いえ、特にありません。蔵原さんのことがそんなに気になりますか?」
逆に問われて啓太は言葉に詰まった。
「あのう・・・今のことは忘れてください。余計なことを聞いてしまいました。どうもすみません」
そう答えたが、彼は話を逸らそうとまったく場違いなことを言ってしまった。よほど吉永に気圧されていたのだろう。
「僕はもうすぐ報道部に戻る予定です。でも、ドラマ制作は良い経験になりました」
すると、吉永は愛くるしい笑顔を浮かべて語りかけてきた。
「報道部へですか。ご活躍を祈っています」
そう言って、彼女は右手を差し出してきたので啓太は握手に応じた。吉永ゆかりの美しく輝くような笑顔に、彼はまばゆい感じがしてならなかった。
打ち上げ会は楽しく和やかに進み、最後に岡山ディレクターが締めの挨拶を行なった。
「皆さん、ご苦労さまでした。これで“完パケ”が済めば14、21日の放送を待つことになりますが、あとはニッカツ映画社との円満な話し合い解決を望むだけです。これは村山編成局長が鋭意努力されていますので、お任せするしかありません。局長、よろしくお願いします」
完パケとは完全パッケージのことで、収録したVTRなどをいつでも放送できる状態にしておくことだ。Fテレビではこの時、アンペックス社製のVTRが2台あった。こう言って岡山が村山に頭を下げると、彼はニコニコ笑いながらうなずいた。 打ち上げが終わり、吉永ゆかりも他のキャストと共ににこやかな表情でリハーサル室を出ていく。啓太は彼らを車両口まで見送ったが、彼女の握手の“ぬくもり”がまだ手に残っているような気がした。
そして、打ち上げ会の数日後、西尾ADが聞き捨てならない情報を入手した。それによると、蔵原圭一が吉永ゆかり事務所に盛んに電話をかけているというのだ。また、吉永本人にも手紙を出したという。どこまで真実なのか分からないが、もし大きな“スキャンダル”にでも発展すると放送自体に影響が出てくる心配がある。
そこで、岡山がスタッフに告げた。
「大したことはないと思うが、蔵原君は思い詰めると何をするか分からないところがある。もしマスコミが取り上げると、吉永の件でニッカツ映画社との交渉にも支障が出るかもしれない。何も起きないことが一番だが、十分に気をつけて情報収集に当たってもらいたい」
芸能界の情報については岡山と西尾が最もくわしいが、植木ADも啓太もいろいろ当たってみることになった。とは言っても、啓太には情報源がほとんどない。せいぜい報道の番組制作班やスタジオ関係者ぐらいだ。彼らだって、蔵原や吉永のことはまったくと言っていいほど知らないだろう。しかし、岡山の指示なので、啓太はできるだけのことはしようと考えた。
調べてみると、蔵原は東京・新宿区内のマンションに住んでいる。社に近いこともあって、啓太は思い切って“張り込み”をすることにした。まるで芸能記者、事件記者みたいだなと思ったが、これも仕事の一つである。人の秘密に迫るみたいで、けっこう興味が湧いてくるものだ。 そして3日目の晩、啓太が見張っていると、マンション2階の蔵原の部屋に明かりが灯った。
夜10時ぐらいだったろうか、啓太はマンションに入り部屋の玄関のブザーを鳴らすと、しばらくして蔵原がドアを開けた。
「こんばんは、Fテレビの山本です。夜分 失礼します」
「ああ、君か。今ごろ何の用なの?」
蔵原は怪訝な顔をして、啓太に中に入れとも言わない。相変わらず不愛想で、少しウィスキーの匂いがする。
「時間がないので単刀直入にうかがいますが、蔵原さんは吉永さんに何度も電話をかけたり、手紙を出したりしているんですか? 吉永事務所は迷惑しているという話ですよ。みんなが心配しているので、これ以上、何もないことを願っています」
啓太が早口に話すと、蔵原は相手をにらみつけて吐き捨てるように言った。
「そんなことを君は言いに来たのか! テレビ局が心配することじゃない。もう帰ってくれ!」
そう叫ぶと、彼は半開きのドアを乱暴に閉めようとする。啓太の足にドアが引っかかったが、そんなことは構わずにバターンと閉めた。啓太は門前払いを食わされ仕方なく帰ろうとしたが、マンションの入り口まで来て、どうしても諦めることができなかった。このまま帰るのは忍びない。
彼は再び2階へ上がると、蔵原の部屋のブザーを鳴らした。2度、3度、4度・・・ たまりかねて蔵原がドアを開ける。今度は防犯用のチェーンを内側から掛けているので、狭い隙間から顔をのぞかせただけだ。
「なんだ、まだ帰らないのか。帰らないなら警察に連絡するぞ!」
「構いませんよ。それなら、僕がここで大声を出しますか? マンションの人はびっくりするでしょうね」
お互いに“脅し”をかける形になったが、しばらくして、蔵原が根負けしたのか呟いた。
「少し話せばいいんだな。それなら、上がれ。少しだけだぞ」
チェーンが外され、啓太は玄関に入った。
「時間は取らせません。こちらの言い分を聞いてください。それだけです」
そう言うと、蔵原は無言でスリッパを揃え、啓太に部屋に上がるよう促した。8畳ほどの洋間は意外に片付けらていて、中央のテーブルには飲みかけのウィスキーグラスが置かれていた。また、部屋の壁には、吉永ゆかりの顔写真が飾られていたのである。
蔵原と啓太は向かい合ってテーブルに座った。啓太が説明を始めると、蔵原はウィスキーの水割りをゆっくりと飲みながら聞いている。けっこう“飲兵衛”だなと思いながら、啓太は一通りの説明を終えると返事を待った。
「分かりました。吉永さんの件のFテレビとニッカツ(映画社)の交渉は直接 僕には関係ありません。しかし、言動を慎むということでは、僕も大いに協力しましょう。ご心配をかけてすまなかったね」
今までとまるで違う蔵原の丁寧な答え方に、啓太は少し戸惑った。これで万事 平穏に放送を待つことができるのだろうか。まだ半信半疑だったが、啓太はひとまずホッと安堵した。
「ありがとうございます。安心しました。岡山らにも伝えますが、また何か不明な点や気がかりなことがありましたら、なんなりと聞いてください。今日はこれで失礼します。夜遅くまですみませんでした」
蔵原に謝意を伝え引き下がることにしたが、啓太はマンションを出ていく時、蔵原と吉永の個人的な関係について何も聞けなかったなことを残念に思った。しかし、それはプライバシーだ。もしそこまで踏み込んで聞いたら、蔵原はきっと怒っただろう。ああいう繊細な男を怒らせるのは良くないし、かえって危険だ。啓太はそう自分に言い聞かせながら帰路についた。
翌日、彼は蔵原と話したことを岡山と西尾に報告した。彼らも一安心といった感じで、あとは村山編成局長とニッカツ側との交渉を見守るだけとなった。そして2日後、村山は東京・日比谷のニッカツ本社へ出向くことになり、相手側の責任者と話し合うことになったのである。
しかし、この交渉は難航した。日活側は吉永ゆかりとはいま専属契約について話し合っているから、五社協定の趣旨に基づいて、テレビドラマ出演は認められないと強硬に主張した。これに対し村山は、吉永はニッカツと専属の再契約をしていないし、現在フリーだからテレビに出演しても何の問題もないと反論した。
結局、この話し合いは不調に終ったが、Fテレビはドラマ『まためぐり合う時』の完パケ収録を行なったのである。あとはニッカツ側が怒って法的措置を取るかどうかだが、そんなことを気にしていたら放送自体が不可能になる。円満な解決を望んでいたが、予定どおり4月14、21日に前後編を放送することになった。
「やむを得ませんね。放送前にもう一度、蔵原さんと会って事情を説明しておきますよ」
西尾や植木と雑談している時に、啓太はそう切り出した。
「うん、蔵原は気むずかしい男だから、きちんと説明しておいた方がいいよ。頼むね」
西尾がそう答え植木も賛同した。ところが、啓太がもう一度 蔵原に会おうとしている直前に、とんでもないことが起きたのである。
それは放送日の3日前だったが、ある芸能プロダクションから岡山ディレクターの席に電話がかかってきた。
「えっ? 蔵原が・・・」
岡山は受話器を取るとしばらく絶句していたが、やがて電話を切ると啓太らスタッフ全員にこう告げた。
「蔵原が自殺を図ったようだ。いま、四谷のK病院に収容されている。誰か・・・ああ、山本君、どうなってるか君はすぐK病院へ行ってくれないか」
「はい。分かったことはすぐに報告します」
こう言うと、啓太は会社の車でただちにK病院へ向かった。ここはFテレビに近いこともあって、報道部時代に何度も来たことがある。先輩らが入院すると見舞ったり、医師に話を聞いたりした所だ。病院に着くと、啓太はすぐに蔵原がいる病室へ向かった。
しかし、面会謝絶・・・ 仕方がないので近くの待合室へ行くと、どこかで見た男が手持ちぶさたな様子で座っている。脚本家の矢崎修だった。彼とは“打ち上げ会”の時に岡山から紹介してもらったが、ドラマ『まためぐり合う時』を脚色して俳優・蔵原を岡山に推薦した男だ。原作の“ピエール像”には、蔵原がぴったりだと信じていたのだ。
「あの~、この前、ドラマの打ち上げ会で紹介してもらったFテレビの山本ですが、矢崎さんも蔵原さんの様子を見に来られたのですね?」
啓太が尋ねると、矢崎は顔を上げ「ええ」とうなずいた。
「あの~、蔵原さんの様子はどうなのでしょうか?」
「さっき、妹さんから聞きましたが、意識不明の重体だそうです」
矢崎はそう答え、隣に座った啓太に説明を始めた。それによると、彼はある芸能記者から一報を知らされK病院に駆けつけたのだ。蔵原は昨夜 睡眠薬・ブロバリンを大量に飲んで意識を失っていたところを、妹の文枝(ふみえ)に発見され救急車でK病院に担ぎ込まれたという。蔵原は自殺を図ったのだ。
「すると、いま昏睡状態ということですか?」
「いや、分かりませんよ。ブロバリンを大量に飲んだから、胃洗浄などをして一命を取り止めようとしているのでしょう。僕は医学のことはよく分かりません」
矢崎が困惑した表情で話すので、啓太はますます不安になった。
「もうすぐ、妹さんがここに来てくれます。彼女の話を聞きましょう」
矢崎がそう言うので、啓太はとりあえず会社に現状を伝え妹さんの報告を待つことにした。公衆電話から会社に連絡して戻ると、ほどなくして文枝が待合室に現われた。彼女は兄とまったく違い、健康そうで根が明るい感じのする女性だった。矢崎の話だと、蔵原より3歳年下で、最近 都内の某出版社に就職したばかりである。矢崎とは兄の縁で2~3回会ったことがあるそうだ。
「こちらはFテレビの山本さんです。一緒に話を聞きますから」
矢崎がそう言うと、文枝が軽く会釈した。
「お待たせしました。兄の容体は相変わらず良くありません。今日一日がヤマ場だと、お医者さんが言ってくれています。ご心配をかけてすみません」
文枝はさすがに暗い表情を見せた。そして、まもなく父と母が東海道線で静岡から駆けつけるという。蔵原兄妹は静岡市の出身なのだ。矢崎が問い質すと、文枝が話を続けた。
「あんまり連絡がないので、昨夜 兄のマンションへ行って合鍵で中に入ると、兄は床の上に倒れていました。そばにはブロバリンの空きびん3個が転がっていましたが、ほとんど空になっていました。300錠近く飲んだのでしょうか。また遺書もありました。これは大変だと、すぐに救急車を呼んでここへ入院させたのです」
文枝はさらに話を続けたが、ほどなくして看護婦が呼びに来たので彼女は病室へ戻った。すわとばかりに啓太と矢崎が病室の前で待機していると、やがて文枝が姿を現わした。やや安堵した表情である。
「なんとか一命は取り留めたようです。ただ当分の間、入院加療が必要だそうです」
彼女の話に啓太らはホッと胸を撫で下ろしたが、まだ安心はできない。睡眠薬の副作用や後遺症などがあるのだ。しかし、取り越し苦労をしても仕方がないから、啓太は文枝に挨拶して、ひとまずFテレビに帰ることにした。後日、彼女からいろいろ話を聞くことにして・・・
社に戻ると、すでに一報を聞きつけて何人かの芸能記者が詰めていた。杉浦部長と岡山が、蔵原は睡眠薬を大量に飲んだが命に別条はないと説明する。記者から質問が出た。
「14日の放送は予定通り行なうんですね?」
「それは変わりませんよ。予定通りです」
記者とのやり取りがしばらく続いたが、杉浦に促されて啓太が病院の模様を説明した。
こうして、蔵原の“自殺騒動”は芸能マスコミの関心を呼んだが、問題はその動機である。マスコミは彼が厭世的で、破滅的性格だからなどと書き立てた。たしかに蔵原にはそういう特徴があるが、それは直接の「動機」とは言えない。あくまでも彼の性格の一面なのだ。
一部のスポーツ紙が、蔵原と吉永ゆかりの関係を匂わす記事を書いたが、啓太はこれこそ真の動機だと考えた。彼が吉永に手紙を書いたり電話をしたり、また言い寄ったことなどを啓太は思い出した。その辺の事情を啓太は蔵原の関係者に聞こうと思ったが、まずは放送が無事に行われることが先決でそちらに関心が集中した。
4月14日夜、ドラマ『まためぐり合う時』の前編が放送された。蔵原の自殺騒ぎがあったせいか視聴率はふだんより高く、その面ではスタッフらの努力が報われた形となった。視聴者からの苦情などは、思ったより少なかったのである。後編の放送日まで1週間あるので、啓太はその間に蔵原の関係者にいろいろな事情を聞こうと思った。
その前に彼は、脚本を書いた矢崎修に、事前の取材をした方が賢明だと考えた。予備知識を持っていた方が、妹の蔵原文枝らに当たりやすいのだ。そこで15日午後、啓太は矢崎の自宅(東京・文京区)近くの喫茶店で彼に話を聞くことになった。
啓太は率直に問い質す。
「蔵原さんの自殺未遂は、吉永ゆかりさんとの関係が原因なのでしょうか?」
矢崎はしばらく考え込んでいたが、やがておもむろに口を開いた。
「まあ、そういうことでしょう。彼から直接聞いたわけではないが、蔵原は吉永との関係に失望して自殺を図ったと見られますね。しかし・・・それより、これは彼の“美学”だと思いますよ」
「美学? 美学とはどういうことですか?」
「うん、蔵原は自分が原作のピエールになり切って、本当にリュースの懐の中で死にたいと願ったのですよ。これは幻想、いや妄想の類(たぐい)ですね。彼は本当に吉永ゆかりの懐で死にたかったのです。これが彼の美学だったのでしょう」
なんだ、現実と幻想をごっちゃにしているではないか。蔵原とはそういう男なのか。それではあまりに“夢想家”ではないか・・・ 啓太はそう考えたが、あのドラマの収録の時に、彼が吉永の腕の中で恍惚としていた姿を思い出した。蔵原は演技という現実と、崇高に死ぬという幻想を混同していたのか・・・
その時、啓太は『ピエールとリュース』の中に出てくるロンサールの詩も思い出した。「恋人よ、あなたの腕に抱かれて死ねたらうれしい。あなたの膝のうえで安らかに死にたい」
このロンサールの詩を、蔵原はいつも口ずさんでいたのだ。すると、彼は本気でそういう死に方をしたかったのか。なんと“ロマンチック”な男だろうかと啓太は思った。しかし、自分もそうなのではないか。自分だって、ピエールのように愛する人の膝の上で安らかに果てたいのでは・・・これが、蔵原の美学なのだろう。
矢崎と会ったあと、啓太は翌日、またK病院へ見舞いかたがた蔵原の様子を伺いに行った。見舞いと言っても相手は「面会謝絶」だから、妹の文枝に会うのが目的なのだ。一応 Fテレビからと言って生花を持参したが、これは文枝に受け取ってもらった。そして、蔵原の様子を伺いたいと言って彼女に待合室へ来てもらったのである。
「大変でしたね。蔵原さんは順調に回復されていますか?」
啓太の問いかけに、文枝は兄の容体についてくわしく語った。彼女は根が正直なのか、また将来、雑誌記者を目指して出版社に就職したせいか、テレビなどマスコミには理解があるのだろう。蔵原は睡眠薬の後遺症などがまだ心配だが、ようやく危険な状態を脱出して一命を取り留めたという。
そこで啓太は、最も気になっている蔵原の“遺書”について聞いた。
「失礼ですが、兄さんの遺書をご覧になりましたか?」
「ええ、でもこれはなかったことにしましょう。兄は生き延びたのですから」
「絶対に口外しませんが、遺書は何通あったのでしょうか。二通、三通・・・?」
文枝は言葉に詰まったが、やがて答えた。
「二通です」
「家族の人とそれ以外に・・・」
「両親宛てと、もう一通ありました」
「もう一通とは、ある女性宛てでしょう」
とたんに文枝の頬が赤く染まり、しばらくして彼女の方から聞いてきた。
「ええ。でも、それがどうしたのですか? 兄が意識を回復したら、処分するかどうか自分で決めるでしょう」
「それは、吉永ゆかりさん宛てではないですか?」
「そんなことは言えません!」
文枝はムッとして答えたが、彼女が否定しなかったので啓太は満足した。
蔵原の秘密を少し知ったので、啓太は納得して文枝と別れた。遺書のことは岡山らに知らせなくても、自殺未遂の顛末はかなりくわしく報告できる。それで、一件落着だろう。あとはスポーツ紙や週刊誌が騒いでもほとんど問題はない。いや、むしろ騒いでくれた方が、ドラマの視聴率が上がって良いはずだ。
こうして4月21日(木曜日)夜、『まためぐり合う時』後編の放送を迎えた。主人公の田島三郎と小野瑩子に扮した蔵原と吉永の演技は、改めて見ても美しいものだった。啓太は感慨にふけりながらドラマを見ていた。特にラストシーンは、米軍の空襲で崩落する壁につぶされて三郎と瑩子が死んでいく。三郎は瑩子にしっかりと抱かれながら・・・
放送が終わると、なにか“解放”されたような気分になった。大勢のスタッフやキャストが参加してドラマはでき上がる。そのドラマが終了すると、みんなが解散するのだ。報道部では味わったことがないような解放感が残る。それがドラマ制作の良いところなのだろう。 放送終了と同時に、みんなで拍手した。打ち上げ会とはまた違った雰囲気である。改めて「ご苦労さん」を言い合い、啓太はFテレビをあとにした。
結局、ドラマの後編は視聴率が30%を超えて大成功に終わった。もちろん、蔵原の自殺騒ぎで世間の注目が集まったのだが、啓太には彼と吉永ゆかりの演技が永遠のものとして映った。それにフロマネとして立ち会えたのは幸運だったが、どうしても蔵原への嫉妬は残る(笑)。しかし、それは仕方がないだろう。あとは、彼が早く立ち直るのを願うだけだ。
それから数日後、3階のフロアで啓太がぶらぶらしていると、石浜報道部長から久しぶりに電話がかかってきた。
「元気にやってるか? ところで、君は5月の連休明けに報道部に戻ることになった。5月6日に正式発令だ。よろしく」
石浜らしい単純明快な言い方だ。ドラマ制作部への異動は短期間だと聞いていたから、啓太は別に驚きはない。むしろ願っていたことだ。「分かりました。よろしくお願いします」と返事をすると、石浜が畳みかけるように言ってきた。
「どうかね。制作の方で組合結成の動きは・・・」
その言葉に啓太はカチンと来た。労働組合結成の話である。報道部を出る時に、石浜からそういう“兆し”があれば知らせろと言われたことを啓太は覚えていた。しかし、そんなことは正直言って何の関心もなかったのだ。
「特にありませんね。仕事に慣れないもので、そういう動きをじっくりと探る時間はなかったです」
啓太は正直に答えた。そう答えながら以前、先輩ADの植木が『この会社はおかしい。労働組合がないって変だよ』と話していたことを思い出した。あれはロケの下見で本所(ほんじょ)界隈へ行った時だった。
「ただ、労働環境に不満を持っている社員はいるようですね。どのくらいいるか知りませんが」
啓太が付け加えると、石浜は「そうか」と答えただけで電話を切った。報道部への異動の内示を受けて、啓太はやっと“本業”に戻る感じがした。しかし、ドラマ制作は人手不足の“助っ人”という立場だったが、いろいろな経験を積ませてもらったと思う。それに、吉永ゆかりとも握手ができたし・・・
また、思っていたより良い人が多かった。報道の方がむしろ“クセ”のある人間が多いのだ。そんなことを考えながら、啓太は岡山PDや西尾、植木ADらに別れを告げドラマ制作部をあとにした。報道へ戻ることに胸をふくらませながら・・・(第1部・終り)
<主な参考文献・ネット資料など>
ピエールとリュース(ロマン・ロラン、渡辺淳訳・鉄筆文庫) ロングラン(村上七郎) 昭和史年表(小学館) 昭和史全記録(毎日新聞) 昭和二万日の全記録(講談社) フジテレビジョン開局50年史 開局からの歩み(フジテレビ) タイムテーブルからみたフジテレビ35年史 ウィキペディア全般 放送業界語辞典(ネット) テレビドラマができるまで(東放学園・ネット) 青春の墓標(奥浩平) 吉永小百合ホームページ また逢う日までーピエールとリュース(ロマン・ロラン、窪村義貫訳・明治図書) メディアの支配者(中川一徳・講談社文庫)


参考文献の一部