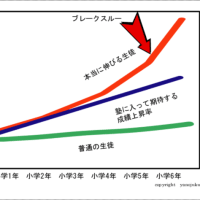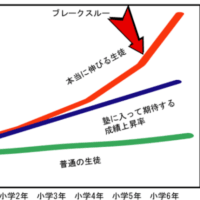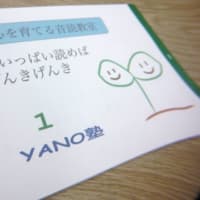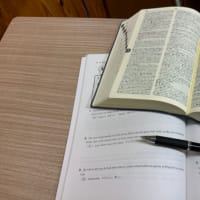複数受験の中でもっとも良い点を参考にしてそれを大学側に提出するというシステムは
アメリカのSATを踏襲しています。
Wikiから引用すると、
「アメリカ合衆国の学校制度では高校卒業までが義務教育期間である。
しかし高校によって学力に差があり、成績評価基準も学校によって
異なるため大学受験で高校の成績のみで合否を判定することはできない。
そこで4,500校余りの高等教育機関からなる大学評議会が標準テストを実施し、
そのスコアで生徒の大学受験の合否を決定することになった。
SATは現在アメリカ国内で一番広く大学受験に使われているテストである。
誰がどの大学で学問を修める学力があるかどうかを判定し、
合否の基準にする目的で1901年に導入され、何度か大幅な改定がなされてきた。
またそれに伴い呼称も変わっている。試験は1年間に7回実施され、
繰り返し受験することが可能である。」
日本式をやめてアメリカ式にするっていうことですね。
しかし、複数受験によって、日々の学校での幅広い学習がそのテストによって
中断されます。
また日本の大学と違ってアメリカのハーバード大でもプリンストンでもそうですが、
日本の大学と違って、面接がとても重要視されます、その際に問われるのは
その学生がどのように地域やボランティアやいろいろな活動に参加しているか
を精査して合否を決めているかということです、これは私の知り合いでアメリカ人の
かたと受験の話をしている時にそのことを特に強調していました。
日本はとにかく入り口が大切です。だから、履歴として早稲田中退 ってことも
よく自慢げに語る人がいますが、アメリカでしたら、ハーバード大中退なんて
履歴は書きませんし、自慢にもなりません。
アメリカ人は何大学を出たかというより、何が出来るか何を志向しているか
の方を重要視しますからね。
とにかく日本の官僚のやっていること、特に文科省と外務省、
ひどすぎます。
センター試験については言いたいことは山ほどありますので、また書きます。
アメリカのSATを踏襲しています。
Wikiから引用すると、
「アメリカ合衆国の学校制度では高校卒業までが義務教育期間である。
しかし高校によって学力に差があり、成績評価基準も学校によって
異なるため大学受験で高校の成績のみで合否を判定することはできない。
そこで4,500校余りの高等教育機関からなる大学評議会が標準テストを実施し、
そのスコアで生徒の大学受験の合否を決定することになった。
SATは現在アメリカ国内で一番広く大学受験に使われているテストである。
誰がどの大学で学問を修める学力があるかどうかを判定し、
合否の基準にする目的で1901年に導入され、何度か大幅な改定がなされてきた。
またそれに伴い呼称も変わっている。試験は1年間に7回実施され、
繰り返し受験することが可能である。」
日本式をやめてアメリカ式にするっていうことですね。
しかし、複数受験によって、日々の学校での幅広い学習がそのテストによって
中断されます。
また日本の大学と違ってアメリカのハーバード大でもプリンストンでもそうですが、
日本の大学と違って、面接がとても重要視されます、その際に問われるのは
その学生がどのように地域やボランティアやいろいろな活動に参加しているか
を精査して合否を決めているかということです、これは私の知り合いでアメリカ人の
かたと受験の話をしている時にそのことを特に強調していました。
日本はとにかく入り口が大切です。だから、履歴として早稲田中退 ってことも
よく自慢げに語る人がいますが、アメリカでしたら、ハーバード大中退なんて
履歴は書きませんし、自慢にもなりません。
アメリカ人は何大学を出たかというより、何が出来るか何を志向しているか
の方を重要視しますからね。
とにかく日本の官僚のやっていること、特に文科省と外務省、
ひどすぎます。
センター試験については言いたいことは山ほどありますので、また書きます。