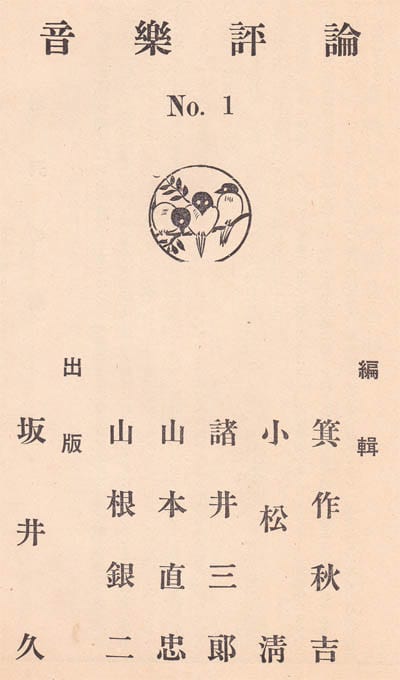オリヴィエ・メシアン(Olivier Messiaen, 1908-1992)は1962年6月20日、イヴォンヌ・ロリオ(Yvonne Loriod, 1924-2010)と共に初来日し、主に「トゥーランガリラ交響曲」の上演、監修のために一ヶ月程滞在しました。
→ 二度目の来日(1978年)
『藝術新潮』1962年9月号にメシアン自身による『日本に演奏して』という記事が掲載されています。
---------------------------------
日本に演奏して
オリヴィエ・メシアン
パリの東北端の高台、氷雨や雪の日には出入りにも困難だと嘆かれるヴィラ・デュ・ダニューブという村落めいた地区に長年住みつき、どんなにその非現代性、不便さを説かれても転居する気にならない私だが、その我が家の門口に「スランガ」と呼ばれる木が一本ある。毎年六月のはじめになると純白の小さい花をいっぱいに咲かせ、爽やかな匂いを漂わせてくれるのだが、花の盛りはわずかに四日である。その季節に講演旅行などで留守にしてせっかくの花を見逃してしまう年もある。我が家の花でさえ見そこなうことがあるのだから「日本のさくら」「日本の紅葉」という特有の自然美にめぐり合わなかったことはあっさりとあきらめている。
「いちばん気候の悪いとき、いちばん自然の貧しい時にいらっしゃって・・」と同情の言葉を何回も受けたが、私にとってはパリ音楽院の卒業試験の終る六月中旬以後でなくてはパリを長期間離れるわけにはいかないのであった。
野鳥を聞くことができるかどうか、それが唯一の心配だった。フランスでは六月すぎではもう鳥の声をきくには時期はずれなのだから。しかし、六月二十日日本についてその翌朝、高輪プリンスホテルの庭の深い木立ではいくつかの鳥の歌が私を迎えてくれ、そのなかには「ジュウイチ」の声があった。二十二日から二十五日まで軽井沢星野温泉に泊って、野鳥研究家の星野嘉助さんに案内されて森林をあるいたが「ジュウイチ」はたびたび私をよろこばせてくれた。「オオルリ」「コルリ」それから「キビタキ」だのと私の耳、私の頭の中では「鳥のカタログ」はどんどん充実していって楽しいかぎりだった。軽井沢の三日三晩の収穫は大きかった。なにしろ朝は四時から山にはいりこみ、夜はまた九時ごろまで探さくの足を休めなかったのだ。そして二十四種もの鳥の声を採譜できたのであった。
日本の野鳥についての予備知識はかなり持っていたつもりだった。というのは作曲家・松平頼則さんが鳥の声の録音テープを数本私にとどけて下さっていたからである。しかし実際にきいてみるとナマの声は別個の感じがする。松林のなか、急流のほとりで思いがけない方向から、不意にきこえてくる声はその自然との調和の美しさばかりでなく、声そのものも或いはリピートがいくつもあったり、リズムの変化もあって複雑、多様なのである。キビタキなどもあるときはモデラートであり、アッチェレランド(漸次急速に)になったり、その変化は面白いのである。
京都で大原總一郎さんにお会いしたとき、「ワグナーの『ニュルンベルグの名歌手』のおわりの方にたしかキビタキの声の模写と思われる個所があるからこの鳥はドイツ、オーストリア地方にも棲息しているのだろう」とのお話があったが、私の知るかぎりではこの鳥はヨーロッパにはいないようだ。もしヨーロッパでキビタキをききつけたらその時は即刻ご報告していさぎよく不明をわびるつもりでいる。
詩的なのはヨタカの声だった。録音できくと単調で陰気なだけだが、浅間の姿を望むところで月の光をあびてきいたときには遠いところに心を引き裂いて持ち去られるような感動をあたえられた。
野鳥に関するプランは軽井沢行だけだったが、「トゥランガリラ交響曲」の録音の仕事が終った日に、私は矢代秋雄さんから富士山麓の須走の野鳥園に行かないかと誘われると、数日間スタジオに引きこもっていたあとだから大自然へのノスタルジアがむらむらとわき上がり、スケジュールの都合を無視して山中湖に旅立った。山中湖の一夜が白々と明けるころ水際に見えた富士の崇高さには思わず嘆息してしまった。野鳥園は開園直後だったので集められた野鳥たちはまだ「籠の鳥」の悲境にあり、歌をきかせる余裕はまったくなかったものの、幸いにも高田さんという野鳥研究家が原始林に案内してくれ、いくつかの鳥の声をきくことができた。忘れ難いのは「コジュケイ」だった。「コジュケイ」や「クロツグミ」は本当に美しい歌をうたう。
あちこちで断片的に語ったが、私が「鳥のカタログ」で使った方式は鳥の声を現場採譜して私の作曲理論によって発展させるが、一つの鳥の声が三分間の音楽になるまでには同種類のものを五十も六十もきかねばならぬし、ソロだけでは足りなくて幾羽もの合唱を採譜する必要もある。そして私はその鳥の生活環境、棲息地帯を音に再現してそこに鳥の歌声をはめ込む、つまり、額ぶちにはめた絵にするのである。今までこうしてブルターニュのシギだのソローニュの池のすずめなどが鳥のガレリーに展示されてきたのだった。その土地のすんだ空気、田園の匂い、海の色彩、その量感などがハーモニーに生かされるのが私の願望なのであった、とこんなことをしゃべっていたら性急な人が問いかけてきた。「メシアンさん、それでは近いうちに『浅間のヨタカ』というものが創作されると期待してよいでしょうか?」と。少し残酷な質問だ!いまはただ日本の鳥たちに自由自在に私の頭の中で飛びまわり、さえずってほしいだけなのだから!私はもったいぶって答えたものである。「私は将来のプランを絶対に語らない主義でしてね」と。
「トゥランガリラ・シンフォニー」の日本初演ということが今回の私とイヴォンヌ・ロリオの日本訪問の中心プランだっただけに、軽井沢から帰京した翌朝はじめてNHK交響楽団の練習に臨んだときは、複雑な感情が私の頭を領していた。楽団の技量は六月の定期公演をきいてわかっていたし、小澤征爾氏の才能にも十分信頼はおいていたものの、しかし、初演というものはいつでもどこでも予期しない困難事がつきまとうことを知っているからだ。二十六日から七月三日まで朝は十時きっちりにはじめて、午後三時まで昼食の一時間をのぞいて指揮者と楽団とはしっかりと合体して、息もつかせぬほどの緊張した稽古がつづけられた。
公演の日(七月四日)の午前中の文化会館大ホールでの総げいこの時には、まったくブラボーと感嘆の声を禁じ得なかった。そして公演の出来ばえについては、それが今まで世界の大オーケストラによる幾度かの演奏のうちでも最もすぐれたものの一つだということをはっきり断言したい。私は指揮者にまねかれてステージに立ったが嬉しさのあまり言葉ものどにつかえ、うろたえた姿をさらしたが、それほど感激が大きかったのだ。
小澤さんの指揮については恐らくいくつかの新聞の批評に語りつくされていると思うが、私自身一言つけ加えないではいられない。世間では彼を天才といっているようで、もちろん、リズムに対する鋭敏性は生まれつきのものだ。しかし、指揮者はいつも「楽団」に直面していてその一人一人の能力とその限界判断を正確に感じとり、その能力を最大に引き出させて、しかも全体の中に投入して完全な一つのものに盛り上げる力が必要なのだ。ただの才能だけでは間に合わぬ。あの若さでまるで六十歳の老練な指揮者のようにすべてをやってのけているのだ。全くあの晩の演奏には一つの導入のまちがいもなかったし、一つの狂った音も鳴らなかった。それに全楽員の真剣な態度にも敬意を表する。
あの公演のあとであの曲について専門家の人々といろいろ話し合ったが、清瀬保二さんが「トゥランガリラ」はフランス音楽というものが今までわれわれに与えてきた概念を越えたヴォリュームとヴァイタリティに溢れている点を指摘したあとで、どうもフランスではベルリオーズの諸作品に一脈通じるのではないかと言われたのには微笑を禁じ得なかった。正しく私にとってベルリオーズは無縁の人ではないからである。二人とも同じ人種なのだ。つまり、彼はグルノーブルの出身、私もまた生まれはアヴィニヨンだが、父がグルノーブルで英文学の教授をしていた関係上この地は私の第二の故郷なのであった。ベルリオーズの想像力、創作欲の羽ばたきを育てたのはあのアルプスの白雪、森林の神秘、それは少年時代の私を取り巻く自然だったのである。
さて、もう一度、「フランス音楽」というものに戻るが、クープラン、ラモー、ドビュッシー、ラヴェル、それからベルリオーズといういずれも独自の音楽をつくっているように、「日本音楽」もまた多くの形式と質によって代表されているではないか。短い今回の滞在で私が知り得たのは氷山の一角にすぎないであろうが、それでも筝曲にも多くの傾向があるのを学んだし、三味線でも文楽と地唄、また長唄とのちがいがわかるし、謡曲もあれば雅楽もあることは、日本の音の世界がいかに豊かであるかを物語っていよう。
文楽はちょうど三和会の東京公演があったので「トゥランガリラ」の録音の休み日を利用して案内してもらった。私が感心したのは「寺子屋」であった。この私塾で起った封建時代の悲劇の複雑な筋と、そしてその多くの人物を描きわける語り手(訳者注・豊竹若大夫)の声量と技巧、太ざおという三味線のしぶい音色は全くユニークなものだ。

↑ 文楽を見る
「能」については、これまた友人達からレコードを送られていて相当理解していたつもりだったが、本物に接すると自分の想像をはるかに超越した美しさ、優雅さに感嘆してしまった。簡素な外観と深奥な内容との対照の妙。鼓の音のニュアンスの豊かさ、あのかけ声は私の心に沁みとおり、微妙なあの「間」のとり方は多くきけばきくほど魅惑されてしまう。出し物は「小督」「蝉丸」「紅葉狩」だったが(訳者注・観世定期能)、私は「蝉丸」が最も好きである。
私は能と文楽を見られたら歌舞伎は割愛してもよいと言っていたのだが、欲の深い性質だから東京を離れる日が近づくとやっぱり歌舞伎も見ておこうと言い出し、言い出すと何度でもくりかえして要求したあげく、「盆興行はお化け芝居」で面白くないと言われるのを押して歌舞伎座に出かけた。やっぱり来てよかったのだ。伝統的な幕のあけ方の伴奏になるキの音の清潔感。「かさね」の芝居では終始観客はゲラゲラ笑っていたが、物語の根底をなす因果応報という仏教の哲学がどうして笑いごとではない。勘三郎という俳優は全くセリフを解しない私たちにも十分納得のいく表情を顔と身体全体でやってのけている。三十年も前にドイツでお化けの出る一幕物を見た後、数カ月も夢にみてうなされた話を幕間にしたら、付添の人が最後の幕は見ないで帰ろうと提案したが、一旦感興をおぼえた以上、中途で止めるわけにはいかない。剛情をはり通して結局殺しの場面まで見てしまった。みんなが笑っているうちは恐ろしくなかったが、最後に私のわきの花道にニューッと出た亡霊にはたまげた。全くてっていした写実だ。
京都では大原氏邸で井上八千代さんの舞踊を鑑賞する機会に恵まれた。畳の上を滑る白足袋のうごき、扇の扱い方など、能にたいへん近くて、さらに柔らかみのある華麗さに恍惚とした。「虫の音」という曲では松虫の声の模写が面白かったので、踊りのあとで地方(じかた)の人たちに何回もひいてみせてもらった。「雅楽」をきくことも「能」と同じに重要なプランだった。中国がこの音楽の発祥地であるにしても、今日演奏されている雅楽はやはり日本の風土、日本人の美学的センスに養われて育った、特殊の音楽だと思う。先年新中国を見学された清瀬保二さんは中共政府は文化財として雅楽の復興に着手していると言われたが、特定のふんいきを背景にして生まれてきている曲目のいわれをきき知る私たちはその背景、環境を抹殺した条件でこの音楽が理解できるのかなと不審に思うのだが・・。私たちはその意味では幸いである。大内山の木立深く、雅楽部の清浄な舞殿できく管弦は最高である。松平頼則さんと一緒に楽譜を参照しながらきいたので楽しみが倍加された感じであった。和琴とか、笙、しちりきとかいずれもその音色、その量感ともにすぐれた楽器である。「還城楽」の豪壮さ!暑熱の白昼、正式の衣装をつけて舞って下さったのには感激した。雅楽拝観後のスケジュールがぎっちりつまっているのも承知の上で、私は大手門から出るとすぐさま銀座に車を走らせて雅楽のレコードを買い漁った。その時は雅楽以外のものは私にとって存在しなかったのだ!

↑ 井上八千代の踊りを見るメシアン(京都・大原總一郎邸にて。以下の画像は小川光三氏【1928‐2016】撮影)
法隆寺の壮大さ、いくつかの門と回廊の調和、東院への道の両側にある松の老樹、かねてから写真で知っていた木造の百済観音のみごとな姿、夢違観音立像のやさしい微笑など、私はノートに記入し切れないほどの芸術に接したのであった。金堂と五重塔の面白いシメトリー、まったくユニークである。法隆寺から唐招提寺にいくとなにかほっとした安らぎを感じる。威光や壮大さよりもここには詩が香っているようだ。千手観音の大手、小手の微妙さに驚嘆する。薬師寺では薬師如来とその両脇に「日光」「月光」の侍者が並び立つ壮観に立ち去りがたい思いで眺め入ったことである。
音楽家の私達の心に深い愛着をおぼえさせるのは大仏殿前の八角灯籠である。日本で最も古い灯籠だそうだが、火舎(ほや)の扉には笛を吹く天人が浮彫されている。いかにもみずからの楽の音に恍惚としている表情がうかがわれる。
灯籠といえば夕ぐれの春日神社で長年の執着の的であった「三千の灯籠の並木」のあたりを逍遥して私は大満悦であった。杉や樟の老樹を縫ってえんえんとつづく灯籠の列――それに灯火がともされたらどのような色彩を呈することだろう。
京都の町では柳が目についた。細い川の流れに沿って柳の枝葉が深々と垂れ、低い屋根、白い壁の家が並ぶ木屋町という通りは車で走りすぎるのが惜しまれた。知恩院の池には睡蓮が浮かんでいた。私は思わず叫んだものである。「モネ君、君よりも以前にここには印象派がいたのだ!」と。

↑ 知恩院本堂にて
それから桂離宮にいくともう私は完全に狐憑きみたいになり、拝観者の列から遠くにとりのこされてはたびたび巡視者に注意されるしまつだった。竹や楓やつつじが(残りの花を二、三つけていて)私をひきとめてしまうからだった。そしてこれらの樹木の姿をうつす池のほとりでまたもや私は叫んだのである。「ドビュッシー君、君よりも以前にここには『水の反映』を作った人がいたのだ!」と。

↑ 桂離宮にて
宮島の厳島神社に詣でたとき、はじめは潮がひいていて、いささかがっかりしていたが、紅葉台という丘に上がって内海を見下ろしてから帰ってくると折よくみち潮になってきて、赤い鳥居が残照の散り交う水中に浮かんだのも注文通りだった。その上、一茶苑での夜食に瀬戸内海の魚のかずかずを賞味していると一点の曇りもない月が出た。桂離宮の天皇たちの月見の宴にも劣らぬ豪華さだ!勿体ないような旅ではあった!
短い旅程の中から広島まで行かれたのはかねてからの知人、エリザベト短大の学長ゴーセンス神父の友情によるものであった。白状すると暑熱と仕事疲れとで広島駅に降りた時は蒸釜から出るようにボーっとしていたのだが、駅頭では男女学生の合唱隊が待ち伏せしていて「祈りませ聖母」といきなりうたい上げて私を驚かせ、私を正気にもどしてくれたのであった。
広島の歴史的受難を世界中で知らぬものはいない。駅頭で新聞記者からこの町へのメッセージを、と求められて私はこう答えた。「私がここに来たということ、それがメッセージです」と。平和記念塔に異国の旅人としての花を捧げたあとで、大聖堂へと向う道々、私は心の中でくりかえしたものだ。やっぱり来てよかったのだと。ここには東京や大阪に見られない近代的な広い道路が走っているが、並木の樹木はまだ幼く弱々しい。しかしこの若い木は何年か先にはうっそうとした緑林にかわるだろう、廃墟から再生した魂の純潔さ、強さを物語るように。
大聖堂の前には神父たちや修道女、信者たちが私達を待っていてくれ、オルガンの奏楽が私を迎えたのであった。セザール・フランクの詩篇の一章が流れる聖堂にひざまずいて私はしばらく祈りつづけていた。受難者たち――死んだ人々と残された人々と――の上に平安の訪れんことを。合唱隊がフォーレのレクイエムから「天国にて」をうたいはじめていた。
訳・編・山口芙美(プロモーター)
-----------------------
。。。メシアンは日本の文化ベタ褒めですね!
最後に、ロリオ夫人の『メシアンと私』です。私はメシアン専門のピアニストではないのよ、とおっしゃっています。
-----------------------
メシアンと私
イヴォンヌ・ロリオ
パリの音楽院でメシアンのアナリーゼとハーモニーのクラスを修了した私はその後彼の作品をいくつか初演することになり、今でもヨーロッパ、アメリカなどの現代音楽祭には招待されてメシアンの作品を度々演奏しています。そして今回の来日では「トゥランガリラ交響曲」のピアノソロの部分を受け持ち、またリサイタルでは第一部がピアノソロで「幼児キリストにそそぐ二十のまざなし」を、第二部ではメシアンとのデュエットで「アーメンの幻影」をひき、メシアンの講演会では「ヌーン・リトミック」と「鳥のカタログ」の抜粋をひくという具合で、まったくのオール・メシアンプログラムであったので、私がメシアンのピアノの専門家のように取り沙汰されてしまったのですが、これには誇張があることを申しておきたいのです。
メシアンのピアノ曲は私より前からひいていたピアニストもあり、現在も方々の国でひかれているのです。ただ、今回メシアンとともにひいた「アーメンの幻影」は初演以来二人で度々やっていますし、「トゥランガリラ交響曲」は初演以来私がひいていますのでこの曲については特別な愛情も持っていますし、演奏についても、自分なりの信念を持つことができるようになってきたことは確かです。
「トゥランガリラ」はあの通りのロマンティックな、そしてまばゆいばかりの色彩感にあふれている曲ですから、ひきながら自分自身も高い空までかけ上がっていったり、また逆に地の底、海の底に引っ張りこまれるようになったり、まったく無限の空間、無限の深さを感じさせられます。現代作品を多くひくことから、メシアンの作品も数多くレパートリーに持つことになったわけです。
ジョリヴェの「ピアノ協奏曲」、シェーンベルクの「コンチェルト」、ミヨーの「協奏交響曲」、オネゲルの「コンチェルティーノ」なども度々ひいています。アルベニスの「イベリア」(全曲)とファリャの「スペインの庭の夜」の二曲は最も好きな作品です。
古典ではモーツァルトが特に好きです。今まで自分のリサイタルではモーツァルトとメシアンの組合わせを度々やっています。不思議にこの両作者のものがお互いに助け合うというか、自分ながら両方ともうまく、楽にひけるのです。日本にきて、はからずも同門の安川加寿子さんの演奏をきくことができたのは本当に幸いだと思いました。欲を言うと二人でモーツァルトの「二台のピアノのための協奏曲」をひいてみたかったのですが――。
よく考えてみるとメシアンのピアノ曲と私の縁はやっぱり特別なのかもしれません。と言うのは、レコードの吹き込みではメシアンの曲が比重が大きいし、その上、私のもらった「グランプリ」はいずれもメシアンの曲(※)なのですから。
※
幼な子イエスにそそぐ二十のまざなし
神の降臨のための3つの小典礼
トゥーランガリラ交響曲
メシアンの初来日については情報をここに追加していきます。