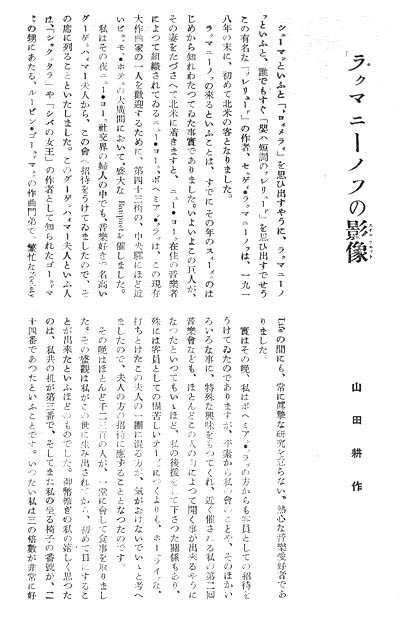アルス社刊『詩と音楽』1923(大正12)年8月号に32歳の山田耕筰(まだ「耕作」)がニューヨークでセルゲイ・ラフマニノフ(Sergei Rachmaninov, 1873-1943)に会ったときの様子が掲載されています。

↑ 北原白秋と山田耕筰の名コンビが主幹。
以下、全文です。古い仮名遣い等は変えました。【 】内は生意気にも自分が口を挟みました。
-----------------------
『ラフマニノフの影像(シルエット)』 山田耕作
シューマンというと「トロイメライ」を思い出すように、ラフマニノフというと、誰でもすぐ「嬰ハ短調のプレリュード」を思い出すでしょう。この有名な「プレリュード」の作者、セルゲイ・ラフマニノフは、1918年の末に、初めて北米の客となりました。
ラフマニノフの来るということは、すでにその年のシーズンのはじめから知れわたっていた事実でありました。いよいよこの巨人が、その妻をたずさえて北米に着きますと、ニューヨーク在住の音楽者によって組織されているニューヨーク、ボヘミアン・クラブは、この現存大作曲家の一人を歓迎するために、第四十三街の、中央駅に程近いビルトモア・ホテルの大広間において、盛大なbanquet【宴会】を催しました。
私はその夜ニューヨーク社交界の婦人の中でも、音楽好きで名高いグッゲンハイマー夫人から、この会へ招待をうけていましたので、その席に列なることといたしました。このグッゲンハイマー夫人という人は、「シャクンタラ」や「シバの女王」の作者として知れらたゴルトマルク【Karl Goldmark, 1830-1915】の甥にあたる、ルービン・ゴルトマルクの作曲門弟で、繁忙なSociety Lifeの間にも、常に真摯な研究を怠らない、熱心な音楽愛好者でありました。
実はその晩、私はボヘミアンクラブの方からも客員としての招待をうけていたのでありますが、平素から私の会のことや、そのほかいろいろな事に、特殊な興味をもってくれ、近く催される私の第二回音楽会なども、ほとんどこの人の力によって開く事が出来るようになったといってもいいほど、私の後援をして下さった関係もあり、殊には客員としての固苦しいテーブルにつくよりも、ホームライクな、打ちとけたこの夫人の一団に混ざる方が、気がおけないでいいと考えましたので、夫人の方の招待に応ずることになったのです。
その晩はほとんど千二三百の人が、一堂に会して食事を取りました。その盛観は私がこの世に生み出されてから、初めて目にすることが出来たというほどのものでした。御幣かつぎの私の嬉しく思ったのは、私共の机が第三番で、そしてまた私の坐る椅子の番号が、二十四番であったということです。いったい私は三の倍数が非常に好きで、とりわけ二十四は、数中の数として平素から最も喜んでいる数なのでした。こうした廻り合わせは何となく、その会が私にとって心地のよいものであるということを予想させました。
会はたしか午後七時ごろから始まったと覚えています。定刻の少し前、私どもがホテルの大玄関を入ろうとすると、そこにはクナイズラー・フォーテットの長として、日本の読者の間にも耳新しくないクナイズラーが、ラフマニノフ夫妻の間に立って来会を迎え、その内適当な人を択んでは、一々ラフマニノフに紹介していました。このクナイズラーといういう人は、その当時ボヘミアン・クラブの会長をつとめていたのでした。
私はその年の三月にニューヨークに到着してから間もなく、ボヘミアンクラブの客として招かれ、その後もいろいろな機会において、クナイズラーと会見したこともあって、見知り越しの間でしたので、私もまたクナイズラーの紹介で、ここでラフマニノフと握手を交わすことが出来ました。
一寸打ち出た所、ラフマニノフの風貌はどことなく印度の高僧を偲ばせるような趣があります。頭は短く一分刈りにし、やや猫背になった肩の上に、筋のあらわれた頭をのせ、その頸の上には、秀でた額と、すき透った鼻と、聡明な顎が、厳粛に、又慎ましやかに坐っています。身の丈は恐らく六尺【182センチくらい】を越えているでしょう。私は何だか洋装した魁偉な禅僧に握手されたような気持で、その静かな相貌を下から見上げました。しかしその時は何分大勢の人がおりましたので、ただ通り一遍の挨拶をして、そのまま会場である大広間に入りました。
大広間に入って見ると、中央には主賓のつくべき大テーブルがしつらえてあって、その大テーブルも、またその周囲に百何十となく置き列べられて円卓も、色とりどりに美しい花をもって、目も眩いばかりに飾られていました。部屋の左右にあるバルコニーにも、円卓が並べられて、既に着席したたくさんの人が、後から来る私どもを見下しておりました。
定刻になりますと、給仕長はすべての人が着席したのを見すまして、各卓の傍に侍してその命をまっておる二百に近いボーイに、一つのサインを与えました。これでいよいよ破天荒のTable Manoeuvreは、こんな壮観を見た事のない私の眼前に開始されたのです。
お話が少し飛びますが、私はどうも、外国の宴会の方法というものが、不思議に思われてなりません。大勢が一堂に会して、まだお互に口も利き合わさないうちから、いきなり腹へものをつめこませ、やがて御馳走で一ぱいになった腹を、どうして空かせようかと思い出した頃に、いわゆるデザート・コースというものに入って、はじめて挨拶があり、演説があるというわけです。もっとも大勢の人が集まる宴席のことですから、こうでもしておかないと、空腹のあまり意見の衝突ががくさん出来はしないかという心配から、こうした来賓瞞着な一方法が講ぜられているのではあるまいかとも思います。
その夜は私のテーブルは、ちょうど主賓のラフマニノフとは、三尺【90センチ位】と隣れていない距離に坐を占めることになりました。そして私の坐している席からは、ラフマニノフの右の半面が、はっきり見えていたのですが、ほとんどこの会が何の会であるかということを忘れてしまわなければならないほど、私どもはいそがしくフォークを皿から口へと運んでいなければなりませんでした。もちろんコースの合間合間には、私どものテーブルを囲んでいる人々と、短い会話を交わしもしましたが、それも千何百の大群衆が各テーブルで遠慮もなくしゃべり立てる話声の四辺の壁にこだまして作り出す大音響の中に葬り去られて、むしろ口を利くのが憶怯なほどに感じられましたので、私はともすると口を噤んで、しきりにラフマニノフの横顔を研究していました。
ラフマニノフは会長クナイズラーの右に坐り、夫人は会長の左に着席していました。ほかにそのテーブルにはメトロポリタン歌劇場の唄い手(といってカルーソーはその夜は見えませんでした)や、指揮者のボダンツキー【Artur Bodanzky, 1877-1939】、ジンバリストの夫人であるアルマ・グルック【Alma Gluck, 1884-1938】、ハイフェッツ【Yasha Heifetz, 1901-1987】(エルマンとジンバリストは見えませんでした、)ラスィアンシンフォニーの指揮者アルチューラ【誰?調べます】、その他が着席していました。そしてラフマニノフは、あだかもその右隣に坐っていたアルマ・グルックと、何かしらしきりに談笑しているように見うけられました。
やがてコースの歩みが追々に進んで、デザート・コースになりますと会長の代理として、ニューヨークの在住音楽家の中でも、令辞にたくみな、美しい言葉の持主として知られるクラブの副会長、ルービン・ゴルトマルクが立って、極めて味のある歓迎の辞を述べました。つづいてラフマニノフの、坊主頭の骨ばった身体が室の中央に現われものの二分間ばかりも、一同の緊張した沈黙の唯中に、見ゆるぎもせずにじっとつっ立っていました。
私は巨人のラフマニノフが、どんな言葉でこの大会衆に挨拶するかと思って、息もこらさず、その横顔を見つめていましたが、ラフマニノフは立ちは立ったものの、実際のところ、如何なる言葉をもって歓迎の辞に答えていいかが判らないもののように、しばらくはその唇を開こうともしませんでした。しかし作曲者としてばかりでなく、指揮者としても、またピアニストとしても、非常にすぐれた楽人として、故国はもちろんのこと、欧州の各地に、数知れぬ演奏会の度を重ねて来た人だけに、こうした場合でも、決してその内兜を見すかされるようなことはしませんでした。やがて固く閉じられた血の気のうすい唇を開いて、静かにしかし明瞭に
"Ladies and Gentlemen!"
と一座の人によびかけました。挨拶の前口上は型通りの立派なものでしたが、しかし私どもはその発音によって、ラフマニノフが英語には不慣れであるということを、逸早く看破することが出来ました。
するとラフマニノフは、一旦閉じた唇を再び開いて、冷い頬に軽い微笑をたたえ、伏目勝ちの目を重く上げながら
"I speak no English. I thank you."
とぎこちなくいいながら、丁寧なお辞儀をしました。広い会場の隅には、この僅かな言葉が、十分に行き届かない所もあったようですが、ラフマニノフの声が消えるや否や、私どものテーブルをはじめ中央の円卓から、すさまじい拍手が起り、それからちょうど池の面に石を投じた時のように、たちまち大きい渦を描いて隅々にまで押しひろがり、四辺の壁にこだまして、再び中央に向って反響の渦を描きながら、物凄いまでにひびきわたりました。この宴会のような拍手の間には、無遠慮なアメリカ人の常として、騒々しい笑声をさえまじえるので、ものの二、三分というものは、大変な騒ぎでありました。壮大な広間を埋めている千余の来会者は、なおその上にもその憧憬の的であるこの巨人の演じたComic SceneのEncoreをさえ要求するのでした。
そのうちに広間の一方に設えられた舞台の幕が静かに開かれて余興のオペラが始まりました。そのオペラの幕間のことです。私とはほとんど背中合せに坐っていたクナイズラーが、急に私の方に向き直って、
「あなたはたしかドイツ語をお話しでしたね。」
とたずねました。そしてほとんど私の答えるいとまをも考えないで
「この遠来の客に対して、遠い東の楽人の一人として、あなたから何かドイツ語で祝詞をのべていただきたい。さすればラフマニノフ氏も非常にお喜びだろう。」
というのです。
私はいったい自分の妙な心持から、偉大とか、巨人とかいわれる人を訪問したりすることを、あまり好んではいなかったのですが、さりとて偶然こうした機会を与えられた場合には、別段それを避けようともしませんでしたので、その夜も快くその言をうけ入れて改めてその席でラフマニノフを紹介してもらいました。実の所、この衆人稠座の中で、こうしたことをするのは、何となく面はゆい心持がしないではありませんでしたが、私は静かに自席を離れ、会長クナイズラーの椅子を譲ってもらって、ラフマニノフの隣に坐し、約五分間に亘って、ドイツ語でいろいろな会話を交えました。
話はもちろん日本の楽界のことにも及びました。
「機会があるならば自分も是非美しい夢のような貴方のお国をお訪ねしたいものです。」とラフマニノフは申しました。私はそうした言葉にある喜びを感じていながらも、現在の私どもの国のありさまを思い浮べて、苦笑をもしながら
「もう日本は夢の国ではありません。余りに現実化してしまいました。もしあなたが夢の国として日本におこしになったならば、おそらく失望なさることでしょう。しかしもし貴方が日本へおこし下さるならば、私どもは如何ばかり幸福に感じ、また光栄に思うかも知れません。もし私にその力が与えられたならば、すぐにも貴方を日本へお招きしたいものです。」
などと打ち語らいました。こうして手短かにラフマニノフとの会談を済ませ、社交界の礼儀として、その隣席にいたグルックにも挨拶し、またその二つ向うの椅子に席をしめていた可愛らしい美少年のハイフェッツとも握手を交して、自分の席に帰りました。こうした間にも、そのホールは会衆のくゆらす煙草の煙と、リキュールの盃の相ふれ合う響とに、静まる間とてはありませんでした。
余興が終ると副会長のゴルトマルクが、再び自席に立ち上がって、
「ラフマニノフ氏は、来会の皆さんに何か一言御挨拶したいのですが、何分英語の力が足りませんので、十分自分の意のある所をお伝えすることが出来ませんのは、残念至極なこと故、その代りに何か一曲ピアノを弾奏して、御挨拶に代えたいと申出られました。」
と、ラフマニノフ氏の意を、来会者一同に伝えました。前の挨拶の時にもまして、すざまじい拍手の音が、堂をゆるがして起ったことは、特に申すまでもありません、そしてラフマニノフは、このすさまじい拍手の中に、やおら立って壇上に上り、静かに美しい音楽を奏ではじめました。
私はその曲が何であったかを覚えていません。私の近くにいた人達も、また私と同じように、その曲の名をいいあてることが出来ませんでした。多分それはその夜の印象を、そのまま曲にした即興的な作品であったろうと私は考えます。とにかく、それは極めて近代的な色彩のある、Poeme風な音楽でありました。
その曲が終ると、再び起る喝采の渦巻の中に、ラフマニノフはまた立ち上って
"Mrs. Rachmaninoff will help me."
といいながら、呆気にとられた来会者の私語のうちに、その夫人を壇上にさしまねいて、何かの小曲を連弾しました。この連弾はもちろん別に問題にすべきほどのものではありませんが、The Land of "Ladies first"のアメリカ人に、この軽い機智がどんな歓びをもって迎えられたかということは、ここに改めて申し述べるまでもないと思います。私どもはこうした事実によって、単に優れた技倆をもった楽人であるばかりでなく、こうしたSocietyの微妙な心理を洞察し得る鋭敏な頭脳の持ち主でもあるラフマニノフを見ることが出来ました。
やがて会はまるで王者を迎える時のような壮大さの中に、終りを告げました。私は来合わせていた近しい人たちと別れを告げてCentral Parkの西側にある、私の寓居へ帰りました。その道すがらも私はたった今目前にした盛大な光景を頭の中に描き出し、アメリカ人と音楽というような問題について、それからそれへと考え耽らずにはいられませんでした。公園の池の辺りには日本のあづまやにも似た瀟洒な亭があります。夜も更けていたこととて、眩いアーク燈の光りが、静かな池の水の面に、一入あざやかにその亭の姿をさかさにうつし出していました。私は何故かしら急に日本が恋しくなって来ました。そして日本の楽界と日本の楽人と、そして音楽などの問題について、しみじみ考えずにはいられませんでした。
その次に私はラフマニノフと会ったのは、たしかその翌年の二月初旬だったと覚えています。私はその日、前に述べたグッゲンハイマー夫人の本家へ招かれていましたので、グッゲンハイマー夫人の自動車の迎えを受け、セントラル・パークに面した第五街の、宏壮な邸宅に足をふみ入れました。その日の客はラフマニノフ夫妻、クライスラー【Fritz Kreisler, 1875-1962】夫妻、ニューヨーク・フィルハーモニー・オーケストラの指揮者ストランスキー【Josef Stransky, 1872-1936】夫妻、クラウディア・ムツィオ【Claudia Muzio, 1889-1936 ソプラノ歌手】、グッゲンハイマー夫人、それと私で、その家の主人の老母や、主婦であるグッゲンハイマー氏の兄嫁、それにニューヨーク社交界のプリンセスとして時めいていたその家の娘などと共に一つにテーブルを囲んで坐りました。こうした小人数の、Privateな会合のこととて、打ちくつろいだ気分を与えましたが、殊に私は来会者の総てと顔馴染であったためか、何となくhomeな感じに浸ることが出来ました。
料理はべつに山海の珍味を集めたというほどではありませんでしたが、気の利いた、面白い取合せのものでありました。私の隣にいた、食道楽のストランスキー夫人などはコースのかわるごとに、巧みな賛辞を浴せかけ、時には私たちには、むしろ滑稽に聞えるほどの舌づつみを打ち鳴らしたりする程でした。小人数の会のこととて、一人一人の話声が、朗らかに響き渡ります。大理石の円柱を囲んで置き並べられた銅像や石像や、珍奇な柱物の間に、銀の食器をささげて木像のようにつっ立っている給仕人も客人達の談笑の声につれて、時々抑え切れない微笑のかげを、その口辺にただよわせていました。
こうして大食卓では、毛色の変った人間が一人いると、一同の注意はともするとこの一人にさし向けられるのが常ですが、この日も食卓についたすべての人々の好奇心は、ほとんどことごとく私一人に集注せられていました。そして私は
「日本人は何を食っているか。」とか
「日本人が竹と紙で作った家に住んでいるというのは全く事実ですか。」
とか、いろいろな質問の矢面に立たねばなりませんでした。その家の娘などは、紙と竹とで家が出来るということを、まるで奇蹟のように考えているらしく、好奇の眼を光らしながら、次から次へ、奇問を連発するのでした。私がこうした絶え間ない質問に辟易しているのを見てとったグッゲンハイマー夫人は、ふだん私から聞き知っていたことを受け売りして、如何に日本通であるかを誇り顔するようにその質問に答えて、私をこの窮境から救ってくれました。
食事が済むと、私たちは客室に移って、そこで又新たに談笑の花をさかせました。ラフマニノフとクライスラーとは、二人でしきりに日本の音楽、ことに音階について話していましたが、二人とも日本の音楽に関して、予想外に深い研究をつんでいるのに、私は驚かされてしまいました。中にもクライスラーは特に熱心で、傍の私を顧みて
「日本音楽には四分音があるということですが、それは事実ですか、そしてまたもしあるとすれば、それは独立して存在し得るものか、または関係的に存在するものなのでしょうか。」
などと質問するのでした。ことに私を驚かせたのは、普通の人には聴き分けることが出来ないといわれているこの四分音を、二人がはっきりと口にすさんで歌い出したことです。そして二人はそれをピアノの音と比べて見ては、しきりにピアノの不完全なことをかこっていました。
「ピアノは西洋音楽の真髄を過るものです。私どもは演奏に便利だという点から、折角の興味をこの音楽につないでいますけれどほんとうに清純なる音を望むならば、むしろピアノから離れた方がよくはないでしょうか。」
とラフマニノフはいっていました。【ラフマニノフが本当にこんなことを言ったのか?】
やがてラフマニノフとクライスラーの二人は、私の作品を何か聞きたいと、熱心に懇望しはじめました。二人とも私の尊敬する人でもあり、何かしら怖ろしいような気もしましたので、実は私はしりごみしていたのですが、傍からグッゲンハイマー夫人が
「あなたのお勉強にもなることですから、早速楽譜をもって来て、ひいてごらんになったら如何です。」
とすすめますので、私はいそいそと自動車にのって、公園を一またぎすれば到達することの出来るほど、間近い所にある私の家に帰り、それ相当の楽譜を運び出して来て、この謹厳な二人の前で演奏しました。私がここで二人の口から傾聴すべき懇切な批評と、尊い新智識とを受け得たことはいうまでもありません。二人の言葉が、日本音階の取扱い方や、対位法の使い方、楽想などについて常に私が考えていたことを、裏書してくれた事なども、私を喜ばさずには置きませんでした。私は二人の所望をうけた時に、むしろ最初から子供らしくその好意を容れて、教えを乞う気持になればよかったものを、徒らに逡巡し、躊躇していたことを後悔した位でした。
ラフマニノフはその晩もごく僅かの英語を語っただけで、主にドイツ語とフランス語でいろいろな人に応対していました。その晩ことに近しく、そして長時間に亘って、いろいろな問題について語り交わしたことによって、私はラフマニノフの美点を、より多く知ることが出来ました。
プロコフィエフが「馬鹿」と罵ったラフマニノフは、モダーニストの話が出た時、プロコフィエフの名をあげて、Talented Pianistといい、その作品についても、むしろ同情のある言葉を発していました。また恩師であったタネーエフは、浅からぬ恩を感じているらしく、口を極めてタネーエフを賞賛していました。しかし過激派ロシアの問題について、いろいろな人からいろいろな質問を発せられた時には、ラフマニノフは
「過去の追憶を辿るのは苦しい。」
と一言したばかりで、口を緘して何事をも語りませんでした。
その晩から十日ばかりたったある午後、ストランスキーの率いるニューヨーク・フィルハーモニーのプログラムに、ラフマニノフの音詩「死の島」が加えられました。ラフマニノフも私も、その日はグッゲンハイマー夫人のボックスに招かれていましたので、幸いにも私は同じボックスの中で、しかもラフマニノフの右隣に坐して、この音詩を聞くことが出来ました。
「死の島」はいうまでもなく、ベックリンの有名な絵画によった音詩です。ベックリンの原画は複製や写真版によって、すべて我国にも知られていると思います。暗い水面に漂う如く浮んでいる小舟が一艘、その中には何方を向いているとも知れない一人の男が、影のように淋しくつっ立っていて、力なく梶を取っています。よるべなき小舟の行く先は、この死の島のほかにはないのでしょう。
こういえば「死の島」は、非常に神秘的な絵のようですが、ベックリンの彩管は、こうした神秘的な予想を、名残りなくカンヴァスの上に現わすべくあまりに非象徴的でした。彼の描いた画面には、ただ裸の哲学と、むき出しにされた思想とが現われているだけで、死の島は全く架空的な存在として、いわゆる絵虚事としてか、私たちの目に映って来ません。
けれどもラフマニノフは、この点で明らかにベックリン以上の芸術家でありました。彼は死の島の哲学と思想とを、自分の心の中にとざかし、あらためて自分自身の死の島として、それを聞くものの心耳に伝えています。死の島に対する怖れと憧れ、死の島の淋しさと悩ましさ、生に即した死というものの諸相が、もっとも多面的にあらわされています。しかしそれは決してベックリンにおけるような、架空的な性質のものとしてではなく、現実的な存在として、私どもの心に如実にその物凄い影を落すのです。そしてこうした「死の島」の姿を写し出すラフマニノフの楽風は、何等の奇を衒わない、極めて健全なもので、しかもそこに流れ出ているものの細かさと、凄さと、そして力とは、聞くものの胸に迫るに十分でありました。
私はこの演奏に非常な興味を覚えながらも一方作曲者であるラフマニノフが、他人の手による自作の演奏を、如何に感じているかを知りたい気持を抑えることが出来ませんでした。私はラフマニノフの感じと、私自身との感じとを比較することによって、そこの何ものかを学び得たいという欲望から、しきりにラフマニノフの態度に注意を払っていました。
ラフマニノフは、その長いすねの上に左ひじをつき、その尖ったくびを軽く左の手で支えながら、静かに演奏を聴いていました。私はその姿から、その顔面の筋肉は、終始ほとんど無表情で、演奏のすんでからも、批評がましい言葉を一言も洩そうとしないのを、私はむしろ奥床しく思いました。
私の見たところではラフマニノフの血管の中には、西洋というよりも、むしろ東洋の血が多重に流れているのではないかと思われるほど、それほど東洋的なあらわれがあるようです。彼はけっしてその感情を裸のままむき出しに現わす人ではありません。それを自分の内にとかし、うちにとかしたものを更に節度を保って静かに、小声に話し出す人であると私は感じました。その表情が音楽者というよりは、聡明な学者らしく見るもの私には何となくなつかしさを強めるもののように思われました。
一面においてラフマニノフは、かの大歓迎会上の挿話によっても知られる如く、却々Wittyな人であります。グッゲンハイマー家の宴でも、よくその真面目な固い頸をふるわせながら、機智に富んだ警句を吐いて一同を笑わせたものでした。しかしいまだに私の脳裡を去りやらぬラフマニノフの印象は、あの演奏会の日の、ゆるがない山のような「考える人」としてのその姿です。
-----------------------
。。。ラフマニノフをガン見する山田耕筰さんの気持ち、よくわかります!
情報を追加していきます。