
ブログを見たら、金魚をクリックしてね。
今日は、いよいよ2011年最後の日。「うーん、いろんなことがあったけど…」とミモロも、感慨深げです。
さて、大晦日と言えば、「年越しそば」。美味しいお蕎麦が食べたいとミモロは、大晦日の前に、ちゃっかり年越しそばを食べに行っていたのです。向かったのは、平安神宮の北側、聖護院のそばにある和風情緒あふれる建物の「河道屋養老」。


築130年という木造の建物は、白川の農家を移築したもの。日本情緒あふれるなかで、ゆっくりとお蕎麦が味わえるお店です。
お座敷に通されたミモロ。


「わー落ち着いた雰囲気が素敵ー!」
さっそくお品書きを見て、年越しそばを選びます。

鴨南蛮、天そば、山かけそば、ざるそば、にしんそばなど、美味しそうな品々がずらり。
「わー迷っちゃうー」と、いつものミモロが始まりました。
ふと隣りの席を見ると…。
 2
22人連れの旅行者が、何やら美味しそうに食べています。

「あれは、もしかして、名物の『養老鍋』?」
生麩、生湯葉、京野菜、飛龍頭、地鶏、エビなど、京の食材が、ふんだんに味わえ、〆には、蕎麦ときしめんが楽しめるお鍋です。
「どうしよう…お鍋も食べたいけど、今日はひとりで来ちゃったしー」
と、ちょっと残念そうなミモロですが、「京都と言えば、にしんそば…今年の締めくくりは、これにしよう!」と、にしんそばを注文します。
しばらくして、ミモロの前に運ばれたお蕎麦。「どうぞ、ごゆっくり…」

「あれ?なんにものってないー。どうしたんだろ?にしん忘れちゃったのかな?」と、何ものっていないお蕎麦を見つめ、ちょっぴり心配そう。

実は、お蕎麦の下に大きなにしんが隠れていました。

「ふーよかったー」とミモロが食べ始めようとしたとき、「ちょっといいですか?」と、隣りの観光客の方が、ミモロにカメラを…。

「かわいいので、ちょっと1枚…」と。
さて、たっぷりとした身のにしんをほぐしながら、お蕎麦を頂きます。
「お汁の味が、すごく美味しい!にしんもいいお味…お蕎麦との素晴らしいハーモニー」とミモロは、お汁を飲み干すほど、気に入ったよう。
ちなみに「にしんそば」は900円。
食べ終わったミモロは、お庭を拝見。

楓の紅葉が、秋は、素晴らしいお庭です。
年末早々に年越しそばを食べたミモロ。「わーもう1年終わっちゃったー」とすっかり年越し気分に。
「河道屋養老」では、12月30日、31日は、年越しそばの販売のみ。お食事はできません。あしからず…

*「河道屋養老」京都市左京区聖護院御殿西門前 電話075-771-7531 11:00~19:00(入店)火曜休 予約をおすすめ。名物「養老鍋」3500円~。ほかいろいろ。交通/京阪神宮丸太町駅徒歩3分
さて、初詣は、ミモロの住む岡崎エリアでは、交通規制が引かれます。
「えーおうちから出られなくなっちゃうの?」と心配そうなミモロ。
3日まで、車の通行が規制されます。
八坂神社では、「おけら参り」が大晦日に行われるため、境内の参拝経路も決められています。


「わー今夜は、どんなことが起きるんだろ?」京都での初めてのお正月に、ワクワクするミモロです。

「みなさま、今年は、お世話になりました。いつもミモロを見守ってくださり、本当にうれしいです。どうもありがとうございます。新年が、みなさまにとって佳き年でありますように…これからも、ミモロをよろしく…会えて、本当にうれしいでーす!」ミモロ













 「ここだよー」とミモロは、暖簾から手招きします。
「ここだよー」とミモロは、暖簾から手招きします。














 なんか由緒と歴史を感じさせるお釜です。
なんか由緒と歴史を感じさせるお釜です。










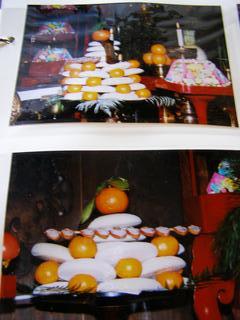


























 「先生、どうもありがとうございました!」もう、ミモロは嬉しくてたまりません。
「先生、どうもありがとうございました!」もう、ミモロは嬉しくてたまりません。

















