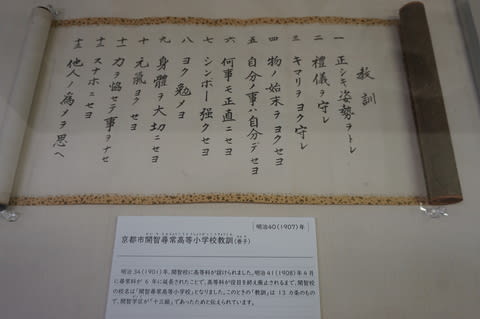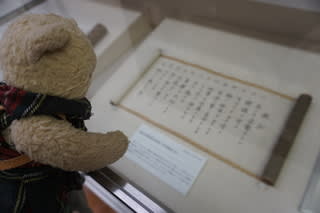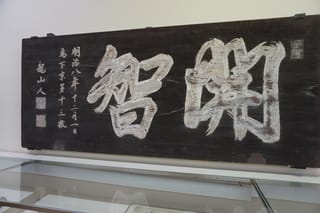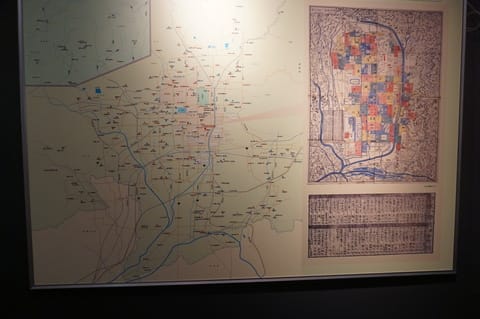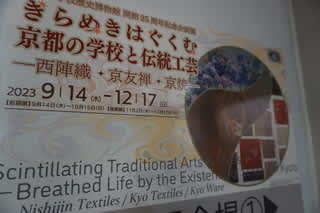「うわ~すご~い!」と思わず大きな声をあげながら、イチョウの下を走り回るミモロ。

木の下には、落葉が、黄金色の絨毯が敷かれたように広がっています。
ミモロがいるのは、京都の町の中心部にある「京都御苑」。周囲約4キロという広大な敷地には、「京都御所」「京都仙洞御所」などの歴史的建造物や京都の工芸の粋を集めた「京都迎賓館」があり、多くの観光客が訪れる京都観光の名所です。
下鴨エリアに住むミモロは、よく自転車でやってきます。「ここは、自然がすごく豊かなんだよ~」と。

敷地内にある建造物は、多くが宮内庁の管轄。また、それ以外の広~い敷地は、環境省が管理しています。
多くの門がある「京都御苑」…ミモロは、東側の「梨木神社」そばの「清和院御門」から自転車でやってきました。
「京都仙洞御所」の壁沿いに進むと…
「わ~見て~真っ赤だよ~」と声が…

北側の草が茂る場所に大きな楓が…

まるで真っ赤な傘を広げたように、枝を横に伸ばしています。
自転車を止めて、草の上を歩き回るミモロです。

広い「京都御苑」は、どこの門から入るかで、歩くコースが異なるのです。
西側は、地下鉄「烏丸線」の「丸太町駅」と「今出川駅」が徒歩3分ほどにあり、交通の便利さ、および駐車場、お休み処などがあり、多くの観光客が訪れ、「京都御所」の周囲や、「京都仙洞御所」の西と南側を散策します。
そこにも紅葉した木々が多く、散策には、気持ちのいいエリアです。
でも…ミモロが行くのは、観光客が少ない場所…そう、「京都御苑」の東エリアです。
「うわ~見て~すごい!」

トコトコ歩いた先に見えて来たのは、大きなイチョウ。
まさにたわわに黄金色の枝を垂らしています。

「京都御苑」の中には、イチョウの大木が数本あり、これもその1本。
本当に、楓もイチョウもノビノビと枝を伸ばしているのは、ここならではかも…
京都の神社仏閣などの境内や日本庭園にある木々とは、趣が異なり、「特別京都らしくない…」と観光客はいうかもしれませんが、その樹齢からして、京都の激動の歴史を見つめてきた大木です。
環境省が管轄するスペースで、苑内の動植物は、大切に保護、管理されて、さすがその管理状態は見事です。
「そうだよね~神社やお寺は、自分で木を管理しなくちゃいけないもの…結構お金もかかるんだって~」と現実的な視点。
観光客を呼び込む紅葉…その盛りを過ぎると、落葉の処理に多くの人が追われます。昔は、焚火など、敷地内で落ち葉の処理ができましたが、今は、焚火は禁止。そのため、多くの落ち葉は、燃やすゴミとして収集処理されます。剪定した木の枝は、燃料チップなどにリサイクルされるため、きちんとまとめたものなら、回収してもらえます。
秋の観光シーズンが終わると、年末年始に向けて、落ち葉のお掃除が各所で盛んに…。京都市の街路樹や公園などの落葉は、落ち葉処理などを手掛ける外部業者に依頼し、結構費用が掛かるそう。
そんな落葉を腐葉土として有効利用する動きなどもありますが、なかなか進んでいません。
観光客にとって、魅力的な紅葉…でも、その蔭で京都市民は、それを維持することに尽力していることも心に留めて欲しいこと。
ミモロも、神社やお寺の美化活動に参加して、京都の魅力を守ろうとしています。
「でも、やっぱりいいよね~ここの紅葉…」と、しばし枝の下で過ごすミモロ。やはりその美しさに言葉はいりません。

この日、ミモロは、イチョウと同じ色の黄色のマフラーでやってきました。なんか保護色みたい…
「京都御苑」は、24時間入れます。夜は、ライトアップなどはされていないので、真っ暗…。
でも、早朝から日没まで無料で紅葉が楽しめる場所です。

「本当に今年、こんなにキレイに紅葉見えると思わなかった~」というミモロ。
遅い紅葉…そのおかげで、イチョウと楓が一度に盛りを迎えています。

さぁ、もっと他の場所にも行ってみましょう~
<ブログを見たら 金魚鉢をクリックしてね 応援よろしく!ミモロより
 人気ブログランキング
人気ブログランキングミモロの通販ショップ「ミモロショップ」はこちら
「ミモロの京都暮らしカレンダー2024」もうすぐ、完売しそう!ご注文はお早く~

ミモロへのお問い合わせ・ご要望は、mimoro1888@gmail.comまで


















































 この日の天気予報は、雨のち晴れなのですが、ここは山里…天候は急に変わることも多いのです。
この日の天気予報は、雨のち晴れなのですが、ここは山里…天候は急に変わることも多いのです。