鞍馬寺と由岐神社の参拝を終えたミモロとお友達は、門前通を歩きます。

「なんかいい匂いがする…」ミモロの鼻がピクピクと。
この通りには、鞍馬名物の「木の芽煮」を売るお店が並んでいます。
そのひとつ「岸本柳蔵老舗」は、農林大臣賞を受賞したお店です。
店先には、自家製の木の芽煮などがずらりと並び、どれも香ばしいお醤油の香りが、ミモロの鼻をくすぐっていたのです。


鞍馬名物の木の芽煮は、平安時代に、ここで修業していた牛若丸が食べていた山椒や山菜の塩漬けから発達したとも言われる味。牛若丸が食べたいたかどうかは、別としても、この地域では、古くから周辺の山々で採れる山菜で塩漬けをつくり、保存食として常備していたそう。明治時代になり、鞍馬寺などへの参拝客の増加で、お土産物として販売するようになったとか。
「店の前の通りは、『若狭街道』といって、京都と福井を結ぶ大切な街道です。昔は、若狭から、鯖や昆布を背負った人が、大勢通ったんですよ」とお店の方。

「わーすごく遠い感じ…」とミモロ。「でも毎年マラソン大会があって、早い人で半日くらいで到着してますよー」と。
若狭街道は、京都の出町から福井の小浜までの約76キロ。昔は、日本海で獲れた鯖に塩をして、一昼夜かけて京都に町に運ぶと、ほどよい塩加減になっていたとか。鯖をたくさん運んだので、鯖街道とも呼ばれる街道のひとつです。
さて、鯖と一緒に運ばれたのが、昆布。この昆布を使い美味しい味になったのが、鞍馬名物、木の芽煮です。細かく刻んだ昆布と山椒などを、じっくりと時間をかけて醤油や砂糖などで煮込んだ木の芽煮は、ごはんが進む味。
木の芽煮以外にも、山椒の実だけでできたピリッと辛い実山椒、ちりめん雑魚を使ったちりめん山椒など、種類もいろいろ。


「お土産にピッタリだねぇー」と、店に並ぶ品々を見て回ります。


「どれも美味しそうで迷っちゃうー」と、なかなか決められません。
「そうだ、まずは、お昼を食べてから、ゆっくり考えようー」と、店の一角にあるお座敷に。

ここでは、そばやうどん、ちらし鮨などが食べられます。

「えーっとミモロは、キツネそばにする」と、大好物キツネそばをさっそく注文。お友達は、天婦羅そばをたのみました。
しばらくして、運ばれたおそばを前に、今にもよだれが…


「いただきまーす!エビとお揚げとちょっと交換しない?」と、お友達の海老天も気になるミモロです。
さて、ランチを食べ終わったミモロは、再び店内へ。今度は、お土産物に興味津々。
 「けん玉だー。ミモロ、ちょっと得意なんだけど…」
「けん玉だー。ミモロ、ちょっと得意なんだけど…」また鞍馬山とかかれた赤い団扇も気になるよう。

「ワオー、ワシは、鞍馬の天狗じゃー」と、
 天狗のお面も付けてみました。
天狗のお面も付けてみました。お店が遊んじゃダメでしょ…。「ハーイ…やっぱり木の芽煮にするー」と、ミモロは、やっと決めたよう。
*「岸本柳蔵老舗」京都市左京区鞍馬本町232 電話075-741-2030 9:00頃~17:00頃 無休
 人気ブログランキングへ
人気ブログランキングへブログを見たら、金魚をクリックしてね





























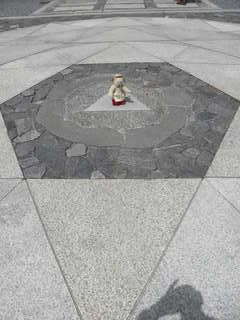
















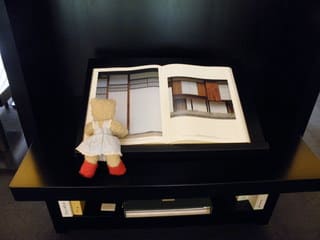

 「わー気持ちいいねぇー」とお庭を眺めるミモロです。
「わー気持ちいいねぇー」とお庭を眺めるミモロです。












