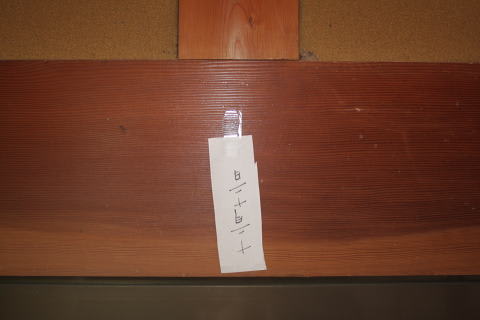かつて明日香村の下平田では旧暦11月1日に行われていた
亥の子の行事。
旧暦というから11月下旬から12月中旬辺りの時期は毎年変動する。
田んぼの稲刈りを終えたころだったが現在は12月15日。
早生稲になって収穫時期はおよそ一か月早くなってきたとイチゴ農家の男性は話す。
その田で収穫した新米の藁で作ったデンボを手にした子どもたちが各家を巡って地面に叩きつけ、収穫を祝う行事を亥の子と呼んでいる。
亥(猪)は多産系の動物で田んぼなどを荒らす。
困った亥ではあるが、その多産の動物は子孫繁栄の象徴でもある。
五穀豊穣の願いも込められているのだろう亥の子の行事は子供たちが主役。
農家の家を継ぐ子供が村内の子孫繁栄を願ってきた。
平田は下平田、上平田の旧村と新興住宅で新しくできた中平田、南平田の4地区だが、亥の子の行事をされているのは下平田だけである。
明日香村では他の地域でも亥の子行事があったという。
「おまえとこはまだそんなことをしているんや」と言われたそうだ。
粟原の地の名もでたが確認はできていない。
平田出身の幼稚園の先生からは「今でもしているの。懐かしいわ」と声をかけられたと亥の子の母親も話す。
デンボと呼ばれる藁棒で地面を叩くのは「田んぼを荒らすオンゴロ(もぐら)を呼び出すのだ」という人もいる。

新米藁で祝う亥の子行事の県内事例は多くない。
現在でも行われているのは高取町の
佐田と
森地区。
大淀町の
上比曽である。
地面を叩きながら囃子唄はどこか懐かしい響きである。
「いのこのばんに もちのつかんいえは はしのいえたてて うまのくそで かべぬって (県文化財調査報告書は「ぼぼのけでやねふいて」が付記されている) ここのよめさんいつもろた 3月3日のあさもろた いわしさんびき さけごごう しんまいわらでいぉうてやろ もひとつおまけにいぉってやろ」と唄う下平田の亥の子唄。
大淀町の上比曽ではドテンコと呼ばれる藁棒を叩いて「ここの嫁はんいつもろた 三月三日の朝もろた イワシ三尾、酒五合 新米ワラで祝いましょう」と新婚さんの家の前で囃子たてる。
高取町の森では各戸を巡って「イノコの晩に モチの搗かん家は 箸の家建てて 馬のクソで壁塗って ここの嫁はん何時貰う 三月三日の朝貰う 鰯三匹 酒五合 新米藁で祝ぉたろか ペッタンコ ペッタンコ もひとつおまけに ペッタンコ ペッタンコ」の台詞で囃子たてる。
佐田では「イノコの晩に モチせん家は 箸の家建てて 馬のクソで壁塗って ここの嫁はん何時貰う 正月三日の朝貰う 鰯三匹 酒五合 サイラ(サンマの開き)腸(わた)で 祝ぉてやれ ドンブラコ ドンブラコ もひとつ おまけに ドンブラコ」 「おー駒(こま)はん 寝ーてんのけ 起きてんのけ 寝てても 起きてても どんないわ 新米藁で 祝ぉてやれ ドンブラコ ドンブラコ もひとつ おまけに ドンブラコ」だ。
台詞に多少の違いはみられるものの、地域の繁栄の願う祝い唄の台詞は一様の決まりがあったのではないだろうか。
現在は廃れているが県内各地で行われていた亥の子の行事の数々。
高取町では薩摩や兵庫も行われていた。
かつて田原本町の
味間でも同じように「イノコの晩に モチの搗かん家は・・・云々」と囃子たてて新婚の家を巡ってデンボで叩いていた。
「イノコの晩に モチ搗かん家は おうちのねーさん起きなはるか 寝てはるか・・・」と思い出す農家の人もいた。
同町の笠形ではホウデンと呼ばれる藁ズトで地面を叩きながら「嫁はん起きてるけ 寝てるけ 新米わらでいぉたろけ」と囃していた事例が『田原本町の年中行事』に残されている。
同本には「亥の子の晩に 餅つかん家は せんちゃのどんぶりこおきみやん(人名)起きてるけ 寝てるけ 新米わらでいぉたろけ」の東井上地区。
「亥の子の晩に 餅つかん家は ・・・ ここのねえさん起きてるけ 寝てるけ」だった多地区などがある。
亥の子の行事は山間に近い辺りや盆地部で数多く見られた亥の子の行事。
いずれにしても、新婚の家を祝うのは子孫繁栄の願いが農耕行事の収穫儀礼と合わさったのではないだろうか。
明日香村ではかつて豊浦、檜隈、阪田、越、栢森では亥の子の日にイノコモチを食べる風習があったそうだ。
檜隈では「ノコの晩に モチつかん家は 箸で家建てて 馬のフンで壁塗って ボボの毛で屋根葺いて ここの嫁さんいつもろた 三月三日の朝もろた 鰯三匹 酒五合 シンマイワラでで祝うたろう もひとつおまけに 祝うたろうか」と囃子ながら地面をデンボで叩いていた。
栢森では氏神さんで山の神祭りを兼ねて新穀の甘酒を供える亥の子祭が行われていた。
東山ではモチを搗いて小豆のアンツケモチをつけて食べていたと『明日香村史』に書かれている。
また、『奈良県立民俗博物館だより』によれば次の地区で行われていたイノコ行事が紹介されている。
下畑ではホーレンと呼ばれる藁棒であった。
「いのこのばんに おもちつかんいえに はしでいえたてて かやでやねふき うしのくそで かべぬって ここのよめさん いつもらう 三月三日のあさもらう」と囃した。
当地では炊きこんだトーノイモをつぶして小豆餡を塗したボタモチを作って食べていた。
上平田ではデンゴロモチと呼ばれる藁棒であった。
「いのこのばんに もちつくいえは はしのいえたてて うまのけで やねふいて ここのよめさん いつもろた 三月三日のあさもろた いわし三匹 さけ五合 しんまいわらで いおてやる」と囃して新婚の家を中心に各戸を回っていた。
越でも同じくデンゴロモチと呼ばれる藁棒だった。
「いのこのばんに もちのつかんいえは はしのいえをたてて うまのくそで やねふいて しんまいわらでいおてやろ ここのよめさんいつもろた 三月三日のあさもろた いわし三匹 さけ五合 しんまいわらで いおてやろ」と囃して新婚の家を巡っていた。
当地ではイノコの日の食べ物はオハギだった。
コイモを炊いてレンゲで潰しアンコを塗したイノコノボタモチだった。
檜隈でもデンゴロモチと呼んでいた。
「いのこのばんに もちつかんいえは うまのくそで かべぬって ぼぼのけいで やねふいて ここのよめはんいつもろう 三月三日のあさもろう いわし三匹 さけ五合 しんまいわらで いおてやろ もひとつおまけに いおたるわ」と囃していた。
稲渕では若衆が嫁さんを貰った家にモチ搗きの杵を持っていって、ハマイコに餅を置いていく真似をした。
ハマイコは叩き割ったようだが、それはどんなものであったのか私は存知しない。
このようにイノコの行事にはイノコノモチ、アンツケモチ、ボタモチなどとよばれるモチがつきものであった。
「モチツクイエ」、或いは「モチツカンイエ」の台詞がそのモチを意味するのであろう。
東山では餅を搗かない家を「いのこのばんに もちつかんうちは・・・・」と囃した。
それはとんでもないケチであると揶揄されたという台詞であった。
また、天理市の藤井でもかつてイノコもあったそうだ。
男の子が村中を歩いて「いのこのばんに モチつかんいえは・・・しんまいワラでいおぅたれ ぺったんこ ぺったんこ」の囃子言葉があったことを六人衆が思い出された。
家の門口をワラ棒で叩いたあとは菓子をもらったそうだ。
昨年に取材した故郷の大阪南河内郡の
河南町では「いのこ いのこ いのこのばん(晩)に じゅうばこ(重箱) ひろて(拾うて) あけて(開けて)みれば きんのたま はいた(入った)ったー ちょこ(しっかりの意)いわい(祝い)ましょ ことし(今年)もほうねん(豊年)じゃ らいねん(来年)もほうねんじゃ おまけ」であった。
その昔はもっと卑猥な台詞があったことを聞いた。
重箱と言えば天理市の楢町にあった興願寺の亥の子の十夜。
「十夜の晩に 重箱ひろって あけてみれば ホコホコまんじゅう にぎってにれば 重兵衛さんの キンダマやった」と歌ったそうだ。
それは如来さんのご回在の日であって如来イノコと呼んでいたと『楢町史』に記されている。
重兵衛さんの台詞は消えた河南町であるが、重箱といい、キンノタマは同じだ。
遠く離れた大阪と天理に繋がる詞章があったことに驚きを隠せない。
下平田の亥の子の唄もそうであったが「今では口にすることができんようになった」と話す総代婦人。
亥の子の日にはボタモチを作って食べていたという。
(H23.12.15 EOS40D撮影)