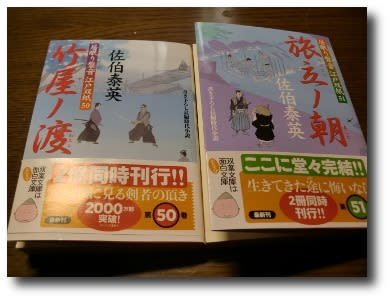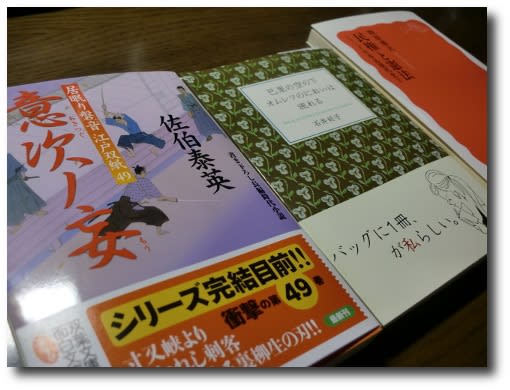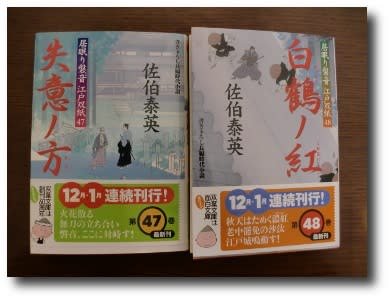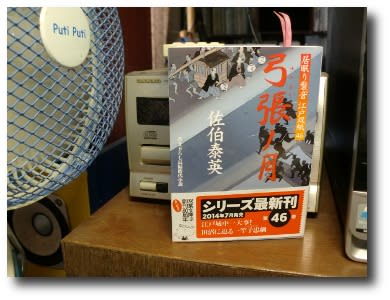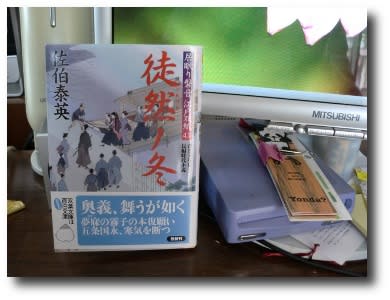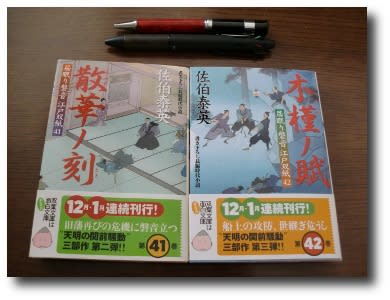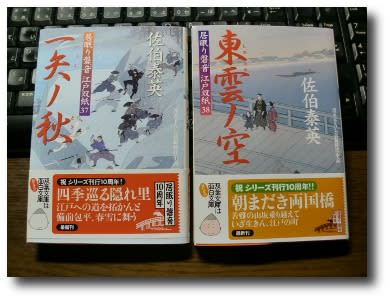豊後関前藩の三人の若者が互いに斬り合うはめに陥った『陽炎ノ辻』以来なんと50巻も読みつづけてきた佐伯泰英著『居眠り磐音江戸双紙』シリーズの最終巻、51冊目の『旅立ノ朝』を読みました。
○
第1話:「見舞い」。坂崎磐音の一家は、豊後関前藩に到着、父・坂崎正睦を見舞います。藩主が隠居を許さないため、正睦は国家老の席を辞することができません。しかし、正睦の病気療養の間に勢力を蓄えてきた中老の伊鶴儀登左衛門が藩政の実権を握ろうとしている、というのが本巻の状況のようです。
第2話:「思い出めぐり」。病床の正睦は、孫の空也が示す直心影流の法定四本之形打太刀を見て生気をよみがえらせます。一方、中老の伊鶴儀登左衛門は、藩主の側室お玉の子の実継を擁して藩の実権の乗っ取りを策している模様。双子の刺客を空也が倒し、親子は奈緒の紅花の畑が広がる花咲の郷を目指します。
第3話:「関前の紅花畑」。奈緒母子に霧子が手伝いに加わり、ようやく順調に栽培できるようになった紅花畑を前に、磐音ら親子と奈緒母子、重富利次郎・霧子らは夕食を共にします。磐音たちが帰った後を、伊鶴儀配下の者たちが襲撃しますが、利次郎と霧子、空也までが残っていたとあっては、襲撃者たちもかなうわけがありません(^o^)/
どうやら、伊鶴儀登左衛門の切り札の男は、坂崎磐音に深い怨みを持つ者のようです。ハハーン、もしかするとあの人かな?
第4話:「寛政の戦い」、第5話:「最後の戦い」。国家老・坂崎正睦が動きます。藩士らに総登城を告げる触れ太鼓が鳴らされ、中老・伊鶴儀一派との対決となりますが、ここから後は実際に読んでからのお楽しみということで、あらすじを追うのは止めましょう(^o^)/
○
この長い物語を、作者はどうしめくくるのか、興味深い結末はなかなか後味の良いものでした。春風駘蕩が持ち味の主人公が悲劇で終わっては話が台無しですし、かといって単に刺客を倒し続けて終わりでは竜頭蛇尾の感を免れません。豊後関前藩の陽炎の辻で始まった物語を再び同じ地で閉じるという円環を、主従あるいは親子の世代交代という手法で後に続くらせん状の物語に転じることで、作者は余韻を残す結末に変えてしまいました。こういう作劇術の点からも、最終話をおもしろく読みました。
あとは、全巻一気再読というお楽しみが待っていますが、しばらくは雪かきと母屋の書棚の整理処分などに追われて、まだまだ先になりそうです。
○
第1話:「見舞い」。坂崎磐音の一家は、豊後関前藩に到着、父・坂崎正睦を見舞います。藩主が隠居を許さないため、正睦は国家老の席を辞することができません。しかし、正睦の病気療養の間に勢力を蓄えてきた中老の伊鶴儀登左衛門が藩政の実権を握ろうとしている、というのが本巻の状況のようです。
第2話:「思い出めぐり」。病床の正睦は、孫の空也が示す直心影流の法定四本之形打太刀を見て生気をよみがえらせます。一方、中老の伊鶴儀登左衛門は、藩主の側室お玉の子の実継を擁して藩の実権の乗っ取りを策している模様。双子の刺客を空也が倒し、親子は奈緒の紅花の畑が広がる花咲の郷を目指します。
第3話:「関前の紅花畑」。奈緒母子に霧子が手伝いに加わり、ようやく順調に栽培できるようになった紅花畑を前に、磐音ら親子と奈緒母子、重富利次郎・霧子らは夕食を共にします。磐音たちが帰った後を、伊鶴儀配下の者たちが襲撃しますが、利次郎と霧子、空也までが残っていたとあっては、襲撃者たちもかなうわけがありません(^o^)/
どうやら、伊鶴儀登左衛門の切り札の男は、坂崎磐音に深い怨みを持つ者のようです。ハハーン、もしかするとあの人かな?
第4話:「寛政の戦い」、第5話:「最後の戦い」。国家老・坂崎正睦が動きます。藩士らに総登城を告げる触れ太鼓が鳴らされ、中老・伊鶴儀一派との対決となりますが、ここから後は実際に読んでからのお楽しみということで、あらすじを追うのは止めましょう(^o^)/
○
この長い物語を、作者はどうしめくくるのか、興味深い結末はなかなか後味の良いものでした。春風駘蕩が持ち味の主人公が悲劇で終わっては話が台無しですし、かといって単に刺客を倒し続けて終わりでは竜頭蛇尾の感を免れません。豊後関前藩の陽炎の辻で始まった物語を再び同じ地で閉じるという円環を、主従あるいは親子の世代交代という手法で後に続くらせん状の物語に転じることで、作者は余韻を残す結末に変えてしまいました。こういう作劇術の点からも、最終話をおもしろく読みました。
あとは、全巻一気再読というお楽しみが待っていますが、しばらくは雪かきと母屋の書棚の整理処分などに追われて、まだまだ先になりそうです。