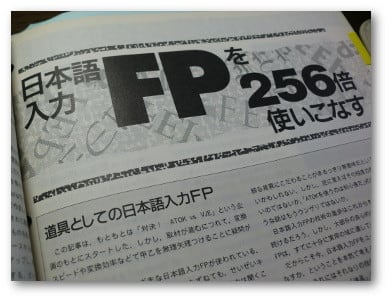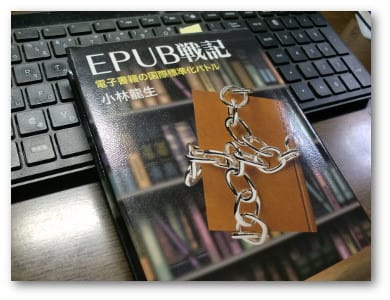大型連休二日目、早朝から少し離れた園地でサクランボの満開期の防除を実施。くたびれたのでコーヒーを飲みながら「らじる★らじる」でNHK-FMを聴きました。「映画音楽の鬼才、バーナード・ハーマン」という特集で、どこかで聞いたことがある曲の作曲者を初めて知りました。
午後からは、暑さをものともせず、妻と二人で老母の野菜畑を耕耘。昨年、放置してしまったため、草が伸び放題になっていましたので、ご近所の皆さんから笑われない程度に手入れをしました。幸い、アスパラや食用菊、食用のギボウシやウルイなどは残っていましたので、そのまま育てます。畑の一部に植えてあるクリスマス・ローズやシャクヤクなども健在でしたが、耕運機のほうはそろそろ点検整備が必要みたい。人間様もくたびれたので、夕方は早めに切り上げました。



ただいま、まさに爛漫の春。サクランボ、モモ、スモモ、梨などの花が咲いています。もうすぐリンゴやプルーンも咲き出すでしょう。晴天の日、畑に出るだけで気持ちのいい季節です。
午後からは、暑さをものともせず、妻と二人で老母の野菜畑を耕耘。昨年、放置してしまったため、草が伸び放題になっていましたので、ご近所の皆さんから笑われない程度に手入れをしました。幸い、アスパラや食用菊、食用のギボウシやウルイなどは残っていましたので、そのまま育てます。畑の一部に植えてあるクリスマス・ローズやシャクヤクなども健在でしたが、耕運機のほうはそろそろ点検整備が必要みたい。人間様もくたびれたので、夕方は早めに切り上げました。



ただいま、まさに爛漫の春。サクランボ、モモ、スモモ、梨などの花が咲いています。もうすぐリンゴやプルーンも咲き出すでしょう。晴天の日、畑に出るだけで気持ちのいい季節です。