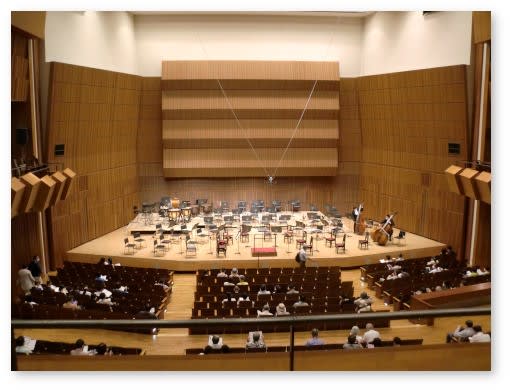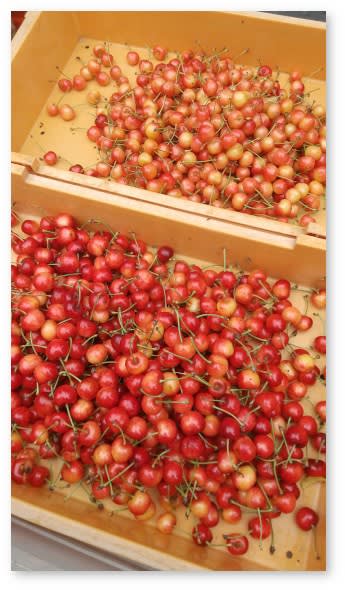昔の、と言っても昭和30〜40年代頃の天気予報は、新聞やラジオ・テレビで知るものでした。天気図があり、気圧配置や前線の位置などから全国予報が出され、各地の予報がそれに続く形でした。これを支えたのは、富士山頂気象観測所(測候所?)を初めとする有人観測体制で、毎日の観測のために富士山頂や各測候所に勤務する人々の苦労は大変なものだったことでしょう。毎日16時に、NHKラジオの気象通報で天気図にデータを書き込み、等圧線を引いて翌日の天気を予想した、そんな時代です。
ところが、昭和から平成に移行する頃の情報化の波は、ビジネスの世界だけにとどまりませんでした。さらにコンピュータ・ネットワークの進歩が拍車をかけ、気象観測体制に無人化・自動化の波が押し寄せます。富士山頂の気象観測が無人化されたのが象徴的な出来事で、各地で気温や降水量などのデータが無人で観測され、自動でデータが送信されるような形に移行していきます。当時の報道では、気象予報業務の合理化・人減らし政策の一環で、無人化により気象予報の精度が低下するのではないかと懸念されたものでしたが。
しかし、その頃、気象予報にコンピュータの導入が進み、シミュレーションの精度が次第に高まっていき、海外の各種気象データもネットワーク化されて加わっていくことによって、大規模シミュレーションも可能になっていきます。大きく見れば、その結果が最近の気象予報の精度の向上なのでしょう。
先日は、午前中は雨の確率が0%でしたが、午後は80%ということでした。お昼になったらやっぱり雨が降り出し、畑仕事から撤収して来ました。ここ数日の雨降りも予報どおり。台風の進路等によって、一週間先の予報が変更されることはありますが、今日明日の予報はほぼ当たるようになってきていると感じます。昔は、当たらないものの代表だった天気予報が、かなり精確に当たるものに変わってきていると感じます。
わがPCやタブレットのブラウザのブックマークには、yamagata-area というフォルダがあり、このトップに「山形地方気象台」のサイトが入っているのは、実はそんな歴史的背景があったのだなあと、空模様を見上げながら、しばし感慨にふけりました。
ところが、昭和から平成に移行する頃の情報化の波は、ビジネスの世界だけにとどまりませんでした。さらにコンピュータ・ネットワークの進歩が拍車をかけ、気象観測体制に無人化・自動化の波が押し寄せます。富士山頂の気象観測が無人化されたのが象徴的な出来事で、各地で気温や降水量などのデータが無人で観測され、自動でデータが送信されるような形に移行していきます。当時の報道では、気象予報業務の合理化・人減らし政策の一環で、無人化により気象予報の精度が低下するのではないかと懸念されたものでしたが。
しかし、その頃、気象予報にコンピュータの導入が進み、シミュレーションの精度が次第に高まっていき、海外の各種気象データもネットワーク化されて加わっていくことによって、大規模シミュレーションも可能になっていきます。大きく見れば、その結果が最近の気象予報の精度の向上なのでしょう。
先日は、午前中は雨の確率が0%でしたが、午後は80%ということでした。お昼になったらやっぱり雨が降り出し、畑仕事から撤収して来ました。ここ数日の雨降りも予報どおり。台風の進路等によって、一週間先の予報が変更されることはありますが、今日明日の予報はほぼ当たるようになってきていると感じます。昔は、当たらないものの代表だった天気予報が、かなり精確に当たるものに変わってきていると感じます。
わがPCやタブレットのブラウザのブックマークには、yamagata-area というフォルダがあり、このトップに「山形地方気象台」のサイトが入っているのは、実はそんな歴史的背景があったのだなあと、空模様を見上げながら、しばし感慨にふけりました。