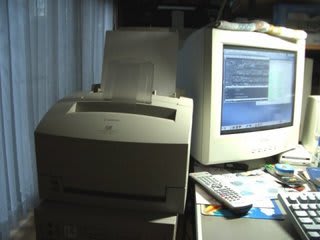平岩弓枝さんの『御宿かわせみ』シリーズ、いよいよ第28巻になりました。文庫本で残るはあと二冊のみ。もうすぐ読みきってしまうのがちょっと残念です。と思いながら、また一方では、今年中に読みきる算段をしている今日この頃。
第1話「江戸の植木市」、植木や盆栽にはとんと興味がない私は、植木市も縁がなく、地元山形市の植木市にもほとんど行きませんが、松太郎の作った箸なら欲しいかも。
第2話「梅屋の兄弟」、兄弟で同じ商売などやるもんじゃないと思うが、お比佐と健太郎が夫婦になれなかった理由が姉弟だったとは。作者はしっかりと麻太郎・千春問題の伏線をしいていると見た。
第3話「佐助の牡丹」、牡丹の花の1位、2位を決めるのに不正があるという。すりかえを防ぐ方法を考えたが、不正を暴かれた悪党は子どもをさらった。しかし、牡丹の花は一晩でボタンと落ちてしまうんじゃなかったっけ。個人的には写真のような芍薬の方が好きです。
第4話「江戸の蚊帳売り」、短気は損気といいますから、あまり性急に結論を急がず、物事はじっくりかまえて取り組んだほうがよろしいようで。
第5話「三日月紋の印籠」、拝領の家宝なんてものがあると、なにかとわずわらしいものです。しかし、世襲の家でこの跡継ぎでは、ちょっとやりきれませんね。
第6話「水売り文三」、出羽の国・上の山とは、現在の山形県上山市ではないですか。なんとまぁ、世間は広いようで狭いものです。文三の優しさが光ります。
第7話「あちゃという娘」、この娘、いい子ですなぁ。こういう子は、きっと幸せになりますよ。誠意のない伊太郎なんかと一緒になってはいけません。自分を安売りしないもんです。
第8話「冬の桜」、宗太郎の弟・宗三郎がよい人生勉強をいたしました。宗太郎、さすが兄貴の貫禄です。
第1話「江戸の植木市」、植木や盆栽にはとんと興味がない私は、植木市も縁がなく、地元山形市の植木市にもほとんど行きませんが、松太郎の作った箸なら欲しいかも。
第2話「梅屋の兄弟」、兄弟で同じ商売などやるもんじゃないと思うが、お比佐と健太郎が夫婦になれなかった理由が姉弟だったとは。作者はしっかりと麻太郎・千春問題の伏線をしいていると見た。
第3話「佐助の牡丹」、牡丹の花の1位、2位を決めるのに不正があるという。すりかえを防ぐ方法を考えたが、不正を暴かれた悪党は子どもをさらった。しかし、牡丹の花は一晩でボタンと落ちてしまうんじゃなかったっけ。個人的には写真のような芍薬の方が好きです。
第4話「江戸の蚊帳売り」、短気は損気といいますから、あまり性急に結論を急がず、物事はじっくりかまえて取り組んだほうがよろしいようで。
第5話「三日月紋の印籠」、拝領の家宝なんてものがあると、なにかとわずわらしいものです。しかし、世襲の家でこの跡継ぎでは、ちょっとやりきれませんね。
第6話「水売り文三」、出羽の国・上の山とは、現在の山形県上山市ではないですか。なんとまぁ、世間は広いようで狭いものです。文三の優しさが光ります。
第7話「あちゃという娘」、この娘、いい子ですなぁ。こういう子は、きっと幸せになりますよ。誠意のない伊太郎なんかと一緒になってはいけません。自分を安売りしないもんです。
第8話「冬の桜」、宗太郎の弟・宗三郎がよい人生勉強をいたしました。宗太郎、さすが兄貴の貫禄です。