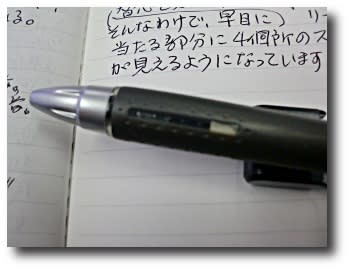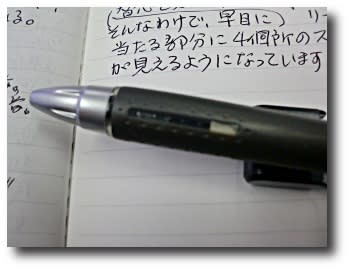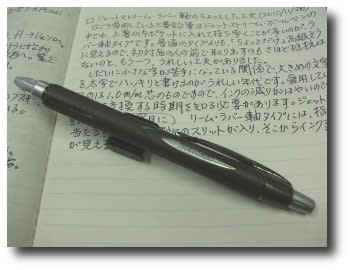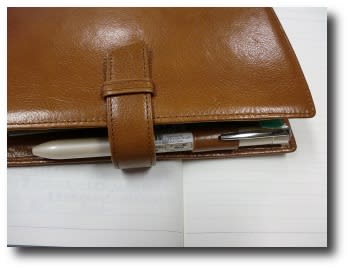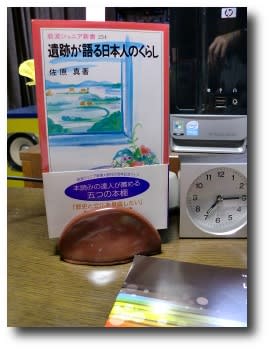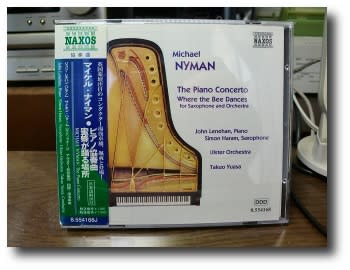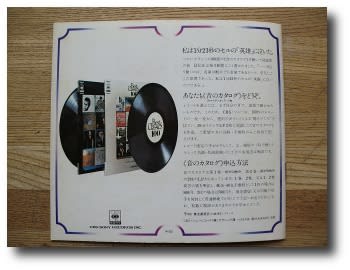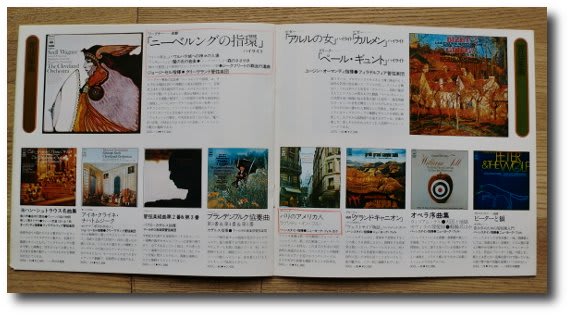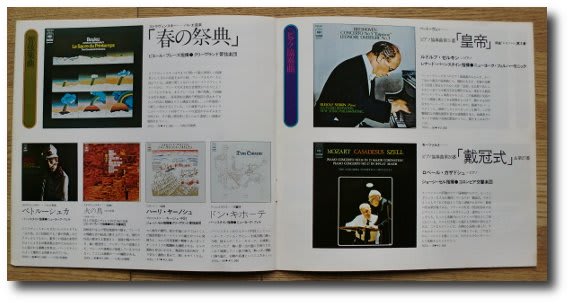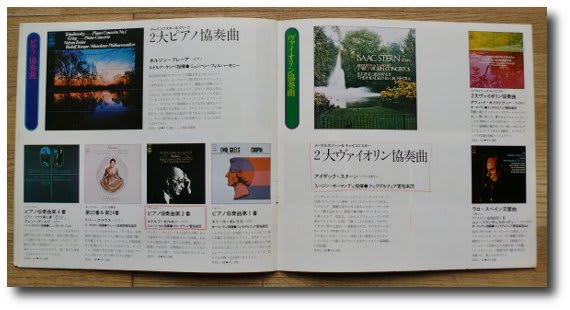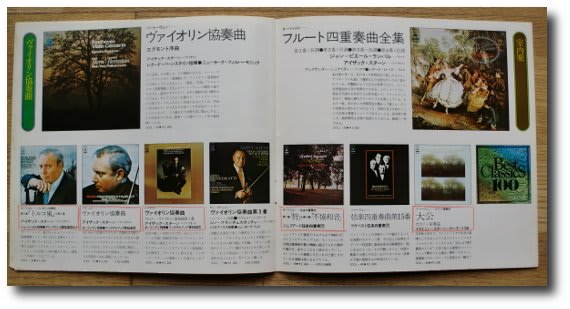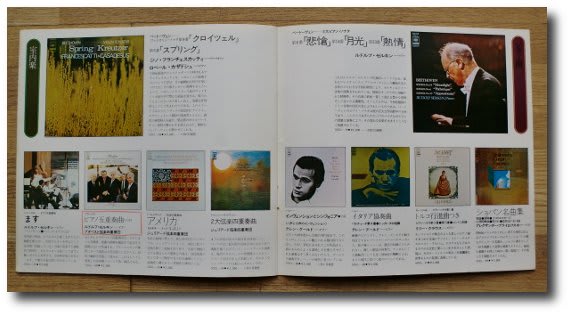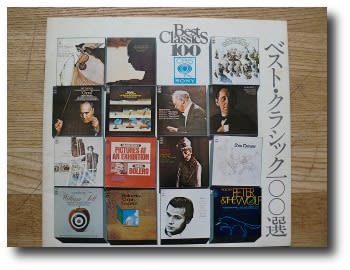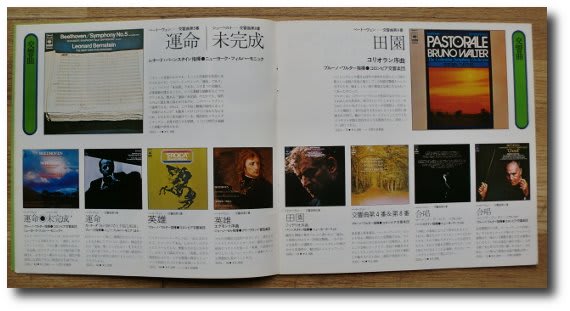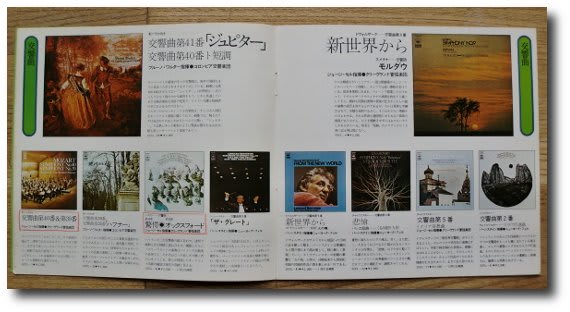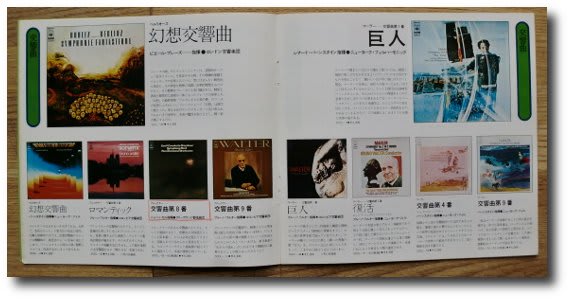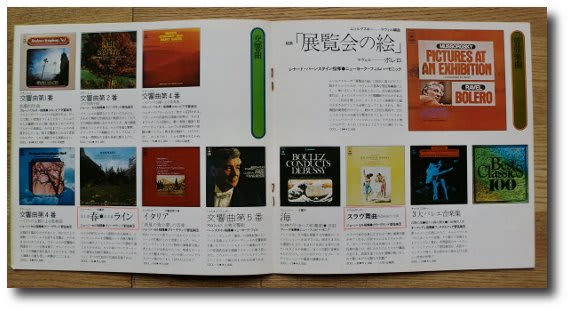濃霧の朝を迎えることが多いこの頃、変則勤務で出勤した土曜日の夜、山形テルサホールで、
山形交響楽団第208回定期演奏会を聴きました。今回は、「J.コクトーと仲間たち」と題して、イベール、ミヨー、プーランクの音楽を取り上げた、フランス音楽の特集です。
夕方、山形駅前の「
江戸寿司」で腹ごしらえをして、咳も止まったし、さあ、行くぞ!と早々に会場入り。高校生のお嬢さんたちと一緒に開場を待ちました。ホールに入ると、ステージにはピアノがすでにフタを開けており、写真のように、いつもの編成・配置とはだいぶ異なりますので、期待も高まります。
まずは飯森範親さんのプレ・コンサート・トークから。今回は、ステージ上の大型スクリーンに、ビュフェの版画を投影しながら、コクトーの詩の日本語訳を読むことができる、という仕掛けだそうです。バーンスタインのピアノ、ベニー・グッドマンのクラリネットで初演されたプーランクのクラリネット・ソナタのメロディは、今日の「人間の声」の最後の部分と共通なのだとか。独唱の中丸三千繪さんも登場して、コクトーは、ラディゲが若死にしたとき、経験したものを詩の中に盛り込んでおり、体験がなければ書けないと感じるとのこと。中丸さんは詩の内容が乗り移ったかのようにハマっているのだそうです。はたしてどんな演奏になるか、楽しみにしつつ、ステージに楽員が登場します。
最初は、イベールの「室内管弦楽のためのディヴェルティメント」です。
楽器編成は、指揮台の周囲に、左から第1ヴァイオリン(4)、第2ヴァイオリン(2)、ヴィオラ(4)、チェロ(4)、その後方にコントラバス(2)、中央後方には、フルート、クラリネット、ファゴットが、さらにその後方にはトランペット、ホルン、トロンボーンが各1ずつ並びます。左手後方にはピアノとパーカッション、バスドラムが陣取ります。
第1曲、序奏、アレグロ・ヴィーヴォ。いたって明るくにぎやかな曲です。
第2曲、行列、モデラート・モルト。静かなHrn-Flに続き、弦とミュートTp、Fgなどが活発に。引用されるパロディ旋律は、行列の様子でしょうか。
第3曲、夜想曲、レント。VcとCbから。Cl-Hrnは暗い夜の雰囲気です。Pfもタンバリンも。
第4曲、ワルツ、アニマート・アッサイ。始まりの序奏はワルツではありませんが、途中から遊園地ふう、いや、酔っ払いの笑い声も入るので、酒場ふうのワルツでしょう。
第5曲、パレード、テンポ・ディ・マルチャ。たしかに、近づいてきて通り過ぎるパレードふうです。バスドラムの音は、大砲?花火?
第6曲、ピアノソロがたたきつけるように始まり、呼子は鳴るわ、ホルンは立ち上がり、トランペットとトロンボーンにはさまれるわ、どんちゃん騒ぎです。最後は指揮者も呼子を吹き慣らし、三色旗を振って終わります。いや~、楽しい!
ステージの上でセッティングを変更する間、ミヨーの「フランス組曲」にちなんだ各地の風景を、映像で紹介・説明します。これはわかりやすくいいアイデアですね。この曲は、もともと吹奏楽のためのものだそうですが、管弦楽のために編曲しているそうな。吹奏楽のときよりも、「アルザス・ロレーヌ」などでは、弦の暗い音色などに、より特徴が出ているそうです。
ステージ上は、おおよそ通常の規模の編成に戻ります。左から第1ヴァイオリン(10)、第2ヴァイオリン(8)、チェロ(6)、ヴィオラ(6)、その後ろにコントラバス(4)、中央後方に管楽器が配置され、フルート(2)、オーボエ(2)、その後方にクラリネットとファゴットが各2、最後尾にトロンボーン(2)となっています。後方左には、ティンパニとシンバルを含むパーカッション(4)が特徴的かな。
第1曲、ノルマンディ。なるほど、たしかに吹奏楽の行進曲ふうです。
第2曲、ブルターニュ。Vc,VlaにのってHrnが、さらにミュートTpと弦にのってObが、単調で憂鬱な旋律を奏でます。オーボエ、いい音だな~。
第3曲、イル・ド・フランス。パリなど中心部でしょうか。活発で都会的な雰囲気です。
第4曲、アルザス・ロレーヌ。独仏により何度も併合を繰り返してきた地域。戦争の悲劇をもっとも多く受けてきた地域です。弦楽合奏による悲歌から。FlとClが入り、他の管も加わり、Timp.とドラムスの静かなリズムは葬列の歩みでしょうか、戦死者の鎮魂でしょうか。弦のトップによる柔らかな響きも美しく悲しく。でも、しだいに高まる感情は、吹奏楽のクライマックスふうです。
第5曲、プロヴァンス。軽快でにぎやか。フルート、ピッコロと小太鼓はファランドールふう。にぎやかに終わります。
ここで、15分間の休憩が入りました。ドリンクを飲んで喉を潤し、階段からふと下を見ると、来年の新シーズンのパンフレットがすでにできており、熱心に読みふける人も。

さて、後半は、演奏会形式で上演されるプーランクのモノドラマ「人間の声」です。私はもちろん始めてです。台本はJ.コクトー、中央の指揮台の脇におしゃれな椅子と電話台が置かれ、その上にはやっぱりおしゃれな電話が。20世紀前半の、
コクトーや
ラディゲや
ビュフェや
エディット・ピアフや
ディアギレフ、ピエール・カルダンが活躍したパリの雰囲気なのでしょう。でも、理系の石頭を自認する当方がわかるのは、ピアフの歌とカルダンのネクタイくらい。コクトーの詩も、この歳になって初体験です(^o^;)>poripori
オーケストラは、先の配置に少し変更があり、金管楽器の一部を減らしたほか、オーボエとコントラバスとの間にハープが、最後尾にチューバが加わります。そして、舞台中央の上部には大きなスクリーン。
チューニングの後、長い間があってステージが暗くなり、スポットライトの中へ中丸さんが登場、藤色のロングドレスです。スクリーンにはビュフェの版画「人間の声」が投影される中、飯森さんが音楽を開始します。木琴が電話のベルを模し、混線にいらだちながら、離れて行った男との最後のつながりになってしまった電話にすがる女性の心理を、表現していきます。フランス語の意味はわかりませんが、スクリーンに投影される版画と日本語訳で、イメージは明確です。はじめは強がり、しだいに哀願するように、最後は望みを失い、電話線を首に巻きつけてベッドに横たわるという心理ドラマです。
うーん、そうですね。マルトというのはお姉さんの名前でしょうし、この女性というのはたぶん自分自身でしょう。この電話というのは、もしかしたらあの世のラディゲからのものなのかもしれません。晩年になって選び出した、アヘンに溺れた青年期の切実な体験を凝縮した言葉に、若い人ならばきっと衝撃を受けるような心理劇だと思いますが、少なくない人の生死を見て、そう遠くない将来、やがて自分も迎えなければならない孤独な旅立ちを思うことがある今日この頃、意外に平静に、モノドラマとしての表現を味わうことができました。今の中丸三千繪さんだからできる、きわめて価値ある演奏会だと感じました。
○
何をいまさらの余談ですが、佐藤麻咲さんのオーボエ、実にいい音ですね。リードを口にくわえて楽器のそうじをするところなどは、まるで「かわいい木枯し紋次郎」ふうですが、出てくる音のよく通ること。モノドラマの中のオーボエのひとふしに、通り過ぎるすきま風の音を聞いたような気がしました。