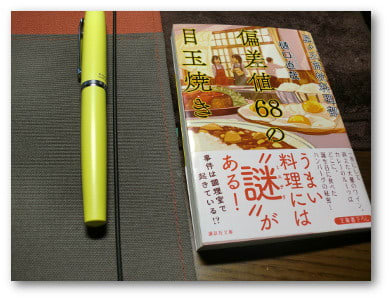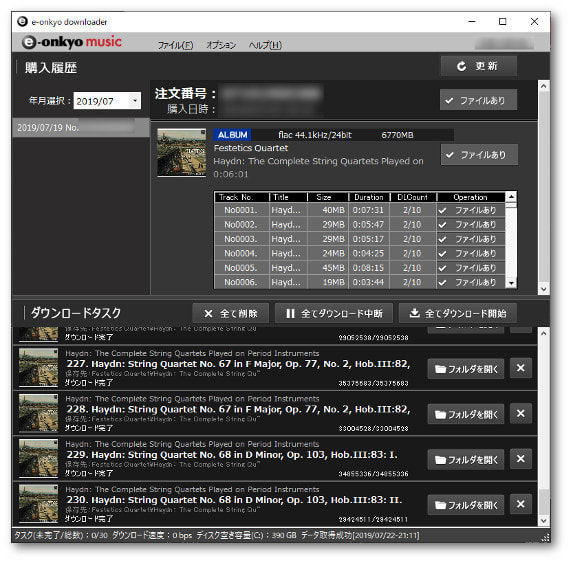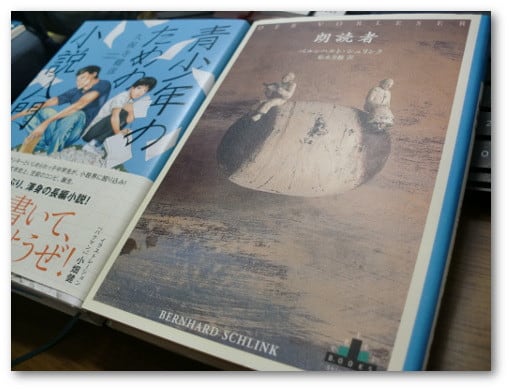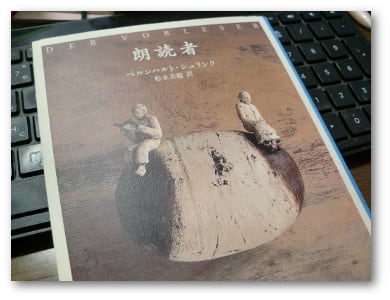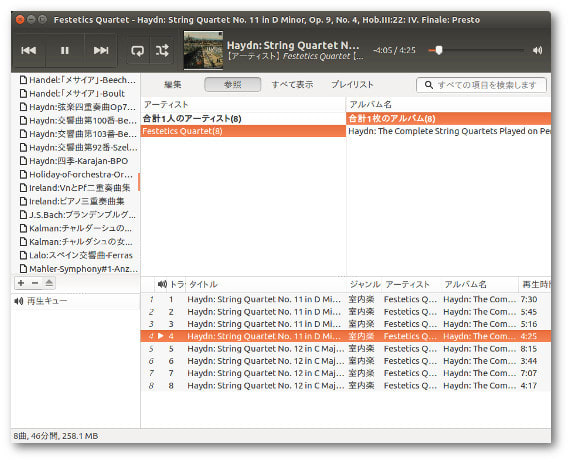文藝春秋社から2018年に刊行された単行本で、梶よう子著『赤い風』を読みました。2017年に埼玉新聞に連載された、地域史に基づく作品のようです。
物語は、江戸時代の武蔵野台地に残された入会地が、多くの村落の秣場(まぐさば)として利用されているところから始まります。境界がはっきりしないために、複数の村落が互いに争う中で、とうとう十歳になったばかりの正蔵の父親・吉二郎が他村の五人組の男たちに襲われた際に息子をかばって頭を強く殴打され、帰宅後に死亡します。しかし、犯人は軽い叩き刑で放免され、遺された母子は他村に労働力として縁付くのです。このような多年にわたる秣場の争いも、新たに川越藩主となった柳沢吉保とその腹心の家老・曽根権太夫らの調査により、川越領として解決をみますが、問題はここから。将軍徳川綱吉の肝いりで三富神殿の開拓が始まります。
ここからは、二年と期限が切られた開拓の経緯が、かなり具体的に描かれます。一軒あたり五町歩の細長い短冊状の土地は、防風林に囲まれた家屋とこれに続く耕地、その奥の屋敷林からなっています。赤い風となる火山灰の土地に、落葉樹の落ち葉を集めて作る堆肥をすきこみ作物を育てるという、今風に言えば「循環エコ農法」。開拓を志して集まってきた人々の中に、成長した正蔵と、父親を殺した鶴間村の悪党・藤兵衛が名前を変えて加わっています。家老・曽根権太夫と嫡男・啓太郎が自ら村に住む開拓は、はたして成功するのか、また正蔵らはどうなるのか、叙事詩的な展開で物語は進みます。
○
なかなかおもしろかった。今も残る川越の三富新田が日本農業遺産に指定されていることなど、初めて知る史実も興味深いものがありました。しいて言えば、後に登場する荻生徂徠など歴史を有名人の智謀に帰着させて展開しようとする傾向には疑問を感じます(*1)が、まあこれは歴史学の論文ではなくて小説ですから(^o^)/
(*1):当地には、やはり江戸時代に、地域の豪農たちが中心になって灌漑用水路を開削したり、あるいは大きな溜池をいくつも作ったりした史実があり、かならずしも有名人の名前が出てこなくても歴史は作られてきたという認識があるからです。
物語は、江戸時代の武蔵野台地に残された入会地が、多くの村落の秣場(まぐさば)として利用されているところから始まります。境界がはっきりしないために、複数の村落が互いに争う中で、とうとう十歳になったばかりの正蔵の父親・吉二郎が他村の五人組の男たちに襲われた際に息子をかばって頭を強く殴打され、帰宅後に死亡します。しかし、犯人は軽い叩き刑で放免され、遺された母子は他村に労働力として縁付くのです。このような多年にわたる秣場の争いも、新たに川越藩主となった柳沢吉保とその腹心の家老・曽根権太夫らの調査により、川越領として解決をみますが、問題はここから。将軍徳川綱吉の肝いりで三富神殿の開拓が始まります。
ここからは、二年と期限が切られた開拓の経緯が、かなり具体的に描かれます。一軒あたり五町歩の細長い短冊状の土地は、防風林に囲まれた家屋とこれに続く耕地、その奥の屋敷林からなっています。赤い風となる火山灰の土地に、落葉樹の落ち葉を集めて作る堆肥をすきこみ作物を育てるという、今風に言えば「循環エコ農法」。開拓を志して集まってきた人々の中に、成長した正蔵と、父親を殺した鶴間村の悪党・藤兵衛が名前を変えて加わっています。家老・曽根権太夫と嫡男・啓太郎が自ら村に住む開拓は、はたして成功するのか、また正蔵らはどうなるのか、叙事詩的な展開で物語は進みます。
○
なかなかおもしろかった。今も残る川越の三富新田が日本農業遺産に指定されていることなど、初めて知る史実も興味深いものがありました。しいて言えば、後に登場する荻生徂徠など歴史を有名人の智謀に帰着させて展開しようとする傾向には疑問を感じます(*1)が、まあこれは歴史学の論文ではなくて小説ですから(^o^)/
(*1):当地には、やはり江戸時代に、地域の豪農たちが中心になって灌漑用水路を開削したり、あるいは大きな溜池をいくつも作ったりした史実があり、かならずしも有名人の名前が出てこなくても歴史は作られてきたという認識があるからです。