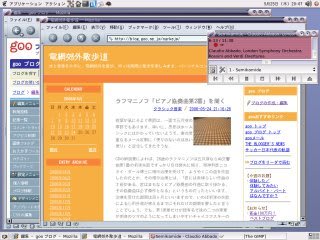通勤に要する時間が短くなり、帰宅が早くなったので、通勤とは別に音楽を聞いたり本を読んだりする時間が増えた。さて何を聞こうかとCDを探すのが楽しみである。今日は、ベートーヴェンのピアノ協奏曲第4番。ベートーヴェンの五曲のピアノ協奏曲の中では、1番とともにお気に入りの音楽だ。
第1楽章、アレグロ・モデラート。ピアノ独奏が静かに始まり、同じ主題を管弦楽が続く。再びピアノが入ると、オーケストラと対話しながら自在にかけまわる。特に管弦楽の充実が見事で、演奏に要する時間の面からも、実に充実した楽章だと感じられる。
第2楽章、アンダンテ・コン・モート。短いが静かに深い緩徐楽章。ベートーヴェンの緩徐楽章はほんとうに魅力的だ。続けて第3楽章が演奏される。
第3楽章、ロンド、ヴィヴァーチェ。重厚な管弦楽をバックに、ピアノ独奏の名技を存分に味わうことができる。最後もスカッとしており、しつこくならないで終わる。
(それも手が伸びる原因の一つだなどと言ったら、偉い人に怒られるか。)
演奏は、フリードリヒ・グルダのピアノ、ホルスト・シュタイン指揮ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団によるLP(ロンドン、L16C-1610)と、レオン・フライシャーのピアノにジョージ・セル指揮クリーヴランド管弦楽団によるCD(SONY SBK-48165)を聞いている。
この協奏曲あたりになると、独奏者ももちろんだが、オーケストラの充実と魅力がほしいと思う。1970年代に来日し、N響を指揮してワーグナーの名演奏を聞かせてくれたホルスト・シュタインがウィーン・フィルを振った演奏は、ゆったりとした遅めのテンポを取りながら時おり激しい強奏を聞かせ、まさに堂々たる響きを楽しむことができる。LPには演奏者の写真などは添えられていないけれど、あの偉大なるおでこをゆらしながら丹念に指揮をするホルスト・シュタインさんの壮年時代の姿が見えるような気がする。いわば、横綱の土俵入りのような演奏か。
その点では、ジョージ・セル指揮のクリーヴランド管弦楽団も、堂々たる演奏だ。ただし、こちらはかなり速めのテンポで、きりりと引き締まったもので、見事なフォーメーションを披露しながら圧倒的な強さを見せるラグビーの試合のようなものか。第2楽章の深さなどは、遅いテンポだけに頼らない緊張感を見せている。
■グルダ(Pf)、ホルスト・シュタイン指揮ウィーンフィル
I=19'03" II=5'52" III=9'57" total=34'52"
■フライシャー(Pf)、セル指揮クリーヴランド管
I=17'59" II=5'07" III=9'03" total=32'09"
第1楽章、アレグロ・モデラート。ピアノ独奏が静かに始まり、同じ主題を管弦楽が続く。再びピアノが入ると、オーケストラと対話しながら自在にかけまわる。特に管弦楽の充実が見事で、演奏に要する時間の面からも、実に充実した楽章だと感じられる。
第2楽章、アンダンテ・コン・モート。短いが静かに深い緩徐楽章。ベートーヴェンの緩徐楽章はほんとうに魅力的だ。続けて第3楽章が演奏される。
第3楽章、ロンド、ヴィヴァーチェ。重厚な管弦楽をバックに、ピアノ独奏の名技を存分に味わうことができる。最後もスカッとしており、しつこくならないで終わる。
(それも手が伸びる原因の一つだなどと言ったら、偉い人に怒られるか。)
演奏は、フリードリヒ・グルダのピアノ、ホルスト・シュタイン指揮ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団によるLP(ロンドン、L16C-1610)と、レオン・フライシャーのピアノにジョージ・セル指揮クリーヴランド管弦楽団によるCD(SONY SBK-48165)を聞いている。
この協奏曲あたりになると、独奏者ももちろんだが、オーケストラの充実と魅力がほしいと思う。1970年代に来日し、N響を指揮してワーグナーの名演奏を聞かせてくれたホルスト・シュタインがウィーン・フィルを振った演奏は、ゆったりとした遅めのテンポを取りながら時おり激しい強奏を聞かせ、まさに堂々たる響きを楽しむことができる。LPには演奏者の写真などは添えられていないけれど、あの偉大なるおでこをゆらしながら丹念に指揮をするホルスト・シュタインさんの壮年時代の姿が見えるような気がする。いわば、横綱の土俵入りのような演奏か。
その点では、ジョージ・セル指揮のクリーヴランド管弦楽団も、堂々たる演奏だ。ただし、こちらはかなり速めのテンポで、きりりと引き締まったもので、見事なフォーメーションを披露しながら圧倒的な強さを見せるラグビーの試合のようなものか。第2楽章の深さなどは、遅いテンポだけに頼らない緊張感を見せている。
■グルダ(Pf)、ホルスト・シュタイン指揮ウィーンフィル
I=19'03" II=5'52" III=9'57" total=34'52"
■フライシャー(Pf)、セル指揮クリーヴランド管
I=17'59" II=5'07" III=9'03" total=32'09"