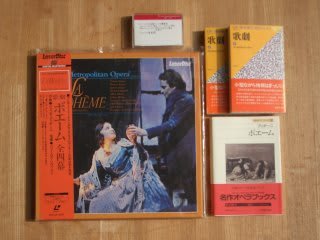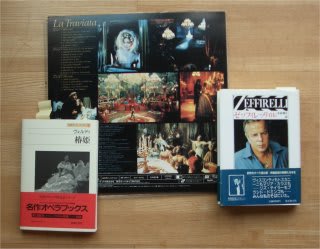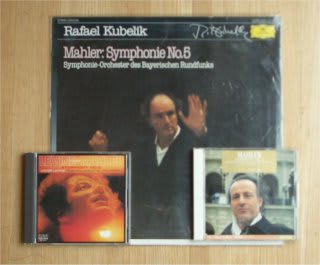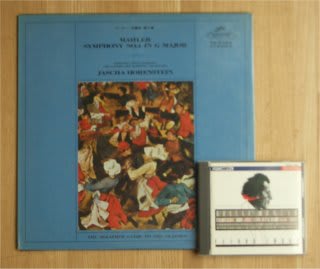最近、コンピュータ環境はきわめて安定している。FMV-6450CL3 のサウンドボードのノイズを除けば、VineLinux3.1 にほぼ満足しているし、TeX/LaTeX/Emacs/Gimp/Mozilla/StarSuite 等のアプリケーションの動作にも、それほど不満はない。
最新のディストリビューションは、それなりに高機能で、高性能なマシン性能を要求するようになり、かつてのLinux=中古機でも可、という図式は薄れた。しかし、世の中にはどんどん中古パソコンが出回る。新機能、新製品と連呼する反面、PenIII/600-800MHz台の中古機が主流である。であるなら、この程度の中古機でも軽く動作するディストリビューションがあっても良いのではないか。そう考えた人はやはりいたようで、TurboLinuxが中古ビジネスに乗り出すとか。WEB閲覧とメール端末程度に割り切れば、充分な能力を持っているのだから、こういう道もあっていい。企業の割り切った用途には充分な気がする。残念ながら、個人は対象外だそうです。
写真は、板戸から夏向きに網細竹の戸に模様替えした和室の様子。この部屋にもLAN回線が引いてあり、メールチェックができるようになっている。
最新のディストリビューションは、それなりに高機能で、高性能なマシン性能を要求するようになり、かつてのLinux=中古機でも可、という図式は薄れた。しかし、世の中にはどんどん中古パソコンが出回る。新機能、新製品と連呼する反面、PenIII/600-800MHz台の中古機が主流である。であるなら、この程度の中古機でも軽く動作するディストリビューションがあっても良いのではないか。そう考えた人はやはりいたようで、TurboLinuxが中古ビジネスに乗り出すとか。WEB閲覧とメール端末程度に割り切れば、充分な能力を持っているのだから、こういう道もあっていい。企業の割り切った用途には充分な気がする。残念ながら、個人は対象外だそうです。
写真は、板戸から夏向きに網細竹の戸に模様替えした和室の様子。この部屋にもLAN回線が引いてあり、メールチェックができるようになっている。