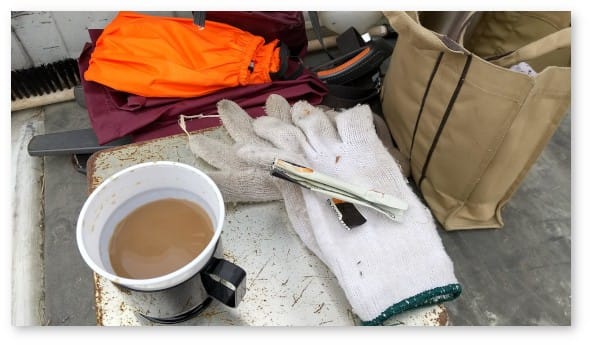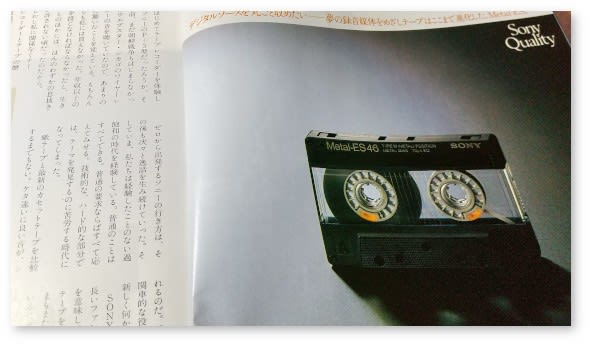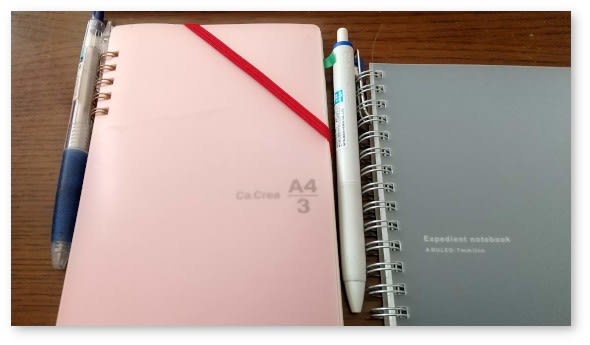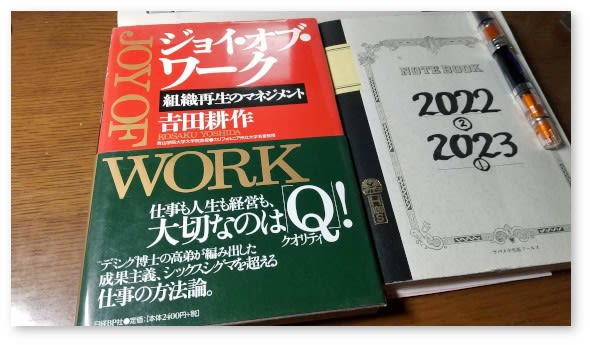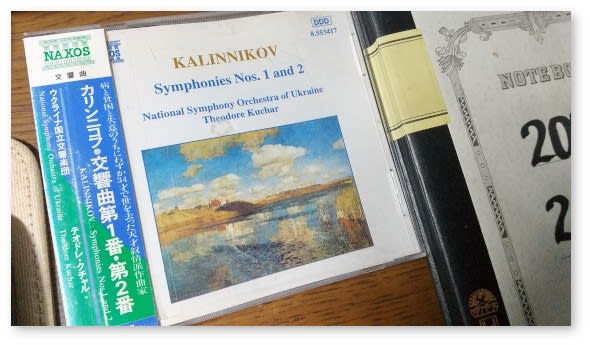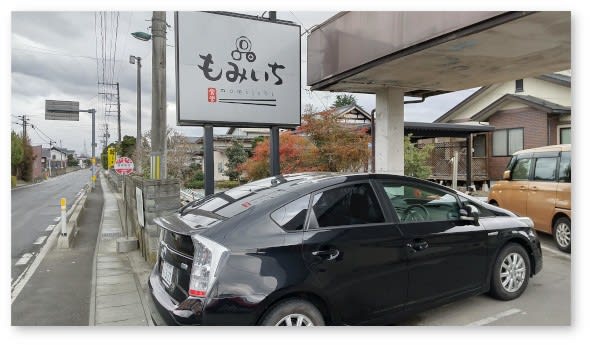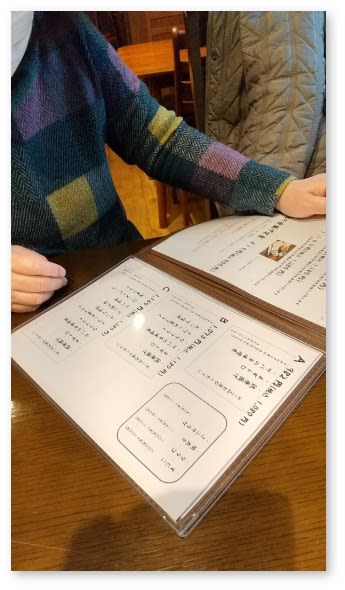山形県の天童市に本社と工場を持つ日新製薬株式会社は、ジェネリック医薬品を中心に製造開発する企業です。近年の好調を背景に、企業メセナとして毎春3月に山響のコンサートを開き、招待客や一般市民等にオーケストラに親しむ機会を提供しています。私はこれまで2016年、17年、18年、22年、23年と聴いていますが、定期演奏会とは異なり親しみやすい演奏会で、毎回楽しみに聴いています。今回は、
- 前半〜モーツァルト/歌劇「フィガロの結婚」K.492より
- 後半〜オーケストラ名曲集
という構成でした。
開演前に山響の西濱秀樹事務局長が登場し、山響の簡単な紹介と日新製薬の会長さんを紹介します。スポンサーの日新製薬の会長さんの話によれば、昨今の同業他社の不始末で医薬品の供給に影響が出ており、会社として全力を挙げて対応しているのだそうです。そのため工場も三交替勤務にせざるをえない状況で、工場の拡張でなんとか二交代に戻したいとのことでした。このあたり、団塊世代とその下の世代の退職、少子化の影響で人手不足が深刻化しており、たいへんだなあと感じます。
もう一つ、西濱さんの話であらためて驚いたことがありました。山響ができてからずっと取り組んでいるスクールコンサートでは、子どもたちに本物の生の音楽を届けて来ているわけですが、演奏を聴いた子どもたちの述べ人数が300万人に達するとのことでした。山形県の人口がおよそ100万人ですので、おそらく山形県の子どもたちは生のオーケストラの演奏を何度も聴いていることになります。これは実はスゴイことなのではなかろうか。
今回、当たった席はだいぶ前の方の右手でしたので、ちょうどパーカッションあたりのステージを見上げる形になりました。そのため楽器配置が判別しにくい面がありましたが、前半のモーツァルトは編成を絞り、たぶん左から第1ヴァイオリン(6? or 8?)、チェロ(3)、ヴィオラ(3)、第2ヴァイオリン(6)の対向配置、コントラバス(2)はチェロの左後方に配置です。正面奥にフルート(2)、オーボエ(2)、その奥にクラリネット(2)、ファゴット(2)、右手奥にホルン(2)、一番奥にトランペット(2)という形でしょうか。入場時のパッと見では、ホルン、トランペットともにナチュラルタイプのようで、作曲当時の楽器を使用することで響きの効果の再現をねらっているようです。
- 歌劇「フィガロの結婚」序曲
- 第1幕 フィガロとスザンナの二重唱「5、10、20」 深瀬廉(Bar)、佐藤亜美(Sp)
- 第1幕 フィガロとスザンナの小二重唱「たとえばもし、奥方様が」 深瀬廉(Bar)、佐藤亜美(Sp)
- 第1幕 フィガロのカヴァティーナ「もし踊りをなさりたければ」 深瀬廉(Bar)
- 第3幕 伯爵とスザンナの小二重唱「ひどいやつだ!なぜ今まで長いこと」 深瀬廉(Bar)、佐藤亜美(Sp)
- 第3幕 レチタティーヴォと伯爵のアリア「訴訟に勝ったと!」 深瀬廉(Bar)
- 第3幕 フィナーレ「さあ、行進曲だ…行きましょう」 オーケストラで
- 第4幕 フィナーレより「すべては静かで穏やかだ」〜「平和を、仲直りを、僕の甘い宝よ」「苦悩のこの日を」 深瀬廉(Bar)、佐藤亜美(Sp)、阿部花音(Sp)、安孫子留架(Ten)、松倉望(Bs)、土田拓志(Bs)
バリトンの深瀬廉さんの経歴等は、
山形市の出身。東京芸術大学卒業、同大学院修士課程修了、ベルリン芸術大学大学院オペラ科並びに歌曲科を修了。第60回学生音楽コンクール第1位、学部卒業時に松田トシ賞など各賞を受賞、第28回市川新人演奏家コンクール最優秀賞、第26回日本ドイツ歌曲コンクール第2位、第29回ラインスベルク国際声楽コンクール入賞、平成29年度文化庁新進芸術家海外研修制度研修生、2016・2018年度ロームミュージックファンデーション奨学生。甲子園や在独日本大使館で国歌独唱を務める。国内外のオペラではモーツァルト「ドン・ジョヴァンニ」のレポレッロ役、ラヴェル「スペインの時」のラミーロ役などに出演、演奏会ではフォーレ「レクイエム」やベートーヴェンの「第九」などでソリストを務める。ベルリン交響楽団、ブランデンブルク国立管弦楽団フランクフルト、山形交響楽団などと共演。声楽を大島幾雄、藤野祐一、福島明也、吉原輝、Carola Hoen の各氏に師事。現在は山形大学講師。
とのことです。
今回は途中で衣装を変えてフィガロと伯爵と両方を歌いました。ホールは多目的ホールですので決して音響的に歌いやすい環境ではないと思いますが、ステージのできるだけ前方に立つことでなんとか響きを掴みながら歌えたでしょうか。しかし、オーケストラをバックにホール全体に響く歌声というのは、あらためてスゴイものです。よく通る天与の声に磨きをかけた歌声は、フィガロのいきいきとした活力と共に伯爵の役柄も歌い分けて、バリトンの歌声の魅力を味わうことができました。また、スザンナ役の佐藤亜美さんほか出演の皆さんは、山形大学および同大学院の学生さんとOBの方々だそうで、真っ赤なドレスの佐藤亜美さんは最初は少し恥ずかしそうなところも感じられましたが、徐々に役柄に慣れてきたみたいで、初々しいスザンナという感じでした。
全体に、サンクスコンサートでは初のオペラということでしたが、やっぱりオペラの場合、どんな場面で何を歌っているのか、よくわからない面があります。正直言って、簡単なストーリー紹介か、できれば字幕があると助かるのになあと感じました。
後半は『愛の名曲の花束』と題して、オーケストラ名曲集となりました。もちろん曲によりますが、楽器編成はモーツァルトのときよりもだいぶ拡大されて、8-7-5-5-3 の弦楽5部に Fl(2), Ob(2), Cl(2), Fg(2), Hrn(4), Tp(2), Tb(3), Tuba, Harp, Timp. にパーカッションというものです。
- ヨハン・シュトラウスⅡ世:ワルツ「春の声」
- ブラームス編曲:ハンガリー舞曲第5番
●指揮者に挑戦コーナー(ハンガリー舞曲第5番)
- エルガー:愛の挨拶
- モリコーネ:ガブリエルのオーボエ オーボエ独奏:柴田祐太(山響)
- ヴォーン・ウィリアムズ:グリーンスリーブスの主題による幻想曲
- スメタナ:交響詩「わが祖国」よりモルダウ
ウキウキするような「春の声」で始まり、ハンガリー舞曲第5番でお手本を聴かせた後で、恒例の「
識者指揮者に挑戦」コーナー。今回は滋賀県在住という若い男性の薬剤師さんと小学生の女の子でした。おそらくは招待客のお一人であろう男性の薬剤師さんは、子供時代にもオーケストラを聴いたことはなかったそうで、生オーケストラを聴くのは初めてだそうです。うーむ、やっぱり本県の子どもたちは山響の恩恵をしっかり受けているぞ(^o^)/
小学生の女の子は、指揮棒の動きより少し遅れて音が出てくるオーケストラの特性から、しだいにテンポが遅くなるという落とし穴にもはまらずに、自分のテンポで指揮を完遂(^o^)/ いい記念になったことでしょう。

(開演前のステージ右側の様子)
今回、一緒に行った妻は、モリコーネの「ガブリエルのオーボエ」がたいへん気に入ったそうです。私は、今回「モルダウ」のパーカッションで、バスドラムと共に鳴り響くシンバルの音が、大きさの異なる2種類のシンバルを使い分けていることを発見! そうだったのか! 微妙に異なるあの「ジャーン」は、鳴らし方によるものではなかったのだな! よく知った曲と思っていても、実はまだまだ新しい発見があるのですね。なんか、すごく得した気分(^o^)/
アンコールは、ブラームスのハンガリー舞曲第1番。阪哲朗さんの指揮による山響の、柔らかな、でも芯の通った演奏が、懐かしさを感じさせるブラームスの音楽の魅力をホールいっぱいに広げていました。また聴きたいなと思ってしまうひとときでした。
(*1):
Ren Fukase 深瀬 廉〜twitter