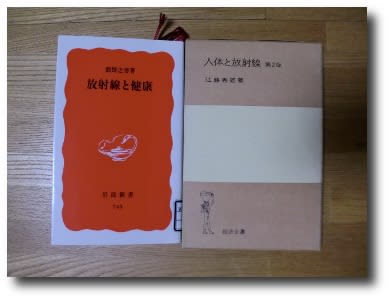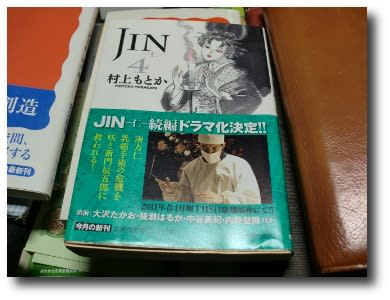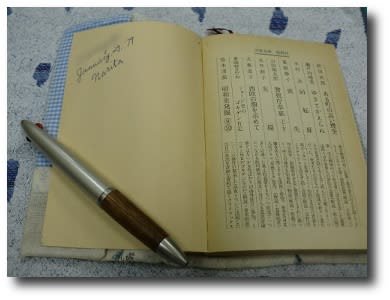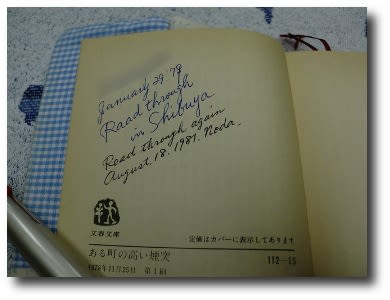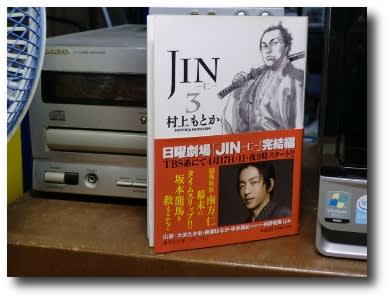私がまだ若かった頃、1960年代末~70年代前半にかけて、ベートーヴェンはメトロノームの発明を喜んだものの、実際の速度表示はとても演奏できず、「無茶」な指定だと決めつけるばかりか、ベートーヴェンのメトロノームは壊れていたとか、ベートーヴェンは速度表示など無視していた、とする記事が少なくなかったように記憶しています。
この頃にはまた、ベートーヴェンの演奏の真髄を示すのは物故した某ドイツの指揮者であり、その遅いテンポこそ、音楽の精神性を表しているのだ、という論調もよく見られました。素人音楽愛好家にすぎない当方は、ふーん、そんなものかと思っていましたが、お気に入りの演奏は快速テンポの溌剌としたものが中心で、今にも音楽が停止しそうでハラハラする激遅演奏には、どうもついていけないものを感じておりました。
どうもこれは、すべての音にヴィヴラートをかけていたのでは、指定の速度で演奏するのは無理だ、というだけの話であって、オリジナルな速度指定に基づき、ノン・ヴィヴラートの古楽奏法で演奏した表現の可能性が見直されるようになったのが、近年の現象なのであろうと思います。
現代楽器を用い、ヴィヴラートを多用した豊麗な音で、ゆったりと演奏される音楽の表現が、心休まる場合も少なくなく、大好きな録音も多いのですが、また一方で、古楽器を併用し、古楽奏法を取り入れて演奏される、透明で快活な音と表現が、たいへん新鮮に魅力的に感じられます。こういう無節操かつゼイタクな素人音楽愛好家の立場からは、ベートーヴェンの速度表示は「無茶」だったとは言えず、むしろ今にも停まりそうな激遅演奏のほうが、高速道路をトラクターで走るような無頼な表現なのかもしれない、と思ってしまいます。さて、実際のところはどうなのでしょう(^o^;)>poripori
この頃にはまた、ベートーヴェンの演奏の真髄を示すのは物故した某ドイツの指揮者であり、その遅いテンポこそ、音楽の精神性を表しているのだ、という論調もよく見られました。素人音楽愛好家にすぎない当方は、ふーん、そんなものかと思っていましたが、お気に入りの演奏は快速テンポの溌剌としたものが中心で、今にも音楽が停止しそうでハラハラする激遅演奏には、どうもついていけないものを感じておりました。
どうもこれは、すべての音にヴィヴラートをかけていたのでは、指定の速度で演奏するのは無理だ、というだけの話であって、オリジナルな速度指定に基づき、ノン・ヴィヴラートの古楽奏法で演奏した表現の可能性が見直されるようになったのが、近年の現象なのであろうと思います。
現代楽器を用い、ヴィヴラートを多用した豊麗な音で、ゆったりと演奏される音楽の表現が、心休まる場合も少なくなく、大好きな録音も多いのですが、また一方で、古楽器を併用し、古楽奏法を取り入れて演奏される、透明で快活な音と表現が、たいへん新鮮に魅力的に感じられます。こういう無節操かつゼイタクな素人音楽愛好家の立場からは、ベートーヴェンの速度表示は「無茶」だったとは言えず、むしろ今にも停まりそうな激遅演奏のほうが、高速道路をトラクターで走るような無頼な表現なのかもしれない、と思ってしまいます。さて、実際のところはどうなのでしょう(^o^;)>poripori