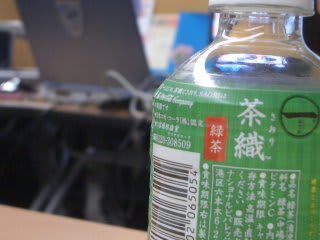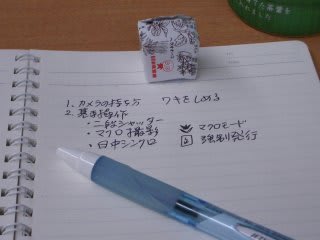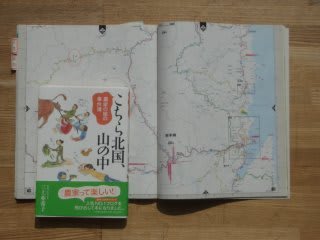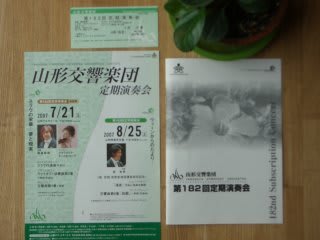最初は新鮮でインパクトがあり、いい言葉だな~と思っていたのに、使われすぎて手あかがつき、あまり自分では使いたくない言葉があります。たとえば「生き様(ざま)」「ふれあい」「出会い」などです。「生き様」は藤沢周平も嫌いな言葉に挙げていましたが、「ざまが悪い」「ぶざま」「ざまあみろ」などを連想する「ざま」と私たちが生きることとを、あまりストレートに結びつけたくはない、と思います。「ふれあい」も同じで、知らない人から「ふれあい」などと言われると、ぺたぺたさわられるようで気色悪い。
「出会い」という言葉も、場面を考えずに頻用するのはいかがなものかと思ってしまう言葉の一つです。宣伝に踊らされて買わされる商品と自分が「出会う」なんて、あまり愉快な状況ではありません。
これが、長らく探し求めていた本やCDですと、話は別です。「30年ぶりに再会した」とか「ようやく巡り会った」などの表現を、私もいたします。偶然の出会いよりも、探し求めていたものとめぐりあうことのほうが、喜びが大きいだけに、表現も強く大げさになってしまう、ということでしょうか。どうやら、言葉にも鮮度があるようです。

「出会い」という言葉も、場面を考えずに頻用するのはいかがなものかと思ってしまう言葉の一つです。宣伝に踊らされて買わされる商品と自分が「出会う」なんて、あまり愉快な状況ではありません。
これが、長らく探し求めていた本やCDですと、話は別です。「30年ぶりに再会した」とか「ようやく巡り会った」などの表現を、私もいたします。偶然の出会いよりも、探し求めていたものとめぐりあうことのほうが、喜びが大きいだけに、表現も強く大げさになってしまう、ということでしょうか。どうやら、言葉にも鮮度があるようです。