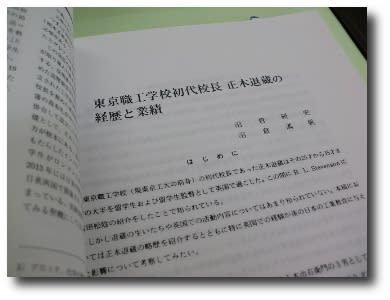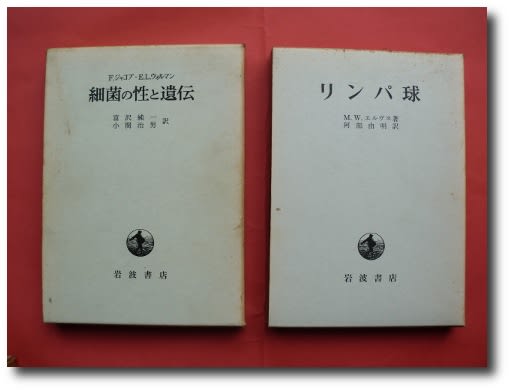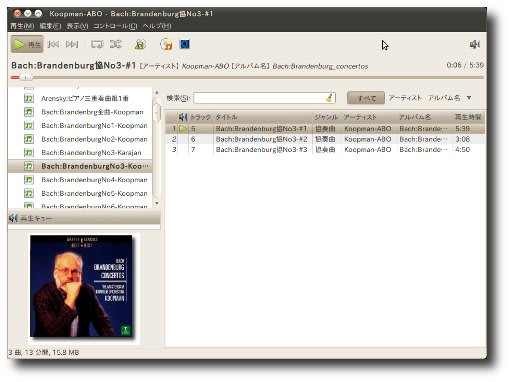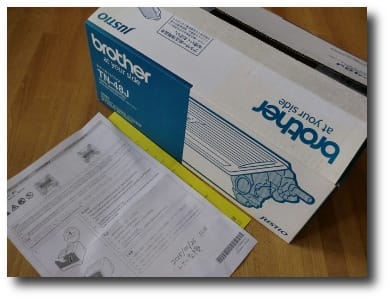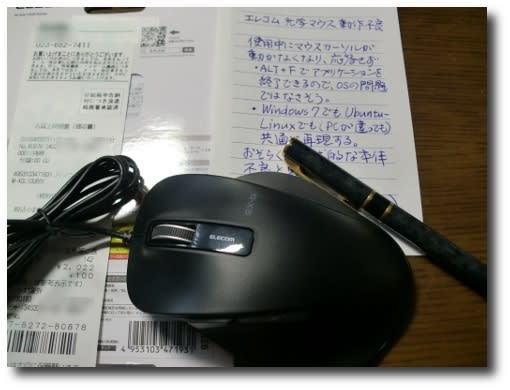バレンタインデーの日曜日、祖母の23回忌や母屋の片付けを済ませて、午後から山形交響楽団「アマデウスへの旅」リクエストコンサートVol.2 に出かけました。今回は二階席の正面付近で、ステージ全体がよく見渡せます。

プレコンサートトークでは、音楽監督の飯森範親さんと西濱事務局長のかけ合いを興味深く聴きました。スキーが大好きな飯森さんは、すでに今シーズンで蔵王に四回目だそうで、スキーの板とシューズとを蔵王のスキースクールに預けてあるのだそうです。今回の演奏会については、まず滅多に演奏されないであろう珍しい曲を含むものとなっている点が特徴だそうで、たしかにそうかもしれません。プログラムは、

- 歌劇「フィガロの結婚」序曲
- 交響曲ニ長調K.141a(K.161/163)"歌劇「シピオーネの夢」のための"
- 交響曲ニ長調K.196/121(207a)"歌劇「偽の女庭師」序曲のための"
- ヴァイオリン協奏曲第5番イ長調K.219「トルコ風」第2楽章・第3楽章 高橋和貴(Vn)
- 交響曲第36番ハ長調K.425「リンツ」第4楽章
- 聖三位一体のミサ ハ長調 K.167
というものです。モーツァルトの若い時代の作品にも、作曲者の天才性が現れているとのことです。
ステージに楽員が登場、例によって女性奏者の皆さんは色とりどりのドレスで、実にカラフル、目の保養です(^o^)/
スタート時の楽器編成は、ステージ左から第1ヴァイオリン(8),チェロ(5)、ヴィオラ(6)、第2ヴァイオリン(8)の対向配置、左端にはコントラバス(3)が陣取って弦楽5部を構成します。正面奥にはフルート(2)、オーボエ(2)、その奥にクラリネット(2)、ファゴット(2)、さらにその奥にはホルン(2)、トランペット(2)、右奥にティンパニが配置されます。
音楽監督の飯森さんが登場、第1曲目、歌劇「フィガロの結婚」序曲。山響にはおなじみ、お得意の曲だと思います。思わずワクワクするような演奏会の始まりです。第2曲目、交響曲ニ長調K.141aは、全3楽章形式の短い曲です。第1・第2楽章は、ザルツブルグの新大司教のために作ったオペラ「シピオーネの夢」K.126の序曲からとられ、それに第3楽章フィナーレを新たに加えたものだそうです。フィナーレの作曲年代は自筆譜の用紙の研究から1772年と推定されているそうで、1756年生まれのモーツァルト16歳の作品ということになるようです。
第3曲目、交響曲ニ長調K.196/121(207a)は、歌劇「偽の女庭師」K.196の序曲が2つの楽章を持つことから、同様に新たにフィナーレを加え3楽章としたものだそうです。楽器編成は、Ob(2),Hrn(2)に弦楽5部。
第4曲目、ヴァイオリン協奏曲第5番「トルコ風」の第2・第3楽章。楽器編成はさらに縮小され、1st-Vn(6), 2nd-Vn(6), Vla(4), Vc(3), Cb(2)が対向配置となる弦楽5部に、Hrn(2), Ob(2)が中央奥に加わります。独奏はコンサートマスターの高橋和貴さんですが、同時に指揮も行うという、いわゆる奏き振りで聴かせてくれました。指揮台なし、ステージ中央に立ち、ゆったりとした実に美しい第2楽章と、活発な第3楽章を楽しみました。
ここで、15分の休憩です。
演奏会の後半は、交響曲第36番ハ長調K.425「リンツ」の第4楽章です。
休憩時間に再びステージ上の楽器配置が変わります。今度は Cbが左端に移動して、8-8-6-5-3 の対向配置をとる弦楽セクションに、管楽器は左からHrn(2)、Ob(2)、Fg(2)が中央奥に、右奥にTp(2)とTimp. という形です。演奏も、全体に精妙なオーケストラ演奏の中でも、例えば流麗かつチャーミングな左側と少し暗めでリズムを刻む右側が掛け合うようなところが随所にあるなど、対向配置が効果的と感じました。
さて、最後は「聖三位一体の祝日のミサ」です。この曲は、楽器編成が1st-Vn(9)が左で中央がVc(5)、右に2nd-Vn(8)という対向配置にCb(3)が左端に位置し、その右横には順に Org, Fg, Ob(2), Tp(4), Timp. と並びます。なんと、ヴィオラがない!
これは、もともとそういう編成なのだそうです。さらに、男声(27)に女声(50)という合唱がずらりと並びますが、独唱者がいません!
これもまた、ミサ曲としては異例の編成ではないかと思います。このあたりも、珍しい曲とされる所以なのかもしれません。
演奏が始まると、やっぱり合唱がすごいです。そして、グローリアやクレドなどの歌い出し役をつとめた男声ソロがすばらしかった! 堂々たるものでした。また、清らかな女声合唱や、弦楽合奏の後に続く合唱の見事さ、ベネディクトゥスでのオーケストラの軽やかさ、細やかさも特筆すべきところでしょう。最後のアニュス・デイでは、2本のTpに2本の少し大きめのTpとティンパニも加わり、厳かに劇性を高めます。いや~、いいなあ!
ほんとに珍しい曲を集めたプレミアム・コンサートでした。最後を締めたのが、アマデウス・コアを中心とする合唱で、実に良かった。
演奏会の後は、妻も私もお腹をすかせていましたので、まっすぐホールを出て、某店で平田牧場三元豚のトンカツを食べました。これまた美味しかった~(^o^)/