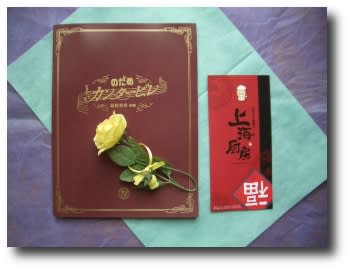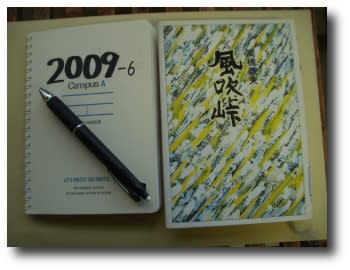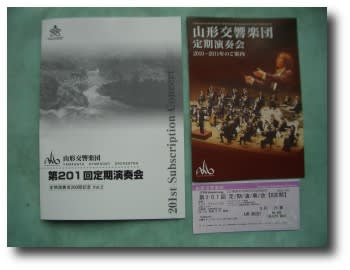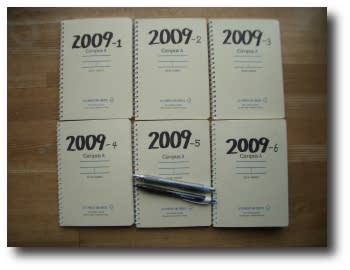なかなか音楽にじっくり耳を傾ける時間が取れません。というよりも、気持ちの余裕というか、ゆとりの問題でしょうか。このところ、暇を見つけて聴いているのが、シューマンのピアノ三重奏曲第1番、ニ短調、Op.63です。
この曲は、シューマンがライプツィヒからドレスデンへ居を移した1847年の6月から10月にかけて作曲されたのだそうで、交響曲第1番の作曲を終えた、作曲家37歳の作品となります。
第1楽章、精力的かつ情熱をもって。低音から上昇するヴァイオリンが、なにか恨み言でも言っているような雰囲気です。ヴァイオリンが激しく自己主張すると、チェロが力強くそれに応じます。途中の中間部、ハーモニクスでまるでヴィオラのように裏返った中音を奏するのはチェロなのでしょうか。ピアノは豊かな和声を聴かせ、弦の歌う旋律を支えます。クララの誕生日のために書かれたとはいうものの、ピアノだけが前面に出すぎることはありません。三者のバランスが、たいへんよく取れていると感じます。
第2楽章、生き生きと、だがあまり速くなく。活発で、はずむようなリズムがたいへんおもしろい。ピアノという楽器は、こういう音楽になると、ほんとうに目覚ましい活躍をするのですね。
第3楽章、ゆるやかに、深い内的な情感をもって。深く沈み込むような、瞑想的な気分を持った楽章です。ゆるやかなヴァイオリンの旋律に、そっと呟くようなピアノに込められた感情。そしてチェロが歌い出すと、それはもう、まだ絶望の淵を覗いてはいない、シューマンの憧れの世界です。
第4楽章、火のような情熱をもって。再び活発で情熱的で、三人の奏者がぶつかり合う音楽です。晴れやかさに陰りをもたらそうとする楽想と、それを押し返し、堂々たる音楽のフィナーレを迎えようとする楽想のせめぎあい。
ピアノ三重奏曲という曲種は、同じ室内楽とは言っても、弦楽四重奏などの、調和を重視する内向性とはやや異なり、奏者の個性が互いにぶつかり触発しあうような面があるように思います。チョン・キョンファ(Vn)、ポール・トルトゥリエ(Vc)、アンドレ・プレヴィン(Pf)という三者の個性が触発し合う様子は、メンデルスゾーンの同曲のほうが顕著のように思いますが、このシューマンの演奏も十分に個性を発揮したものです。
いっぽう、ジャン・ユボー(Pf)とジャン・ムイエール(Vn)、フレデリック・ロデオン(Vc)の三人の演奏は、より親密な雰囲気を重視したもののようです。両者の間には、テンポの設定に若干の違いはありますが、演奏時間はほとんど同じです。むしろ、音楽の表情、身振りの大きさ、そういう雰囲気の違いが大きいのかもしれません。
■チョン・キョンファ(Vn),アンドレ・プレヴィン(Pf), ポール・トルトゥリエ(Vc)
I=12'40" II=4'36" III=6'25" IV=7'51" total=31'32"
■ジャン・ユボー(Pf), ジャン・ムイエール(Vn), フレデリック・ロデオン(Vc)
I=12'22" II=4'59" III=6'23" IV=7'46" total=31'30"
これまで、エラートの「シューマン室内楽全集」で楽しんできました(*1)が、たまたま購入した「メンデルスゾーンとシューマンのピアノ三重奏曲第1番」チョン・キョンファ、トルトゥリエ、プレヴィン盤は、今年、もっとも印象的なCDの一つでした。メンデルスゾーンも名演ですが、すでに記事にしております(*2)ので、今回はシューマンの第1番のほうで。
(*1):
シューマンのピアノ三重奏曲第2番を聴く~「電網郊外散歩道」
(*2):
今日は花の金曜日~メンデルスゾーンのピアノ三重奏曲を聴く~「電網郊外散歩道」