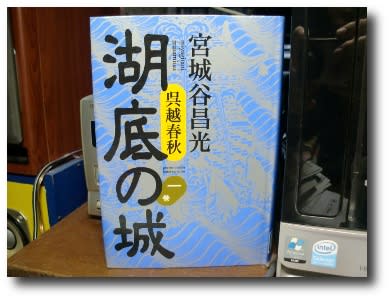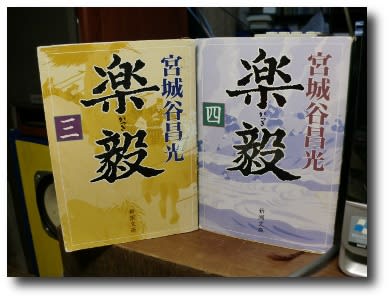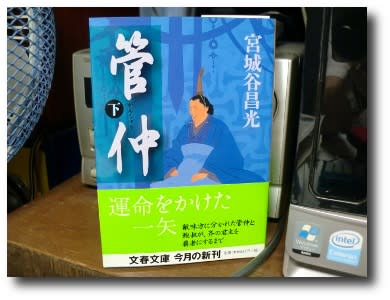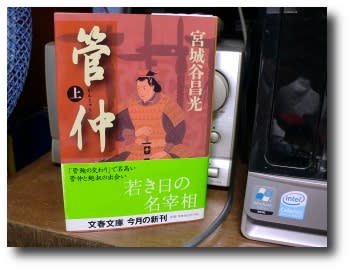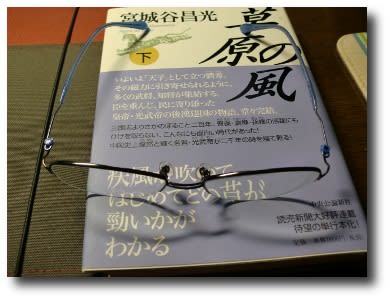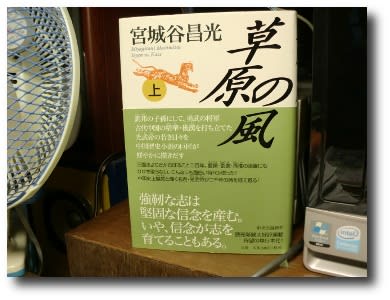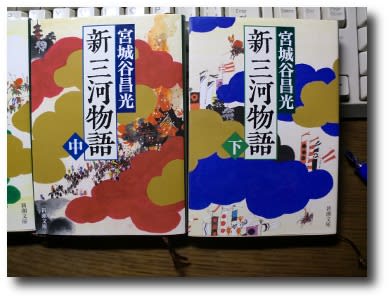講談社刊の単行本で、宮城谷昌光著『呉越春秋~湖底の城』の第三巻を読みました。講談社刊の単行本で、雑誌「小説現代」に連載中のものです。本巻は、楚王と費無極の奸計により、父・伍奢と兄・伍尚が斬首されることとなった刑場を、伍子胥とその配下の者たちが襲撃する場面から始まります。残念ながらこの襲撃は失敗するわけですが、伍子胥たちが誰も命を落とさないで逃げることができるところがすごい。
「太子をたすけよ」という父の遺言により、伍子胥は太子の亡命先の宋に向かいますが、途中で褒氏の子の小羊を預かり援けることになります。宋を出て鄭に向かいますが、亡命をためらって父の死の原因となった太子は、晋に欺かれて落命し、伍子胥らの一行は、内乱の中、鄭兵に追われながらかろうじて脱出、太子の子の勝を助けて呉に向かいます。
呉に向かった船の着いたところは、朱旦という大商人専用の船着場で、徐兄弟の紹介により蘭京に会います。蘭京は呉王の子で、王の命令により棠邑に住み、スパイ活動を束ねていたのでした。さらに伍子胥は、かつて呉の王位相続に関わる乱れを防いだ季札に会います。季氏の好意で用意された家では、かつて楚都の尹礼家で見初め結婚を申し込んだ女性・小瑰と再会します。楚の康王の娘であった小瑰は、尹礼の計らいで王家の争いから助けられ、養女としてひそかに育てられていたようです。伍子胥が一目ぼれしたのが長女の伯春ではなく養女の小瑰であったために、尹礼家では求婚を断った、というのが真相だったのでしょう。
伍子胥と小瑰、御佐と婚約していた青桐はここで結婚しますが、落ち着いてはいられません。公子光を通じて呉王に拝謁した伍子胥は、高く評価してくれた公子光の客となることを承諾します。伍子胥の片腕というべき右祐の妻となっている桃永の兄ではないかという彭乙は、両親を殺した永翁を恨んでいますが、永翁は妹の桃永にとっては育ての親ともいうべき人です。どうやら大きな謎があるようで、青銅の小函の中に入っていた絵図が、その鍵を握っているようです。
○
第三巻まで来ましたが、第四巻まではすでに刊行されているようですので、ストーリーを忘れないうちに、なんとか次巻を探してみましょう。大長編になりそう、という予感は、ズバリ当たったようです。
「太子をたすけよ」という父の遺言により、伍子胥は太子の亡命先の宋に向かいますが、途中で褒氏の子の小羊を預かり援けることになります。宋を出て鄭に向かいますが、亡命をためらって父の死の原因となった太子は、晋に欺かれて落命し、伍子胥らの一行は、内乱の中、鄭兵に追われながらかろうじて脱出、太子の子の勝を助けて呉に向かいます。
呉に向かった船の着いたところは、朱旦という大商人専用の船着場で、徐兄弟の紹介により蘭京に会います。蘭京は呉王の子で、王の命令により棠邑に住み、スパイ活動を束ねていたのでした。さらに伍子胥は、かつて呉の王位相続に関わる乱れを防いだ季札に会います。季氏の好意で用意された家では、かつて楚都の尹礼家で見初め結婚を申し込んだ女性・小瑰と再会します。楚の康王の娘であった小瑰は、尹礼の計らいで王家の争いから助けられ、養女としてひそかに育てられていたようです。伍子胥が一目ぼれしたのが長女の伯春ではなく養女の小瑰であったために、尹礼家では求婚を断った、というのが真相だったのでしょう。
伍子胥と小瑰、御佐と婚約していた青桐はここで結婚しますが、落ち着いてはいられません。公子光を通じて呉王に拝謁した伍子胥は、高く評価してくれた公子光の客となることを承諾します。伍子胥の片腕というべき右祐の妻となっている桃永の兄ではないかという彭乙は、両親を殺した永翁を恨んでいますが、永翁は妹の桃永にとっては育ての親ともいうべき人です。どうやら大きな謎があるようで、青銅の小函の中に入っていた絵図が、その鍵を握っているようです。
○
第三巻まで来ましたが、第四巻まではすでに刊行されているようですので、ストーリーを忘れないうちに、なんとか次巻を探してみましょう。大長編になりそう、という予感は、ズバリ当たったようです。