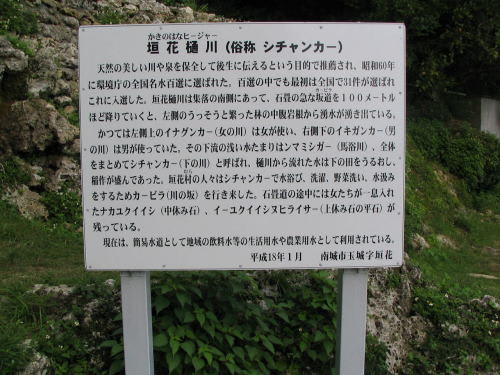小禄駅の近くにある琉球新麺 「 通堂 ( とんどう ) 」

通堂の店内

博多ラーメンのようなコクがあって美味しい
小禄駅前にあるジャスコの裏に、沖縄では珍しいラーメン店がある。
フツー沖縄では沖縄すば ( そば ) なのだが、
そんな沖縄に来て博多風ラーメンに出会うことは稀である。
味も博多で食べるものと遜色がなく、おいしいラーメンである。
奥武山公園駅 ⇒ 小禄駅の間で流れる車内メロディーは、
「 小禄豊見城 ( うるくとみぐしく ) 」 である。
小禄 豊見城 垣花 三村 三村ぬアン小達が
揃とうてぃ布織い話 あやみぐなよ 元かんじゅんどー
上泊 泊 元ぬ泊とぅ 三村 三村ぬ二才達が
揃とうてぃ塩たち話 雨降らすなよ 元かんじゅんどー
辻 仲島とぅ渡地とぅ 三村 三村ぬ女郎小達が
揃とうてぃ客待ち話 美ら二才から はい行逢らなや
潮平 兼城 糸満とぅ 三村 三村ぬアン小達が
揃とうてぃ魚売い話 安売いすなよ 元かんじゅんどー
赤田 鳥堀 崎山とぅ 三村 三村ぬ二才達が
揃とうてぃ酒たり話 麹出来らしよ 元かんじゅんどー
( 略 )
小禄村 豊見城村 垣花村の 三つの村の ねーさん達が
揃って布織りの話 模様を織り間違えるなよ 元がとれないよ
上泊村 泊村 元の泊村の 三つの村の にーさん達が
揃って塩炊きの話 雨降らすなよ 元がとれないよ
辻 仲島 渡地の 三つの村の ねーさん達が
揃って客待ち話 美男子が来ると良いね
潮平村 兼城村 糸満村の 三つの村の ねーさん達が
揃って魚を売る話 安売りしたら 元がとれないよ
赤田 鳥堀 崎山の 三つの村の にーさん達が
揃って酒造りの話 麹を上手くつくろう 元がとれないよ
三村節は、別名 ( 小禄豊見城 ・ うるくとみぐしく ) とも呼ばれ、
昔の三つの村のそれぞれの生業や特色を唄い込んだ童唄である。
また、女の子が二人向き合い、片手を互いに合わせたり、
両手を一緒に合わせたりする遊戯の時にも唄われる。
小禄、豊見城、垣花の三村は、現在小禄と垣花が那覇市になっており、
豊見城も市として発展している。
かつて三つの村は琉球絣の産地であった。
潮平、兼城、糸満の三つの村は、糸満市に統合され、
旧、糸満は漁師のまちとして有名である。
上泊、泊、元の泊は、現在泊港がある国道58号線沿いの村で、
上泊は現在の新都心「おもろまち」あたりであった。
辻(ち~じ)、仲島、渡地(わたんじ)は、
国道58号線をはさんだ那覇のバスターミナル付近の繁華街で、昔の遊郭街であった。
首里、赤田、崎山は酒造りの盛んな場所で、現在も多くの酒造所がある。
※ アン小 ( あんぐゎ ) とは、姉小で、未婚の娘のことを意味する。
二才 ( にせた ) とは、若い男を意味する。